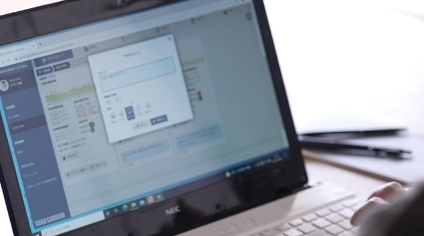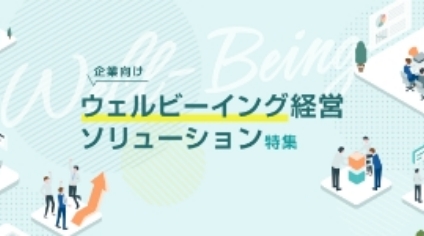サイト内の現在位置
コラム
時間外労働とは?
定義やルール、残業代の計算方法などを詳しく解説

UPDATE : 2023.03.31
時間外労働とは、労働基準法で定められた法定労働時間を超えて行う労働のことです。労使間で合意した「所定労働時間」ではなく、法律で定められた「法定労働時間」が対象になります。本記事では、法定労働時間と所定労働時間の違い、時間外労働の上限、残業代の計算方法などをわかりやすく解説します。
INDEX
- 時間外労働とは?法定労働時間を超えた労働を指す
- 法定労働時間
- 所定労働時間
- 36協定と時間外労働の上限
- 36協定の締結
- 時間外労働の上限時間
- 時間外労働の賃金
- 通常の残業代(割増賃金)
- 固定残業代(みなし残業代)
- 労働制度別の残業代(割増賃金)計算方法
- 通常の労働時間
- 変形労働時間制
- フレックスタイム制
- 裁量労働制
- 給与形態別の残業代
- 年俸制、月給制、日給制
- 時給制
- 歩合給制
- 勤怠管理システムで労働時間を正確に把握・管理
- まとめ
時間外労働とは?
法定労働時間を超えた労働を指す
時間外労働とは、労働基準法において定められた「法定労働時間」を超えた労働、またはその時間のことです。従業員に時間外労働を課すことは、労働基準法によって原則禁止とされていますが、36協定(労働基準法第36条に基づく労使協定)を締結した場合のみ、例外として認められます。
時間外労働の対象となるのは、法定労働時間を超えた労働です。混同されがちな用語に「所定労働時間」があります。
法定労働時間
法定労働時間とは、労働基準法第32条によって定められた労働時間のことを言います。法定労働時間は、原則として「1日8時間、1週間40時間」と定められており、「少なくとも週1日、もしくは4週間を通じて4日以上」の休日を従業員に与える義務も示されています。
従業員に時間外労働を課す場合は、36協定を締結して労働基準監督署長に届出をおこなった上で、残業代(割増賃金)を支払わなければなりません。残業代の算出方法については後述します。
所定労働時間
所定労働時間とは、会社側が定めた労働時間のことで、始業から就業までの時間から休憩時間を引いた時間のことを言います。たとえば、始業が10時で終業が18時、休憩時間が12時〜13時だった場合、所定労働時間は7時間となります。
所定労働時間は、法定労働時間を超えて設定することはできません。また、残業代の支払いが必須になるのは、法定労働時間を超えた労働についてです。
たとえば前述の場合、10時に出社して19時に退社すると、所定労働時間外の労働は1時間となりますが、法定労働時間外の労働は0時間となります。この際、残業代が発生するかどうかは労使の定めによります。
36協定と時間外労働の上限
企業が従業員に時間外労働を課すためには、36協定の締結と順守が必要となります。また、36協定を締結した場合でも、時間外労働(残業)や休日労働の上限時間は存在します。それぞれについて、以下で簡単に解説します。
36協定の締結
36協定とは「労働基準法第36条に定められた労使協定」の通称で、正式名は「時間外・休日労働に関する協定届」といいます。企業が従業員に法定労働時間を超えて労働させたり休日労働をさせたりする場合には、「労働者の過半数で組織する労働組合、または、労働者の過半数を代表する者」と書面で36協定を結び、所轄の労働基準監督署長に届出をする必要があります。
時間外労働の上限時間
36協定を締結した場合でも、時間外労働の上限時間は存在します。労働基準法における時間外労働(残業)の上限は、月45時間、年360時間となっており、原則としてこれを超える労働をさせることはできません。しかし、繁忙期や緊急時の対応が必要な場合には、労使間で「特別条項付き36協定」を締結することで、例外として以下の上限まで時間外労働が可能です。
●特別条項付き36協定を締結した場合の例外
- 年720時間以下
- 2〜6か月の平均が80時間以下*
- 単月で100時間未満*
- 年6か月が限度
*時間外労働+休日労働
時間外労働の賃金
時間外労働が発生した場合、労働基準法第37条で、残業代の支払いが義務付けられており、支払うべき残業代の計算方法も定められています。ただし、働き方の多様化が進む近年の状況から、実際にどのくらいの残業代を支払うべきかについては、労働時間の取り決めや給与体系により変化します。まずは、原則的な残業代の計算について紹介します。
通常の残業代(割増賃金)
残業代には、時間外(残業)手当、休日手当、深夜手当の3種類があります。また、時間外手当は「月に何時間の時間外労働をしたか」によって異なります。具体的な割増率は以下の表の通りです。
| 種類 | 支払う条件 | 割増率 |
|---|---|---|
| 時間外手当(残業手当) | 法廷労働時間(1日8時間・週40時間)を超えたとき | 25%以上 |
| 時間外労働が限度時間(1か月45時間、1年360時間など)を超えたとき | 25%以上(*1) | |
| 時間外労働が1か月60時間を超えたとき(*2) | 50%以上(*2) | |
| 休日手当 | 法廷休日(週1日)に勤務させたとき | 35%以上 |
| 深夜手当 | 22時から5時までの間に勤務させたとき | 25%以上 |
残業代は、種類と条件に応じた割増率に時間外労働の時間を乗算したものとなります。また、種類が複数ある場合は割増率が加算されます。たとえば、深夜に時間外労働をした場合の残業代は、時間外労働の割増率(25%以上、または50%以上)に、深夜労働の割増率(25%以上)が加算されます。具体的には時間外労働を22時~翌1時まで行い、時間外手当(残業手当)と深夜手当をそれぞれ25%とした場合、22時から翌1時の労働に対する賃金の割増率は50%になります。
固定残業代(みなし残業代)
残業代の例外として、あらかじめ一定時間の残業を設定して、その分の残業代を固定給に含んで支払う「固定残業(みなし残業)代」があります。企業は、時間外労働が発生したか否かにかかわらず、固定残業代も含めた賃金を支払います。ただし、設定したみなし残業時間を超えて時間外労働した場合、企業は超過分の残業代を追加で支払う必要があります。
労働制度別の残業代(割増賃金)計算方法
近年では、「フレックスタイム制」や「裁量労働制」など、多様な働き方が広がっています。そのため、前述した残業代の計算式があてはまらないケースも増えてきました。ここからは、通常の労働時間の場合に加え、変形労働時間制とフレックスタイム制における残業代計算方法を解説します。
通常の労働時間
通常の労働時間は、土日祝日が休日、1日8時間勤務の企業を想定しています。法定労働時間は1日8時間・1週間40時間が原則です。この場合の残業代は以下の計算式で求められます。
●残業代=法定労働時間を超えた労働時間×1時間あたりの基礎賃金×割増率(25%*)
*割増率は種類と条件で変化
変形労働時間制
変形労働時間制とは、月や年単位で、繁忙期や閑散期に合わせて労働時間が増減する制度のことです。たとえば、繁忙期は所定労働時間を1日10時間(*1)、閑散期は1日5時間など、業務の状況によって労働時間を変えることができます。変形労働時間制には、1週間単位(*2)、1か月単位、1年単位があります。
変形労働時間制でも、法定労働時間を超えた時間外労働に対しては、残業代を支払わなければなりません。たとえば、繁忙期である月〜水の所定労働時間をそれぞれ10時間、閑散期である木〜金の所定労働時間をそれぞれ5時間と設定した場合、月曜日に11時間労働した場合は1時間分の残業代が発生します。一方で、金曜日に7時間労働した場合は法定労働時間内なので残業代は発生しません。ただし、あらかじめ定めた単位において、週の平均が40時間を超えた場合は割増賃金が発生します。割増賃金の計算式は「通常の労働時間」と同様になります。
また、変形労働時間制でも時間外労働を課す場合は36協定の締結が必要となります。労働時間の上限は、1か月単位の場合は月45時間・年360時間となり、1年単位の場合は月42時間・年320時間となっています。
*1:変則労働時間制における所定労働時間の上限は10時間まで
*2:1週間単位の「非定型的変形労働時間制(第32条の5)」は、規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業において、労使協定により、1週間単位で毎日の労働時間を弾力的に定めることができる制度
フレックスタイム制
フレックスタイム制とは、一定の期間(清算期間)についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、従業員が出社時間と退社時間を決めることができる制度です。2019年4月の法改正により、清算期間の最長が1か月から3か月に延長されました。フレックスタイム制の多くは、必ず出勤すべき時間(コアタイム)と、自由に出退勤できる時間(フレキシブルタイム)で構成されています。
フレックスタイム制では、清算期間内の総労働時間が法定労働時間を超えると残業代が発生します。法定労働時間の総枠は以下の式で求められます。
●法定労働時間の総枠=40時間×清算期間の日数÷7
フレックスタイム制の時間外労働は、清算期間が1か月を超えるかどうかで計算方法が変わります。清算期間が1か月以内の場合は、「実労働時間-総労働時間」が時間外労働時間です。清算期間が1か月を超える場合は、以下のふたつの手順で時間外労働時間を算出します。
- ①1か月ごとの週平均50時間を超えた労働時間
- ②①を除いた清算期間全体の「実労働時間-法定労働時間(週平均40時間)の総枠」
ここで算出された時間外労働の時間を、「通常の労働時間」の式に当てはめて割増賃金を算出します。
裁量労働制
裁量労働制とは、事前に取り決めた一定の労働時間を実労働時間としてみなす制度のことです。たとえば、みなし労働時間を8時間とした場合、実労働時間が6時間でも10時間でも、8時間労働とみなします。
裁量労働制の残業代は、みなし時間の設定によります。たとえば、みなし時間が法定労働時間と同じ8時間であれば、基本的に残業代は発生しません。ただし、みなし時間が法定労働時間である8時間を超えている場合は残業代が発生します。たとえば、みなし時間が9時間の場合、たとえ実労働時間が6時間であっても、1時間分の残業代が発生します。また、22時から5時の深夜勤務や、法定休日に勤務した場合は、裁量労働制であっても通常と同様の割増賃金が発生します。
| 概要 | 時間外労働に該当する労働 | |
|---|---|---|
| 通常の労働時間 | 法定労働時間は1日8時間・1週間40時間が原則。土日祝日が休日 | 法定労働時間を超えた労働 |
| 変形労働時間制 | 月や年単位で、繁忙期や閑散期に合わせて労働時間を増減する | 月間または年間の法定労働時間を超えた労働 |
| フレックスタイム制 | 従業員が出社時間と退社時間を決めることができるが、必ず出社していなければいけない「コアタイム」が設定されていることが多い | 清算期間内の総労働時間が法定労働時間を超えた労働 |
| 裁量労働制 | 事前に取り決めた一定の労働時間を実労働時間としてみなす | みなし時間が法定労働時間である8時間を超えた労働 |
給与形態別の残業代
時間外労働における残業代は、給与形態(年俸、月給、日給、時給など)でも違いがあります。基本的に、残業代の計算式そのものに変化はありませんが、給与形態によって1時間あたりの基礎賃金の計算が変わります。
なお、原則として管理監督者は残業代(および休日手当)が発生しません。労働基準法における「管理監督者」は、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」をいいます。管理監督者に当てはまるかどうかは、役職名ではなく、職務内容、責任と権限、勤務形態等の実態によって判断されます。一方で、管理監督者であっても深夜手当は発生します。
年俸制、月給制、日給制
年俸制、月給制、日給制における残業代は以下の計算式を用います。
●残業代=法定労働時間を超えた労働時間×1時間あたりの基礎賃金×割増率
ただし、式の中にある「1時間あたりの基礎賃金」は給与形態によって異なります。
●年俸制の場合:1時間あたりの基礎賃金=年俸額÷12月÷1カ月の平均所定労働時間
●月給制・日給制の場合:1時間あたりの基礎賃金=月給額(日給額)÷1カ月(1日)の所定労働時間
月給30万円の従業員の残業代
具体的な例として、月給30万円の従業員(所定労働時間8時間)が月30時間の時間外労働をした場合の残業代を計算します。就業日は20日間、深夜・休日労働はなしとします。
- ①1時間あたりの基礎賃金=300,000円(月給)÷{20(就業日)×8(所定労働時間)}=1,875円
- ②残業代=30(時間外労働時間)×1,875(1時間あたりの基礎賃金)×1.25(割増率)=70,312円(端数切捨て)
- ③該当月に支払う賃金=300,000円(月給)+70,312円(割増賃金)=370,312円
時給制
時給制は主にパートやアルバイトに対して採用される給与形態で、法定労働時間を超えた場合は残業代が発生します。時給制の場合、時給額がそのまま1時間あたりの賃金になります。残業代の計算方法は、年俸、月給、日給制と同様です。
たとえば時給1,300円の従業員が月に30時間の時間外労働を行った場合、以下のように計算します(深夜・休日労働はなし)。
- ①残業代=30(時間外労働時間)×1,300(1時間あたりの基礎賃金)×1.25(割増率)=48,750円(端数切捨て)
- ②基本給に割増賃金48,750円を上乗せして支払う
ただし、時給とは別になんらかの手当を支払っている場合、基礎賃金は手当も含んだ額となります。また、時間給は原則として法定労働時間を1分でも超えると残業代が発生します。
歩合給制
労働基準法第27条では、「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」と定められています。つまり、歩合制であっても時間外労働に対しては残業代が発生します。なお、歩合制は「固定給+歩合給」という形もあり、残業代は固定と歩合のそれぞれで計算する必要があります。本記事では「固定給+歩合給」の計算方法を解説します。
- ①それぞれの1時間あたりの基礎賃金を計算
・固定給の1時間あたりの基礎賃金=月給額÷1カ月の所定労働時間
・歩合給の1時間あたりの基礎賃金=歩合給額÷残業を含めた総労働時間 - ②固定給に対して1.25を乗算する
・1時間当たりの固定給の残業額=1時間あたりの基礎賃金×1.25 - ③歩合給に対して0.25を乗算する
・1時間あたりの歩合給の残業額=1時間あたりの基礎賃金×0.25* - ④「②」と「③」を加算して1時間あたりの残業代を算出
- ⑤時間外労働をした時間に1時間あたりの残業代を乗算して残業代の総額を算出
*歩合制の場合、時間外労働に対する1時間あたりの基礎賃金は給与総額に含まれているため、残業代は時間単価の25%以上(深夜労働は25%以上、休日労働は35%以上)となる
たとえば、固定給25万円、歩合給5万円の従業員が、月30時間の時間外労働をおこなった場合、以下のように計算します(就業日は20日間、深夜・休日労働はなし)。
- ①それぞれの1時間あたりの基礎賃金を計算
・固定給の1時間あたりの基礎賃金:250,000円÷(20日×8時間)=1,562円(端数切り捨て)
・歩合給の1時間あたりの基礎賃金:50,000円÷(20日×8時間+30時間)=263円(端数切り捨て) - ②固定給に対して1.25を乗算する
・1時間当たりの固定給の残業額=1,562円×1.25=1,952円(端数切捨て) - ③歩合給に対して0.25を乗算する
・1時間当たりの歩合給の残業額=263×0.25=65円(端数切捨て) - ④②と③を加算して1時間あたりの残業代を算出
・固定給+歩合給の1時間あたりの残業代=1,952円+65円=2,017円 - ⑤時間外労働をした時間に1時間あたりの割増賃金を乗算して総額を算出する
・総残業代=2,017円×30時間=60,510円
| 1時間あたりの基礎賃金 | 残業代の計算 | |
|---|---|---|
| 年俸制 | 年俸額÷12月÷1カ月の平均所定労働時間 | 法定時間外労働時間×1時間あたりの基礎賃金×割増率 |
| 月給制 | 1時間あたりの基礎賃金 =月給額÷1カ月の所定労働時間 |
|
| 日給制 | 1時間あたりの基礎賃金 =日給額÷1日の所定労働時間 |
|
| 時給制 | 時給額 | |
| 歩合給制 | ・固定給の1時間あたりの基礎賃金 =月給額÷1カ月の所定労働時間 ・歩合給の1時間あたりの基礎賃金 =歩合給額÷残業を含めた総労働時間 |
1時間当たりの固定給の残業額(1時間あたりの基礎賃金×1.25) + 1時間あたりの歩合給の残業額(1時間あたりの基礎賃金×0.25) |
勤怠管理システムで労働時間を正確に把握・管理
時間外労働は、原則として発生させないことが理想です。しかし、現実的にはすべての業務を法定労働時間内に終えることは難しいでしょう。たとえ時間外労働が発生してしまったとしても、従業員の健康に配慮し、最小限にとどめることが求められます。
また、近年は働き方が多様になり、リモートワークや裁量労働制などを採用していると、従業員の労働時間が見えにくくなります。管理者側が知らないうちに従業員が過度な残業をしている、といった場合もあるでしょう。そういった状況の中で従業員の労働時間を正確に把握し、残業代の算出をすることは、容易ではありません。複雑化する労働時間や残業代の算出を正確に行うためには、IT技術を活用した勤怠管理が有効です。
たとえばNECソリューションイノベータのクラウド型勤怠管理システム「勤革時」なら、以下のような機能があります。
- 出退勤時刻、残業・休憩等の状況をリアルタイムで確認可能
- 打刻、スケジュール変更、休暇申請、残業申請など申請情報をシステム管理
- 残業時間の上限規制、年5日間の年次有給休暇の取得など、「働き方改革関連法」に対応
- クラウド型なので直行直帰の従業員勤怠も正確に把握
従業員の労働時間や残業時間が設定値を超える場合にアラート表示させるなど、システムによって過度な時間外労働を未然に防ぐことができます。勤怠管理システムを活用し、従業員の時間外労働が上限時間を超えないように管理しましょう。
まとめ
働き方改革が進む昨今では、オフィスに出勤してタイムカードを押す、という従来の働き方の常識が変化し、多様な勤務体系が実現している一方、企業にとっては従業員の労働時間を把握しにくいという課題があります。上限を超えた時間外労働を従業員に課したり、36協定違反を犯したりしてしまえば、法令違反となるため、時間外労働は最小限にとどめることが必要です。そのためにもIT技術を用いて、適切な労務管理や業務効率化を図りましょう。