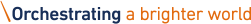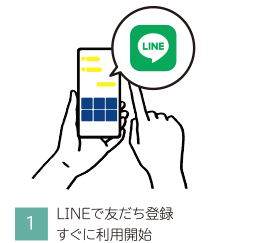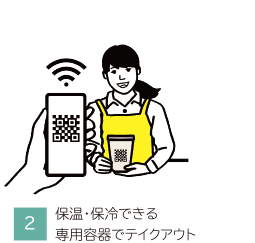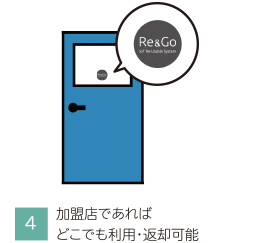容器シェアリングサービス「Re&Go」NECソリューションイノベータ×共創パートナー

-
- イノベーション推進本部 加藤 一郎
- 昭和63年「機械翻訳をつくりたい」と、前身の神戸日本電気ソフトウェア(当時)に入社。自身が行うサーキュラーエコノミー活動の延長線上として『Re&Go』に参画。
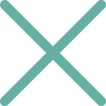
-
- NISSHA 株式会社 吉村 祐一様
- 株式会社リコーでの複合機などの電子回路設計を経てNISSHAへ。「プラスチックゴミ問題の解決」をテーマに『Re&Go』を立ち上げ、プロジェクトリーダーを務める。
テイクアウトの容器は
使い終えたら捨てるもの。
そんな当たり前を、
技術×仕組みで変えていく。
環境負荷低減
- Re&Go(リーアンドゴー)
- 京都の資材・デバイスメーカーNISSHAと共創した容器シェアリングサービス。飲食店のテイクアウト容器を回収、洗浄して再利用する仕組みで廃棄プラスチックを削減。COVID-19の影響でテイクアウトが増える中、環境負荷低減に向けた取り組みとして注目を集める。2020年12月から2021年2月にかけて、沖縄県読谷村で実証実験を実施。
使い捨てだった容器をリユースへ。新しい発想のサービスをともにつくる。
- 加藤
- 2019年2月、新しいサービスを立ち上げるためにLINEを使った実証実験を行いたいと吉村さんから連絡いただいたのがはじまりでした。その日のうちに「やろう」と即決したのをよく覚えています。私自身、当社で早くからLINEを使った実証実験をしていたこともあり、望まれているものを提供できると思いました。
- 吉村
- 私はもともと電気系のエンジニアで、以前から環境負荷を低減する技術の開発に取り組んでいました。日本のプラスチックゴミの多くは容器包装。より大きな貢献がしたいと思い、コーヒーカップやお弁当の容器をリユースしてシェアする『Re&Go』を立ち上げることに。実現のためにはICTに長けたパートナーが必要でした。
- 加藤
- お話を伺って非常に頼られていると感じましたし、これまで取り組んでいたサーキュラーエコノミー(循環型経済)の活動を、具体化できる人とアイデアに出会えたと思いました。受けない理由がありませんでした。
- 吉村
- ゼロから新しいサービスをつくるので、ICTの部分だけを委託する関係ではうまくいかないと思っていました。加藤さんに話をするとすぐに社内の方を巻き込んで話を進めてくださって、一緒にスピード感を持ってやれたのがありがたかったです。
- 加藤
- 吉村さんとは、最初にお会いしたときから同じ方向を向いている感覚がありました。「もしかすると僕らの世代では実現できないかもしれない」と話していたのが印象的で、私がこれまでの活動の中で抱いた意識と合致していた。
- 吉村
- 実はリユースの概念は、昔は日常に浸透していたのです。たとえば牛乳瓶やお酒の瓶など、100年前は容器のリユースもありました。衛生面の問題で使い捨てに置き換わった歴史がありますが、今は洗浄施設も整っているし、誰が使ったかの管理もできる。今こそ先を見据えて変えていけるタイミングなのだと思います。
沖縄で実証実験を完了。不完全でも世に出せば、可能性が広がっていく。
- 吉村
- 『Re&Go』の強みは容器のシェアによるゴミの削減。地域内の参画店舗ならどこでも返却できる利便性をベースに、容器循環や空きリソースの活用といった広がりを考えていることもユニークなポイントです。容器を洗浄する飲食店や輸送パートナーの空き時間をデータで可視化して、地域の方の時間を有効活用するのです。
- 加藤
- 容器の単なるリユースであれば飲食店の方々でも思いつくかもしれませんが、そこで得られたデータを使うところまでは発想が及ばないのではと思います。データを活用するという概念は、そこを本業にしている当社だから提案できたことだと思います。洗浄・輸送パートナーのデータの他にも、容器がいつどこで借りられ、どんな時間に返却されるのか、飲食店側に役立つデータも提供できます。
- 吉村
- 参画いただく飲食店の方々にもメリットがある仕組みですよね。利用者が容器を返しに行くサービスなので、そのついでに買い物をする可能性がある。データを活用することで、お店側にもよりメリットを提供していけると思っています。
- 加藤
- 今はそういった『Re&Go』の考え方を知ってもらう段階ですね。沖縄で実証実験を行い、さまざまな手段で広報することで、興味を持ってくれた飲食店や輸送パートナー、洗浄パートナーの方から問い合わせが増えました。うまく巻き込んでいくスキームづくりはこれからの課題と思っています。
- 吉村
- 石垣島のカフェとか、四国の豆腐屋さんとか、地方自治体や海外からもお問い合わせいただきました。実証実験の段階でサービスはできあがっていませんでしたが、不完全でも世に出すことが大切で、そこから可能性が広がっていくと実感しました。まずは認知をされることが次につながっていくのだと思います。
足りないのはモノではなく仕組み。漠然とした思いを起点に、少し先の未来へ。
- 加藤
- 私がICTの道に進んだのは、船乗りの夢を諦めたからでした。山口県の田舎の育ちで、父親が船乗りだったため自分もそうなるとばかり思っていましたが、視力が悪かったため学校に入れず断念。新しい夢を見つけるためにICTを使ってみようかなと。昭和63年、「コンピュータってすごい」となりつつある時代に、少し先のモノをつくりたいという気持ちで入社して、今もその延長線上にいます。
- 吉村
- 私は福井県出身で、小中高大とバレーボールをやっており、中高はキャプテンでした。そこで気づいたのが、「チームプレーは仕組みをつくらないとうまくいかない」ということ。これが原体験となり前職も今も、人が利用してくれる仕組みを考えることに魅力を感じています。『Re&Go』においてもただモノをつくるのではなく、人を動かす仕組みをつくることで広く普及させたいと思っています。
- 加藤
- 私はエンジニアなので、誰かに「こんなことをやりたい」と言われた時にモチベーションが上がります。漠然としていてもいい。自分にやりたいことがあるというより、人の思いに応えて、技術で何かしら世の中を新しくすることに貢献したくなるのです。『Re&Go』は吉村さんの漠然としていても芯の通った強い思いがあって、一緒に考えながらつくれるので、とても楽しくやらせていただいています。
- 吉村
- 楽観的で突き進むタイプの私にとって、加藤さんが冷静な視点でコメントをしてくれるのは非常にありがたいですね。環境のための製品というと、今は海洋プラスチックを再利用して作ったスニーカーなどさまざまな「モノ」が生まれています。けれどアクションにつなげるためには、誰もが参加できる「仕組み」が必要だと思っていて、『Re&Go』はそういった環境負荷を低減するための世の中にまだない「仕組み」になれるのではないかと思います。


LINEでの登録で誰でも簡単に利用できるのが『Re&Go』の特長のひとつ。加盟店のQRコードを使って容器の貸し出しから返却までを管理。
リユースを当たり前の社会にする。
それだけでなく、地域をもっと活性化する。

- 加藤
- 私自身、環境問題やリユースに対しては「いいことだから、知っておいた方がいい」ぐらいの意識でずっと生きてきました。それが3年ほど前から仕事で関わるようになって、ようやく自分ごととして意識するようになった。吉村さんのように熱意を持って活動されている方々と議論して、一緒に動くことで前向きになってきました。
- 吉村
- 今やどの企業もSDGsを目標に掲げていて、人々の環境意識も高まり、環境に全く興味がない人は少ないと思います。けれど問題が大きすぎると人は動けないのですよね。だから日々の生活に直結したサービスで「簡単にできるんだよ」というメッセージを届けていく必要がある。それだけでなく、やはり海外の事例などを見ていると、法制化をして変えていく必要性も感じます。ゆくゆくは省庁や政治に働きかけて、この仕組みをスタンダードにしていかなければと思っています。
- 加藤
- みんなSDGsに関心はあるし、良いことだと思っているけれど、実際に貢献できる手段を持っている人は少ない。LINEを使って登録できて、借りたカップを喫茶店に返すだけで気軽に貢献できる『Re&Go』の意義はそこにありますよね。使い捨てという今のかたちが当たり前だと決めつけるのではなくて、そうじゃないかたちがあるという体験を届けたいと思います。
- 吉村
-
まずはカップリユースという概念を広げていくことが大事ですね。そして少し先の話になりますが、5G通信や自動運転など次に進んだ世界の中で、リユースが別軸で広がっていくことも考えています。今はまだカップを返却に行くのが面倒という人もいるかもしれませんが、たとえば物流のICTプラットフォームや自動運転が進んだ世界では、自宅の前にカップを置いておけば、誰かが回収しに来てくれるといった未来があるかもしれません。
環境問題に関しては、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)が発表したように、産業革命前と比べた世界の平均気温が1.5℃以上上昇するのが、以前の想定より10年ほど早まり2040年頃になることが予測されています。つまり私たちが生きている間に何かしら対策を導き出さなければいけません。また地域経済の活性化など、さまざまな社会課題と『Re&Go』を結びつけて解決していきたいと、おぼろげながら考えています。
- 加藤
-
これまでもお話ししてきたように、「リユースを当たり前の社会にする」ということは『Re&Go』のプロジェクトとしての大きな目標です。さらに当社は地域に密着した会社なので、データを収集し蓄積してさまざまサービスに活用することで、地域の活性化につなげたい。
そして私個人としては、「人がやさしいことをすると、ほめられる社会をつくりたい」と思っています。今までICTは効率化など人間が楽になるために使われてきましたが、これからは生活がより豊かになって人々が嬉しくなる、そういった感情の部分に役に立てれば素晴らしいこと。この『Re&Go』というサービスも、そのための一助になれると思っています。