サイト内の現在位置
NEWS
ジャパンバイオデザイン活動におけるエクスターンシップ・スタンフォード研修
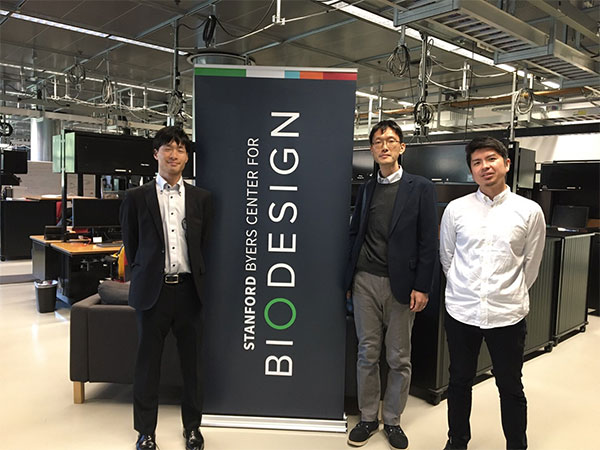
DATE:2020.03.26
研究テーマ:新テーマ探索
1.はじめに
昨年10月から主に仙台で活動し、また2月に3週間の北米出張を経て、久しぶりに本拠地の新木場の職場に顔を出したら、「どちらさまでしたっけ?」と同僚にボケられた、新テーマ探索グループの藤田です。というのも、ジャパンバイオデザイン(JBD)の東北大学チーム第5期生として参加しており、その中でシリコンバレーでのエクスターンシップと、スタンフォードでの研修が2月にあったためです。その内容の概要を報告させていただければと思います。
2.バイオデザインとは
バイオデザインのきっちりした説明は、外部のサイトに記載がありますのでそちらに譲りますが( 一般社団法人日本バイオデザイン学会、東北大学ジャパンバイオデザインなど)、スタンフォード大学で始まった、ビジネスになる医療機器をうまく作るためのプログラムです。そのプログラムの序盤を自分なりにご説明すると、
一般社団法人日本バイオデザイン学会、東北大学ジャパンバイオデザインなど)、スタンフォード大学で始まった、ビジネスになる医療機器をうまく作るためのプログラムです。そのプログラムの序盤を自分なりにご説明すると、
「医療機器でイノベーション起こしたいなら、シーズ(技術)からじゃだめよ。ニーズ(主に潜在的な要求)から見つけていかないとね。ニーズは会議室で起こっているんじゃない、(医療)現場で起こるんだ!だから、ちゃんと医療現場をその目でしっかり見て、そこに潜んでいるニーズを拾ってきてね。あ、10個や20個のニーズじゃあ、ビジネスになるネタなんて見つからないよ。200個は見つけてね。それだけ見つけても、ビジネスになるのはせいぜい1,2個だからね。」
という感じです。これを1人でやれ、と言われると絶望に打ちひしがれそうですが、ちゃんとチームを組みます。通常、多様な人材(医療従事者、エンジニアなど)の混成チームでやることになっております。冒頭写真のスタンフォード大学内にあるスタンフォードバイオデザイン(SBD)のフロアで撮影された3人がそのチームメンバーで、柿花隆昭さん(向かって右側、理学療法士)と、原井智広さん(同左側、医工学研究科大学院生)、中央が私です。
JBDの活動として、現場観察でのニーズ抽出、ニーズスクリーニングを経て、2月上旬はトップニーズの、必要となる条件の明確化(ニーズ仕様書の作成)を行うフェーズにおりました。今年の7月中旬の修了式までに、ニーズから抽出される解決技術の内容、事業計画までを完成させる予定です。このプログラムを終えると、実際にスタートアップを立ち上げるためのプロセスが身につくことになりますが、まずは本プログラムで勉強したことを会社に持って帰りたいと考えており、このプロセスを新テーマの創出における、ニーズに合致したシーズ開発に活用したいです。JBDの関係者からは、プログラム終了したとたんに、会社辞めてスタートアップを立ち上げたくなるかもよ、と言われましたが。
3.本研修の日程・内容概要
本研修は、2月第2週目から3週間の日程の中で、前半2週間はエクスターンシップ先での就業体験、後半1週間はスタンフォード大学での研修でした。エクスターンシップって何?と思った方、私もそう思ったのですが、エクスターンシップは、インターンのような就職のための職業訓練的な活動ではなく、実地的に学びを深めるなどを目的に行う短期就業体験です。今後のスタートアップ起業や、ビジネス案のブラッシュアップ方法などの参考にするために、いくつかのスタートアップやインキュベーター企業の中から、各メンバーで1つを選択し、実施しました。
スタンフォード大学での研修では、せっかくなら本場のスタンフォードバイオデザインで修行してこい!ということで、SBDのファカルティ(大学教員)による講義やメンタリング、バイオデザインに関連する医療機器メーカーへの訪問を実施し、次のコンセプト検討に向けた改善点の確認や、次の対策へつなげていきます。
私としては、IT技術につながりそうなニーズをシリコンバレーの方々と議論し、ブラッシュアップすることで、プログラム終了後にそのニーズに対する技術開発に取り組めるベースを作りたいと考えておりました。
今回の研修の中で、特に印象深かったエクスターンシップ先での活動内容を中心にご紹介いたします。
4.エクスターンシップ
私のエクスターンシップ先としては、サンノゼの北側に位置するニューアークにある Triple Ring Technologies(TRT社)へお世話になりました。このニューアークという地、ニューヨークと音が似ているから、さぞかし摩天楼が乱立するにぎやかで騒々しいところだろうと期待していったのですが、全く逆で、高い建物が皆無のわりとのどかな雰囲気、というか日中、人がほとんど歩いておらず、目につくのは車、車、車、たまに建物、なところでした。今回、近くで用を足せば車なんて借りなくてもよいだろうと高をくくっていたのですが、これが大間違いであることを後々、痛感しました。ここに2週間もいるとなると、ホテルの近所の店だけでは、絶対に飽きてきます。隣のショッピングモールへ行こうとすると、一山歩いて超えるくらいの覚悟が必要です(ちょっと大袈裟かも)。
Triple Ring Technologies(TRT社)へお世話になりました。このニューアークという地、ニューヨークと音が似ているから、さぞかし摩天楼が乱立するにぎやかで騒々しいところだろうと期待していったのですが、全く逆で、高い建物が皆無のわりとのどかな雰囲気、というか日中、人がほとんど歩いておらず、目につくのは車、車、車、たまに建物、なところでした。今回、近くで用を足せば車なんて借りなくてもよいだろうと高をくくっていたのですが、これが大間違いであることを後々、痛感しました。ここに2週間もいるとなると、ホテルの近所の店だけでは、絶対に飽きてきます。隣のショッピングモールへ行こうとすると、一山歩いて超えるくらいの覚悟が必要です(ちょっと大袈裟かも)。
さて、お世話になったTRT社はインキュベーターで、スタートアップや他の医療機器メーカーの支援をする企業です。医療機器メーカーだけでも、10数の企業が入っており、業務連携を行っておりました。この期間中に、中を見せていただきましたが、いろいろとモノを作っている様子がわかりました。のちにSBDのメンバーに聞いたところによると、TRT社をプロトタイピング企業と呼んでいたので、ああなるほど、試作品を作るのに特化しているのだな、と後になって気づきました。

TRT社の外観。駐車場含めて、圧巻される大きさ。

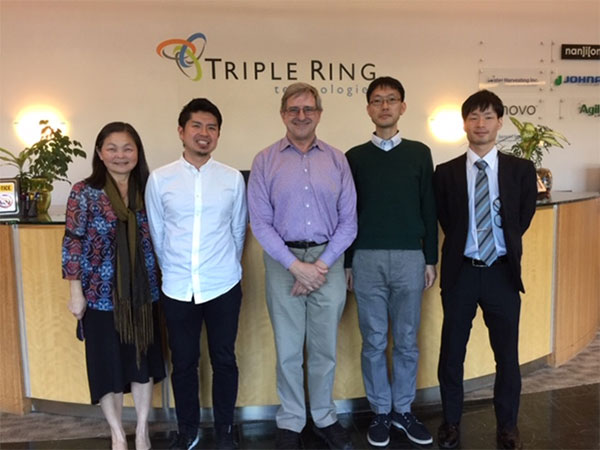
真ん中のJoeさん、向かって左端のMaraさんには非常にお世話になりました。
当初、エクスターンシップ先でできそうなこととして、先方の業務の支援をするか、自分のプロジェクトの支援を依頼するかだなと思っておりました。以前にここでエクスターンシップを行った元フェローの方曰く、この会社は放置プレイとおっしゃったので(実際そんなことはなかったのですが)、後者のほうが良いと考えました。そこで、バイオデザインのフェローである私がシーズの話をするとどうかなとは思いますが、私の専門である画像認識につながりそうなニーズを議論したいという思いがあったことから、そのニーズのブラッシュアップを主に依頼しました。
ニーズの内容をプレゼンし、議論することになりますが、議論し合うのが難しい!高速で繰り出される英語についていくのは、卓球の伊藤美誠と対戦するくらい(したことはないですが)難しかったです。そこで、AIスピーカーの認識率を30%向上させるくらいゆっくり話してもらったり、ホワイトボードに書いてもらったりと、気を使っていただきました(いざ書いてもらったら、頭のいい人は字が下手だという都市伝説を体感しましたが)。自分だけでなく、先方にもコミュニケーションで苦労させてしまいましたが、ニーズの内容整理や、不明瞭な点などを洗いだせたり、既存ソリューションの調査を支援いただいたりしました。これでビジネスが実施できるのかといわれると否ですが、一歩半くらいは前進した気持ちです。
この期間に、他のチームメンバー2人もそれぞれのエクスターンシップ先からTRT社へ招待し、初顔合わせとしてお互いに紹介をしたり、ニーズの内容を議論したりしました(受付前の写真は、その日に撮影されたものです)。エクスターンシップ中での特別対応とはいえ、他のメンバーも含めた顔合わせ・議論に半日近く時間を割いていただきました。このことから、先方はお互いのことを知って支援しあえる関係になる、いわゆるネットワーキング的な部分を重要視していると感じました。シリコンバレーや、ビジネス業界では一般的といえば一般的なのかもしれませんが、自分から行う上記のようなネットワーキングは敷居が高いと感じてしまう面もあります(展示会などで、名刺交換だけで終わってしまったり…私もあります)。今回のエクスターンシップを通して、例えば問題と共通認識できることに対して、お互い議論できたりすると、もう少し深い理解が相互にでき、ビジネスにつながる可能性が出てきそうと思いました。

SBDが入っているJames H. Clark Center

5.スタンフォード研修
最後の1週間は、各地のエクスターンシップ先でそれぞれ(自由に)活動していたチームメンバーが合流してスタンフォード大学周辺に泊まり、スタンフォード大学で本場のバイオデザインプログラムを受けてきました。今回、共同作業がやりやすいのと、宿泊費の折半による経費の削減を考え、チームメンバーと同一の宿泊先に泊まることとしました。この宿泊先、スペックは高く快適だったのですが、以前はサンフランシスコおよびベイエリアで1,2を争う治安の悪い地域だったらしいです(汗)。昔よりは改善しているためか、幸いなことに、何事も起きませんでしたが、同じような目的で宿泊地を選ぶ際には、地域の安全性をよく確かめてから選択するようご注意ください。
スタンフォードでの研修では、大きく分けて(1)バイオデザインプロセスの講義、(2)メンタリングによるニーズのブラッシュアップ、および(3)医療機器メーカーの見学を行いました。特に(2)は、今後のニーズのブラッシュアップに関して、貴重なアドバイスを頂けました。紙面の都合上、これらのスタンフォード大学での研修の詳細は記載しませんが、別の機会にご紹介できるかもしれません。
ちなみに、スタンフォード大学内は、冒頭の写真や、SBDのフロアが入っているJames H. Clark Centerや、その他建造物がたくさんあり、広すぎて、迷子になりそうでした。グッズを販売しているところ(ブックストア)もありましたが、文房具と衣類(大学名が入っているTシャツとか)が多かった印象です。スタンフォード印の饅頭のような、みんなで分け合えるお菓子を期待していたのですが、飲食物が見つからなかったのは残念でした。
6.終わりに
非常に簡単にではありましたが、今回のエクスターンシップ・スタンフォード研修で、印象に残ったところを中心にご紹介しました。少しでも雰囲気をつかんでいただけたら幸いです。
エクスターンシップ先では、またシリコンバレーで仕事することがあるのか、と再三聞かれました。「I’ll be back!」とは言いませんでしたが、次にここに来るときは、ぜひ新規事業を立ち上げてシリコンバレーに戻ってきたいと強く思いました。
担当者紹介
研究テーマ:バイオデザインプロセスの習得と応用
担当者:藤田 光洋
コメント:東北大学バイオデザインプログラムに参加して、ニーズに基づいた研究開発の方法を模索しております。
連絡先:NECソリューションイノベータ株式会社 イノベーションラボラトリ 新テーマ探索グループ
ilab-contact@nes.jp.nec.com
