サイト内の現在位置
NEWS
ATD-ICE 2018に参加してきました!(第1回)
ATD-ICE 2018に参加してきました!
DATE:2018.06.06
研究テーマ:エンゲージメント
こんにちは、エンゲージメントの研究をしている山本です。
昨年から日本でも注目されるようになってきた従業員エンゲージメントですが、どうすれば向上できるのか?といった対策がよく分かっていません。そこで、5月のはじめ(GW終わり)に開催された世界最大の人材開発学会ATD-ICE 2018 (Association for Talent Development International Conference and Exposition 2018)に参加してきました!
当社の参加は2年目になりますが、今年も  株式会社人財ラボ様の視察ツアーに参加させてもらいました。昨年は別のメンバーが参加したので、私自身は初めての参加です。
株式会社人財ラボ様の視察ツアーに参加させてもらいました。昨年は別のメンバーが参加したので、私自身は初めての参加です。
ATD-ICE 2018の全体的な傾向は、他社のブログに任せるとして、私自身が見てきた内容を中心に書いていきたいと思います。

エンゲージメントに関するセッションが100以上!
ATD-ICE 2018は、米国サンディエゴで開催され、10,000人以上が参加し、400以上のセッションが4日間で実施されます。セッションは、10コンテンツトラックと4つインダストリートラックに分類されています。

◆コンテンツトラック
- Learning Technologies
- Leadership Development
- Training Delivery
- Instructional Design
- Talent Management
- Career Development
- Global Human Resource Development
- Learning Measurement & Analytics
- Science of Learning
- Management
◆インダストリートラック
- Sales Enablement
- Government
- Healthcare
- Higher Education
全トラックを対象として、”Engage”でセッション検索をしてみると、なんと115セッションもありました!
とても一人では周りきれません。
仕方ないので、「何をするとエンゲージメントを向上できるのか?」という疑問に集中し、エンゲージメントに関するWhy, What, Howのうち、Whyについてのセッションを選び聴講してきました。結果的に、Science of Learningのセッションが多くなってしまいました。
選択にあたり、事前にすべての資料をダウンロードし、セッションの内容をチェックしておきました。しかし、セッション数が膨大で、なぜ選んだのか忘れたり、参加してみると目的と合わないセッションだったりして、事前のセッション選択がかなり重要だと思い知らされました。来年も参加者がいれば、アドバイスしたいと思います!
無意識の意識化(Unconscious to Conscious)
私が参加出来たセッションの中で頻出したキーワードは「無意識(Unconscious)」でした。例えば、リーダーの無意識な行動による弊害について(Mary-Clare Race, SU204)や、内発的動機づけは人の無意識部分にアプローチする必要がある(Michael Patterson & Sheryl Roy, SU103)とか、マインドフルネスは自己の無意識を意識化すること(Claus Breede, SU403)などです。意識化という意味で「気付き(Awareness)」も、よく聴かれました。
「無意識」と類似する概念として、「バイアス(Bias)」も多く聞かれました。例えば、ハリケーンが女性名だと被害を小さく見積りがち(Howard Ross, W106)とか、採用面談で人種や性別、年齢でステレオタイプな人物像を当てはめがち(Howard Ross, W106)などです。しかし、「バイアス」は人類が進化の過程で獲得してきた脳内回路のショートカットで、「バイアス」がないととても生活できない、という指摘もありました(Howard Ross, W106)。そのため、「バイアス」とどう上手く付き合うかが重要なのかなと思いました。
次によく聴かれたのが、「目的(Purpose)」「意義(Meaning)」です。ただし、ここでいう「目的」は、外部から与えられたものではなく、自分の価値観に基づくものです(Britt Andreatta, M106)。「意義」は、主観的重要さを表していますが、主観的重要さは価値観によります。そのため、「目的」と「意義」は切っても切り離せないものだそうです(Britt Andreatta, M106)。でも、自分の価値観は普段意識しませんよね?だから、ここでも無意識の意識化が必要になるのかなぁと思いました。
最後に「信頼(Trust)」も何度か目にしました。目的・意義は、個人の内面の話ですが、「信頼」は、個人間の関係性の話ですね。「信頼」を高めるには、幸せホルモンと呼ばれている脳内物質オキシトシンが分泌されるとよいとされています。その最初の1歩は、「意外な感謝や称賛」だそうです(Kenneth Nowack & Paul Zak, SU313)。感謝は、「当たり前だ」と思う気持ちがあると忘れてしまいがちな感情です。だから、感謝するべき状況を意識する必要があるのですが、これも無意識の意識化の一種なのかもしれません。
テクノロジーの可能性
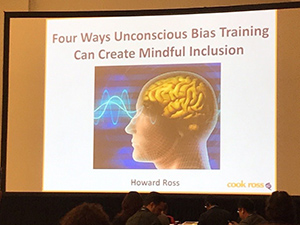
ATD-ICE 2018は、人材開発の学会なので、研修や学習へのテクノロジー適用が主流です。しかし、基本的には「アルゴリズムには人間のバイアスがない」ので、人間の無意識を意識化するという領域は、テクノロジーが有効に機能する領域かもしれません。もちろん、アルゴリズムを作る人間のバイアスが入る余地はあります。少ないですが、採用面接前に「人間はどういうバイアスを持ちやすいか」を通知する(Howard Ross, W106)といった例が挙げられていました。
まとめ
頻出キーワードは「無意識」
- 人材開発では「無意識の意識化」が基礎的課題
- 「無意識の意識化」はITで解決できる可能性がある
- 第1回は、山本が聴講してきた内容から考えられるキーワードをお届けしました。他のサイトとは、一味違う内容になっていると嬉しいです。
次回は、注目したセッションを抜粋して、少し詳しくお届けする予定です。
(次回へつづく)
担当者紹介
研究テーマ:エンゲージメント
担当者:山本 純一
コメント:元物理屋、元プログラマー、元スパコン屋なのに、なぜか組織を研究しています。
連絡先:NECソリューションイノベータ株式会社 イノベーションラボラトリ ウェルビーイングAIグループ
