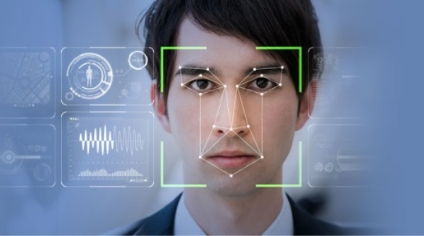サイト内の現在位置
コラム
東日本大震災の地震から10年
進化した「防災テック」で企業を守れ
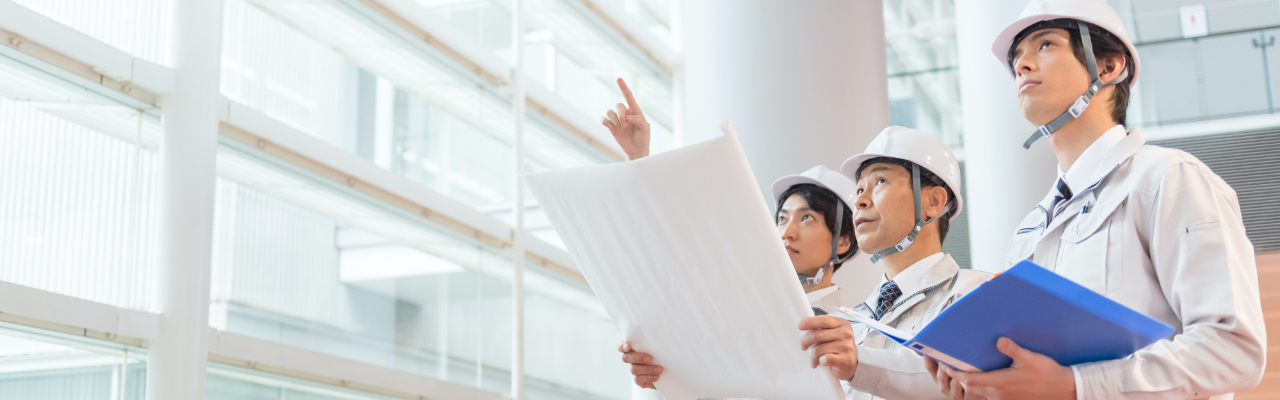
UPDATE : 2021.04.02
既存の産業やサービスにICT技術を導入して新たなビジネス領域を創造する「クロステック(X-Tech)」という考え方が広がっています。その中で、特に大きな注目を集めている存在が、防災にテクノロジーを導入する「防災テック」です。
2011年3月11日に発生した東日本大震災は、人、地域、そして企業の防災に対する考え方を大きく変えました。それから10年が経過した今、防災テックは大きな進化を遂げています。
近年では、VRを使った避難訓練、AIやビッグデータを用いた災害予測、そして震災時の避難所問題から学んだ被災者支援システムなど、特にICTを活用した防災テックが次々と誕生しています。
今回は、そのような自然災害に備えた防災訓練や対策など、最新の「防災テック」についてご紹介します。
INDEX
-
自然災害大国ニッポンに欠かせない
「防災テック」とは -
間接倒産9割、1千万円以上の損失3割
企業は自然災害による損害を回避できるのか? -
【災害が起きる前に】
VRやAI・ビッグデータを活用した防災テック- VRを用いた防災避難訓練
- ビッグデータを活用した津波予測システム
- AIを活用した浸水予測AIシステム
- 測位衛星データをもとに前兆を検出する地震予測アプリ
-
【災害が起きてしまった後も】
テクロノジーを活用した安否確認・被災者支援- BCP策定の第一歩は安否確認から
- 災害時のツイートを解析し“被災地を見える化”
- 張り紙ではなく顔照合システムでの安否確認
- まとめ
自然災害大国ニッポンに欠かせない
「防災テック」とは
「防災テック」とは、「防災」と「テクロノジー」を掛け合わせた造語です。自然災害の発生予測、現場の状況確認、災害時の情報通信、被災者の生活支援など、災害によって発生する様々な問題をテクノロジーで解決することを指しています。
近年、日本では自然災害が多発していることもあり、防災テックに対する関心が急速に高まっています。
東日本大震災から10年が経過した今でも余震は続いており、気象庁の発表によると2021年2月11日までに、マグニチュード6.0〜6.9の余震は120回。マグニチュード7以上は10回発生しています。
世界有数の火山大国でもある日本は、111もの活火山を抱えており、これは世界の活火山の約1割を占めています。これらの活火山は、常に大規模噴火の可能性を秘めています。
その他にも、多発する豪雨・豪雪、台風の巨大化などの問題にも適切な施策を取らなければなりません。2020年より訪れているコロナ禍も自然災害の一種と言えるでしょう。このように、日本は自然災害と常に隣り合わせなのです。
これらの自然災害に備えるため、内閣府は2020年2月13日に「防災×テクノロジー タスクフォース」の設置を発表しました。このタスクフォースは、「内閣府副大臣の下、内閣府及び内閣官房の防災対策、科学技術・イノベーション政策、IT 戦略、宇宙政策等を担当する部局が連携して、防災対策における ICT や新たなテクノロジーの活用を進めるための施策を検討」を目的としたものです。
大規模な自然災害は、国、企業、そして人に、様々な面で甚大な被害を与えます。災害が隣り合わせである日本にとって、防災テックは喫緊のテーマであるとも言えます。
間接倒産9割、1千万円以上の損失3割
企業は自然災害による損害を回避できるのか?
自然災害がもたらす被害には、自社の被災で発生する「直接的な被害」に加えて、顧客やパートナーの被災で発生する「間接的な被害」と2種類あります。企業にとってより深刻な影響を及ぼすのは、後者の間接的な被害です。
2020年3月に東京商工リサーチが発表した調査結果によると、「東日本大震災」の関連倒産は、108カ月連続で発生し、累計1,946件(2020年2月29日時点)に及びます。被害パターン別の内訳を確認すると、事務所や工場などが直接損壊を受けた「直接型」が11.5%、取引先・仕入先の被災による販路縮小などが影響した「間接型」が88.4%。間接型被害が大半を占めています。
「2019年版 中小企業白書」から「被災によって受けた被害内容」の内訳を調べてみると、「役員・従業員が稼働不可能となる」が44.5%と最も多くなっています。その一方で「販売先・顧客の被災による、売上の減少」が39.1%、「仕入先の被災による、自社への原材料等の供給停止」が25.7%と、取引先や仕入れ先の被災による間接的な被害も少なくありません。
被災時における物的損失額は、従業員の規模にかかわらず、100万円以上の損害を受けた企業が約7割以上。1,000万円以上の損害を受けた企業は約3割を超えています。
また、被災して取引先数が減少した企業の約5割以上が、「被災前の水準に戻るまで1年以上の期間を必要とした」、もしくは「元の水準に戻っていない」と回答しています。
これらのことから、防災テックは自社のみならず、取引先や仕入れ先なども含めた広い視野で検討する必要があることがご理解いただけるでしょう。
【災害が起きる前に】
VRやAI、ビッグデータを活用した防災テック
災害による被害を最小限に抑える手段として、近年注目を集める防災テック。どのようなものがあるのか、代表的なものをいくつか紹介しましょう。
VRを用いた防災避難訓練
まず、いつ起きるか分からない災害への防災対策として取り組みたいのが「避難訓練」です。
株式会社理経は、企業や自治体向けの災害訓練サービス「防災訓練用VR」を開発。VR(バーチャルリアリティ)技術を用いて災害を疑似体験できるものです。災害訓練は広いスペースや大がかりな準備を必要とするケースが多く、災害状況の再現は容易にできるものではありません。しかし、VRを用いれば、数人程度の小人数でも手軽に災害訓練が実施できるようになります。現実に近い質感で火災や水害などを映像で再現した状態で訓練するため、実際の災害に遭遇したときも冷静な対処が行えると期待されています。

ビッグデータを活用した津波予測システム
また、東日本大震災では津波による深刻な被害を受けましたが、その津波の被害を予測するシステムも開発されています。2018年5月に東北大学や東北大学ベンチャーズパートナー、NEC、国際興業などが共同で設立したRTi-cast(アールティアイキャスト)は、「リアルタイム津波浸水・被害推計システム」を提供。このシステムは、津波減災ビッグデータ解析などから地震発生後の津波の発生判定、断層の推定、津波初期水位の計算、津波浸水シミュレーション、被害予測を最短20分で可視化、配信。津波発生とほぼ同時に被災場所と被害状況が一目でわかるので、被災者の救助や復旧作業がより迅速に行えるようになるでしょう。
AIを活用した浸水予測AIシステム
東京大学発のベンチャー企業であるArithmer(アリスマー)も、高度数学と最新のAI技術を活用した「浸水予測AIシステム」を提供しています。ドローンの測量データから3D地図を高速作成し、3D地図の地形データをもとにAIが降水量や河川の決壊箇所などの浸水状況を予測。このシステムを使えば、家屋1軒ごとにセンチメートル単位での浸水状況の予測が可能です。
東日本大震災で大きな被害を受けた福島県広野町が、被災状況を事前確認できる対応措置として、全国で初めて「浸水予測AIシステム」の導入を決定しました。
測位衛星データをもとに前兆を検出する地震予測アプリ
そのほか、株式会社地震科学探査機構(JESEA)が開発した「MEGA地震予測」では、天気予報と同じ感覚で地震の予測情報を配信。測位衛星データから地殻変動の情報を読み取り、今地殻のどこにひずみが蓄積しているのかを解析し、大地震の前兆を検出します。JESEAの研究により、これまで予測困難とされていた地震の日時や場所、規模を正確に特定できる日もそう遠くはないかもしれません。
【災害が起きてしまった後も】
テクロノジーを活用した安否確認・被災者支援
ここまでは、災害の発生前(もしくは発生時)の防災テックについて紹介しましたが、災害が発生した後を支援する様々な防災テックも開発されています。
前述したように、東日本大震災では間接被害型の倒産が約9割を占めており、被災後も安定した業績を保つために、BCP(事業継続計画)の策定が重要となっています。近年では、多くの企業がBCP対策システムやツールを導入しています。
BCP策定の第一歩は安否確認から
例えば、関西電力グループの気象光学研究所が提供する安否確認システム「ANPiS(アンピス)」では、気象庁から配信される災害情報を自動で一斉配信し、従業員の安否や出社可否などの確認結果を自動で集計。シンプルな設定で簡単に操作できるため、企業、自治体や学校など幅広い組織に活用されています。BCP対策の第一歩として、このようなシステムを導入する企業も増えているようです。
関連記事:「シリーズ BCPの視点 第1回 災害対策、危機管理対策を織り込んだ事業継続力向上のシナリオづくりへ」
災害時のツイートを解析し“被災地を見える化”
昨今では、被災状況をいち早く把握して迅速な災害対応を行う手段として、SNSの活用が注目されています。Twitter JapanとNTTデータ、NECの3社が共同開発した「高度自然言語処理プラットフォーム」は、Twitterに投稿された被災状況や避難場所などの情報を可視化・解析するソリューションです。2つのAIを用いて、すべての投稿を災害カテゴリや地名で分類して画面に表示します。Twitterは真偽不明な投稿も少なくありません。事実と異なる投稿を検知して表示する機能も搭載されているので、様々な情報が飛び交う災害時でも正確な情報を入手して、安全な場所に避難できます。
張り紙ではなく顔照合システムでの安否確認
大規模災害では通信基地局の損壊により通信手段が限定されてしまう可能性もあります。東日本大震災では、携帯電話が繋がりにくい状態となり、家族や知人の安否を調べるために避難所の掲示板に張り紙をするなどの手段がとられました。
そのような課題を解消する手段の一つが顔認証です。株式会社理経が提供する「避難者顔照合システム」は、各避難所に設置されたカメラの前を通過した人を高速で撮影・登録してデータベースに保存。安否を確認したい人は自分のスマートフォンなどに保存されている写真をアップロードし、データベースに登録された写真と照合して、個人の居場所を特定することができます。
このように、災害発生後を支援するため、様々なテクロノジーを活用した安否確認や被災者支援システムなどが日々開発されています。
まとめ
現在防災テック市場は、日本をはじめ世界各国で注目されています。米GoogleやIBMなどのグローバル企業から、AI開発やデータ解析を得意とする振興のベンチャー企業まで、多種多様な企業が続々と参入しています。
今後、防災テックのテクノロジーはますます進化していくでしょう。ただし、地震をはじめとする自然災害の発生時間や発生場所などを正確に予測できる技術が商用化されるには、もうしばらく時間がかかりそうです。
いつ、どこで起こるかわからない自然災害に備え、現在の最新のICTを活用して「今、できること」から始めるようにしましょう。