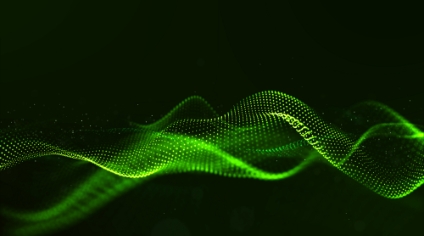サイト内の現在位置
専門家コラム
「COVID-19」を経験した教育現場と教育ITの今後
- 【執筆者】武田 一城氏 株式会社ラック
- インテグレーション推進事業部 チーフマーケティングアドバイザー(特定非営利活動法人 日本PostgreSQLユーザ会 理事)

UPDATE : 2021.12.17
世界中で数多くの感染者を出した新型コロナウイルス「COVID-19」の影響で、日本の教育現場は本格的にオンライン授業に移行したが、成功例はほとんどなかった。日本は世界トップクラスの通信インフラと教育水準を誇るにもかかわらず、オンライン授業をはじめとする教育ITがなぜ根付かないのか。その要因と日本の教育ITの今後について、システムプラットフォーム、セキュリティ分野のマーケティングスペシャリストとしてIT業界で活躍するラックの武田 一城氏が詳しく述べていく。
日本の教育と教育ITの現状
現在の日本は、世界での地位は一時よりは落ちてきているとはいえ、今でも米国と中国に次ぐGDP世界第3位の経済大国だ。そして、情報通信インフラでも世界のトップレベルと遜色がないレベルだ。 海外とビジネスをしているとよくわかるが、日本の通信品質の高さは非常に大きな意味を持つ。
2020年代ともなると日本に限らず世界各地でブロードバンドという広帯域ネットワーク網が普及している。そのため、すでに世界中のどこでも通信品質は日本同様だと思われがちだが、海外では同じ国でも地域によって、通信環境にばらつきがある。それに比べて日本は人が住んでいるところであれば、ほとんどの地域で光ファイバーを使った高速通信ネットワークが利用できる。この点は、ITに限らず全国一律にインフラ整備をしがちな日本の政策が良い方に転んだ典型例だろう。
そして、全国に張り巡らした情報通信インフラはパンデミック発生時においても有効に機能し、何の問題も無く学校教育が実施された――となれば良かったのだが、現実はそれほど甘くなかった。
日本は、世界有数の教育国と言って良いだろう。全国に約25,000校におよぶ小中高校が存在し、47都道府県のどこに居ても、基本的には同レベルの教育を受けることができる。もちろん、大都市圏の中高一貫の名門校と過疎が始まっている地域で全くレベルの差が無いとは言えないものの、各種の制度を活用すれば、本人の学ぶ意識で何とかなるレベルの差と言っていいだろう。少なくとも日本において、明確な教育格差と呼ばれるようなものは、ほとんど無いと言える。
2020年春からのパンデミック発生が直接的な原因となって、日本各地でオンライン授業がはじまった。この場合のオンライン授業のメリットや実施理由は、その時点では「学校に行かなくて済むのでCOVID-19感染の危険が回避できる」という1点だけだったと思われる。結局のところ、緊急事態宣言による休校が決まり、それが長期になることから、学習カリキュラムの実行が難しくなった。長期化する緊急事態宣言に対応するため、オンラインによる授業が実施された――これが日本初の本格的なオンライン授業開始の大まかな顛末と言えよう。
しかし、ITインフラのレベルは高かった日本であったが、それがそのままオンライン授業の成功に繋がらなかった。その理由は、オンライン授業を含む教育ITを実施する環境が整っていなかったことが最大の要因だ。
もちろん、ここで言う教育IT環境は、パソコンやタブレット、校内のネットワーク機器などのモノではない。ここ数年の教育ITの盛り上がりもあって、中高一貫の私立高校や先進的な教育ITを実施していた自治体などではそれなりに整っていたからだ。
しかし、肝心の教育コンテンツやITを使って教師と生徒をどのように結び付けるかという、肝心の部分が整備されていなかった。これは、まさかこれほどの大規模なパンデミックが発生すると想定されていなかったこともあるが、明治期の学校令から連綿と築き上げてきた日本の教育システムにITを上手に組む込むことが出来ていなかったことが最大の理由だろう。そのため、多くの学校でオンライン授業が通常の授業と同じように何の問題もなく実施されたというような例はほとんど見られなかった。
世界の教育ITの事情
OECDでは生徒の学習到達度調査(PISA)という統計データを定期的に発表し、その調査結果を3年ごとに教育水準を測る指標として「読解力」「数学的リテラシー」「科学的リテラシー」の3つのランキングとして公開している。
2021年10月時点で最新となる2018年のデータから、読解力は11位であるものの、数学的リテラシーは1位、科学的リテラシーは2位と、日本の生徒は文句なしにトップクラスの学力と言える。この結果は、日本の教師や生徒の質、ひいては教育水準や制度が非常に高いことを示していると考えてよいだろう。例えば、日本の教師が行っている板書の技術や授業における様々な工夫などは世界に誇ってよいレベルであり、それらが日本の教育を支えていると言える。
しかし、PISAには「ICT活用調査」というものがあり、それによると、日本は学校の授業(国語、数学、理科)におけるデジタル機器の利用時間が短く、OECD加盟国中で最下位だという衝撃的な事実が判明した。
しかも、「ネット上でチャットをする」「1人用ゲームで遊ぶ」というような項目は、双方ともOECD平均を大きく上回っている。これはスマートフォンや携帯ゲーム機のようなデバイスや家庭でのインターネット利用という個人での活用や普及が進んでいることを示している。それに対して「コンピュータを使って宿題をする」という項目では、OECD平均が22.2%に対して、日本は3.0%の利用に留まっており、教育分野でのITの普及がOECD加盟国中でも非常に遅れていることが顕著に表れてしまった。
[出典]文部科学省 国立教育政策研究所「OECD 生徒の学習到達度調査2018のポイント」
先述のPISAの調査結果は2018年のデータなのでパンデミックの状況を示していないものの、この調査からパンデミックまでの2年間で日本の教育現場で劇的に変わる事件などがあった事実は無かった。また、世界でも日本同様にパンデミックが発生したことを鑑みると、現在でもこの傾向は変わっていないと思われる。つまり、日本は世界でも有数と言える教育を実現できている。しかしながら、教育分野におけるIT化は非常に遅れているという事実がこのデータから推測できる。
教育ITが普及しない3つの要因
これまで、日本の教育現場は教育ITの効果については懐疑的だったと思われる。国家の教育政策としては、何度かIT化を模索したものの、普及して来なかったからだ。もちろん、中高一貫の私立学校、首長が教育ITに熱心な地方自治体、そして精力的に教育ITを実践している教員が個人プレイの延長として地域ごと教育IT熱を高めた場合などもあった。しかし、日本全体として教育IT熱は高まらなかった。
教育ITが普及しなかった最大の要因は、教育現場のモチベーションの低さが無視できない。教育現場は、ITの何が問題で導入を推進しないのだろうか。それを考察していくために、筆者が教育ITの普及しない要因と考えている以下の3点を述べていく。
●要因①: IT運用の問題
ITは各端末やネットワークが本来の動作をさせるための一定の運用をする必要がある。ITの運用とは、機器の故障時の対応はもちろんOSやファームウェアのバージョンアップなどがあり、適切にITを運用することが求められる。ITリテラシーの高い企業などでは、この分野の専門知識をもつ専任のシステム担当者が居ることが普通だが、学校においては大学や専門学校等にしか専任のシステム担当が居ないのが一般的だ。そのため、ほとんどの小中学校は、ITの運用に現場の負担が増大することが考えられる。
●要因②:現場で最適化された教育技術とのすり合わせの問題
教育が数値化して管理することが難しい分野であったため、ITの歴史において効果が出にくい分野とされてきた。そして現在、講義や実験動画などのリッチコンテンツが充実しつつあり、教育分野でITの効果が表れ始めているが、教室における教育技術と全て折り合いがついている訳ではない。日本は、津々浦々に高い教育技術を普及させることにすでに成功していたこともあり、ITとどのように共存させていくかというすり合わせが難航している感がある。
●要因③:教育IT実施の意思決定の問題
日本は、太平洋戦争の敗戦によって、それ以前の軍国教育的な教育制度への反省から国家ではなく地方自治体が教育方針を決めることが前提の制度となっている。そして、それを担う機関が県や市区町村にある教育委員会だ。しかし、教育委員会はあくまでも地方自治の組織の延長線上にあり、その地域の商工会の方などが委員になることも多く、教育の専門家とは言いにくい。またITに関しても同様であり、現状では私立校では理事長および校長、公立校では運営する自治体の首長の示す方針で意思決定がなされている。
このような要因が複雑に絡み合っているのが日本の教育ITの現状だと言える。教育方針を決定する人が、ITの専門家でも教育の専門家でもなく積極的な推進が難しいこと。また、ただでさえ忙しい教育現場にIT運用という大きな負担が増えること。さらに、既存の授業のやり方とのすり合わせが未だ出来ていないことなどが重なっている。
そのため、できるところから教育ITを推進していくという意見は概ね賛成だが、その場合は、教育格差と情報格差がダブルパンチの状態となることが懸念される。さらに、複数世代に渡って格差が固定されることも避けねばならず、このような推進をするならば、格差の是正処置を併行することが必要となる。
パンデミックを経験した世界における教育ITの今後
COVID-19のパンデミックによって、集団で学ぶというこれまでの常識が不可能になるまさに緊急事態の状況に世界は陥った。そのため、学校では登校しなくても学習ができる方法として、オンライン授業が全世界で実施されることになった。
今後については、COVID-19自体の脅威もさることながら、それ以外の細菌やウイルスの脅威もあり、社会全体がパンデミックの発生を前提とした仕組みを整備する必要があるだろう。その意味でのオンライン授業や教育ITの活用は、必須になっていくだろう。
そして、パンデミックでオンライン授業のことばかりが取り沙汰されたが、教育ITの本来のメリットはそれだけではない。特に21世紀に入ってからは世界の発展の中心は、ITとなってきている。もちろん、英語や数学などの従来科目の重要性は変わるものではないが、ITを学生時代に習得できていれば、それだけで社会の荒波を渡る上で大きな武器になる。そのため、これからの教育には従来の科目だけでなくITを学んでおく必要性が増している。
ただし、IT分野の進化は非常に速い。ソフトウェア開発環境やITインフラは一般的に5年以上使われることは無いため、あまりに特化した教育ではなく、技術の方向性が多少変化しても対応できる基本的な考え方を学ぶべきだろう。
その考え方とは、コンピュータに命令する時にどうすれば伝わるかというコンピュータとのコミュニケーションだと言える。コンピュータを動かすための作法や仕組みをわかっていることが、IT中心となった社会を生きていく上で重要な知識となる。そして、それが礎となり応用も可能になれば、様々な知恵も生まれてくるようになるだろう。
このように、COVID-19によるパンデミックは、日本の教育ITの利用を急激に拡大させる契機となった。しかし、教育でITを本格的に利用する環境が整ったとは言い難い。日本流教育ITが成功するまでには、様々な創意工夫や紆余曲折がまだまだ必要となるものの、教育とITがうまく融合しなければ日本の未来は暗いものになる可能性が高い。そのため、教育ITの成否こそが、50年後の日本発展の試金石になっていると言えるかもしれない。

■執筆者プロフィール
武田 一城(たけだ かずしろ)
株式会社ラック インテグレーション推進事業部 チーフマーケティングアドバイザー
(特定非営利活動法人 日本PostgreSQLユーザ会 理事)
2000年問題の真っ最中である1998年にIT業界に就職。インターネットビジネス草創期にマーケティングと戦略の重要性に目覚め、システムプラットフォーム、セキュリティ分野におけるマーケティングスペシャリストとなった。製品・サービスの新規立ち上げの実績を数多く経験。特に次世代型ファイアウォール分野では日本市場の立ち上げ自体に大きく貢献した。現在では、web/雑誌の執筆実績も多数あり、アニメやゲーム、城郭などのたとえ話でわかりやすいセキュリティの解説などで定評がある。その他、日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA)や情報処理推進機構(IPA)のワーキンググループ・委員会活動と共に、セミナー講演なども精力的に実施している。