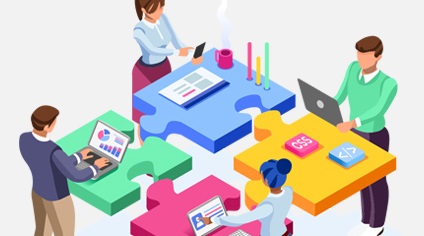サイト内の現在位置
コラム
これで安心!入社手続きで必要な
準備や書類を徹底解説

UPDATE : 2022.01.18
社員を採用すると、人事労務担当者は必要な書類を迅速に用意し、手続きする必要があります。本記事では、採用にあたっての事前準備や必要な書類について詳しく解説します。
後半には、人事労務担当者が入社手続きで苦労しがちなポイントにも触れるので、スムーズに入社手続きを進めるための参考にしてください。
INDEX
- 社員が入社する前に人事労務担当者がやっておきたい準備とは
- 雇用契約書・労働条件通知書の準備
- 内定通知書の準備
- 入社承諾書・誓約書の準備
- 入社手続きで必要になることが多い書類とは
- 扶養控除等申告書
- 健康保険被扶養者異動届
- 雇用保険被保険者証
- 源泉徴収票
- 年金手帳
- 給与振込先の届書
- 状況次第で判断!会社によっては必要な書類について
- 住民票記載事項証明書
- 健康診断書
- 身元保証書
- 従業員調書
- 卒業証明書
- 免許および資格
- 計画が大事!人事労務担当者が入社手続きで苦労しがちなポイントとは
- 帳票作成
- 必要書類の紛失対応
- 外国人の入社手続き
- まとめ
社員が入社する前に人事労務担当者がやっておきたい準備とは

採用された従業員が安心して入社できるように、入社前に雇用契約の内容や労働条件を明確にしておかなければなりません。この段落では、従業員が入社する前にやっておくべき準備について説明します。従業員がスムーズに入社手続きをするための準備の参考にしてください。
雇用契約書・労働条件通知書の準備
まず雇用契約書と労働条件通知書の準備をしなければなりません。雇用契約書と労働条件通知書は、使用者(会社)と従業員との間における労働条件の取り決めを要約したものです。雇用契約書と労働条件通知書の違いは、誰が書類に署名又は記名押印をしているかの差で、使用者と従業員両方の署名又は記名押印がある方が雇用契約書、使用者側のみが署名又は記名押印をしている方が労働条件通知書です。
事前に口頭で労働条件などの説明をするだけでは、「言った」「言っていない」のトラブルが発生する可能性があるため、使用者が従業員に対して行った説明を文書化することで、従業員との入社後のトラブルを防止する役目があります。労働条件は、正社員や契約社員、アルバイトなどの雇用形態や労働時間、業務内容に関係なく、使用者と従業員の双方が共有しておくことが重要です。
内定通知書の準備
従業員に対して採用の意思を伝えるために、内定通知書(採用通知書)を作成します。内定通知書は使用者から従業員に対して感謝を示す形式的な書類です。一般的には、内定通知書の他に入社承諾書と誓約書をセットにして送付することが多く、内定通知書には従業員の入社意志を再度確認する目的も含まれています。内定通知書に記載しなければならないポイントは、「採用応募についての御礼」「採用内定のお知らせ」「同封書類の案内」「入社日」「提出が必要な書類と提出期限」「問い合わせ先(人事担当者の連絡先、担当者名など)」の6点です。もし入社日が未定の場合は、別途連絡する旨を記載しておきましょう。
入社承諾書・誓約書の準備
内定者が入社するのかどうかの意思を確かめるために、入社承諾書・誓約書を作成する必要があります。前述したように、内定通知書とセットで送付し、署名や押印をしてもらい返送してもらう形が一般的です。そのため、入社承諾書・誓約書を送付するときは、返信用封筒を添えておきましょう。なお、形式や記載する内容は企業によってフォーマットが異なりますが、就業規則や守秘義務、履歴書の記載事項、損害賠償などについての事柄を記載することが多いです。
入社手続きで必要になることが多い書類とは
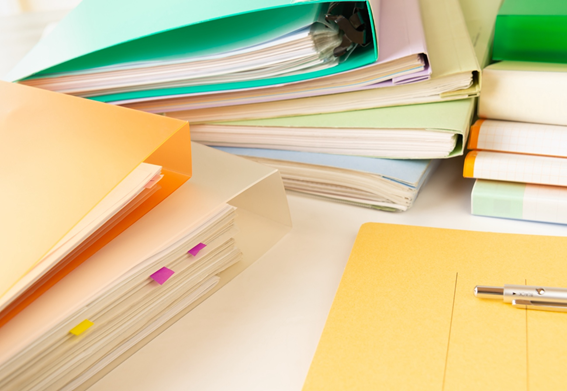
内定者の入社が決まったら、入社時にさまざまな書類を提出してもらわなければなりません。この段落では、大抵の会社で必要となる書類の種類について解説します。
扶養控除等申告書
社会保険や税金の手続きで必要な書類が扶養控除等申告書で、給与所得者の所得税の源泉徴収額を決めるときに使われます。扶養控除等申告書は会社側で用意する必要があり、扶養家族がいない場合でも提出は必須です。記載する内容によって、配偶者控除や扶養控除、障害者控除などを受けられるため、必ず入社する際に記入してもらいましょう。なお、捺印は認印でも問題ありません。
健康保険被扶養者異動届
健康保険被扶養者異動届は社会保険の手続きに必要な書類です。この書類は、扶養義務のある家族がいる場合のみ提出してもらいます。扶養控除等申告書と同じく、フォーマットは会社側で用意しなければなりません。新卒入社の場合でも扶養義務のある家族を持っている可能性があるので、扶養家族の有無を入社時に確認しておく必要があります。捺印に関しては、扶養控除等申告書と同様に認印でかまいません。
雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者証は雇用保険に加入させるために必要な証明書です。新卒入社の場合は、雇用保険に加入していない場合があるので、雇用保険被保険者証の新規加入手続きをする必要があります。中途採用の場合は、退職時に本人に雇用保険被保険者証が返却されるため、入社時に本人が所持している場合が多いです。もし、本人が所持していなければ、前職の会社が預かっているケースが多いので、返還を求めて提出してもらいましょう。なお、本人が紛失していた場合は、管轄のハローワークで再発行してもらえます。
源泉徴収票
年末調整をする際に必要な書類が源泉徴収票です。源泉徴収票は前職を退職するときに受け取る書類で、中途採用だけでなく学生時代にアルバイトをしていた学生も該当します。4月や10月など年内に入社する場合は提出が必須ですが、入社が年明けの場合は提出してもらう必要はありません。源泉徴収票は年末調整をする時期に必須な書類なので、入社時の手続きに必ずしも必要というわけではありませんが、忙しい時期に慌てなくて済むように入社時に受け取っておくのが効率的です。
年金手帳
年金手帳は厚生年金に加入させるために必要です。基本的に年金手帳は会社が保管するものなので、前職を退職する際に本人に返却されるようになっています。会社によっては、年金手帳を従業員本人に管理させる場合もあるため、厚生年金の加入手続き終了後に社員に返却するのか決めておくのが無難です。なお、年金手帳を紛失していた場合は、社会保険事務局で再発行してもらえます。通常であれば、申請から2週間程度で自宅に郵送されるので、従業員の手元に届いたらすぐに持ってくるように伝えておくことも重要です。
給与振込先の届書
従業員に給与を振り込むために、給与振込先の届書も提出してもらう必要があります。給与振込先の届書には、給与を振り込むための口座情報を記入してもらわなければなりません。会社側でフォーマットを用意し、支店名や口座番号、口座名義人などの必要事項を記入してもらいましょう。会社によっては、支店名や口座名が記載された銀行通帳のページのコピーの提出を求める場合もあるので、自社ではどうするのか決めておくことが重要です。なお、給与振込先の届書の捺印は、銀行に届けている印鑑を使う必要はなく、認印で問題ありません。
状況次第で判断!会社によっては必要な書類について

会社によっては、これまで紹介した書類以外にも入社時に提出してもらわなければならない書類がいくつかあります。この段落では、場合によっては必要になる書類について解説します。
住民票記載事項証明書
履歴書と同じ住所に住んでいるか確認し、住民税の支払いを適切に行うために必要な書類が住民票記載事項証明書です。住民票記載事項証明書のフォーマットは会社で用意する必要があり、従業員が氏名や住所を記入した後、役所の窓口に持参してもらい証明印を押してもらわなければなりません。郵送で受け付けている市区町村もありますが、役所は平日しか開いていない場合が多いので、いずれにしても余裕を持って提出日を設ける必要があるでしょう。
住民票を提出してもらう方法もありますが、会社にとって不要な個人情報も記載されており、個人情報保護の観点からリスクを避けるために、住民票を提出させる会社は減ってきています。必要な情報だけを確認可能な住民票記載事項証明書を利用するのが無難です。
健康診断書
健康診断書は、従業員の現在の健康状態を適切に知りたいときに提出してもらう書類です。診断項目は、会社の定期健診に準じた内容の健康診断を受けてもらうのが基本で、会社によっては入社時に健康診断を設けて、その結果を直接会社が受け取る場合もあります。健康診断書を統一したいときは、会社が受診場所を指定することも効果的です。また、従業員の年齢によっては、呼吸器系や心機能の検査などを行う生活習慣病検診を受診させなければならず、35~40歳以上の従業員を採用する場合は、生活習慣病検診を加えることも検討する必要があります。
身元保証書
身元保証書も必要な場合があります。入社後になにか問題が起きた際に、身元保証人が連帯して賠償責任を負うことを約束してもらうための書類です。身元保証書を提出してもらうことで、不法行為や債務不履行などで会社に損害を与えた場合に、賠償能力がない従業員に代わって責任を取ってもらうことができます。身元保証書は決められたフォーマットがなく、会社独自のものを用意し、肉親など保証人の条件などを定めておかなければなりません。従業員ではなく、身元保証人に押印してもらう必要があり、必要に応じて印鑑証明の提出を求める会社もあります。なお、特に指定がなければ、認印で問題ありません。
従業員調書
人事管理のための基本資料にしたい場合は、従業員調書の提出を求めるのが有効です。従業員調書とは、家族構成など従業員の情報が記載された書類で、従業員のデータを管理するのに役立ちます。ただし、従業員調書の記入を求めずに、履歴書で代替する会社も増えてきているため、提出物の削減を優先したい場合は、わざわざ用意する必要はありません。
卒業証明書
卒業証明書は、学歴が間違っていないかどうかを確かめるために提出を求めます。基本的には、新卒や第二新卒者に対して提出を求めることが多く、新卒者の場合はまだ卒業していないため、卒業見込証明書を提出してもらうことが一般的です。第二新卒者には、卒業証明書の原本ではなくコピーを提出してもらい、卒業証明書を紛失していた場合は、卒業校に申請すれば再発行してくれるので手続きを進めてもらいましょう。なお、中途採用には、卒業証明書を求めるケースはほとんどありませんが、必要な場合は提出を求めます。
免許および資格
職種によっては免許や資格が必要になるので、免許および資格関連の書類を提出してもらわなければなりません。たとえば、長距離ドライバーなどの運送業の場合は無事故証明書、通訳の仕事をする場合はTOEICの結果通知などが該当します。また、日商簿記1級や社会保険労務士など特別な資格を理由に採用した場合は、業務において必須ではない資格でも提出を求めましょう。なお、資格証明書を紛失している場合は再発行してもらえますが、時間がかかる可能性があるため、従業員には早めに通知しておくと業務効率がアップします。
計画が大事!人事労務担当者が入社手続きで苦労しがちなポイントとは
人事労務担当者が入社手続きをする際に、苦労しやすい代表的な事柄としては、以下の4つが挙げられます。
帳票作成
帳簿作成は最も時間のかかる作業のひとつで、労働者名簿や賃金台帳、出勤簿など、新入社員に必要な情報をすべて入力しなければなりません。情報を揃えることはもちろん、入力作業事態にも多くの時間がかかるので根気が必要な作業といえます。
必要書類の紛失対応
意外とありがちなのが、従業員が必要書類を紛失してしまっている場合です。
特に、雇用保険被保険者証書や年金手帳を紛失した場合は、ハローワークや社会保険事務局で再交付してもらう必要があり、入社手続きの作業スケジュールに大きく影響します。
必要書類が従業員の手元にないことを考慮したうえで計画を立てるようにしましょう。
外国人の入社手続き
外国人を雇う場合は、在留カードやパスポートの提出も必要なため、日本人よりも提出書類が多くなります。また、国外に在住している外国人を雇う場合はビザ申請が必要で、国内に住む外国人を雇う場合よりも、さらに手続きが複雑になります。
外国人を採用する場合は業務が多くなることを頭に入れて、スケジュールを決める必要があります。
まとめ
中途採用を活発におこなっている会社などでは、入社手続きは不定期に発生するものです。いつ従業員を採用しても対応できるように、必要な書類や手続きの流れをしっかり理解し、スムーズに作業できる体制を整えておきたいですね。
手早い対応は入社する従業員からの信頼感にも繋がります。ぜひ、本記事を参考にして入社手続きの準備をしておきましょう。