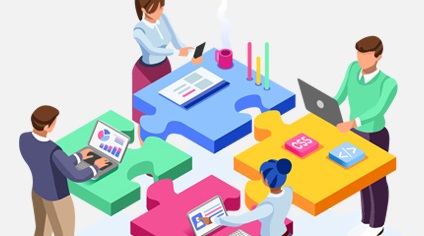サイト内の現在位置
コラム
有期雇用契約とは?
トラブル防止のために大切なポイント

UPDATE : 2022.01.25
企業と労働者の合意のうえで働く期間をあらかじめ定めておくことを「有期雇用契約」といい、企業側にとっては不足している労働力をピンポイントで補えるというメリットがあります。しかし、2013年4月にルール改正が行われたことで注意すべき点も以前に比べて多くなっています。
そこで、本記事では有期雇用契約の仕組みを説明するとともに、ルール改正によって何が変わったのかについても紹介していきます。
さらに、企業が有期雇用を結ぶ際の注意点も併せて解説します。
INDEX
- そもそも有期雇用契約とはなにか
- ポイントは3つ!改正労働契約法による有期雇用契約の変更点
- 無期労働契約への転換
- 雇止め法理の法定化
- 不合理な労働条件の禁止
- 企業が有期雇用契約を結ぶ際のポイント
- 契約期間・更新の有無をはっきりさせる
- 明確な労働条件を提示する
- 雇用契約を守る
- 有期雇用で対応が必須なこと
- 就業規則の用意
- 社会保険への加入
- 有期雇用契約を契約期間中に解除できるケースとは?
- トラブル防止!雇い止めのルールとは
- まとめ
そもそも有期雇用契約とはなにか
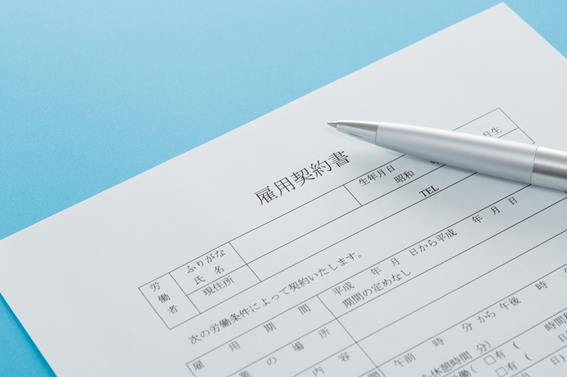
有期雇用契約とは企業と労働者が期間を定めて労働契約を結ぶことであり、労働基準法第14条1項にてその契約期間は最大で原則3年と定められています。ただし、これには例外があり、「高度な専門知識や技術」「特定の経験」「満60歳以上」などといった条件を満たせば、5年の契約期間が認められるようになります。そして、一度契約を締結すれば、その期間中はやむを得ない事由がない限りは企業側と労働者側のいずれに関わらず、原則として一方的に契約を終了することはできません。
ちなみに、有期雇用契約とは異なる契約方法に無期雇用契約がありますが、これは契約期間が存在せず、契約更新が必要ではない契約方法のことを指します。この契約を締結すると、やむを得ない事由がある場合を除いては期間に関わらず労働者を解雇することができなくなります。その代わり、労働者側は逆にいつでも退職する自由が認められることになります。
また、有期雇用と混同されがちな言葉に「正社員の試用期間」があります。確かに、正社員の試用期間は一定の契約期間が定められています。しかし、試用期間終了後は正社員として雇用することが前提となっており、有期雇用契約のように期間いっぱいで必ず契約が終了するというわけではありません。さらに、定められた契約期間中に正社員として雇用するか否かの判断がつかない場合は、試用期間を延長することも可能です。
ポイントは3つ!改正労働契約法による有期雇用契約の変更点
2013年4月に施行された改正労働契約法により、有期雇用契約のルールは大きく変化しました。一体どのように変わったのでしょうか。本段落ではその変更点を大きく3つのポイントに分け、それぞれ具体的に解説していきます。
無期労働契約への転換
有期雇用契約の第1の変更点として挙げられるのは、無期雇用への変換ルールの追加です。従来であれば企業と労働者の間で結ばれる労働契約が有期か無期かは完全に両者の合意に基づくものでした。ところが、改正後は有期労働契約が繰り返されて累計で5年以上になった場合、企業は労働者の希望に応じて無期雇用契約に変換しなければならなくなったのです。これは改正労働契約法第18条に定められており、全企業を対象としています。
そのため、条件を満たした有期雇用契約の労働者が無期転換を申し込んだ場合、企業側としてはこれを拒否することはできません。また、無期転換申込権が発生しないよう、早めに雇用契約を打ち切ってしまうのは好ましくないとされているため、無期雇用を希望する労働者への対応は慎重さが求められます。ただし、無期雇用への変換といっても、必ずしも正社員として雇用しなければならないという意味ではないので、その点は勘違いしないようにしましょう。求められているのはあくまでも契約期間を有期から無期に転換させることのみであり、待遇を正社員として扱うかどうかは別問題です。
雇止め法理の法定化
変更点の2つ目としては雇止め法理の法定化が挙げられます。これは最高裁判所においてすでに確立されていた「雇止め法理」を正式に法律として制定したものです。
ちなみに、雇い止めとは有期雇用契約労働者に対して労働契約の更新を認めないことを指しますが、法改正以降は企業側がこれを無制限に行えなくなったのです。具体的には、改正労働契約法第19条に定められており、有期労働契約の契約期間の満了時に労働者が契約の更新を希望しているとみなされる場合は、「客観的にみて合理的な理由があって社会通念上相当であると認められるとき」以外は雇止めを宣言しても無効になるとしています。これは雇止めが無条件に行われ、労働者が突然仕事を失うのを防ぐためのものです。
たとえば、何度も契約を更新し、実質的に無期雇用と変わらない状態にも関わらず、突然雇い止めをしても無効になります。また、有期労働契約者が「契約が更新される」と想定する合理的な理由があったのにも関わらず、雇い止めをした場合も同様です。
不合理な労働条件の禁止
3つ目の変更点は「不合理な労働条件の禁止」です。これは正社員ばかりを優遇し、非正規社員との間に理不尽な待遇格差が生じるのを防ぐ目的で定められたルールです。
改正労働契約法第20条に定められており、業務内容や責任の程度、あるいは職務の内容及び配置転換、さらにはその他の事情に関して無期雇用契約者と有期雇用契約者との間に不合理な差があってはならないとしています。代表的なものとしては賃金・労働時間・福利厚生・交通費などが挙げられますが、その他あらゆる労働条件に関して両者に差が出ることを禁じているのです。たとえば、通勤手当、食堂の利用、安全管理、災害補償や教育訓練に至るまですべて同じでなければならないというわけです。
もっとも、正社員とアルバイトなどの場合、最初から行っている仕事の性格自体が大きく異なっているため、そうした事情を考慮したうえでの合理的な区分は認められています。ただし、その場合でも、非正規社員と正社員で待遇に差が発生したときは、非正規社員はその理由を事業主に説明してもらうことができると定めています。
したがって、人事労務担当者のみなさんは、実際に説明を求められても即座に対応できるように日頃から準備しておくことが大切です。なお、労働条件などを巡って労働者と揉めてしまい、どうしても解決の目処が立たないという場合には都道府県労働局にて、無料の紛争解決手続きを行うという手もあります。そうすることで、事業主と労働者との間で裁判をしなくても問題の解決が可能となります。
企業が有期雇用契約を結ぶ際のポイント

企業が労働者と有期雇用を結ぶ際には注意すべきポイントがいくつかあります。本段落ではいざというときに困らないよう、その注意ポイントを3つの観点から説明していきます。
契約期間・更新の有無をはっきりさせる
まず気をつけなければならないのが、募集時もしくは契約時に契約期間や更新の有無を明示しなくてはならないという点です。口頭で説明しただけでは十分ではなく、書面やメールなどを用いて文書によって契約内容を明示することを義務付けられているのです。また、更新の有無については最初に「自動更新をする」「更新する場合もある」「更新はしない」のいずれかなのかはっきりさせ、そのうえで、更新をしない場合の基準を説明しておく必要があります。
ちなみに、主な基準としては「労働者の勤務成績・態度」「労働者の業務遂行能力」などが挙げられます。さらに、「会社の経営状況」や「契約満了時の業務量」などといった企業側の都合を基準に含めることも可能です。いずれにしても、雇用を巡る無用なトラブルを避けるために、契約時には単にそれらの内容を明示するだけではなく、企業と労働者の双方が納得のうえで雇用契約書を結んでおくのが望ましいといえます。
明確な労働条件を提示する
労働条件を曖昧にしておくとのちのちトラブルにつながる可能性も考えられるため、契約を結ぶ際には明確な労働条件を提示する必要があります。ちなみに、労働条件とは労働契約の期間、就業の場所、業務内容、賃金、労働時間、休暇・休日、保険適応の有無などです。
また、労働時間に関しては単に1日何時間というだけではなく、始業や終業の時刻や所定労働時間を超える労働は毎月どの程度あるのかなどについても説明しておいた方がよいでしょう。従事する業務内容が複数にわたる場合は代表的なものを一つだけ説明するといったやり方は避け、該当する業務についてはすべて記載しておくのが賢明です。
なお、労働契約を締結する際には、これらの労働条件を口頭で伝えるのではなく、書面や電子メールなどで交付しなくてはなりません。文面には上記の内容に加えて、「賃金の決定、計算および支払いの方法」「賃金の締め切りおよび支払いの時期」「解雇事由を含む退職の条件」なども記載しておきましょう。さらに、パートタイム労働者の場合は昇給の有無、賞与の有無、退職手当の有無などの説明が別途必要となります。これらについてもトラブル回避のために書面にまとめておくことが大切と考えられます。
雇用契約を守る
有期雇用契約を結んだならば、一方的に中途解雇することは原則として認められません。では、倒産や店舗閉鎖などのやむを得ない理由で解雇しなければならないケースの場合はどうでしょうか?
その場合でも定められた手順にしたがって行う必要があります。まずは、契約を結ぶ際に退職に関する事項を書面にて明示し、そのうえで、最低でも解雇する30日前にその旨を通達しなければいけません。
ちなみに、主な有期雇用契約の種類としては契約社員、嘱託社員、パートタイム・アルバイトなどが挙げられます。嘱託社員とは契約社員の一種で一般的には定年退職後に再雇用された労働者を指し、パートタイム・アルバイトとは労働時間が比較的短くて補助的・臨時的な業務を行う労働者のことです。いずれにしても、定めた期間の雇用契約を守らなければならないという点では皆同じです。
有期雇用で対応が必須なこと
有期雇用契約に基づいて労働者を雇う際には、契約の締結以外にも行わなくてはならないことがいくつかあります。
就業規則の用意
まず、自社に正社員用の就業規則しかない場合は、有期雇用契約の労働者を対象とした就業規則を別途で用意しなければなりません。なぜなら、有期雇用契約と無期雇用契約では賃金や有給休暇といった待遇面で差が発生するケースが多いからです。したがって、個別に就業規則を用意しなければ、有期雇用契約の労働者にも正社員と同じ就業規則が適用され、待遇面も同じにしなければならなくなってしまいます。
社会保険への加入
社会保険は雇い入れた日から加入の義務が生じます。もし、未加入だった場合は処罰の対象となるので注意が必要です、ただし、週の所定労働時間もしくは月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3未満、あるいは雇用の契約期間が2カ月以内の場合はその限りではありません。一方で、雇用保険に関しては週の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがあれば加入させる義務が生じます。
有期雇用契約を契約期間中に解除できるケースとは?
有期雇用契約を一度行えば、基本的には契約期間中の解除はできませんが、一部例外も存在します。
労働契約法第17条には「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。」とありますが、たとえば、天災による被害などによって事業継続が困難になった場合などが挙げられます。
ちなみに、中途解雇が認められるケースであっても雇用契約が2カ月以上の労働者に対しては解雇までの猶予期間を30日間置かなければなりません。もし、どうしても即日解雇しなければならないというのであれば、代わりに30日分以上の平均賃金を支払うなどの対応が必要です。
ただし、やむを得ない事由で企業が経営破綻した場合、あるいは懲戒処分を事由とする解雇、さらには日雇いの労働者、試用期間である労働者などといったケースにおいてはこれらの対応は不要となります。
トラブル防止!雇い止めのルールとは

有期契約労働者に対して雇い止めをする場合は守るべきルールがいくつか存在します。そして、そのルールに反した場合は、たとえ正当な理由があったとしても雇い止め自体が無効になりかねないので注意が必要です。まず、雇い止めを視野に入れたうえで有期契約労働者を雇うのであれば、契約締結の段階でその基準を労働者に明示しておかなくてはなりません。
また、更新の有無や判断基準に関して変更があった場合は、労働者に対してできるだけ早くその事実を明示する義務があります。
ちなみに、雇い止めの予告は期間満了の30日前までに行わなくてはならず、もし労働者が雇い止めの証明書を請求してきた場合には即座に対応し、遅延なく交付する必要があります。なお、厚生労働省が策定した「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について」という資料において、労働者の意に沿わない雇い止めはなるべくしないようにという努力義務を企業側に対して提言しています。具体的には、「契約を1回以上更新かつ1年を超えて継続して雇用している有期契約労働者との契約更新を行う場合、企業側は契約の実態や労働者の希望を踏まえたうえで、契約期間をなるべく伸ばすように努めなくてはならない」というものです。
まとめ
改正労働契約法施行にともなう有期雇用契約の変更により、以前のように企業側が自由に雇い止めを行うことは難しくなっています。それを知らずに有期雇用契約者に対して中途解雇などを行ってしまうと、思わぬトラブルに巻き込まれることにもなりかねません。
したがって、有期雇用契約を結ぶのであれば、契約に伴うルールを十分に把握し、そのうえで企業側は労働者に雇用契約や労働条件を明示することが重要になってきます。改正労働契約法や有期雇用契約などに対する理解を深め、雇用に関するトラブルを未然に防いでいきましょう。