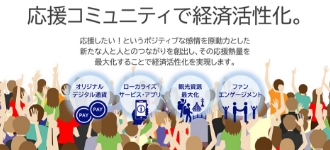サイト内の現在位置
コラム
デジタル地域通貨は地域活性化の切り札になるか

UPDATE : 2022.04.08
地域通貨とは、特定の地域やコミュニティ内だけで流通、利用できる通貨のことです。地域経済や地域コミュニティを活性化させる効果が期待でき、昨今ではデジタル地域通貨(電子地域通貨)が注目を集めています。本記事ではデジタル地域通貨がもたらす3つの効果や地域経済が活性化した成功例、課題、今後の可能性などについて解説します。
INDEX
- 地域通貨とは?
デジタル化により再注目される- 地域通貨と法定通貨の違い
- デジタル地域通貨とは?
地域経済の活性化と地域コミュニティのベースに- デジタル地域通貨がもたらす効果
- デジタル地域通貨により地域経済が活性化した成功例4選
- 【さるぼぼコイン】3年間累計で40億円のコインを販売(岐阜県高山市・飛騨市・白川村)
- 【negi】プレミアム商品券をデジタル化(埼玉県深谷市)
- 【アクアコイン】ボランティア活動で市から行政ポイントを付与(君津信用組合、木更津市、木更津商工会議所)
- 【かつしかPAY】非接触型キャッシュレス決済の利用促進で地域活性化(葛飾区商店街連合会)
- デジタル地域通貨の課題
- 運用・管理にあらたな労力が必要
- キャッシュレス決済との競合
- 地域通貨を持つ動機付けが必要
- デジタル地域通貨がもたらす可能性
- まとめ
地域通貨とは?
デジタル化により再注目される
地域通貨とは、特定の地域やコミュニティ内だけで流通、利用できる通貨のことで、地域経済や地域コミュニティを活性化させる効果が見込まれています。日本において、地域通貨は1999年発行の地域振興券が着想のきっかけとなり、2000年代前半にブームとなりました。全国で発行された地域通貨の数は延べ650(2019年12月時点)、稼働しているのは180程度(2020年12月時点)と言われています。
なかでも漫画『鉄腕アトム』にちなんで、東京都の高田馬場・早稲田で2004年に発行された「アトム通貨」は現在でも流通している代表的成功例。ですが、多くの地域通貨は維持管理コストや利用者数の伸び悩み、偽造の問題などから廃止や休眠状態になるのがほとんどでした。しかし近年、デジタル技術の進展、特にブロックチェーン技術の活用により従来の課題をクリアした「デジタル地域通貨」が登場し、再び注目を集めています。
地域通貨と法定通貨の違い
地域通貨は地域の自治体や企業、NPO、商店街などが独自に発行します。利用可能な範囲は地域および期間も限定されることが多いため、「今ここでしか買えない」購買心理を刺激し、地域内での経済循環を促す効果があると考えられています。また、貯蓄させずに流通を促す目的のため、無利子で資産価値を無くしているのも特徴の一つです。
一方、「日本円」や「米ドル」などその国の法律により定められた通貨が法定通貨です。国内どこでも使用でき、価値は国が保証しています。「通貨」とは正しくは法定通貨のみであるため、地域通貨は厳密にいえば「通貨」ではありません。
デジタル地域通貨とは?
地域経済の活性化と地域コミュニティのベースに
デジタル地域通貨とは、これまで紙幣型や通帳型だった地域通貨をデジタル化した電子決済手段です。技術発展やスマートフォンの普及もあり、現在はスマホアプリによるQRコード決済方式が主流となっています。従来の紙ベースの地域通貨に比べ、デジタル地域通貨は印刷コストや運用面での労力を大幅に削減。また、加盟店側にとってもQRコードを店頭に掲示しておくだけで済むので、導入のハードルが低いのも大きなメリットです。さらに改ざんや不正利用にも強いブロックチェーン技術により、偽造リスクも大幅に低減できます。
デジタル地域通貨がもたらす効果
期待が高まっているデジタル地域通貨。ここでは地域にもたらす効果をご紹介します。
地域内の経済が活性化し、循環する
近年ではオンラインショップなど生活地域外での購買機会の増加により、地域内における経済循環がますます困難になってきています。しかしデジタル地域通貨であれば、従来型の地域通貨と同様に、地域内店舗での買い物利用や店舗間同士の仕入れなどでの利用が期待できるでしょう。地域外への経済流出を抑え地域内の流通を活性化し、経済循環を促進します。また、公共料金や行政サービスの料金などにも使用できれば、行政コストの削減や地域住民の利便性向上にもつながります。
地域コミュニティのベースになり得る
デジタル地域通貨は主にスマホアプリ経由でやり取りされます。地域住民に日常的に使用されるアプリはコミュニケーションのプラットフォームとしても活用でき、地域コミュニティのベースにもなり得ます。例えば、地域事業者と住民や、住民同士との間で感謝や応援のためにチップ的に通貨を贈ったり、行政側から住民に通貨をポイントとして付与し社会的な取り組みへの参加を促したり、といったことも可能です。さらに、デジタル地域通貨アプリを行政手続きに利用すれば、公共料金等の支払いだけでなく、住民への広報や災害情報などの告知、あるいは住民から行政施策へ意見する際の伝達手段としての活用も期待できます。

経済活動が可視化されデータ活用が可能に
デジタル地域通貨では通貨利用によって発生した経済活動がデータ化され、可視化することができます。地域内における通貨の流れを把握することで、データに基づいたマーケティングリサーチが可能となり、経験則や他地域の成功事例の模倣など根拠が弱い施策ではなく、その地域に合致した客観的で具体的な施策を立案、展開することも可能となります。
デジタル地域通貨により
地域経済が活性化した成功例4選
実際にデジタル地域通貨を導入、運用して成果を挙げた成功例を4つご紹介します。
【さるぼぼコイン】3年間累計で40億円のコインを販売(岐阜県高山市・飛騨市・白川村)
飛騨高山の民芸品にちなんだ「さるぼぼコイン」は、岐阜県高山市、飛騨市、白川村の2市1村で2017年にスタートしました。発行主体は飛騨信用組合で、デジタル地域通貨の草分け的存在です。「さるぼぼコイン」は1コイン=1円に相当し、専用のスマホアプリでQRコードを読み取って支払います。コインの有効期限は1年、チャージは飛騨信用組合の窓口や専用チャージ機で行えるほか、全国のセブン銀行ATMでも可能です。2021年8月末の時点で、ユーザー数は22,000人、加盟店舗数は1,600店舗以上で累計決算額は42億円。「多産多死」と言われる地域通貨のなかではもっとも成功した事例の一つと言われています。
成功の理由としては、
・チャージでプレミアムポイントを付与(発行当時としては先駆的)
・市県民税や国民健康保険料、水道料金などの支払いも可能
・防災情報配信など地域のデジタル回覧板として機能
・情報サイト「さるぼぼコインタウン」で域外のコイン利用も可能にし、地域の「外から内」への流通経路も構築
などが挙げられます。
【negi】プレミアム商品券をデジタル化(埼玉県深谷市)
「negi(ネギー)」は深谷ネギで有名な埼玉県深谷市の地域通貨です。1negi=1円に相当し、有効期限は2年で、利用形態はスマホアプリとカードタイプの2種類。2019年に還元率10%を乗せた電子プレミアム商品券として、合計1億1千万negiを発行しスタートしました。
「ネギー」のアプリは現金やクレジットカードでチャージできるほか、全国のセブン銀行ATMでもチャージすることが可能です(カードタイプは現金のみ)。利用時はアプリでQRコードを読み取るか、カードのQRコードを読み取ってもらい支払います。取扱店は2022年3月現在で720店を超えました。「ネギー」はふるさと納税の返礼品にも使われるほか、コロナ禍の飲食店支援のためのポイント還元や若者への応援事業などにも活用され、地域活性化に寄与しています。
【アクアコイン】ボランティア活動で市から行政ポイントを付与(君津信用組合、木更津市、木更津商工会議所)
「アクアコイン」は千葉県の木更津市と君津信用組合、木更津商工会議所が連携して2018年10月にスタートしました。1円=1コインとして専用のスマホアプリで利用できます。「アクアコイン」は君津信用組合窓口や全国のセブン銀行ATM、プリペイドカード、チャージ機などでチャージでき、支払いはQRコード読み取りで行います。加盟店は2022年3月時点で700店以上。
木更津市は指定のボランティア活動などの参加者に対して、「らづポイント」というポイントを「アクアコイン」で配布しています。また住民の健康促進のため歩いた歩数に応じたポイントも「アクアコイン」で付与。さらに公共料金等の支払いにも利用でき、まさに官民一体となって地域経済とコミュニティの活性化、一体化を後押ししています。
【かつしかPAY】非接触型キャッシュレス決済の利用促進で地域活性化(葛飾区商店街連合会)
「かつしかPAY」は葛飾区商店街連合会が、区の支援を受けて2021年に発行したデジタル商品券。スマートフォンやタブレットで店舗に掲示してあるQRコードを読み取って決済します。1セット1万円で1万2,000円分(プレミアム率20%)の商品券として、事前申込制で50,000セット、発行総額6億円分を販売しました。利用可能期間は2021年10月から翌年1月末まで、加盟店数は2021年8月時点で約250店舗でした。
「かつしかPAY」はコロナ禍における非接触型キャッシュレス決済の普及と、地域店舗の支援、地域経済の活性化を促進したとしています。紙の商品券に比べて加盟店の負担が小さいことが、スピーディーな展開を可能にしました。
デジタル地域通貨の課題
地域活性化に多くの恩恵をもたらすデジタル地域通貨ですが、いくつか課題も存在します。
運用・管理にあらたな労力が必要
従来の地域通貨に対するデジタル地域通貨の大きなメリットは、導入や運用コストの削減です。確かに紙の地域通貨の印刷や管理業務、偽造対策などに伴うコスト、労力は大幅に削減できますが、デジタルならではの新たな手間が発生するのも事実。デジタルサービス供給元との関係構築やサーバーの管理、維持、セキュリティ対策などは不可欠です。また、紙ベースでもデジタルでも、利用者が減れば通貨価値が下がり発行元の負担だけが増加するという悪循環は変わらないため、依然として取扱店舗と利用者の拡大には常に努める必要があります。
キャッシュレス決済との競合
先述したデジタル地域通貨「さるぼぼコイン」が登場した2017年の段階では、まだキャッシュレス決済自体が目新しかったので、その便利さが普及を後押ししてくれる状況でした。しかし現在では「PayPay」を初めとする大手キャッシュレス決済サービスが全国どこでも普及し始めています。便利さが同じならば、利用者は取扱店舗の多さやキャンペーンのお得さなどで比較しがちなため、他サービスとの競合を強いられます。したがって、他のサービスにはない付加価値やメリットを提示しなければなりません。
地域通貨を持つ動機付けが必要
デジタル地域通貨であれ従来型であれ、地域通貨は利用可能な場所と期間が限定されています。域内の経済活性化のためですが、それはあくまで発行者側の論理であって、利用者からすれば不便なだけであり、いつでもどこでも使えるに越したことはありません。つまり地域通貨はそもそも不便さを強いるものなので、その不便さを補ってでも使いたいと思わせるだけの理由、動機付けが必要です。存続している地域通貨の多くが、「地域のために役立てたい」「地元のコミュニティを応援したい」「顔が見える関係を大切にしたい」といった、発行者と利用者双方の思いを可視化する面を備えているように、単なるお金やツールに留まらない「ストーリー」の設計も欠かせないでしょう。
デジタル地域通貨がもたらす可能性
デジタル地域通貨には確かに様々な課題も存在します。しかしながら、地域を豊かにする可能性は決して小さくはありません。デジタル地域通貨ならば、クレジットカードやキャッシュレス決済サービスでは地域の外に流出してしまう手数料を地域内に留めることができますし、アプリのメッセージ機能で店舗から利用者にお礼をするといった使い方も可能です。
自治体においては、サービス利用券などを代替させることで行政コストを削減できるほか、前述の「アクアコイン」のようにボランティア活動や健康促進活動と結びつけて住民の行動変容を促す、あるいは行政が住民に広報や告知を行うなど、地域コミュニティにおけるコミュニケーションの活発化、円滑化といった効果をもたらします。デジタル地域通貨は地域の基盤となるプラットフォームとして、地域経済のみならず、地域社会全体を豊かにする可能性を持ち得ているのです。
まとめ
日本で地域通貨が発行されておよそ20年。全国各地で実に多くの地域通貨が発行され、そのほとんどが廃止、休止を余儀なくされてきました。しかし技術発展やスマートフォンの普及などに後押しされて登場したデジタル地域通貨は、かつての地域通貨の課題を解決し、新たな展望を切り拓いています。
デジタルならではの課題もありますが、デジタル地域通貨は経済の活性化に留まらず、いまの日本の地域社会が抱える様々な課題にリーチできる切り札として、地域社会全体を活性化させるポテンシャルを有しています。特に、地域振興券等をすでに採り入れている自治体などにおいては、デジタル地域通貨の導入を検討してみてはいかがでしょうか。