サイト内の現在位置
未来を担う「将来世代」との
対話
FR(Future Generations Relations)活動でWell-being実現を目指す


人間が幸福感を感じるうえで欠かせない要素の一つである「豊かさ」。それは必ずしも物質的な充足だけで測れるものではありません。特に近年は精神的な、実感としての「豊かさ」の重要性が大きく見直されるようになってきました。そうした中で注目を集めているのが「Well-being(ウェルビーイング)」という概念です。NECソリューションイノベータも会社としてこの概念を追求。その取り組みの一環として、日本経済新聞社が立ち上げた「Well-being Initiative」に2023年度より参画しています。ここではその活動内容と現時点での成果について、この取り組みを推進するデジタルヘルスケア事業推進室主席主幹の山口美峰子とデジタルビジネス推進本部主任の栗原司に聞きました。
Well-being Initiativeは、Well-beingを
より深く社会に浸透させていくための企業横断の取り組み
まずは、NECソリューションイノベータが2023年度より参画している「Well-being Initiative」がどういった団体なのかを教えてください。
山口:これからの時代において「Well-being」という概念がますます重要な課題になっていくことは明らかです。そうした中、Well-beingの大切さをより多くの人たちに伝え、認知・理解していただけるようにしていくことがWell-being Initiative最大の目的の一つです。さらに、Well-beingを目に見えるようにしていくための指標を実装していくことも目指しています。Well-being Initiativeはこの主旨に賛同する企業や有識者・団体等が連携して、必要となる研究から、その成果の実践までを幅広く行う、コンソーシアム(共同事業体)のようなものです。

Well-being Initiativeにはどういった企業が参画しているのですか?
山口:日本経済新聞社での発足になりますが、企業経営において、人的資本経営や健康経営、事業戦略など様々な観点でWell-beingを重要視している26社(日本経済新聞社含む)が参画しています(2023年12月時点)。
NECソリューションイノベータがWell-being Initiativeに参加した背景についても聞かせてください。
山口:私が所属するデジタルヘルスケア事業推進室は、「誰もが健幸に、自分らしく生きられる社会の実現」をめざして、予防に貢献する技術開発、サービス開発に取り組んでおり、私はその中でも特にメンタルウェルビーイングのプロジェクトに携わっています。メンタルヘルスケアはマイナス状態をゼロに戻すような、いわば疾患軸で語られることが多いのですが、ゼロからプラスに、より良くしていくという観点も大切で、当社としてもそこに目を向けたサービス、事業を考えていく必要があると思っていました。
まさにWell-beingの観点ですね。
山口:その通りですね。そうした思いのもと、まずは当社の社員にWell-beingを考えてもらうべく、2022年にWell-beingの社内講演会を3回ほど開催しました。こちらに登壇いただいた、予防医学研究者で医学博士の石川善樹先生に、2022年の秋ごろからご指導いただく機会を得ましたが、石川先生がWell-being Initiative立ち上げのきっかけを作ったこともあり、ご紹介を受けて2023年度から参画させていただくことになりました。
将来世代との対話からWell-beingを加速させる「FR活動」
Well-being Initiativeでは具体的にどのような活動を行っているのですか?
山口:大きく3つの委員会で取り組みを行っています。1つ目はWell-beingを軸とした経営モデルの研究を進める「経営委員会」、2つ目が社会のWell-beingを可視化するため、GDW(Gross Domestic Well-being)をGDPに並ぶ新しい指標にしていく活動をおこなう「社会指標委員会」、そして最後が「シンボリックアクション」と呼ばれるWell-being Initiativeだからこそできる象徴的な活動ですね。実は昨年度までは企業だからこそできる効果的なアクションはなにかを研究していたそうなのですが、私たちが参加した2023年度からは実際に参加企業で実践していこう、そこから周囲の企業へと広めていこうということで、NECソリューションイノベータも「シンボリックアクション」の一つである「FR活動」に取り組んでいます。

FR活動とはどういったものなのでしょうか?
山口:FR活動とは、株主や投資家向けに行う「IR(Investor Relations)活動」から発想された造語で、将来世代(Future Generations)と対話し、関係性を築く活動を意味しています。
栗原:これまで企業は株主を筆頭としたステークホルダーとの対話は行ってきましたが、未来を生きる当事者である将来世代はそこに含まれていませんでしたよね。FR活動は、日本のこれからのウェルビーイングのために、次の時代を担う将来世代ともしっかり対話し、その思いを汲み取り、そこから学ぶことでそれを経営に活かしていく、「将来世代と企業の対話の接点をつくる」という取り組みです。なお、ここでいう「将来世代」は、今の子供たちだけではなく、まだ生まれていないさらに先の世代の子供たちです。ただし、取り組みによっては未来の高齢者という意味で、私たちの世代も含むこともあります。
「将来の当事者」たちを相手に対話を行い、それを経営戦略に反映していこうということですね。
栗原:そもそもの「きっかけ」は、日本人の人生満足度がとても低かったり、小学生の憧れの職業のなかに、「働きたくない」という回答がものすごく多かったことにショックを受けたためです。

なぜそんな回答が出てきたのかというと、現役世代である私たちの働き方や暮らしを見て、将来に希望を持てなくなったからではないかと考えました。なんか疲れてばかりで楽しそうに見えていないんじゃないかな、と。
大人がどういう仕事をしているのか、子供が具体的にわかっていないということもありそうです。
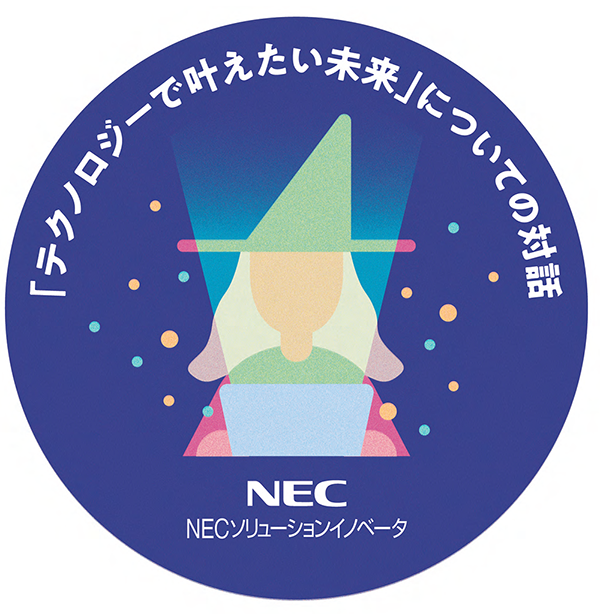
栗原:確かに、小学生に私たちの仕事や働き方を説明してもきっと理解できないと思います。そこで今回は、「テクノロジー」を「未来を築く魔法」に、「エンジニア」を「魔法使い」になぞらえて、私たちの仕事に興味を持って対話できるよう工夫しました。ロゴが魔法使いになっているのはそのためです。
2024年度も、FR活動を通じて
さらに社員のWell-being向上、サービス価値向上を目指す
これまでのFR活動についてお聞かせください。
栗原:実はNECソリューションイノベータでは、Well-being Initiativeに参画する前から、FRに近い活動を続けていました。小中学生向けのプログラミング教室や、従業員とその家族を対象とした交流イベント、講演会などですね。ただ、主催部署が別々に企画・実施していたので、これを機に共通のテーマ(=テクノロジーで叶えたい未来)を設定し、つなげていくことにチャレンジしています。
2023年12月には、常務の野口が拓殖大学でサステナビリティについての講義を行いました。テクノロジーを活かしたSDGsへの取り組みを学生に知ってもらうよい機会になりました。
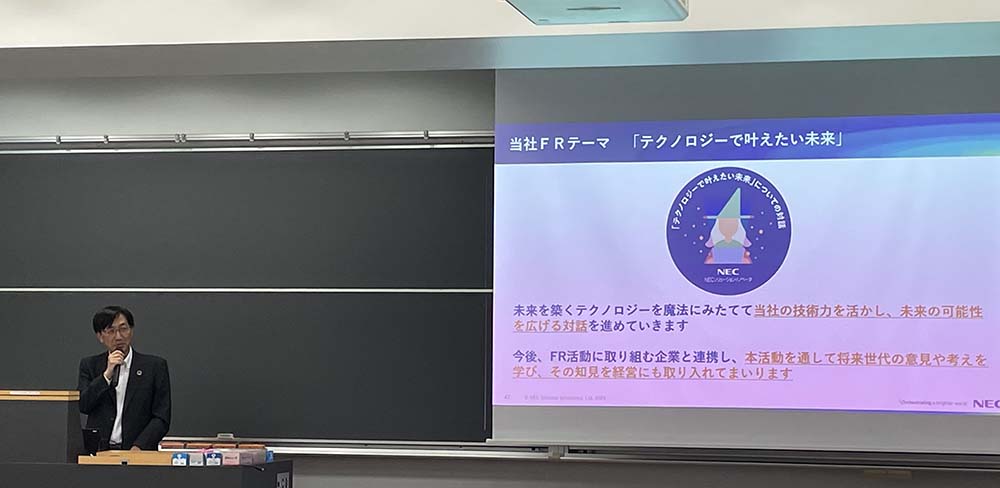
一連の取り組み、対話の中で、印象に残っていることはありますか?
栗原:社員とその家族を対象としたコミュニケーションイベントを開催し、身近な大人が働く会社を知ってもらうために当社の役員と子どもたちとの交流の場を設けました。そこで私の息子と社長が対話することになりました(笑)。息子はまだ小学1年生なので当然、技術的なことは何もわかりません。そこで「将来、もし魔法が使えるようになったらどんなことをしたい?」「どうすればそれを実現できると思う?」と話を進め、最終的には父親の会社が何をやっているのかを知ってもらうという流れにしました。
理解してもらえたのでしょうか?
栗原:はい。最後に「将来どうなりたいのか」を聞いたところ、「パパと同じ会社に入りたい」と答えてくれました。自分が大人になったらどう働くのか、イメージを持ってもらえたのは、一つの大きな成果だったと思います。もちろん、対話の内容を即経営に反映できるわけではないのですが、まずは一歩目を踏み出せたのではないでしょうか。
ほかにはどういった取り組みをされていますか?
栗原:沖縄で地域のフリースクールと連携した児童生徒向けプログラミングの体験イベントや、大阪・関西万博に向けて大阪府と大阪市が共同で取り組んでいる教育プログラムへの協力などを行いました。「対話」を通じて、さまざまな気づきがあったと感じています。

山口:一つ面白かったのが、このFR活動それ自体が、参加する社員のWell-being向上につながっている部分があるな、と。自分たちと異なる世代の価値観に触れることの大切さに気づかされましたし、これは将来のサービスの価値向上にも役立っていくと思っています。

2023年11月、大阪・関西万博に向けた高校生とのワークショップに参加
最後に今後の展望についてもお話しください。
栗原:これまで社内の各所で個別に行われていたさまざまなFR“的”な活動について、「テクノロジーで叶えたい未来」という一つの軸を作ることができたのは大きかったと思っています。今後はより「将来世代と経営陣との対話」を大切に、活動を拡大していきたいと考えています。
山口:私たちの仕事はどうしても直近の納期に追われてしまいがちなのですが、それだけではWell-beingにはつながっていきません。自分たちの仕事が社会にどう役立っているのか、これからの社会をどう変えていくのか、自分にとってどういう意味を持つものなのか、と考えること自体が大切なのではと思います。FR活動はその機会の一つになるのかな、と。FR活動を通じて、自分の子供や、近所の中学生、高校生など、将来世代をより具体的にイメージしていけるような取り組みを増やしていければいいなと思っています。

<関連リンク>
UPDATE:2024.2.15