サイト内の現在位置
距離や言語の壁を乗り越えて新たな働き方を創り出す。
「バーチャルプロジェクトルーム INTEGLIVE」

NECソリューションイノベータでは、仮想空間や生成AIなど、先進の技術を用いてシステムインテグレーション(SI)業務の高度化と生産性向上を目指す「スマートSI」の実現に取り組んでいます。それをサポートする仕組みの一つが、「バーチャルプロジェクトルーム INTEGLIVE(インテグライブ)」です。グローバルへの提供を前提とした仮想空間の開発という会社として初の試みに、すべてが手探り状態の中で挑戦した「INTEGLIVE」のプロジェクトメンバーに、開発の経緯や想いについて聞きました。
- ※INTEGLIVE(インテグライブ)は、社内で利用している名称です。
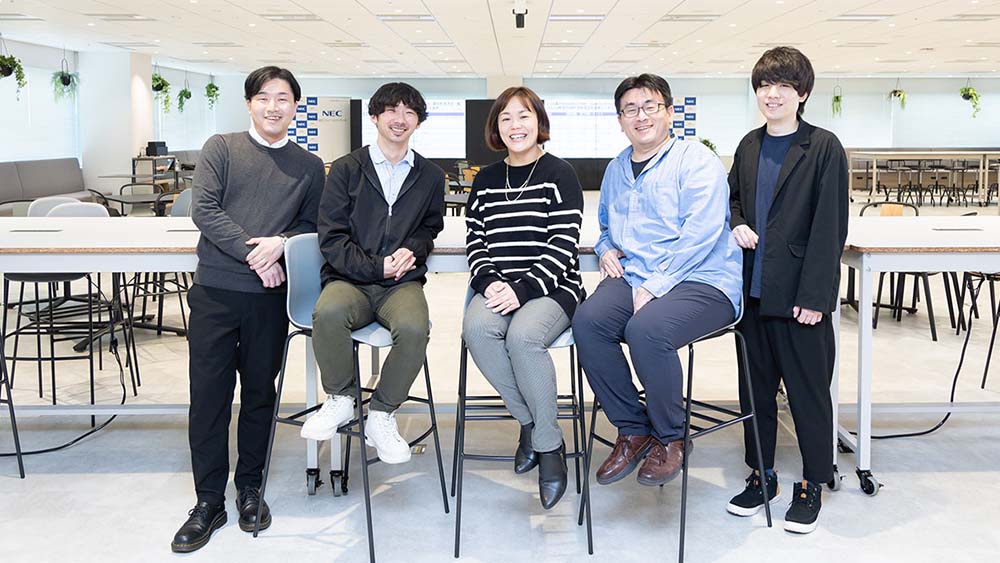
仮想空間の技術でサービス事業を変革する「INTEGLIVE」
2019年から開発に着手し、社内に実装された「バーチャルプロジェクトルーム INTEGLIVE」。名称は、「INTEG(=System Integration) 」と「LIVE= 即時」を組み合わせた造語で、仮想空間を用いてSI業務の効率化を支援するためのツールです。
NECソリューションイノベータは活動拠点が日本全国に点在しており、オフショア・ニアショアの国内外のパートナー企業とも仕事をする機会が多いため、コロナ禍以前よりリモート会議システムやクラウド上の開発環境等を活用していました。とはいえ、対面で行う業務のほうが効率よく作業を進められていたことも事実。そこで、仮想空間上にプロジェクトルームを整備し、リアルとバーチャル(デジタル)の両方のメリットを活かし、コミュニケーションと作業環境における生産性の向上を目的に、本プロジェクトがスタートしました。
2020年から、コロナ禍の影響により、NECソリューションイノベータではリモートワークが急速に進みました。新たに大きな課題となったのが、社員同士のコミュニケーションです。隣に座っていた同僚に気軽に声をかけて相談する、といったことが難しくなり、チャットツールを用いた文字の説明では誤解が生じることも。オンラインミーティングを設定するには、関係者の予定を合わせてビデオURLを発行するひと手間が必要になります。
そうした課題を解決するのが「INTEGLIVE」です。社員はウェブ上の仮想空間にアクセスし、「会話可能」「取り込み中」「一時離席」「応答不可」などのステータスを表示。「会話可能」であれば、オフィスで勤務しているのと同じように声をかけて会話ができる、というシステムです。


「INTEGLIVE」のメリットを、開発メンバーの一人である正能は次のように語ります。
「最大のメリットは、国内外に散らばっている社員を一つの仮想空間でつなげられる点です。離れた場所にいても、同じ仮想空間にいれば物理的な距離は関係なく、誰がいるのかすぐにわかります。マイクをオンにすれば気軽に会話ができますし、スピーカーをオンにすれば他の人の会話も聞こえてくるので、チーム内のコミュニケーションも活性化されます」

オンラインならではの機能もあります。
「複数人で集まって会議をしたいときは、仮想空間内でミーティングルームを作って、そこにメンバーが集まります。ルームは簡単に作れますし、リアルオフィスのように空き状況を確認する必要はありません。また会議内容はリアルタイムでテキスト化され、文字データとして蓄積されます。自動翻訳機能も備えており、英語、ベトナム語、中国語など他言語の発言もすぐに日本語で読むことができます」(正能)
前例のない試みだからこその苦労と楽しさ
仮想空間の開発は会社として初めての試みでした。技術面での苦労を、木村と沼野は次のように話します。
「何をどう設計すればいいのか、手探り状態でした。音声をテキスト化する機能については、自社開発のシステムを使うのか、それとも既存サービスから選ぶのかを検討しなければなりません。新しい機能を追加する場合に、利用中のシステムやサービスではうまくいかないケースもあります。そのため、常に試して工夫して改善する必要がありました」(木村)

「開発手法の違いに苦労しました。以前の部署ではお客様に提供するシステムを開発していましたが、最初に仕様を固めてから開発に着手するケースがほとんどでした。一方、『INTEGLIVE」の開発は試作品を作ってテストを繰り返すプロトタイプ開発の手法で行いました。ここに慣れるのがけっこう大変でした」(沼野)

プロジェクトのリーダーの小川も、社内運用に至るまでを振り返ります。
「なにしろ初めてのプロジェクトなので、社内で運用する際のルールや制度がまったくない状態でした。開発のどの段階で誰に確認をとればいいのか、どの段階で正式に『ローンチ』として公開すればよいのか、まったくの手探りでした。私たちチームメンバーだけで決められるものではないので、情報システム部門や人事部門、法務部門などいろいろな部署に確認をとって協力を仰ぎました」(小川)

リリースして1年超で1,700人が登録。導入効果は年間約2.5億円
NECソリューションイノベータは現在リモートとオフィスのハイブリッドな勤務体制をとっています。「INTEGLIVE」は、遠方に住んでいる、育児や介護などの事情があってリモートにせざるを得ない、また、耳が聞こえにくいなど、多様な環境にある社員の働きやすさを助ける存在でもあります。そうした点が評価されたのか、2022年9月に正式に展開したのち、現在、約1,700人の社員が利用登録をしています。 開発チームの独自調査では、「INTEGLIVE」によって年間約2.5億円の効果が生まれたと算出しています。これは、オフィスを借りた場合の賃料、会議室の予約や翻訳、議事録作成で発生する工数などについて、社内でヒアリングを行った結果から推定したものです。
「INTEGLIVE」の今後について、武市と木村は次のように話します。
「バーチャルやメタバースという言葉に惹かれ、試しに使ってみようとする人はいますが、慣れる前に使用をやめてしまう人も結構いるんです。ツールは、使い続けてもらわないと価値がなかなか伝わりません。使い続けてもらうためにも、意義や利便性について発信し続けていく必要があります。徐々にではありますが、『なくては困る』という声も上がっています。今後も利用者を広げていければと思います」(武市)

「少子高齢化の影響で今後はだんだんと働き手が減っていきます。いろいろな人が快適に働ける環境を構築して生産性を高めていかないと、企業を維持していくことはできません。そうした課題を解決する道具の一つとして『INTEGLIVE』が役立ってほしいと思います」(木村)
新しいことへのチャレンジを社内全体でサポート
NECソリューションイノベータには「ジョブチャレンジ制度」という、社員が希望のポジションに応募し、選考に合格した場合に異動することができる、社員と組織のマッチングを実現する制度があります。正能と沼野は、このジョブチャレンジ制度を利用して、「面白いことをやってみたい」「新たな技術を使ってみたい」とプロジェクトに加わりました。 「『INTEGLIVE』は新しいことへのチャレンジを繰り返して生まれました。いろいろな課題にぶつかりながら、メンバーの力と多くの人の協力で、それを乗り越えてきました。一人ではできないことも、みんなの力を合わせれば実現できる。それを『INTEGLIVE』を通して、身をもって体験しました。新しいことにチャレンジすると、悩むことや困ることがたくさんありますが、当社には新しいチャレンジを応援してくれる人がいますしチャレンジしやすい風土があります。さらにサポート制度も充実しています。」(小川)
「メンバー5人のうち、2人は東京、3人は大阪で勤務しています。それでも久々に会ったという気が全然しなくて、ずっと一緒にいたような感覚です。会っていなくても会ったような関係が築ける。『INTEGLIVE』はそんなツールです」(小川)
UPDATE:2024.3.1

