サイト内の現在位置
SF未来創造ワークで描く「次の50年」 生成AIと小説で未来を創る
NEC Solution Innovators 50th Anniversary


2025年9月9日に創立50周年を迎えたNECソリューションイノベータは、50周年を機に、未来を見据えたカルチャー変革に取り組んできました。
その施策の1つが、SFプロトタイピングを活用した「SF未来創造ワーク」です。生成AIを駆使し、50年後の社会や暮らしを想像しながら、その未来像を小説として描き出す──SFプロトタイピングの研究者と小説家が社内にいるNECソリューションイノベータだからこそ実現できた挑戦です。
ワークショップでは、社員たちが自由に未来を語り合い、技術や社会の可能性を大胆に描きました。今回は、その過程と、未来を構想する力を育むヒントを紹介します。
なぜ、創立50周年の今「SFプロトタイピング」なのか
創立50周年を迎えるにあたり、NECソリューションイノベータは「これからの社会にどんな価値を提供していくべきか」という問いに向き合ってきました。未来の社会を見据え、NECソリューションイノベータが果たすべき役割を構想する──その一環として実施したのが、SFプロトタイピングを取り入れた「SF未来創造ワーク」です。
SFプロトタイピングとは、SF的な発想を活かしながら、未来像を想像し、対話し、共有する手法のこと。近年はビジネスの現場でも注目されており、実際にSF作品からヒントを得て生まれたプロダクトやサービスも少なくありません。
NECソリューションイノベータがこの手法を採用した理由は、技術ありきではなく、「ありたい未来」から逆算して構想する力を育むためです。さらに大きな特徴は、社内にSFプロトタイピング研究者の伊藤右貴と、新規事業創出の担当で小説家でもある田中伸幸という2人の専門家が在籍していること。研究と創作という異なる強みを掛け合わせることで、ワークショップで生まれた構想を“ただのアイデア”で終わらせず、より具体的な未来像として描くことができます。
講師を務めたのは、SFプロトタイピングの第一人者である宮本道人氏。
「既存の技術の延長線上ではなく、未来から逆算して考える──。SFプロトタイピングはそのための強力なツールです。NECソリューションイノベータが社内に創作の力も持っていることは、非常に大きな強みだと感じます」(宮本氏)
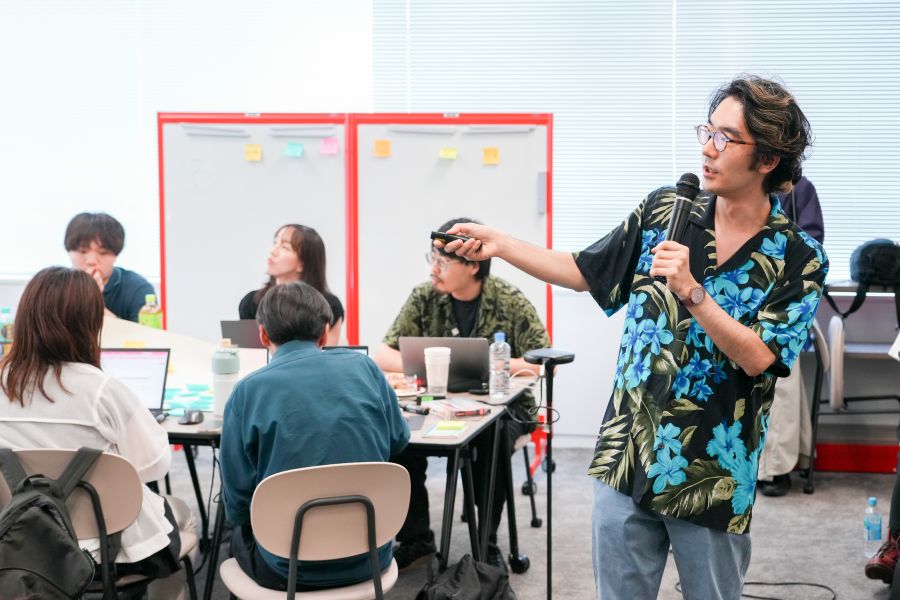
株式会社SF実装研究所 代表取締役
筑波大学 国際産学連携本部 産学連携准教授
東京科学大学 未来社会創成研究院 特任准教授
慶應義塾大学 SFセンター 特任講師
生成AIと対話しながら描く、50年後の未来
ワークショップ当日、約30名の社員が5つのグループに分かれ、「①公共・行政サービス」「②リテール・ショッピング・決済」「③ヘルスケア」「④モビリティ」「⑤通信」というテーマで50年後の未来を議論しました。
進行はシンプルながら、その内容は濃密です。生成AIを活用しながら、「想像」、「対話」、「共有」の3ステップを繰り返し、未来を構想するためのロードマップを描きました。
今回の特徴は、生成AIを積極的に活用した点です。ワークショップデザインも担当した宮本氏は、回答が似通わないよう、各グループ内で異なる生成AIモデルを使うことを推奨しました。多くの参加者は、NEC独自の生成AIサービス「NGS(NEC Generative AI Service)」を利用。NGSは、NEC独自の大規模言語モデル(LLM)に加え、GPT-4などの外部モデルも選択できる柔軟さに加え、入力したデータが再学習に使われないため安心して利用できるという特徴があります。配布されたプロンプト例を参考に、参加者は試行錯誤しながらAIを使って発想を広げていきました。

最初は、参加者が事前に考えてきた「趣味」と「自分の仕事」に関連する単語をAIに入力し、関連するユニークな単語を提案させるアイスブレイクからスタート。続いて、AIで造語を作り、「50年後に実現したい」斬新で時に“ぶっ飛んだ”ビジネスアイデアを自由に広げていきました。議論を重ね、各グループは最終的に1つのアイデアに絞り込みます。
さらに、AIで設定したキャラクターのペルソナになりきり、50年後のNECソリューションイノベータ社員やパートナー、お客様、エンドユーザーとして未来を描く即興劇を実施。異なる立場の視点を取り入れながら想定されるリスクを洗い出し、AIの推論も活用して、50年先を見据えたビジネス戦略を完成させました。



宮本氏は、この手法の本質をこう語ります。
「まず未来を想像し、次にその未来に起こり得る課題を想像し、最後に課題を解決する方法を想像する──この流れが想像力を広げる鍵になります。こうしたプロセスを通じて、より柔軟に発想を広げられるようになるんです」(宮本氏)
AIと創造力が交わる、新しいワークショップ体験
ワークショップを終えた参加者からは、これまでにない体験で刺激的だったという声が多く聞かれました。
「これまで経験したワークショップでは、パソコンを閉じてアイデアを出し合うブレインストーミングが中心でした。でも今回は、生成AIをパートナーとして使いながら、自分の発想を広げていくプロセスが新鮮でした。業務でAIを触る機会はあっても、定型的な回答や肯定ばかり返ってくることも多かったので、どうすればAIの思考を引き出せるのか学べたのは大きな収穫です」
「他の参加者が社会や技術の未来をどう考えているのかを知りたくて参加したのですが、予想外の発見がたくさんありました。ディスカッションでは新しいワードや視点が次々と飛び出し、普段の業務では出会わない発想に触れられたことが一番の刺激でした。特に、長文のプロンプトを使って生成AIを駆使する体験は、多くのメンバーにとって初めてで、新鮮さを楽しんでいる様子が印象的でした」


社内でSFプロトタイピングの研究を行い、今回のワークショップの企画・運営にも携わった伊藤右貴は、会場全体の熱量をこう振り返ります。
「生成AIが提案した、50年後を見据えた新しいテクノロジーやサービスのアイデアを起点に、活発な議論が繰り広げられていました。NECソリューションイノベータらしい、技術的に深いワークだったと思います。ここまで大規模に多くの社員を対象としたのは初めてなので、今後はこの手法を社内でどう活かせるかを考えていきたいです。より良いワークショップの設計ができれば、新規事業開発などにも応用できるはずです」(伊藤)

イノベーションラボラトリ
SFプロトタイピングを活用した価値創出や新規事業創出手法の研究を推進
講師の宮本氏は、「プロンプト次第で生成AIの使い勝手は格段に変わる」とAI活用の可能性を強調します。
「生成AIは、“答えを出すため”ではなく、“想像を広げるため”に使うべきです。今回のワークを通じて、多くの参加者がAIを使ったアイデア出しの方法を体得できたと思います。今回学んだアプローチを、ぜひ日々の業務でも生かしてほしいですね」(宮本氏)

50周年、その先を描くために──物語で未来をかたちづくる
今回のSF未来創造ワークの大きな特徴は、未来のビジョンを構想するだけで終わらず、その未来像をより具体的に示すため、自ら小説を描き上げるプロセスにまで踏み込んだ点です。生まれた2本の小説は、講師の宮本氏と、NECソリューションイノベータの社員であり小説家でもある田中伸幸がそれぞれ執筆しました。作品には漫画家のハミ山クリニカ氏が描いたイラストが添えられています。
会場で参加者の様子を見守っていた田中は、こう振り返ります。
「最終的に小説としてまとめる立場なので、どんなアイデアが出てくるのか正直ハラハラしていました。でもNECソリューションイノベータらしい単語があちこちから飛び出し、皆が楽しそうに議論しているのを見て安心しました。技術的にもコアなワードが多く、非常にいい取り組みだったと思います。“こんな未来にしたい”という想いを持って日々の業務に臨むことが、生産性の向上にもつながると実感できたワークショップでした」(田中)

イノベーションラボラトリ 主任
所属部署では観光業における新規事業創出を担当。
MENSA会員。2013年講談社にて新人賞を受賞し、作家デビュー。NFT小説大賞等様々な賞を受賞。
講師の宮本氏も「非常にユニークなアイデアが出てきて、聞いていて面白かった」と語ります。
「例えばあるチームは、“魂”と“税金”を組み合わせて、『2041年に魂税を導入する』という発想をしていました。一見突飛に思えるかもしれませんが、『それを実現するにはどんな技術や仕組みが必要か』と真剣に議論を深めていたのが印象的でした。また、“自治体の都市OSモデル”といった高度なテーマについても、参加者全員が深いレベルで議論し合えていた。こうした自由度の高い発想を支えるのは、NECソリューションイノベータの社員の高い技術力と柔軟な視点だと感じます」(宮本氏)
NECソリューションイノベータは、想像力と創造性を組織文化として育み、未来をかたちづくる力へとつなげていきます。技術の進化にただキャッチアップするだけでなく、「ありたい未来」から逆算する発想を大切にしながら、社会とともに新たな価値を生み出し続ける──。
SF未来創造ワークは、その挑戦を象徴する取り組みであり、次の50年を描くための最初の一歩です。

50年後の自治体AIはどう進化するのか。
失敗がなくなる未来で、人は「失敗」をどう手に入れるのか。
SF未来創造ワークから生まれた2本のSF小説を、ぜひご覧ください。
『村役場と村長のはなし』 作:宮本道人氏
50年前、小さな自治体に導入されたAI「弊役場」は、住民一人ひとりの幸せを願った“ある職員”の想いを受け継ぎ、村を支え続けてきた。
世代を超えて紡がれる理念と、AIと人間の共進化が生み出すのは、“人間らしい自治体DX”の未来。
近未来の自治体像を描いた、ちょっと先の物語。
『失敗の失敗は成功?』 作:田中伸幸(NECソリューションイノベータ)
2075年、AIがあらゆる失敗を未然に防ぐ社会で、「失敗体験ツアー」を企画する佐藤は、コンテンツ不足に頭を抱えていた。
失敗学の研究者・井上と協力し、「新しい失敗」を生み出す挑戦が始まる──。
AIとの知恵比べが導く、予想外の“失敗のカタチ”を描いた近未来ストーリー。
<関連リンク>
UPDATE:2025.9.18
 暮らしを支えて50年 NECソリューションイノベータのエンジニア集団がDXをリード: NEC Stories | NEC
暮らしを支えて50年 NECソリューションイノベータのエンジニア集団がDXをリード: NEC Stories | NEC