サイト内の現在位置
未来を担う将来世代との学び合いをとおして、個人のWell-beingを高め、充実感を得られる社会へ。
[事業成長のためのエンジン]
Well-being推進(将来世代と企業の対話)
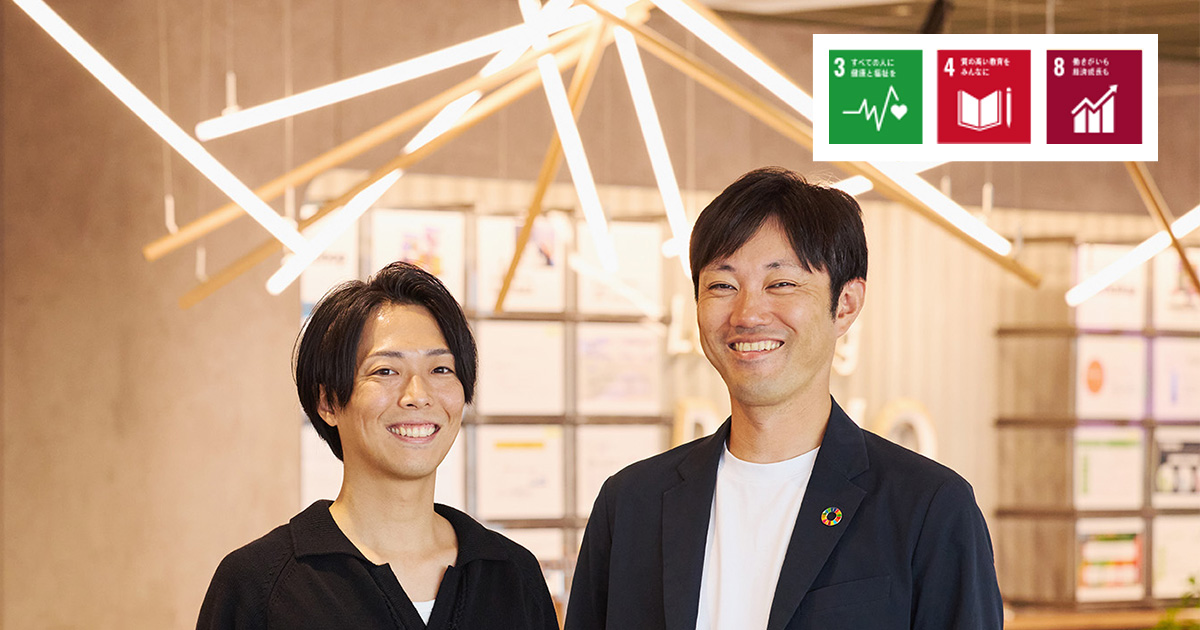

公益財団法人Well-being for Planet Earth
代表理事
石川 善樹 様
1981年、広島県生まれ。予防医学研究者。「人と地球が調和して生きるとは何か」をテーマに、国内外で様々なプロジェクトに取り組む。

AI・データアナリティクス事業部
栗原 司
2011年入社。Web系システム開発やシステム運用・企画に携わる。現在はWell-being Transformation事業に従事し、企業の社員が楽しく働ける社会の実現に尽力する。
以下敬称略

| プロジェクト概要 |
|---|
 近年、心身の豊かさだけではなく、社会参加や良好な人間関係が社会的な充足感をもたらすWell-beingの概念に注目が集まっています。NECソリューションイノベータは企業としてこの概念に賛同し、2023年度からWell-beingをより深く社会に浸透させていく「Well-being Initiative(以下、WBI)」※1に参画しています。WBIでは日本のWell-beingを高めるために、企業にも積極的な役割を求めており、当社はWBIの活動の中で「将来世代」※2との対話を企業価値の向上につなげていく「FR活動」※3に取り組んでいます。
|
― どのように課題を解決し、どのような未来を描くのか ―

現在多くの企業が取り組むSDGsは、2030年をゴールとしています。WBIはその先に世界が取り組むべき課題として、充実度や満足感といった個人の「主観」を指標に据えることを長期的なビジョンにしており、GDPを補完する、あるいは超える新指標としてGDW(Gross Domestic Well-being:国内総充実)を創出しようと考えています。一方、日本で働く現役世代やシニア世代の人生満足度は世界的にも低く、経済的な豊かさを享受しながら幸せを実感できていない実態があります。Well-beingの低下は個々人の生活の質を落とすだけでなく、企業や社会の生産性の低下やアイデアの創出を停滞させる可能性があり、社会全体が持続的な成長と発展を目指すにはWell-beingの向上が不可欠です。
- 日本人の人生満足度が低いことは、将来世代や社会のWell-beingを損ねる可能性がある
- Well-beingの低下は個人への影響にとどまらず、企業や社会の生産活動も停滞させる
- 将来にわたり社会全体が持続的に発展するために、Well-beingの向上が望まれている

将来世代は未来の社会を担う礎です。企業が日本の未来を担う将来世代のWell-beingを高める施策の一つとして、将来世代を重要なステークホルダーの一員と捉え、対話からその思いを汲み取るFR活動が注目されています。将来世代と企業が対話する「場」を設けることは、将来世代にとっては働く現役世代から仕事の有り様を学び、将来へのモチベーションを持つきっかけになります。また、働く現役世代にとっても、自らの仕事を見直し自己肯定感を高める機会になります。さらに企業にとっては、新たな製品やサービスのコアとなるアイデアが得られる利点があり、三者それぞれのWell-beingを高める施策として大いに期待されています。
- 日本の未来を担う、将来世代のWell-beingを高めたい
- 様々な世代同士で対話できる「場」を設け、各世代が別の世代の視点から「学び」を得る
- 将来世代との対話から、持続的な企業・事業活動を行ううえでの「気づき」を得る

これまで当社では、小中学生に向けたプログラミング教室や職場見学会などの形で、企業市民活動に取り組んできました。しかし、これらはあくまで将来世代への「教育」の域にとどまっていました。2023年は積極的に活動を推進し、互いの対話や学び合いを重視する「FR活動」への移行に向け、施策の数々を「テクノロジーで叶えたい未来」というテーマで統合しています。

地域のフリースクールと連携した児童生徒向けプログラミング体験イベントの実施
当社沖縄支社にて、地域のフリースクールと連携した児童生徒向けプログラミング体験イベントを実施しました。近隣の学生14名が参加し、指先の動きと画面を連動させて操作するゲームやプログラムの構築体験をとおして、プログラミングの楽しさや可能性に触れることで、「テクノロジーで叶えたい未来」を想像してもらいました。
大阪・関西万博に向けて、高校生のアイデアを形にするワークショップイベント
大阪・関西万博のテーマでもある、「いのち輝く未来社会のデザイン」を高校生と一緒に考える教育プログラムに当社社員が参画しました。「健康な生活が続く未来」をテーマにした高校生の創作アイデアに対し、専門的な知見を持ったプロである当社社員からアドバイスを実施。全3回のワークショップイベントで、理想の未来と現状のギャップをICTでどのように補うのかを体感してもらうことで、高校生の柔軟で自由なアイデアを形にできるように支援しました。
大学生との講義内でのディスカッションを実施〜SDGsの実践〜
拓殖大学から、「学生1人ひとりが国政的視野を持ち、積極的にチャレンジしていくタフな人間力を身につけたグローバル人材(=拓殖人材)」育成の観点で、当社にオファーをいただきました。参加した12社が各社の取り組みを講義する中、FR活動として「テクノロジーを使ってどのような未来を叶えたいか」を講義の中でグループディスカッションしてもらいました。テクノロジーを生かしたSDGsの取り組みを、学生と共有する良い機会にもなりました。
NECソリューションイノベータ社内イベント「NEScrum祭」※4
当社社員とその家族約400名を招待した、コミュニケーションイベントを実施しました。イベント内では将来世代との対話の「場」づくりを心がけ、「魔法を使って夢が叶うなら」など、未来が想像しやすくなる質問で、働く現役世代と将来世代が双方向にインタビューを実施しました。当日は社長をはじめ役員もイベントに参加し、将来世代との交流を図りました。
- ※4NECソリューションイノベータの文化・体育・サークル活動の総称。

― NECソリューションイノベータが描く未来 ―

WBIの推進で豊かさが実感できる社会へ
当社は2023年度からWBIに参画し、参加企業15社とともに共同シンボリックアクション※5を開始しました。WBIの施策の一つである当社FR活動では「テクノロジーで叶えたい未来」をテーマに掲げ、未来の可能性を広げる対話を推進しています。今後もWBIに賛同する企業と連携し、社会にWell-being向上の大切さを伝えていくとともに将来世代の知見を経営にも取り入れ、社会の幸せと発展に貢献していく考えです。
対話から生まれるそれぞれのWell-being
企業と将来世代の対話の場を設定するFR活動をとおして、将来世代が私たち企業に期待することを知り、また、彼らが未来に対し真剣に思考する機会を創出できました。一方で、参加した社員にとっても、自分の仕事の意義ややりがいを見つめ直す場になっており、将来世代と働く現役世代それぞれのWell-beingの高まりを感じています。一人ひとりが「私」を主語に「未来のありたい姿」を想像することは、社会の活力を高め、サステナブルな世界の実現に踏み出す一歩になるでしょう。
- ※5WBIの参画15社が、その会社ならではの「FR活動の対話テーマ」を一斉提示する動き。
Project Story
新時代の豊かさを考える、Well-being Initiative

栗原:WBIを知るきっかけになったのは、2022年度より実施しているWell-beingの向上を目指すミーティングで石川先生の指導を受けたことです。成熟する社会におけるWell-beingの重要性について、社員自身が考え実感することで、当社が提供する価値にどのように反映できるかを解説いただきました。石川先生はWell-beingをより深く社会に浸透させていく取り組みであるWBIの創設に重要な役割を果たされていたこともあり、そのご縁から当社も参画しています。
石川:Well-beingには、平均寿命や個人あたりの年収などのデータ化しやすい「客観的Well-being」と、人生の充実度や満足感といった「主観的Well-being」がありますが、後者については、特にここ十数年では世界全体で停滞が起きています。客観的にも主観的にも、誰ひとり取り残すことなくWell-beingな社会を未来に遺せる か、私たちは将来世代から宿題を突きつけられている状況です。こうした世界の中で、NECソリューションイノベータさんはWBIに参画され、2030年で終わりを迎えるSDGsの先の社会課題にWell-beingを位置づけ、様々な実践と働きかけを行っています。ともにこれからの時代に新しい価値を創ることを楽しみにしています。
将来世代との対話から、社会全体のWell-being向上を探る

栗原:「FR活動」の取り組みのきっかけは、日本の現役世代やシニア世代の「人生満足度」の順位が世界の中でも低いことを知り、この状況は将来世代のWell-beingにも影響するだろうと考えたからです。企業として、持続的な成長と社会全体の健全な発展を目指すためには、将来世代のWell -beingの向上が不可欠と考えました。当社のFR活動のテーマは「テクノロジーで叶えたい未来」です。ICTの高い技術力を「未来を築く魔法」と捉え、その可能性を広げる対話を将来世代と進めることで、彼らがテクノロジーの力で、自ら希望に満ちた未来を築ける環境を整えたいと考えています。
石川:NECソリューションイノベータさんが行っている活動は、2023年にほかの14社との共同シンボリックアクションとして発表されました。企業はこれまで、株主をはじめとするステークホルダーとは対話してきましたが、将来世代はさほど重視してきませんでした。サステナブルな社会を構築するには、いかに将来世代と「対等」な立場でこちらが教えるだけではなく、耳の痛い意見も受け入れるような「学び合う」関係性をつくれるかが肝要だと考えられています。
「場」の設定が、将来世代と現役世代双方の刺激に

栗原:2023年度のFR活動では「NEScrum祭」という社内のコミュニケーションイベントに、社員とその家族の約400名を招待しました。会場には社長も来場し、小学生と将来の夢について意見を交わしました。当日、社長と私の子どもも対話をさせていただき、最終的には「パパと同じ会社で働きたい」という発言が飛び出して、自身の思わぬWell-being向上につながりました。当社は「テクノロジーで叶えたい未来」というテーマで多数の施策を実施しています。 この活動は、将来世代が未来に対し真剣に思考する契機になっていますし、当社への期待も聞くことができています。また、参加した社員にとっては、異なる世代の価値観に触れる重要性を認識する機会となり、今後のサービス向上につながると私たちは感じています。
石川:私たちが将来世代から学んだと思えたときは、おそらく将来世代も「働く現役世代から学ぶことがあった」と感じているのではないでしょうか。場を設けて、何かしら双方に学びがあるのであれば、それは十分によい機会です。普段、社員の方々は、お客様や社内に向けて仕事をされることが多いと思いますが、誰のために仕事をしているのか、こうした交流から見つめ直すことが大事です。
栗原:当社はこれまで、プログラミング教室や職場見学会といった手段で、将来世代のための企業市民活動※6を行ってきました。これらは主に小中学生を対象とした育成や交流を中心にしていましたが、彼らの意見を学び、経営に反映させるまでには至っていませんでした。また、せっかくの取り組みも、その多くが将来世代への「教育」の域からは抜け出せていませんでした。
こうした反省をもとに、企業市民活動の一つであるFR活動では将来世代の声を経営層にまで届けて、その意見を経営方針や戦略に反映させることを将来の目標に置いています。
- ※6ICTを活かしたプログラミング活動や身近な清掃活動などを全国規模で行い、地域に密着した課題の解決と社会づくりに貢献する取り組み。
将来世代と現役世代の対話が、未来に起こすイノベーション

栗原:FR活動は、これまでの企業市民活動をサステナビリティという違った観点で捉えるきっかけになっています。企業市民活動に参加する社員の方々は、自身の仕事と両立しながら社会貢献の思いを持って活動してきましたが、その取り組みは個々の地域で独立していました。それらが、FR活動という業界や産業も越えた枠組みに 広がり、社会への影響力が増すことで社員一人ひとりのやりがいという面でWell-being向上に寄与しています。加えて、この活動から得られた知見が製品開発やサービスに反映されれば、企業全体の成長力だけではなく、社員のモチベーションもこれまで以上に増し、サステナブルな企業への原動力になるでしょう。
石川:人は多くの時間を働くことに費やしています。そのため「働くことのWell-being」を充実させることは、生産性向上などで企業価値を高めるだけでなく、結果として個人の人生のWell-beingにも大きな影響を与えます。一方で、現代の企業では個人は全体的な業務プロセスの中で一部を担うことになり、貢献性を実感しにくい側面があります。将来世代と対話することは、あらためて自分の仕事を見つめる機会になり「働くことのWell-being」に寄与すると考えられます。これは同時に、将来世代にとっても働くことへの興味や洞察を深めるよい機会になるのではないでしょうか。
栗原:当社は、約10,000人のシステムエンジニアが多様な分野で活躍するテクノロジーの会社です。現代に生きる私たちにとってテクノロジーは欠かせない存在ですが、WBIに触れたことでそれが未来にも本当に価値を持つのか考えるようになりました。今後は、テクノロジーを提供する側の責任としてこれまで以上に長期的な視点で技術のあり方を考える必要がありますし、そのヒントになるのがFR活動だと感じています。
石川:創造性に関する研究によると、イノベーションが起こりやすいのは「エッジの効いた若者」と「大局観を持ったベテラン」が組み合わさったときであると報告されています。FR活動を通じて、将来世代とともにイノベーションを起こしたいという志が拡がることを期待しています。NECソリューションイノベータさんが持つテクノロジーという強みが最大のアピールポイントになるのは間違いありません。
栗原:具体的な貢献が見えてくるのはまだ数年先かもしれません。しかし、社内で手がける各プロジェクトで将来世代を重要なステークホルダーと捉え、対話をとおして、自分たちのテクノロジーの価値や意義を再確認することがFR活動の第一歩だと思います。そして、発見した「強み」をもとに、WBIに賛同する企業や団体と連携しながらよりよいサービスや価値提供につなげ、将来世代に実りある未来を創造していきたいと考えています。
UPDATE:2024.11.29