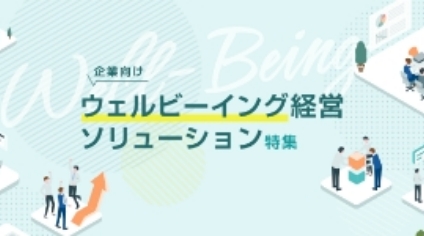サイト内の現在位置
コラム
テレワーク先進企業に学ぶ取り組み事例10選
~「手当」「コミュニケーション」「健康」~

UPDATE : 2021.04.28
依然として新型コロナの脅威は過ぎ去っていない現状、今後もテレワークが継続・定着していくことは確実です。そうした中、テレワーク移行がうまくいっている企業と、うまくいっていない企業の差が明確になりつつあります。ここでは先進企業の取り組みを紹介し、テレワークを成功に導くためにやるべきことを明らかにしていきます。
INDEX
- テレワークを加速させるには企業側の工夫がカギ
- 【手当】金銭的インセンティブで移行を促す
- 毎月2万円の在宅勤務手当など、積極的な取り組み多数(ドワンゴ)
- 毎月2万円、さらに初回は5万円を支給(アイレット)
- やむを得ず出社する社員にも手当を支給(さくらインターネット)
- テレワーク一時金の使い途を社内外に公表(SmartHR)
- テレワーク手当はいくらが“相場”なのか?
- 【コミュニケーション】ユニークな仕組みで活性化する
- 全社Zoom飲み会「バーチャル・ハッピーアワー」を実施(Dropbox Japan)
- 社内ラジオ&ランチで孤独感を癒す(チャットワーク)
- 朝礼ならぬ「夜会」を実施(スマートキャンプ)
- 効果的なコミュニケーション促進サービスも続々登場
- 【健康】社員の心と身体をリモートでもしっかりサポート
- テレワークうつ 予防チームを発足(日清食品ホールディングス)
- 運動不足解消手当を支給(アジャイルウェア)
- ユニーク施策で社員の気持ちに寄り添う(LITA)
- そもそも働き過ぎを抑制すべき
- まとめ
テレワークを加速させるには企業側の工夫がカギ
テレワークは企業によって利活用の格差が大きくなるといわれています。そうした中、際立つのがテレワーク先進企業の活用事例です。一部の企業ではオフィスを引き払い完全テレワーク化するなどという話も。
テレワークがうまくいっていない会社からすると「なぜ?」と疑問を持つかもしれませんが、こうした企業では、テレワークを成功に導くための工夫をしっかりしているのです。
工夫なくして成功はありません。ここでは今、テレワークのメリットを最大限に引き出しているテレワーク先進企業の取り組みを、「手当」「コミュニケーション」「健康」の切り口でピックアップしてご紹介します。
【手当】金銭的インセンティブで移行を促す
多くの社員が積極的にテレワークを活用するためにはどうすればいいのか。最もシンプルで分かりやすい施策は「手当」。金銭的インセンティブを設けることでテレワークという新しい、ともすると面倒にも感じる取り組みへの不満を軽減し、やる気を刺激します。
毎月2万円の在宅勤務手当など、積極的な取り組み多数(ドワンゴ)
『ニコニコ動画』などで有名なインターネット総合エンタテインメント企業ドワンゴは、他社に先駆け2020年2月にテレワーク移行を宣言。その手応えを受けて2020年7月1日には在宅勤務の恒久化を目指すと発表しました。その際、テレワークで働く社員には月額2万円の在宅勤務手当を支給すると決定。
同社は、テレワークで出社比率が減った分、空いたオフィススペースを活かし、会議スペースやフリーアドレス席の拡充も実施しました。やむを得ず出社しなければならない場合のオフィス空間の快適さを高めています。また、通勤時間がかからなくなった分の時間的な余裕を使った他部署業務への参加(兼務)など、事業をよりブーストさせていくような取り組みも積極的に行っています。
関連記事:緊急事態宣言解除後の働き方を新時代のビジネスリーダーたちが語るスペシャル対談<前編>「テレワーク」が浮き彫りにする企業の課題と将来性
毎月2万円、さらに初回は5万円を支給(アイレット)
KDDI系列のシステム・Web開発会社アイレットは、2020年10月から本格的に在宅勤務をベースとした業務体制へ移行。それに伴い、自宅のテレワーク環境を整えるための「環境設備補助金」を5万円、そして毎月2万円の「在宅勤務支援手当」を導入しました。
同社はそれ以外にも新入社員・内定者向けの研修をオンラインで行うなど、積極的にテレワークを推進。2021年2月には、東京都が提唱する「テレワーク東京ルール」実施企業に認定されています。
やむを得ず出社する社員にも手当を支給(さくらインターネット)
インターネットインフラを提供するさくらインターネットも早くからテレワークに移行した企業です。2020年4月8日には「出社禁止」という強い措置を発令しました。その際、自宅でのテレワーク環境を整えるために「臨時特別手当」1万円と「臨時通信手当」3,500円を支給。5月以降は毎月3,000円の通信手当を支給しています。
その上で、やむを得ず出社せざるを得ない一部業務の担当者に対して1日5,000円もの「緊急出勤手当」を支給し、話題となりました。これにより同社の出社率は2020年4~11月の平均値で12.5%に。今後はオフィスの「再構築」を目指していくと発表しています。
テレワーク一時金の使い途を社内外に公表(SmartHR)
クラウド人事・労務ベンチャーのSmartHRは、緊急事態宣言中を「強制リモートワーク期間」とし、原則、在宅勤務を指示。「リモートワークお願い手当」として毎月1万5,000円を支給しています。
また、それとは別に「リモートワーク環境を整える手当」として2万5,000円を支給。あえて「どう使ってもいい」とし、支給された社員が何をどのような理由で買ったかという情報や、各人のワークスペースの写真を共有するといったユニークな取り組みを行っています。
テレワーク手当はいくらが“相場”なのか?
ここまで紹介してきた先進企業では、1万円/月を超える高額なテレワーク手当が目立ちますが、一般的な相場は3,000~5,000円程度。テレワークに必須のインターネットプロバイダ利用料金が概ね3,000円/月なので、その辺りが基準となっているようです。
なお、多くの企業ではテレワーク手当の支給開始と並行して定期代の支給を廃止し、実費精算にしています。
【コミュニケーション】ユニークな仕組みで活性化する
テレワークで多くの人が懸念しているのが、実際に顔を合わせる機会がなくなることによるコミュニケーションの劇的な低下です。業務によっては生産性の低下にも直結するため、それを理由にテレワークの解除を求める経営者、従業員も少なくありません。
しかし、それもアイデア次第で解決可能だとテレワーク先進企業は考えているようです。
全社Zoom飲み会「バーチャル・ハッピーアワー」を実施(Dropbox Japan)
2000年代からベンチャー企業を中心に流行し、今でも多くの企業で行われている定例社内懇親会「ハッピーアワー」。これをテレワーク環境で行っているのがDropbox Japanです。
同社では毎週金曜日の夕方に全社員を招待するかたちで大規模Zoom飲み会「バーチャル・ハッピーアワー」を実施。ただ集まって飲むだけではなく、MC(社員による交代制)主導のイベントや、ランダムに選ばれたメンバーとのチャットなど、よりコミュニケーションを促す工夫がなされています。
社内ラジオ&ランチで孤独感を癒す(チャットワーク)
人気コラボレーションツール『Chatwork』で知られるチャットワークは、テレワークに移行した2020年春から社員限定の参加型インターネットラジオ番組をスタート。社員DJによるライブトークに、社員リスナーが投稿ハガキの代わりにチャットでコメントを入れていくかたちで社内コミュニケーションを活性化させています。
同社ではそのほか、オンラインのランチ会もスタート。かねてより実施していた4,000円/月までのランチ代補助制度と合わせ、社員が新型コロナ禍で孤立しないよう工夫をしています。
朝礼ならぬ「夜会」を実施(スマートキャンプ)
法人向けSaaSの比較・検索サイト『BOXIL SaaS』を運営するスマートキャンプは、2020年4月のテレワーク移行後、「夜会」という新たな取り組みを始めました。夜会は毎日午後6時30分から午後7時まで行われる部署単位のミーティング。いわば朝礼の夜版なのですが、定時のラストに行うことでオン/オフを意識させ、テレワークで起こりがちな、だらだらと残業してしまうのを防ぐことに成功しました。
また、同社ではこのほか、エンジニア向けのコミュニケーション施策「SMARTCAMP Tech Talk」も定期的に実施。エンジニア達がそれぞれ興味のある技術ネタを持ち寄り、1人あたり約5分紹介しあう取り組みです。そうした場を作ることで、社内全体の技術力向上に加え、仲間の興味やスキルを把握できるメリットがあります。
効果的なコミュニケーション促進サービスも続々登場
どうしても自社にフィットしたコミュニケーション活性化のための取り組みが思いつかない、作り込んでいる時間がないという場合は、市販の社内コミュニケーション促進サービスを使うのも良いでしょう。特にこの1年は、市場ニーズの盛り上がりを受けて、多くの魅力的なサービスがスタートしています。
例えば『バーチャルランチクラブ for Biz』(提供:エッグフォワード株式会社)は、社内で面識のない社員と繋がり、15分のビデオ通話ができるというもの。“リアル”ではあり得ないようなマッチングによって、新たなアイデア、ビジネス創出を加速させています。
Dropbox Japanの事例で紹介したような、オンライン懇親会を盛り上げる仕組みも多数登場しています。これまでも多くのオンライン懇親会向けサービスを提供してきたマックスパートは、新コンテンツとして『オンライン謎解きゲーム』を開始。流行りの謎解きゲームをテレワークの仕組みを使って実施することで、チームの一体感を高めています。
【健康】社員の心と身体をリモートでもしっかりサポート
新型コロナ禍から社員を守るために始めたはずのテレワークですが、急激な環境変化で逆に心身に大きなダメージを受けてしまった話もよく聞かれます。本当の意味でテレワークを成功させるためには、社員の心と体の健康をサポートする取り組みも欠かせません。
テレワークうつ 予防チームを発足(日清食品ホールディングス)
カップヌードルなどで有名な日清食品グループは、2020年8月に“with コロナ時代”の新たな健康経営活動として、「テレワークうつ 予防チーム」を発足。グループ従業員約1,360名を対象に、専用機材を利用した疲労ストレスの計測やそれに基づく対策プログラム、オンライン面談などを実施し、ストレスの改善、働きがいとワークライフバランスの向上を図っています。
運動不足解消手当を支給(アジャイルウェア)
Webシステム開発企業アジャイルウェアは、社員の腰痛・運動不足解消を目的に1人2万円の手当を支給。当初は作業用デスクやPCチェア、姿勢矯正クッションなどの購入を対象としていましたが、社員からの声を受けて、腰痛・肩こり・運動不足解消のための用途にも使えるように。結果、フィットネス器具や、トレーニングゲームソフト、動画サービスなどが購入されたそうです。また、リモートでラジオ体操を行うなど、運動不足に陥りがちなエンジニアをサポートしています。
ユニーク施策で社員の気持ちに寄り添う(LITA)
コミュニケーション不足に苦しんでいるのは大企業だけではありません。2017年に起業したばかりのPR企業LITA(社員数10名)は、たくさんのユニークな取り組みでコミュニケーションを促進。社員が自宅に花を飾れるようにする費用(2,000円/月まで)を支給する「花セラピー」制度など、気持ちよく働ける仕組みを構築することで、ストレスの緩和、モチベーション向上などに成功しています。
そもそも働き過ぎを抑制すべき
ここまでテレワークのための健康管理施策を紹介してきましたが、そもそも改めるべきはテレワークによる働き過ぎです。残業はしないものの、進捗が気になってついつい深夜にメールをチェックしてしまう、などということも抑止する必要があります。
社員がダラダラと働き過ぎてしまうことを防ぐためには、社員がいつ、どのように働いているかをしっかり把握する必要があるでしょう。『NEC 働き方見える化サービスPlus』など、働き方の見える化を支援するサービスの導入も検討していきましょう。
まとめ
ここまで挙げた多くの事例のように、テレワークがうまくいっている企業は各社、さまざまな工夫を行っています。ただ漫然とテレワークを実施するだけでは、大きな成果は得られません。テレワークの効果を最大限に発揮するためにも、これらの先進企業を参考に積極的な施策を打っていきましょう。