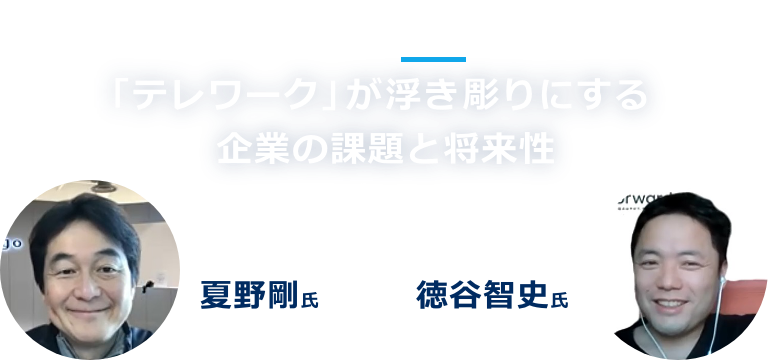サイト内の現在位置
特集

UPDATE : 2021.04.09
2020年4月の緊急事態宣言発令以降、日本中の企業で加速したテレワークの導入。国内オンラインエンタテインメントのリーディングカンパニーであるドワンゴの代表取締役・夏野剛氏と、リクルートグループや総合商社を支援するなど、組織・人材コンサルティングのリーディングカンパニーであるエッグフォワード代表取締役・徳谷智史氏は、これによって各社が潜在的に抱えていた課題と将来性が顕在化すると語る。
夏野 剛(なつの たけし)氏
株式会社ドワンゴ代表取締役社長・慶應義塾大学特別招聘教授
97年NTTドコモに入社。「iモード」「おサイフケータイ」などの多くのサービスを立ち上げ、執行役員を務めた。現在は、株式会社ムービーウォーカー代表取締役会長、KADOKAWA(2021年6月22日付けで代表取締役社長に就任予定)、トランスコスモス、セガサミーホールディングス、グリー、USEN-NEXT HOLDINGS、日本オラクルの取締役を兼任する。
徳谷 智史(とくや さとし)氏
エッグフォワード株式会社 代表取締役社長
組織・人財開発のプロフェッショナル。京都大学卒。大手戦略コンサル入社後、アジアオフィス代表を経て、人の可能性を最大化するべく、「世界唯一の人財開発企業」を目指しエッグフォワードを設立。総合商社、メガバンク、戦略コンサル、リクルートグループ等の大手からスタートアップまで、業界トップ企業数百社に人財・組織開発やマネジメント強化のコンサルティング・トレーニングを幅広く手がける。
同時に、キャリアの専門家として2万人を超えるビジネスパーソンの意思決定・成長支援を実施。NewsPicksキャリア分野プロフェッサー。東洋経済Online連載。著書「いま、決める力」等。
INDEX

緊急事態宣言解除後も
テレワークは続く? 続かない?
--都心部の緊急事態解除が間近とされている中(編集部注:取材後に緊急事態宣言の解除が決定しました)、我々が気になっているのはテレワークという働き方が今後も続くのかです。お二人はどのように考えていらっしゃいますか?
夏野:緊急事態宣言解除後のテレワークに対する企業の対応は大きく2つに分かれると考えられます。テレワークという働き方の良いところを採り入れて、リアルな出社も交えた形のベストミックスをきちんと編み出せる企業と、やっぱり昔は良かったと以前の形に戻そうとする企業ですね。
私は今回の新型コロナ禍は全ての働き手と経営者に大きな気付きを与えたと思っています。ここでその良さを活かした、進化したワークスタイルに変えられない企業は、正直、この先成長することはないだろうというくらいの気持ちでいます。ここでまた元に戻してしまう企業は、この後、成長が止まって生産性も上がっていかないと考えていいのではないでしょうか。
徳谷:私も全く同感です。結論から言うと、テレワークは今後も続いていきますが、夏野さんのおっしゃるように、企業の対応は大きく2つに分かれていくでしょう。
ただ、テレワークを上手に活かしていく企業にも、リアルの価値はある程度残っていくと考えています。ここぞという時やカルチャーを浸透させるためには、やはり対面の方が有効なシーンはあるので、完全に全てをテレワークにするということにはならないでしょうね。
--今後の企業のテレワーク活用は「2つに分かれていく」とのことですが、やれる企業とやらない企業の分かれ目はどこにあるでしょうか? たとえば業種、業態別に傾向があるとか……。
徳谷:経営トップがどこまで柔軟に変化に対応できるか、本気で変化する意志があるか、そこに尽きると思います。業種、業態による違いよりも、傾向として、やはりベンチャー企業はテレワークを積極的に活用していく方向にあるようです。そもそも、経営の意志として、対面の働き方を所与としていない会社も多い。
対して、古き良きトラディショナルな日本企業は原則出社に戻すところも多いようですが、これも規模感の違いというより、経営サイドの考え方の違いや固定観念によるところが大きいのではないかと思います。
夏野:本当に経営者次第ですよね。経営者が変える気がなければ変わらないし、経営者が変える気があればいくらでも変わる。ちなみに僕の知り合いのベンチャーには、社長が体育会系気質で完全に元に戻す、やっぱり顔を見てやりたいというところもあります。
徳谷:メルカリさんも新型コロナ禍前は対面重視とおっしゃっていましたけど、社会情勢に応じていち早くリモートに切り換えましたよね。本当に経営者次第なんだと思います。
ドワンゴ、エッグフォワードは
これまでも、これからもテレワークをフル活用
--「経営者次第」というお話が出てきたところで、お二人の会社、ドワンゴとエッグフォワードの取り組みについて教えてください。
夏野:ドワンゴは2020年2月14日にテレワーク移行を宣言し、3か月くらいやったところで充分にいけるということがわかったので、7月からは原則テレワークに変えてしまいました。
その時に、オフィスに固定席がほしいか、いらないかというアンケートをとっているのですが、約82%の社員が「いらない」ということで、今、彼らの固定席はオフィスにありません。
一方で残りの約18%、総務や人事部門などには固定席がほしいという人が多かったのですが、彼らにしても毎日出社しているわけではありません。結果として、オフィスフロアにだいぶ余裕ができたので全面的な改装を行い、ワンフロアは完全に会議室だけになっています。さらにもうワンフロアはスタジオにして、撮影があるときだけ来るようなかたちに改めました。
ですのでドワンゴの社員にとってオフィスとは毎日出社する場所ではなく、何かイベントがあるときに来る場所というふうに定義が変わっています。
そして、それに伴い、固定席のない、テレワークが主の社員に対しては月額2万円のリモートワーク手当を毎月恒久的にお支払いするという手を打っております。
--ドワンゴが、まだ緊急事態宣言が出ていない2月の時点から先駆けてテレワークに移行したのは当時も話題になりましたね。
徳谷:テレワーク手当をほぼ全社員に出すというのは素晴らしいですね。ちなみに、エッグフォワードでは以前から自由な働き方を推奨しているので、新型コロナ禍による大きな変化というのは特にありませんでした。
新入社員など、ケアやフォローが必要な場合は例外ですが、それ以外の社員については、“価値”をきちんと出せれば、いつ・どこで働いても自由です。働き方は人それぞれで、出社=価値ではないですよね。以前も、そしてこれからもそれは変わりません。
テレワークにおける“問題”のほとんどは
経営者の意識改革で解決できる
--なるほど。ただ、ドワンゴも、エッグフォワードも、日本の企業の中ではかなり先進的な部類に入ると思います。ですので、次の質問は「一般的な企業において」ということでお答えいただきたいのですが、今後、テレワークを積極的に推進して行くにあたり、どんな問題、課題があるのかを教えてください。
夏野:先に結論を言ってしまうと、「問題だ」と思っているだけで、実際に問題であることはほとんどないと思います。
以前のやり方に固執する人ほど、テレワークではあれができない、これができないと言いますよね。たとえば見よう見まねができないから新人教育ができないなんて言いますが、今どき、コンピューターで仕事するのに見よう見まねもないでしょう。隣に座って使い方を見てもらっても仕方がないわけで。
人事評価などもそう。リアルに会わないと評価できないなんていうのは印象論とか主観論でしかありません。そもそもの人事評価が間違っていたと思うべきです。
何にせよ、工夫次第でやりようはいくらでもあります。たとえば雑談が減ってしまったことによる社内コミュニケーションの低下が問題なら、お昼とか特定の時間を決めて、特に用がなくてもセクションのメンバーで話す場を設けるとかできますよね。
繰り返しますが、「問題だ」というのは新しい状況に適応できない人がそう言っているだけで、実は本質的には問題でもなんでもないと思っています。
--厳しい指摘ですが、詳しく説明されると納得しかありませんね……。徳谷さんはテレワークの問題、課題についてどのようにお考えですか?
徳谷:事実ベースで言うのであれば、世の中がテレワークに切り替わっていく中で、経営者や上司のマネジメント能力の低さ、業務設計の甘さが顕在化してしまうという問題が起きています。結果として、メンタル面での不調を訴える社員が増えたり、業務効率が落ちたり……。
対面が原則だった時代は、そういった部分を周囲がフォローしてごまかせていた部分もあったのですが、リモートではそうはいきません。目標設定やコンディション管理、業務の設計がそもそもきちんとできていないとスタックするのは当然のことです。要はテレワークの問題ではなく、もともとの設計の問題なのです。逆に、これを機に早めに対策したことで、これまで以上の成果を出せるようになっている企業も多いんですよ。
--やはりまずは経営サイドの意識改革が必要だと言うことですね。
徳谷:はい。あとは、先ほど夏野さんのお話にもあった雑談の件についても、最近かなり多くのご相談があります。
テレワークではどうしても目的をもったコミュニケーションが中心になってしまうので、ちょっとした雑談、特に違う部署の人と軽く話すといった業務外のやり取りが減ってしまうんですよね。そうすると、決まった枠の中だけで物事を考えるようになってしまって、部門横断で新しいアイデアが生まれたり、そこから何かプロジェクトが始まったりということもなくなってしまいます。イノベーションが生まれにくい組織風土になってしまうんです。感度の高い経営者は、この潜在的課題にも先んじて手を打っています。
企業の価値観が薄まらないようにする
仕組み作りが大切
--エッグフォワードではこうした相談に対して、どのようなコンサルティングを行っているのですか?
徳谷:エッグフォワードでは、全体のあるべき組織像や全体設計から入るコンサルティングも行いますが、トピックとしては『バーチャルランチクラブ for Biz』という部門横断のコミュニケーションツールを開発・提供しています。他の部門にどのような人がいて、どのような興味を持っているのかがわかり、部門の垣根を越えて、15分のビデオ通話ができるというもので、導入企業が増加しています。なお、こうした対策は企業ごとに状況や目的が異なるので絶対的な正解はありません。他にも、会議体の設計などから入っていくケースもあります。
--会議体の設計ですか? そのあたり、もう少し詳しく教えてください。
徳谷:たとえば、弊社が長くコンサルティングをさせていただいているリクルートグループさんは、全社会議をとても重視しています。弊社支援に限らない公開情報でもあるように、全社会議などでも、単に全員が参加するだけでなく、なるべく皆の顔が出るような設計にして、専門の司会者も立てて、テレビ番組さながらの作り込みをしているのは有名なお話です。
--なぜ、そこまでするのでしょうか?
徳谷:リクルートさんに限らず、組織強度が高い会社と言うのは社員全員が同じものを見て、同じ価値観を共有して、同じことを目指す、という一体感を持った体験を実現したいと考えています。しかし、社員同士の距離が物理的に大きいテレワークではそれが難しいので、各社さまざまなやり方を模索しています。規模は全く違いますが、エッグフォワードも同じ理由から全体会議には力を入れています。
--その他、一般の会社でできる取り組みはありますか?
徳谷:オフィスではなく自宅で働くことになるので、環境を整えるための費用やツールを提供する会社は多いですね。自宅をオフィスにしたときに、どうすれば快適に生産性高く働けるか、そこを会社としてきちんとサポートするところが増えてきました。
あとは、会社が大切にしている価値観やバリューがテレワークによって薄まってしまわないように、個人任せにせず、制度にきちんと組み込んでいくことが大事です。たとえば週報と関連付けて、バリューに基づいた行動がどれくらいできたのかを把握、それができている人を賞賛……要は定期的に、価値観に基づいた承認の機会を設けて、皆が同じ物差しで仕事に臨めるような仕組みを作るとかですね。
エッグフォワードでも以前からやっていますが、こうした取り組みを、最近あらためてきちんとやっていこうという企業がかなり増えてきています。会社としての基準を示すことになる他、周囲から認められることで孤立感もなくなりますし、それこそ部署の垣根を超えたコミュニケーションのきっかけにもなったりするんですよ。
ドワンゴでは1000人規模で
リモート忘年会を実施
--ドワンゴではいかがでしょうか?
夏野:ドワンゴではダイレクトコミュニケーションの場をいろいろと設定しています。たとえばこれまではマネージャークラスの管理職と社長の僕が直接コミュニケーションを取ることってあまりなかったのですが、オンラインならばそれが簡単にできるので積極的にやるようになりました。マネージャー希望者4名とZoomで話したりすると、これまで見えていなかったものが見えてきて面白いですよ。
こういう風にすると喜んでくれるのかとか、こちらの意図が全然伝わっていなかっただとか……。これ、昔の日本企業だと上司がフラフラと席のそばに行って話しかけるみたいなかたちで実現していたと思うのですが、今の時代、そのやり方は単なる仕事の邪魔なので、きちんと場を設けてコミュニケーションをしかけるというのが大事です。
--社長と対面で話す機会があるというのは、社員側にとっても大きな気付きになりそうですね。
夏野:もう1つ、新型コロナ禍で大きく変わったのが全社飲み会です。ドワンゴでは毎年年末にイベントスペースを借り切って、1000人規模で忘年会をやっていたのですが、2020年末はそれをZoomに切り換えて、1000人でのリモート忘年会をやりました。
--1000人ですか!?
夏野:もちろん、単に1000人を集めただけではありませんよ。部屋をたくさん作って各人が自由に移動できるようにし、そこで社長賞の表彰をして100万円の報奨金をあげたりするとけっこう盛り上がるんです。ちなみにその時は、全社員の自宅に食事を送って、食べているものは皆同じという環境を作りました。すごく面白かったので、今年もこのやり方でいいかなと思っています。
徳谷:同じ食事を届けるというのは面白いですね(笑)。
--こういったアイデアはどういうところから発想されるんですか?
夏野:リモートでのコミュニケーション活性化はアメリカ企業の取り組みが良くできていて参考になりますね。彼らは新型コロナ禍の前からテレワークを普通に使いこなしているんですよ。たとえば他部署の違うレイヤーの人をメンターとして指名することで、部署横断のコミュニケーションを活性化させるというのはシリコンバレーの企業ではわりと普通に行われていたりします。
日本企業もこういうときこそ、少し視野を広げて、テレワークで上手くやっている国や企業の制度、取り組みをどんどん採り入れていくのがいいんじゃないですかね。こういうことを言うと、すぐにうちの会社では無理とか言い出す人が現れるんですが、ちゃんと正しく実践すれば、何の障害もなく実現できるはずですよ。
ドワンゴでもない、エッグフォワードでもない、市井の一企業がテレワークを契機に働き方、会社の体質を変えていくことはできるのか?本対談の後編では、夏野氏、徳谷氏が、変革に向けて必要となる仕組み作りについて語ります。