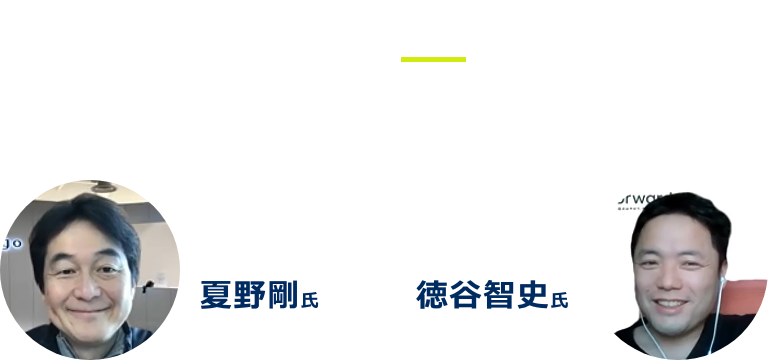サイト内の現在位置
特集

UPDATE : 2021.04.09
新型コロナ禍をきっかけとしたテレワーク移行が浮き彫りにした国内企業のさまざまな、問題、課題を、新時代のビジネスリーダーであるドワンゴ夏野剛氏、エッグフォワード徳谷智史氏が一刀両断するスペシャル対談。後編では、アフターコロナ時代のあるべき働き方、新しい働き方で「成果」を得るためにどうすれば良いのかを両氏に訊く。
夏野 剛(なつの たけし)氏
株式会社ドワンゴ代表取締役社長・慶應義塾大学特別招聘教授
97年NTTドコモに入社。「iモード」「おサイフケータイ」などの多くのサービスを立ち上げ、執行役員を務めた。現在は、株式会社ムービーウォーカー代表取締役会長、KADOKAWA(2021年6月22日付けで代表取締役社長に就任予定)、トランスコスモス、セガサミーホールディングス、グリー、USEN-NEXT HOLDINGS、日本オラクルの取締役を兼任する。
徳谷 智史(とくや さとし)氏
エッグフォワード株式会社 代表取締役社長
組織・人財開発のプロフェッショナル。京都大学卒。大手戦略コンサル入社後、アジアオフィス代表を経て、人の可能性を最大化するべく、「世界唯一の人財開発企業」を目指しエッグフォワードを設立。総合商社、メガバンク、戦略コンサル、リクルートグループ等の大手からスタートアップまで、業界トップ企業数百社に人財・組織開発やマネジメント強化のコンサルティング・トレーニングを幅広く手がける。
同時に、キャリアの専門家として2万人を超えるビジネスパーソンの意思決定・成長支援を実施。NewsPicksキャリア分野プロフェッサー。東洋経済Online連載。著書「いま、決める力」等。

そもそも問題の本質は
「テレワークだから」ではない
--前編ではテレワークで発生しうる問題・課題を、ドワンゴやエッグフォワードを含む先進的な企業がどのように解決しているのか、取り組みをたくさん聞かせていただきました。その流れでもう1つ、現在問題になっていることについてお話をきかせてください。
それは「労働時間」です。経営者の側からすると社員がサボっているのではないかと疑ってしまい、社員の側からすると拘束時間のむやみな長期化と、みなし残業のような問題がおきてしまうようなのですが、この辺り、お二人はどのようにお考えですか?
夏野:リアルに会社に出勤していても、サボる人間はサボっていますよね。テレワークだとサボるのではないかなんていう考え方は、そもそも古いですよ。間違っています。
徳谷:私も同感です。テレワークだから、テレワークじゃないからというのは問題の本質ではありません。業務管理ができていないところは、テレワークだろうが、そうでなかろうができていないんですよね。なので、そういう問題が出てきたと感じている企業は、むしろこれをよい機会と捉えて、改善していくようにすべきだと思います。
--前編でもお話ししていた「企業が抱えていた問題がテレワークによって顕在化される」ということですね。
徳谷:その通りです。これは何も労働時間の問題だけでなく、全ての業務に当てはまります。最近、テレワークによる効率低下をきっかけにコンサルティングの依頼をされることが多いのですが、よくよく聞いてみると、特に営業などで顕著ですが、業務プロセスが全然設計されていないことがほとんどなんです。それは本当にテレワークの問題ですか、と。
--そうなる原因って、どんなところにあるのでしょうか?
夏野:やはり経営者です。経営者が「(テレワークは)顔を見て話せないからイヤだ」とか言っている会社ではそういうことが起こりがち。でもそれってテレワークの問題ではなくて、ただの感情ですよね。こういうことを言っている人の経営している会社は新しい環境に適応できないので、放っておけばいいんじゃないですかね。
--もし、自分の勤めている会社の経営者や上司がそういう人だった場合は……。
夏野:転職したほうがいいですよ! 日本人は、なぜか自分がおかしいなと思うことが続く会社に居続けねばならないと考えてしまいがち。我慢して、時間をかけて中から変えていきたいなんて言う人もいますが、それは不可能です。なぜなら権限がありませんから。21世紀において、組織をボトムアップで変えていくなんてことはありえません。
--なるほど……。では経営者が意識を改め、トップダウンで会社の体質を変えていくにはどうすればいいとお考えですか?
夏野:インセンティブ設計に尽きると思います。先ほど(前編)でもお話ししたよう、ドワンゴでは毎月2万円のテレワーク手当を出しています。それに加えて、毎日オフィスまで通う時間も必要なくなりますよね。一般的なビジネスマンは準備の時間も含めたら毎日2時間以上通勤に使っているわけです。それって人生の壮大な無駄だと思いませんか? もし、社員がそれに気がついていないのであれば、経営者はそれに気付かせるべき。それによって社員の人生が豊かで幸せになれば、クリエイティビティも上がっていくんですよ。
徳谷:ここまでのお話、終始、夏野さんに共感しかありません。企業が上から変わっていくというのもその通りだと思います。
ルールで縛るのではなく、
社員の内発的動機を引き出すことが重要
--今、夏野さんからインセンティブでテレワーク移行を促すというお話がありましたが、徳谷さんとしてはどういったやり方があるとお考えですか?
徳谷:仕組みという観点でお話すると、経営者も含めて、社員一人ひとりが自分の頭で考えるような仕組み作りが大事だと考えています。何が現在の組織課題で、どこを目指していくのかといったことを当事者である社員が提言して、そしてそれをきちんと汲み取れるような組織にしなければなりません。
そのためには、「内発的動機」を上手く引き出せるようにすることです。今、マネジメントが上手くいっている企業のほとんどがそのように転換していっています。「テレワークじゃなければいけません」「週何日までしか出勤してはいけません」といったルールのみで縛るやり方、言うなれば外発的な動機付けは、これからの時代機能しなくなっていくと思います。
本人のやりたいことをどう引き出すか、それと会社の目指すゴールをどう重ねるか。そこにちゃんと納得感を持たせることができれば、あとはそのベストなやり方を一緒に考える。たとえば、弊社がお手伝いをさせていただいているリクルートさんには「Will・Can・Must」という考え方がありますが、そういうソフト面での仕組みを強化していく必要性は、このコロナ禍においてますます大きくなってきていると感じています。
ハード面について考えるのであれば、「目標」と「評価」でしょうね。労働時間に対する生産性や価値というところに目標を置いてしまえば、テレワークであろうとなかろうと、自然と効率的な働き方を個々が志向していくようになります。
夏野:ルールで縛るのが違うというのは私も同感です。ドワンゴがテレワークを推し進めているのも、なにもテレワークが絶対に正しいからルール化したいのではなく、多くのシーンにおいて、テレワークの方が効率的だからというだけ。別に強制したいわけじゃないんです。自分の判断でどっちが効率的なのかを考えればいい。実際、私だって、全てをリモートでやっているわけではありません。必要なときは出社しているわけですから。
大切なのは社員一人ひとりがきちんと考えるようにしていくこと。最終的にはそれがもっとも効率的なんだと思いますよ。
徳谷:そのあたり、少し実例を挙げる形で補足させてください。私たちも創業当初から組織育成や変革コーチングなどの面で一部サポートさせていただいているユーザベースさんというベンチャー企業(編集部注:ソーシャル経済メディア『NewsPicks』や、経済情報プラットフォーム『SPEEDA』などを運営)は、会社のルールだからこうする、ではなくて、チーム単位で、自分たちの頭で考えてやり方を選んでいくんですよね。部署やシーンによってベストな働き方は変わってきますから、共通のルールに無理矢理はめ込んでも意味がないことをよくわかっているんです。
このときに大切なのが、組織の上位概念の目標が何なのかをきちんと浸透させておくこと。これは、一般に「OKR(Objectives and Key Results)」と言うのですが、きちんとObjectives(目標)を決めて、その下にKey Results(成果)を置いてあげれば、あとは各自、各部署がベストなやり方を追求するようになります。
まずはゼロベースで考えよう、
そして外をちゃんと見よう
--最後に、ここまでのお話を踏まえた上で、これからの時代、我々がどのように働いていくべきなのか、アドバイス、メッセージをいただけますか。
夏野:とにかくやってみよう、ということですね。世の中にはやってもいないのにできないと文句を言う人が多すぎる。その状況でベストな施策がなんなのかは手探りしないとわかりません。その上で、だいたいのことはやってみればやれることだったと分かります。そのために役立つツールもたくさん出ているので、とりあえずまずはやってみる。それが一番大事だと思います。
特に経営者側がトップダウンでやってみるということが極めて重要ですね。テレワークの効率化は日本的なメンバーシップ型雇用ではやりにくいということを言う人もいますが、関係ないと思いますよ。まずはやるという決意、です。
--徳谷さんはいかがですか?
徳谷:そうですね、2つあります。1つ目は、「目的に対してゼロベースで考えよう」ということ。結局、働き方というのは手段でしかないので、前例はひとまずおいて、目的にたどり着くためにどういうアプローチがあり得るのかをしっかり考えてほしいですね。これは経営者だけでなく、現場レベルでも同じです。上司がこう言っているからではなく、ちゃんと自分でも考えてほしい。
2つ目は、「外をちゃんと見よう」ということ。働き方ひとつとっても、経営者はなぜか同じ業種、業界内での比較をしたがるのですが、もはや「我々は製造業だから」とか「我々は飲食業だから」といった業界の概念で考えることに意味がなくなりつつあります。たとえば製造業でもIT関連事業をやっているようなところがあったりするわけですが、それは従来の業界の枠の中で語れるのかといった具合ですね。
ですから、経営視点でも外や未来をしっかり見るようにしてほしいですね。それは個人視点でも同じ。自分の組織に課題があると感じたら、まず外を見てみてほしいです。
ちなみに、外というのはよその企業というだけでなく、自社の別の部署も含みます。テレワークでは他の部署やプロジェクトに首を突っ込みやすくなるので、常にアンテナを張っておくのは大事なのではないかなと。
夏野:あ、それはドワンゴでもやっていますね。先ほどもお話ししたよう、テレワークに移行した人は各人2時間以上の時間的余裕ができたので、その時間を使って他の仕事をやってみたり、他の部署と兼務してみたりという社員がこの1年でものすごく増えました。
この効果は絶大でしたね。なにせ、わずかな人件費でものすごい知見のある人を使えてしまうわけですから。働く側にとっても面白い仕事だったら全然苦になりませんし、収入も増えるしで、今そうした取り組みを強化しているところです。
こうした、貴重な人的リソースをグループ内で共有できるみたいなことは、テレワークだからこそ実現できることの1つではないでしょうか。
徳谷:本当にそう思います。テレワークで、逆に効率化されすぎて、スケジュールがタイトすぎるみたいなお話も聞きますが、本当は、今後の目指す組織や事業の在り方を踏まえて、メリットも多く享受できるはず。テレワークという手段にとらわれすぎず、経営側は上段からきちんと考えていただきたいですね。
--本日は貴重なお話、本当にありがとうございました。