サイト内の現在位置
コラム
大きく変化した働き方のスタイル。これからどうなる?
「働く」ことに対する意識の変容に遅れを取ってはならない

UPDATE : 2022.10.07
多くの人が気軽に集うのが当たり前だった時と比べ、コロナ禍を経たことで働き方が大きく見直され、さまざまな取り組みをスタートする企業が多く見られるようになりました。「働く」ということへの心構えや仕事の進め方がどんどん変容する中で、果たして現在のオフィスはどうあるべきなのでしょう。さまざまな企業の働き方の変化を間近で見てきた「はやし総合支援事務所」の代表・林雄次さんに、企業の動向とテレワークをうまく活かす方法、そして今後どうあるべきかについて、率直にお聞きしました。
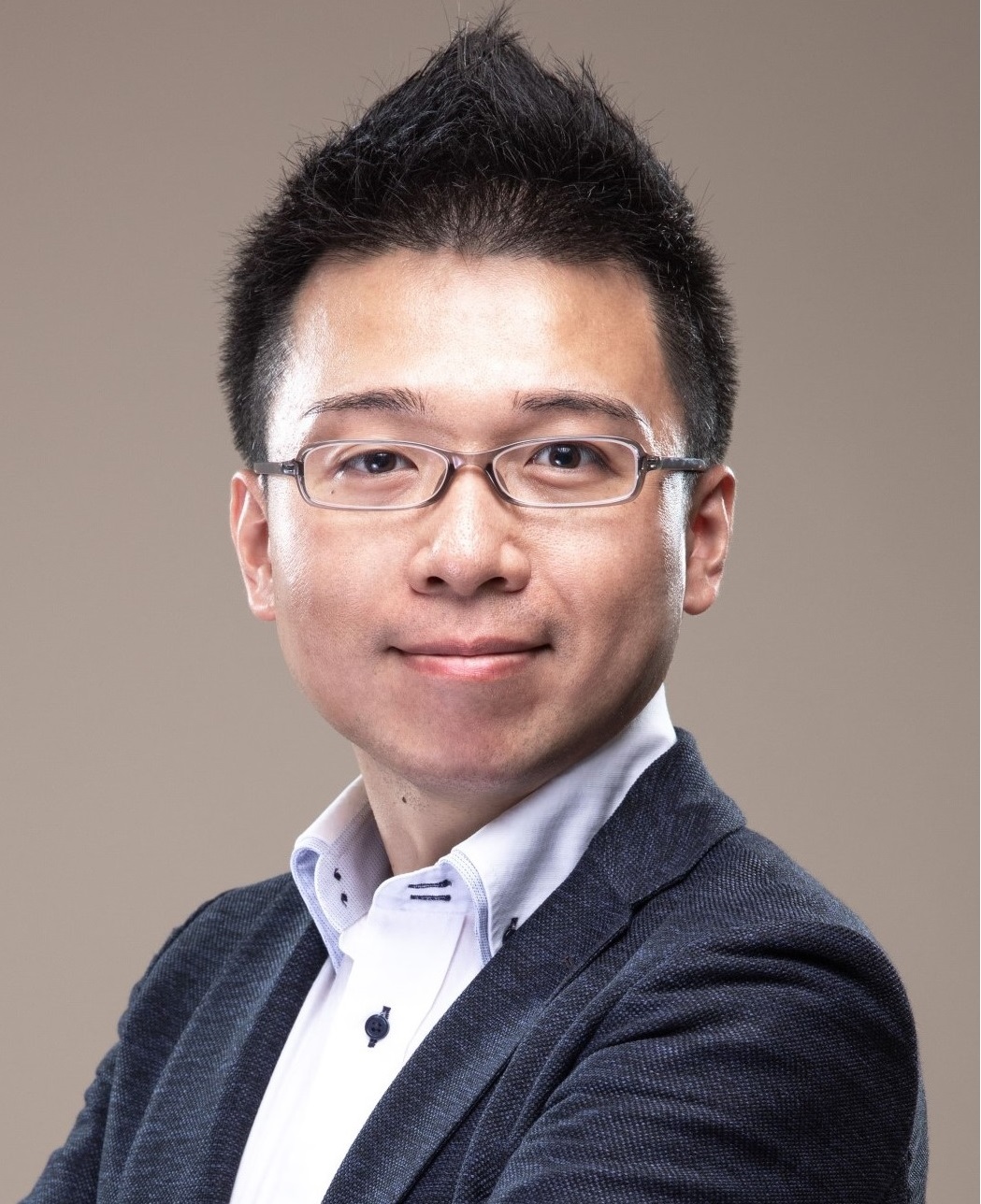
プロフィール
林 雄次(はやし ゆうじ)さん
はやし総合支援事務所 代表
大手IT企業でシステム開発に従事。社会保険労務士と行政書士の資格を取得し、2018年に開業。開業以来、職員全員がテレワークを実施するなど、ITを駆使した効率的な事務所運営を行っている。
また、中小企業診断士、情報処理安全確保支援など多数の資格を所有し、企業の業務改善も数多く手がける。
INDEX
- 実際のところ、各企業でテレワークは続いている?
- せっかくの多様な働き方を活かしきれていない
- リモートワークにおける労働時間の問題点
- テレワークを進めるにあたって重要な「準備期間」
- 現状の業務内容を書き出す
- 業務の無駄を省いていく
- 新しい業務フローを作る
- 必要なツールを導入する
- テレワークでおすすめのツールやサービス
- 勤怠管理
- 電話サービス
- 電子契約の推進
- 将来的な人材確保においても多様な働き方について考えたい
- まとめ
実際のところ、各企業でテレワークは続いている?
これまで「働く」ということは会社に通勤することであり、何かリアルな、実態を持ったものであったと思います。それがコロナ禍で物理的に集まることが難しくなったことで、「働く」ことは「会社に行く」こととセットではなくなった。働くこと自体の考え方がコロナ禍前と比べて明らかに変わってきたように思います。
ただ、情勢が比較的落ち着き経済活動が元通りになると、これまで通りの働き方に戻す企業が多い傾向にあります。興味深いのは、テレワークをやめた理由が必ずしも上層部の意向だけではないということ。従業員からも「テレワークは仕事がしにくいから、これまでの“集まって働く”仕事の仕方に戻したい」という意見が多く集まっているようです。

テレワークやリモートワークは、ちゃんと活用すればとてもいい働き方だと個人的には思っています。私自身を振り返ってみても、会社勤めの時代から裁量労働制でさまざまな案件を処理していたので直行直帰がほとんどで、何の問題もありませんでした。また、そのような環境で開業したこともあって移動中にはPCで事務処理を行い、客先でも打ち合わせや作業をするなど1日中さまざまな場所で仕事をし、結果的に現在は従業員も含めて完全テレワークです。
せっかくの多様な働き方を活かしきれていない
テレワークだからといってゆるく仕事をしているわけではもちろんありません。時間や場所に捉われずに仕事をしている関係で、休日に溜まった作業をすることもありますが、その分平日にワーケーションを取って調節したりもします。
テレワークを実行するには制度や仕組みを整える必要がありますが、きちんと理解して遂行すれば、会社にとっても従業員にとってもメリットの大きい働き方だと感じます 。
しかしそういったテレワークの良さを分かっていなかったり、未経験であったりすることから、なかなか実行に移しにくい一面もあります。コロナ禍で一時的に行ったテレワークという環境を活かしきれないまま徐々に元通りになっていくと普及しようとしても難しい。そんなジレンマが各企業にあるように思います。
リモートワークにおける労働時間の問題点
最近増えているリモートワークを見てみると、実はここにも労働時間に関する新たな問題が出てきています。会社への帰属意識が強すぎる従業員がリモートワークをすると、残業時間をつけずにたくさん働いてしまうという問題です。ここには組織・個人、両方の問題が潜んでいます。
まずリモートワークでの長時間労働による組織側のメリットとしては少ない経費でアウトプットが増えると考えられていること、そして個人のメリットとしては短時間で高いアウトプットであると判断され、実績だけ積み増せることです。
一見両者のメリットが合致してうまく回っているようにも見えますが、実際は従業員が帰属意識のもとでかなり無理をしている状態。「長時間労働のデメリット」でも提示した事態がいつ起こるか分からない綱渡りが続き、結果的に組織の負担へ繋がります。 そうならないためには、「正しい時間で正しいアウトプット」が大切です。そうできない従業員が多数いるのであれば、会社として新たな施策を考えるべきでしょう。そして「正しい時間で正しいアウトプット」ができているかどうか把握するために、労働時間や業務内容をきちんと記録することがとても重要です。
テレワークを進めるにあたって重要な「準備期間」
テレワークがうまく機能すれば、満員電車に疲弊することもなく、自分の用事にもフレキシブルに対応でき、多様な働き方ができるようになります。しかし、せっかくのテレワークの良さを享受できないままの企業もあります。これはなぜなのでしょうか。
私は、テレワークのための準備期間をしっかりと設けていなかったことに理由があると考えています。
準備期間とはどういうものか。以下にその流れをご紹介します。
①現状の業務内容を書き出す
一人ひとりの業務内容を考えてみると、実は明文化されていないものが意外と多いことに気づくはずです。例えば、Aさんは基本的にはBという業務を遂行するけれど、昔からCという会社と懇意にしているから、Cの業務はAさんがやる、などいったケースはどこの会社でもあるのではないでしょうか。 空気感でなんとなくみんなが把握しているような仕事が実は多分にあって、会社に集っていたときにはその場の空気で共有できていました。しかしテレワークにおいてはそれができないので、きちんと明文化しないと「あの仕事は誰がやったの?」という事態が頻発して破綻します。そのために、まずは業務内容の棚卸しのような感覚で、一人ひとりの仕事内容を書き出すことが必要です。
②業務の無駄を省いていく
仕事内容がきちんと把握できたら、次はやめられる部分を選別する作業に入ります。
テレワークをはじめ業務の効率化を考えたとき、ツールを導入するなどの新たな施策を考えがちです。しかし、現状の業務でいっぱいいっぱいのところ新たにやらなければならないことを追加すれば業務を圧迫し、これも破綻へと繋がります。
無駄だと思われる部分を省いて業務のスリム化を目指していきます。
③新しい業務フローを作る
やるべき業務がしっかりと見えた段階で、テレワーク用の業務フローを作っていきます。 郵便物が届いたときにはどうするかや、請求書を発行する際の流れなど、細かな業務一つひとつをメンバーに振り分け、誰が何をやるかを明確にしていきます。
④必要なツールを導入する
そこまでして、ようやくツールを導入します。 ここまで細かく整えていれば、どのツールを使えばテレワークがしやすいのかが明確にわかるはずです。無駄のない効率的なテレワークのためのツールやサービスを導入しましょう。

テレワークでおすすめのツールやサービス
テレワークがしやすいよう、さまざまなツールやサービスがリリースされています。おすすめのサービスをいくつかご紹介してみます。
■勤怠管理
テレワーク下においていちばん気になるのが勤怠管理ではないでしょうか。企業からもテレワークでの勤怠管理についてご相談を受けることがよくあります。その際には「なるべくライトなものを導入してください」とお伝えするようにしています。
PC起動中はずっと画面録画をする、というようなアプリもありますが、これは明らかに従業員にとって負担です。100%管理することはどうしてもできないと理解して、かつ放ったらかしではないことが示せるライトな勤怠管理ツールの導入をおすすめします。
■電話サービス
オフィスに掛かってきた電話を従業員のスマートフォンに転送するサービスです。例えば弊社の場合、市外局番03の会社の電話番号に電話が掛かってきた場合、0秒でIP電話に転送する流れになっています。
その上で従業員全員のスマートフォンにIP電話のアプリを入れており、全員のスマートフォンが10秒間鳴ります。そこで取れなかったらさらに別の電話サービスに転送され、電話の内容を聞き取ってチャットで送ってくれる。従業員はそのチャットを見て「私が折り返します」などのリアクションが取れます。
これなら電話の取り逃がしがないため、オフィスにある物理の電話よりもサービスレベルが上がっているといえます。
■電子契約の推進
契約書でのやりとりが必要なときには、電子契約を推奨しています。そもそも契約は、契約書を交わしたことで成立するのではなく、「契約しましょう」という意志の合致だけで成立するもの。契約書がまるで契約を司る“魔法の紙”のような印象を持たれていますが、単なる成立時のメモ書きのようなものなので、ほとんどの場合が電子契約で全く問題ありません。 もちろん従前のやり方にこだわる会社もあろうかと思いますので、その際は柔軟に対応すると良いでしょう。
そのほかにも、インターネットFAX、クラウドストレージ、データベース、メールの共有システム、チャットなど、弊社では10前後のサービスを利用しています。 業務の中にはどうしても代行できないもの、例えば郵便物をはじめ物理的に“モノ”が届く場合においては、開封し中身を見て振り分ける、という作業が必要になってきます。こういった細かな業務に関しても誰が担当するのかを明確にし、スムーズなテレワークを叶えたいところです。
将来的な人材確保においても多様な働き方について考えたい
2010年代、テレワークをなかなか実行に移せなかった企業が多くあった中で、2020年のコロナ禍で半強制的にテレワークが始まり、じわじわと新しい働き方を模索する企業が出てきました。これをきっかけに働くということ自体を見直す動きや、働くことを再定義しようとする企業も増えていくのではないでしょうか。

これから社会へ出ていく若い人材の中にも、仕事の内容よりも、柔軟な働き方ができるかどうかを優先して会社を選ぶ人が多くなってくることでしょう。日本は今後少子高齢化の時代に突入し、将来的に人材確保が難しくなるのは自明の理です。だからこそ、今この時代に新しい働き方に移行していけるかどうかは、20年後生き残っているかどうかにも繋がるのではないでしょうか。今のままの会社のあり方で規模を維持するのは厳しくなるに違いありません。
まとめ
フィルムカメラ全盛の時代から、約20年かけてデジタルカメラが当たり前の時代へとじわじわ移り変わっていったように、働き方もじわじわと変わり、いつの間にかテレワークをはじめとした新たな働き方がスタンダードな時代が訪れる。そこに乗り遅れないためにも、多様な働き方についてもう一度考える機会を持ってみるべきではないでしょうか。











