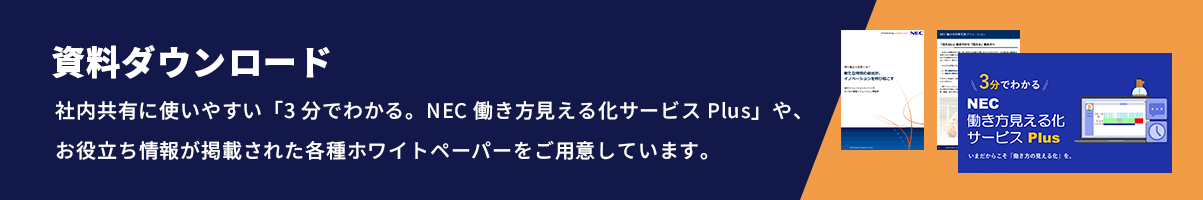サイト内の現在位置
【在宅勤務にも対応】
社内コミュニケーション活性化の方法“8選”!

在宅勤務の増加や働き方改革の影響もあり、社内コミュニケーションに課題を感じる企業が増えています。社内報や研修、コミュニケーションツール、ラフな面談などの活用で、コミュニケーションの活性化を図ることが大切です。
【在宅勤務にも対応】社内コミュニケーション活性化の方法“8選”!
フレックスタイムや時短勤務をはじめ、働き方の多様化が進んでいます。それに伴い、従業員同士が顔を合わせてコミュニケーションを取る機会が減ってきているのも事実です。「在宅勤務が導入されてから、社内のコミュニケーションが減ってしまった」と悩む企業も多いかもしれません。そこで今回は、社内コミュニケーションを活性化させるために、今知っておくべきノウハウを分かりやすく紹介します。在宅勤務におけるコミュニケーションを活性化させる方法についても解説しますので、ぜひ自社の働き方を見直す際の参考にしてみてください。
- ※在宅勤務におけるメリットや課題、解決方法について詳しく知りたい方は合わせてご一読ください。
在宅勤務にありがちな悩みとは?解決法“4選”も紹介!【人事・上司必読】
社内コミュニケーションとは?
社内コミュニケーションとは、従業員同士・上司と部下・経営層と従業員が円滑にコミュニケーションを取り合い、連携を図ることです。お互いがスキルや知識を共有し合い、組織全体で高め合うことで、より大きな利益を生むという目的があります。特に日本は労働力人口が漸減しており、今までより生産性を高めなければいけない現状です。社内コミュニケーションの活性化によって連携が進めば、組織全体の生産性向上も期待できます。
社内コミュニケーションが重要になってきた背景とは?
それでは、社内コミュニケーションがより重要になってきた理由には、どんなものがあるのでしょうか。時代背景も踏まえながら、大きく2つの観点で解説します。
(1)労働観の変化
近年は労働観が大きく変化しており、「仕事と私生活のバランスを重視したい」「仕事よりプライベートを充実させたい」と考える人が増えています。自分の時間や家庭を優先する人が増え、仕事終わりのいわゆる“飲みニケーション”の場も減っているかもしれません。こうした変化から、自然と社内の関係も希薄になってきています。
また、先読みが難しい時代ということもあり、日本ではこれまで当たり前だった終身雇用制度が崩れ始めています。「新卒で入社した会社に、定年まで勤め上げる」という常識も通用しなくなってきました。転職や独立で人材の流動性が高まるなか、「どうせ数年後にはいなくなるので、社内の人間関係には固執しなくてもいい」と考える人も増えています。結果として、多くの企業で社内コミュニケーションや連携の文化が薄れつつあるのです。
(2)「働き方改革」によるワークスタイルの多様化
政府が推し進める働き方改革では、「誰もが個々の事情に応じた、多様で柔軟な働き方ができる社会をつくる」ことが目的として掲げられています。こうした動きのなかで、在宅勤務や裁量労働制、時短勤務やフレックスタイム制度などの新しいワークスタイルも広まってきました。結果として、個々が自由な時間に出社・退社できるようになり、顔を合わせてやりとりする機会も減ってきています。特に在宅勤務においては、従業員同士が離れた場所で働くため、コミュニケーションが希薄になり、業務を進めにくくなることが問題視されているのです。
社内のどこに、コミュニケーションの課題があるのか?
HR総研が人事担当者を対象に行ったアンケート調査によれば、「社内のコミュニケーションに課題を感じている」と答えた企業の割合は約8割にものぼりました。かつ、「コミュニケーション不足は業務の障害になる」と答えた企業の割合は97%にものぼり、いかに企業が社内のコミュニケーション不足に苦心しているかがうかがえます。
では、具体的に社内のどこでコミュニケーションの“壁”が発生しているのでしょうか。ここでは、「上司と部下」「メンバー同士」「部門間・事業所間」「経営層と従業員」という4つの人間関係における課題を紹介します。
(1)上司と部下
業務を進めるうえで、上司と部下の間に溝を感じている企業も多いようです。例えば、「上司が部下の働きぶりに関心を持たない」「上司が部下に仕事を任せきりで、ほとんどアドバイスやサポートをしない」「部下は上司をメールのCCに入れれば、報告がすむと思っている」などの内容が挙げられます。上司と部下のコミュニケーションが不足すると、トラブル発生時の対応が遅れたり、適正な人事評価を行えなかったりといった弊害も生まれかねません。
(2)メンバー同士
部署内の従業員同士が、コミュニケーション不足に陥っている企業もあります。例えば、「最低限の会話しか交わさないので、いざというときに相談できる相手がいない」「先輩から後輩への教育が行き届いていない」「お互いの問題点を指摘しないので、成長がない」などです。メンバー同士のコミュニケーションが不足すると、連携が進まないのはもちろんのこと、スキルやノウハウの伝承が行われず組織全体が停滞してしまう懸念もあります。
(3)部門間・事業所間
先に紹介したHR総研のアンケート調査では、コミュニケーション不足が生じている箇所に関して「部門・事業所間」と答えた人の割合が68%でトップでした。例えば、「各部署が協力し合わない“セクショナリズム”に陥っている」「問題が起こったとき、部署同士が責任をなすりつけ合おうとする」「別の部署に仕事を頼むとき、誰に依頼すればいいか分からない」などです。部門間の連携が取れていないと、組織全体の生産性低下を招きます。
(4)経営層と従業員
経営層と従業員の間に、コミュニケーション不足を感じている企業も多いです。例えば、「経営方針やビジョンが従業員に浸透していない」「経営層が従業員の意見にまったく耳を傾けようとしない」などが挙げられます。経営層の想いが正しく従業員に伝わっていないと、組織全体のモチベーション低下にもつながりかねません。
社内コミュニケーションのメリットとは?
それでは、社内コミュニケーションの活性化による企業のメリットとは何でしょうか。大きく6つ紹介します。
(1)生産性の向上
社内コミュニケーションが活発になると、部署間・従業員間で連携が進むようになります。全員で協力して業務を行えるようになるため、一部の人が業務を抱え込む心配もなくなり、組織全体の生産性も向上するでしょう。また、ノウハウの横展開が進むことで、個々のスキルアップが可能になり、会社としての成長も期待できます。
(2)従業員の満足度向上
コミュニケーションが活性化すると、従業員が自分の意見を発しやすくなり、居心地の良い空間が生まれます。結果として、従業員の満足度が高まり、エンゲージメント(会社のために貢献しようという意欲)の向上にもつながるでしょう。これと関連深い言葉に、「心理的安全性」があります。心理的安全性とは、誰もが「自分は尊重されており、意見を否定されない」という確信を持ち、自由に発言・行動ができる状態を指す言葉です。社内コミュニケーションを活性化させることで、この心理的安全性を育み、従業員の安心感を高めることもできます。
(3)顧客の満足度向上
部署間や従業員間でコミュニケーションが取れていると、万が一のトラブル時にも迅速に連携しやすくなります。例えば、顧客からのクレームが発生した際にも、すぐに関係部署が情報を共有し合って対応できるようになるでしょう。結果として顧客から「社内連携が取れている会社」としてイメージされ、顧客満足度も向上できます。
(4)イノベーションの創出
社内コミュニケーションが活性化している会社では、アイデアも活発に出し合える社風が生まれます。例えば、異なる部署のメンバー同士が集まり、イノベーション創出のプロジェクトを発足させようとする気運も高まるでしょう。結果として、新しい商品やサービスが生まれやすくなり、会社全体の利益につながる可能性も高いです。
(5)不正行為の抑制
社内コミュニケーションが活発ということは、従業員がお互いの働きぶりに興味・関心を持っているということです。もしある従業員がコンプライアンス違反をしようとしても、別の従業員が気づきやすくなり、注意できるようになります。結果、不正行為の抑制につながり、企業としてトラブルを未然に防ぐこともできるでしょう。
(6)企業イメージの向上
社内コミュニケーションが盛んな会社は、「働きやすい会社」「居心地の良い会社」として従業員からの評価が高まります。それに伴い、対外的なイメージも高まるでしょう。求人広告や面接でも、「従業員の満足度が高い会社」として求職者にアピールできるようになるはずです。結果として、多くの志望者が集まることも期待できます。社内コミュニケーションは従業員の流出を防げるだけでなく、優秀な人材の確保にもつながりやすいのです。
社内コミュニケーションを活性化させる“8つ”の方法!
それでは、実際にどのような方法で社内コミュニケーションを活性化させればよいのでしょうか。
企業が取り組むべき施策として、大きく8つ紹介します。
(1)コミュニケーションツールの導入
チャットツールや社内SNSを導入することで、従業員同士がより気軽にコミュニケーションを取れるようになります。メールではどうしても形式張った文章になってしまいますが、こうしたコミュニケーションツールならひと言だけのメッセージやスタンプでラフにやりとりできるものです。また、タスク管理やToDoリストの作成も行える「グループウェア」であれば、コミュニケーション活性化と同時に業務の効率化もかなえられるでしょう。
(2)レクリエーションイベント
従業員が参加したくなるような社内イベントを企画するのも、ひとつの手法です。例えば、スポーツ大会や部署をまたいだ親睦飲み会、趣味でつながるイベントなどが挙げられます。同じ人ばかりではなく、できるだけ幅広い職種・志向性の人が参加できるように、イベント内容を工夫することが大切です。また、企業が主催するというよりは、従業員に主体となって企画・運営してもらう方がよりコミュニケーションが活性化されるでしょう。
(3)社内報
社内報で会社の出来事を伝えるのも、コミュニケーションの活性化につながります。例えば、毎月異なる部署の従業員にインタビューしたり、象徴的な活躍をした従業員のノウハウを紹介したりと、できるだけさまざまな人が登場する場になるとよいです。その方が読み手も多くの人と間接的に面識を持つことができ、会ったときに声もかけやすくなるでしょう。Webで社外に公開して、ブランディングにつなげられるのも社内報の魅力です。
(4)社内研修
社内研修を通じて、スキルアップと同時に従業員同士の仲を深めることもできます。グループワークやワークショップで意見を交わすことで、お互いの知らなかった一面を理解できるようになるでしょう。例えば、さまざまな部署のミドルマネジメント層を集めて、「チームビルディング」に関する研修を行うとします。そうすれば普段なかなか会うことのない管理職同士が意見交換でき、いざというとき相談できる相手も見つけられるはずです。
(5)オフィスレイアウトの工夫
自然と会話が生まれるようなオフィスの配置にすることも、効果的です。例えば、各人が席を自由に決められる「フリーアドレス制」にすれば、普段話さない人とも会話が生まれます。また、休憩室を新たに作ることで、息抜きがてら気軽に従業員同士が話せるようになるでしょう。休憩室を新たに増設するのが難しい場合は、オフィスの空いているスペースにコーヒーメーカーを置くだけでも、従業員がラフに集まれる空間が自然と生まれます。
(6)部活・サークル
趣味でつながれる部活やサークルも、コミュニケーションの活性化には最適だと言えます。部活・サークルの良いところは、業務で接点がないような従業員同士も、無理なく親睦を深められることです。運営にはどうしても資金が必要になるため、会社公認の部活・サークルには会社から補助金を支給するといった制度も有効でしょう。
(7)面談
面談を通じて、上司と部下がコミュニケーションを図ることも大切です。例えば、上司と部下が1対1で行う、「1on1ミーティング」も効果的でしょう。1on1ミーティングは一般的な面談と違い、業務と関係ないプライベートな話題や悩みもラフに話すのが特徴です。そのため、部下が上司に対して気軽に相談できるようになります。
(8)柔軟な人事制度
従業員がさまざまな部署に異動し、人脈を広げられるような人事制度も効果的です。そのひとつとして、従業員が一定期間、別の部署で業務を行う「社内留学」が挙げられます。普段とは違う場所に身を置くことで、新しいスキルを獲得できるのと同時に、さまざまな職種の人たちと親睦を深めることができるでしょう。また、従業員が自らの意志で異動先を選べる「社内FA制度」も、コミュニケーション活性化のきっかけとして有効です。
在宅勤務で社内コミュニケーションを活性化させるポイントとは?
「COVID-19」の影響から、在宅勤務を導入した企業も多いかもしれません。デル・テクノロジーズ株式会社が中堅企業を対象に行ったアンケート調査では、2020年6月時点で63.9%の企業がテレワークや在宅勤務を実施しています。一方で、同調査で「今後は在宅勤務を継続しない」と回答した企業の多くが、その理由を「コミュニケーションが難しい」と答えました。社内コミュニケーションの不足は、在宅勤務でより顕著になる傾向があるようです。
そこで今回は、在宅勤務の実施下において、社内コミュニケーションを活性化させる方法を3つ紹介します。
(1)コミュニケーションのルールを決める
顔の見えないチームメンバーともやりとりできるツールとして、チャットツールや社内SNSを導入している企業も多いと思います。在宅勤務において大切なのは、こうしたツールの使い方についてあらかじめルールを設けておくことです。というのも、在宅勤務ではチームメンバーが何をしているのかがリアルタイムに把握できません。もしも相手が業務に集中していた場合、チャットツールのやりとりをストレスに感じる可能性もあります。
そのため、「急いでいるときは無理に返信しなくてよい」「上司は部下に即レスを強要しない」「あくまで連絡は業務時間内に行い、残業につながらないようにする」といった決まりごとを設けることが重要です。ある程度ルールが決められていた方が、従業員が無理なく順応でき、コミュニケーションも取りやすくなるでしょう。
(2)顔の見えるコミュニケーションも取り入れる
メールやチャットなど、文面上のやりとりだけでは伝えられる情報も限られてしまいます。上司としては、実際に部下の表情や仕草まで見て、状況を判断したいときもあるでしょう。そこで大切なのは、顔の見えるコミュニケーションも定期的に取り入れることです。例えば、Web会議ツールを使って週1回必ず1on1ミーティングを行う、という取り組みが挙げられます。上司の顔が見える方が、部下としても「頑張りを見てもらえている」と安心感を強められるものです。押しつけにならない程度で、顔の見えるやりとりも取り入れるとよいでしょう。
(3)スケジュールやタスクを見える化する
在宅勤務でコミュニケーション不足に陥る原因は、「相手が今何をしているのか分からない」ことにあります。なぜなら「今忙しかったらどうしよう」と相手に気を使って、連絡を控えてしまうこともあるからです。そこで重要なのは、チーム内において「誰が」「いつ」「どのような業務を行っているか」を“見える化”することです。チームメンバーのタスクやスケジュールがひと目で分かれば、上司が声をかけやすくなり、同僚もサポートしやすくなります。見える化する方法としては、専用のITツールやシステムを導入すると非常にスムーズです。
- ※「業務の見える化」については、こちらで詳しく解説しています。ぜひ合わせてご覧ください。
在宅勤務の生産性を上げるポイントは「業務の見える化」にあり!
まとめ
長時間労働の対策としては、「労働時間・業務の見える化」と「社内コミュニケーション活性化」が非常に重要な鍵になります。ぜひ新しいツールの導入も含めて、現状の業務フローを見直してみてはいかがでしょうか。
ちなみに当社では、チーム内の長時間労働を是正できるツールとして『働き方見える化サービス Plus』を提供しています。ツールでは従業員のPC操作時間を記録できるため、勤務時間の正確な把握が可能です。働き方改革と言えば、上層部からトップダウンで推し進めるイメージがあります。ただ、ツールによって働き方が可視化されることでチーム内での意識改革が推進され、“ボトムアップ”で働き方改善につながる効果も期待できます。
そして、当ツールでは従業員のタスクや気分も可視化できるので、チーム内で円滑に連携も図りやすくなります。さらには、閲覧したアプリやファイルの履歴も見える化できるため、働き方の改善にも有効です。在宅勤務時の残業削減・コミュニケーション活性化にもお役立ちできるツールですので、残業対策についてお困りの際はお気軽にご相談ください。
- ※「業務の見える化」については、こちらで詳しく解説しています。ぜひ合わせてご覧ください。
在宅勤務の生産性を上げるポイントは「業務の見える化」にあり!
特集コラム
関連資料
3分でわかる。NEC働き方見える化サービスPlus
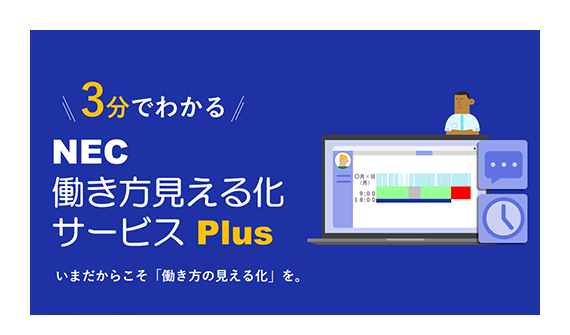
在宅勤務の3大課題
「コミュニケーション不足」「生産性の低下」
「隠れ残業」をいかに解決するか?
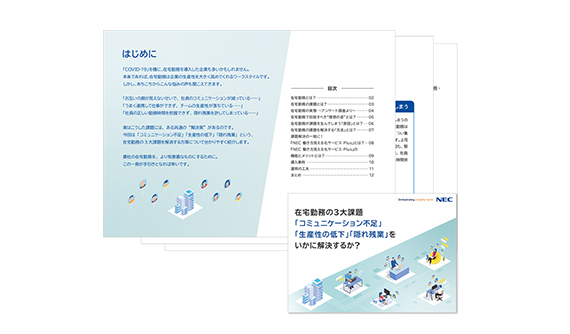
 「社内コミュニケーションに関する調査」結果報告|HRpro
「社内コミュニケーションに関する調査」結果報告|HRpro