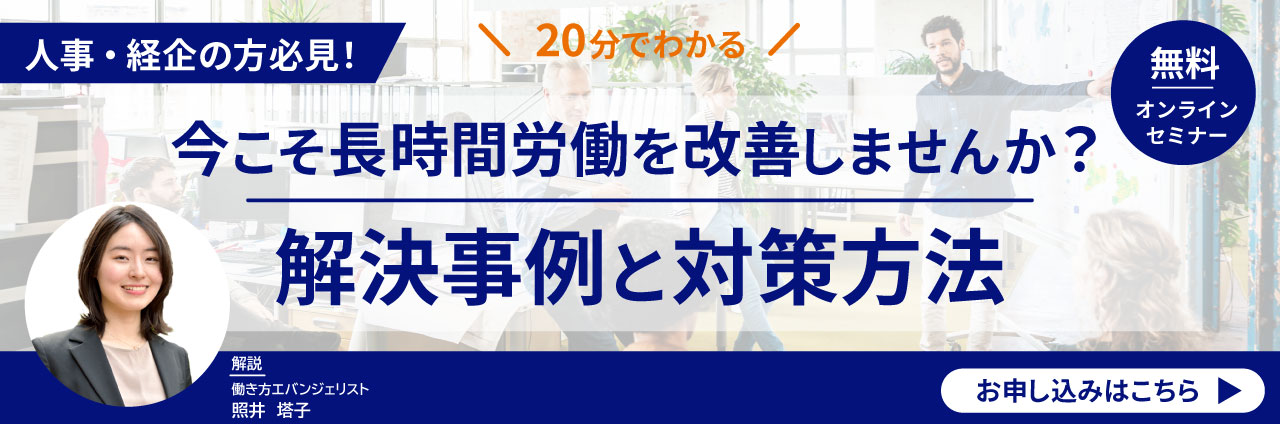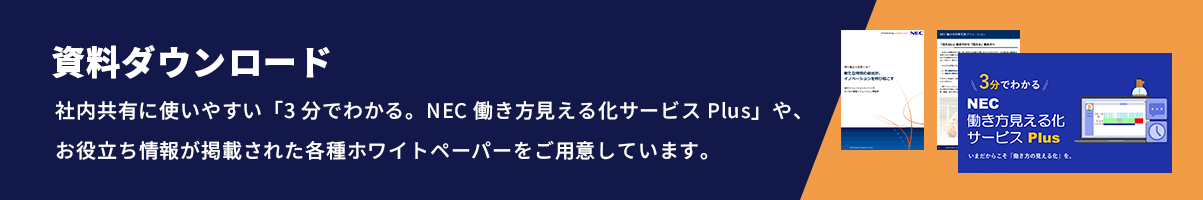サイト内の現在位置
長時間労働の対策“7選”残業を
減らすには、労働時間の適正管理が鍵!

「働き方改革関連法」によって、新たに残業時間の上限が定められ、罰則規定も設けられました。また在宅勤務の導入が進む今、長時間労働の増加が問題になっています。
長時間労働の対策“7選”残業を減らすには、労働時間の適正管理が鍵!
2019年に「働き方改革関連法」が施行され、上限を超える残業には新たに罰則が科されるようになりました。企業としても、長時間労働の是正と残業の削減が急務となっています。ただ、「思うように残業を減らすことができない」と悩む企業も多いのではないでしょうか。実は、残業を減らす鍵は労働時間の適正管理にあります。そこで今回は、長時間労働を生んでしまう原因や対策方法について分かりやすく紹介します。残業を減らして自社内での働き方改革を推進するために、ぜひ参考にしてみてください。
長時間労働の“基準”とは?
長時間労働とは、どれくらいの時間を指すのでしょうか。それについては、「長時間労働=○○時間」と具体的に決められているわけではありません。ただし、「労働基準法」と「働き方改革関連法」によって、法律上の労働時間・時間外労働(残業)の上限が定められています。まずは、この上限時間について以下(1)にて解説。その後(2)で、「過労死」「精神疾患」の発症と関連が認められる時間外労働の基準についても説明します。
(1)法律で認められる労働時間の上限とは?
【法定労働時間】
1日8時間・週40時間以内
これは、労働基準法32条で定められた労働時間の上限です。基本的に企業はこれを超えて、従業員を働かせてはいけません。ただし、時期や職種によっては残業が発生してしまうこともあるでしょう。そこで「36協定」という協定を労働者と締結し、所轄の労働基準監督署に届出をすれば以下の範囲内で時間外労働が認められます。
【「36協定」で定められた時間外労働(残業)】
月45時間以内・年360時間以内
これは、労働基準法36条で定められている「36協定」を締結・提出した場合の、時間外労働の上限です。原則として企業は、労働者にこれを超える時間外労働をさせてはならず、超えると罰則(※1)の対象となります。ただし、臨時的な特別な事情(「繁忙期につき業務量が著しく増加してしまう」といった事情)がある場合は、「特別条項付き36協定」を労使間で結び、同様に届出をすれば以下の範囲で時間外労働をさせることが可能です。
【「特別条項付き36協定」で定められた時間外労働(残業)】
時間外労働…年720時間以内
時間外労働+休日労働の合計…月100時間未満で、2・3・4・5・6ヶ月間それぞれの平均がすべて80時間以内
時間外労働が「月45時間」を超えるのは、年6ヶ月まで
これは「特別条項付き36協定」を締結・提出した場合の、時間外労働の上限です。こうした細かな基準が設けられたのは、これまで特別条項付き36協定を結べば、無制限の時間外労働が可能だったからです。そこで「働き方改革関連法」で新たに上記の上限が定められ、違反した場合に罰則(※1)が科されるようになりました。こうした働き方改革関連法の規定は2019年4月から大企業で、2020年4月から中小企業でも適用されています。
- ※1罰則…6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
(2)健康を害するレベルの長時間労働とは?
【過労死ライン】(※参考1)
発症前1ヶ月間で約100時間を超える時間外労働
発症前2~6ヶ月間で1ヶ月当たり約80時間を超える時間外労働
上記は、過労死と長時間労働との間に関連性が強いと評価できる、目安の時間外労働です。一般的に「過労死ライン」とも呼ばれています。ちなみに過労死とは、「業務で過剰な負荷がかけられた結果、脳血管疾患・心臓疾患で死亡すること」「業務で強い心理的な負荷を受け、精神疾患を起こして自殺により死亡すること」などを指します(※参考2)。
【業務に起因する精神障害の基準】(※参考3)
発病直前の1ヶ月間で約160時間以上の時間外労働
発病直前の3週間で約120時間以上の時間外労働
発病直前の2ヶ月連続で1ヶ月当たり約120時間以上の時間外労働
発病直前の3ヶ月連続で1ヶ月当たり約100時間以上の時間外労働 など
上記は、業務に起因する精神障害の発症があった場合、業務上で「強い心理的な負荷」があったかどうかの基準となる数値です。厚生労働省によれば上記は目安で、これに至らなくても心理的負荷が強度であると因果が認められる場合もあります。
日本における労働時間・残業時間の実態とは?
それでは、日本では長時間労働や残業について、どのような状況にあるのでしょうか。
データも交えながら、4つの切り口から実態を解説します。
(1)総実労働時間
厚生労働省の調査によれば、日本における年間の総実労働時間は減少傾向にあります。2012年の「1765時間」から断続的に減少し、2018年には「1706時間」となりました。背景には、勤務時間の短いパートタイム労働者の増加もありますが、過労死対策や働き方改革などの取り組みが少しずつ成果へつながった結果とも言えます。
(2)長時間労働する人の割合
同じく厚生労働省の調査によれば、「長時間労働者」の割合も減少傾向にあります。月末1週間の就業時間が60時間を超える労働者の割合は、2003年に「12.2%」でしたが、2018年には「6.9%」まで減少しました。ちなみに人数で言うと、2003年から2018年のあいだに長時間労働者の割合は、約240万人減少したことになります。
(3)海外と比較した長時間労働者の割合
ただし、海外と比較すると長時間労働の割合は、高いと言わざるを得ません。厚生労働省によれば、2018年における日本の年平均労働時間は「1706時間」で、韓国・アメリカに次ぐ3位でした。また、週49時間以上働いている長時間労働者の割合は、日本で「19.0%」です。これはフランスの「10.1%」、ドイツの「8.1%」などと比べて高く、先進国のなかでも長時間労働が多い結果となっています。
(4)在宅勤務による影響
昨今では「COVID-19」の影響もあって、在宅勤務の導入が加速している状況です。在宅勤務では、働き方がブラックボックス化してしまい、“隠れ残業”が増えてしまう懸念も指摘されています。実際、日本労働組合総連合会の調査によれば、テレワークになって通常勤務よりも長時間労働になることがあったと答えた割合は「51.5%」にものぼりました。また、同調査では「時間外・休日労働をしたにもかかわらず申請しないことがあった」という人の割合も「65.1%」と高い数値です。在宅勤務が導入された結果、見えないところで長時間労働が問題化している可能性もあります。
- ※在宅勤務における課題、解決方法についても知りたい方は合わせてご一読ください。
在宅勤務にありがちな悩みとは?解決法“4選”も紹介!【人事・上司必読】
長時間労働の原因(残業が減らない理由)とは?
それでは、長時間労働が是正されない理由とは何なのでしょうか。大きく5つの観点から紹介します。
(1)人手不足による業務過多
不景気のため、新たに人材を採用するのが難しい企業も増えています。また、日本における生産年齢人口の割合は年々減少を続けており、2019年には過去最低の59.5%を記録しました。そのため慢性的な採用難に陥っている企業も少なくありません。全体の業務量が変わらない状態で人手不足になると、従業員1人当たりの業務が増えてしまいます。そうなると、従業員が無理をしなければならず、長時間の残業につながってしまうでしょう。
(2)マネジメント層の意識の低さ
マネジメント層・管理職が、残業削減に対して意識を向けないことも原因のひとつです。例えば、「特定の従業員に業務が偏っているにもかかわらず、仕事の割り振りを見直さない」「チーム内の労働時間を把握しておらず、部下の残業を見逃してしまっている」などが挙げられます。ちなみに経済産業省のアンケート調査によれば、長時間労働の原因について「管理職(ミドルマネージャー)の意識・マネジメント不足」と答えた人の割合が44.2%と最多でした。マネジメント層の意識改革なくして、長時間労働の是正は難しいと言えるかもしれません。
(3)メンバー本人の意識の甘さ
上司だけでなく、従業員本人が残業削減に本気で取り組んでいないケースもあります。例えば、「残業を前提として業務のスケジュールを組んでいる」「残業代が多くもらえるので、あえて長く会社に残っている」といった人も少なくありません。まずは本人に、残業を減らす必要性について認識させ、意識改革させる必要があります。
(4)残業を“善”とする社内風土
日本は昔から、「残業する人=頑張っている人」という労働観があります。例えば、従業員が「上司に認めてもらいたいから残業しよう」と考えてしまうケースも少なくありません。こうした残業を善とする社内風土が残っていると、組織全体で長時間労働が慢性化してしまうでしょう。実際、経済産業省のアンケート調査でも、長時間労働の原因を「長時間労働を是とする人事制度・職場の風土」と答えた割合は部長クラスのなかでは40.0%でした。一朝一夕には難しいかもしれませんが、組織の全員が「残業を減らす」という方向に意識を傾ける必要があります。
(5)無駄な業務の多さ
普段は当たり前に行っている定型業務のなかにも、無駄が潜んでいることがあります。例えば、「形式化している朝礼」「開始時間に参加者が集まらず、時間が延びてしまう打ち合わせ」「上司の押印や本人の手書きが必須の社内書類」などです。本来であれば削減・時間短縮できるはずの業務のために、無駄な工数が発生してしまい、残業につながっている可能性もあります。まずは業務を“見える化”し、無駄を洗い出す作業が必要でしょう。
長時間労働を解消する(残業を減らす)対策“7選”!
それでは、実際に残業を減らすために、企業はどのような対策を取ればよいのでしょうか。
大きく7つに分けて、長時間労働を是正するための方法を紹介します。
(1)勤務時間・タスクを“見える化”して適正管理する
長時間労働の原因は、従業員の「業務内容」と「スケジュール」を正確に把握できていないことにあります。逆に言えば、チーム内において「誰が」「いつ」「どんな業務を行っているか」が見えれば、業務フローに潜む無駄な工程を早期に発見することが可能です。例えば、「メンバーが上司の確認を待っている時間がある」「通常は数分ですむ作業を1時間かけて行っている」といった無駄が分かれば、改善の手も打てるようになります。そのため、専用のITツールを活用しながら、従業員のタスクと一日のスケジュールを可視化することが大切です。
また、日々の「勤務時間」を見える化することも重要です。特に在宅勤務においては、上司が目で見て部下の出社・退社を確かめられないため、隠れ残業が増える傾向にあります。そのため、PCの操作時間を記録し、勤怠管理システムと連携させるといった仕組みで、客観的に従業員の勤務時間を管理することが効果的でしょう。
- ※「業務の見える化」については、こちらで詳しく解説しています。ぜひ合わせてご覧ください。
在宅勤務の生産性を上げるポイントは「業務の見える化」にあり!
(2)無駄な業務を思い切って省く
日々の定型業務のなかに不必要なものがあれば、思い切って省いてみることも大切です。例えば、「打ち合わせは最小限の人数で行う」「出力が不必要な資料は、わざわざ印刷せずにデータで送る」などが挙げられます。また、いつもの業務も工夫次第で“時短化”できることがあります。例えば、「打ち合わせは時間を決めて、その間に必ず結論を出す」「打ち合わせ前に予習ができるよう、資料をメールで共有しておく」「紙で行っている業務をExcelやITツールで自動化する」などです。普段の業務を一度見直し、効率化していく姿勢が必要でしょう。
(3)マネジメント層の意識を変える
マネジメント層の意識が変われば、チーム内の長時間労働が是正されることもあります。例えば、「上司が部下の適性とキャパシティを考えながら、業務を公平に降り分ける」「上司が率先して定時退社することで、部下が帰りやすいようにする」などです。マネジメント層の意識を改革するために、企業が働きかけていきましょう。
また、いきなり管理職に対して「意識を変えろ」と言っても難しいものです。そのため、企業が管理職に向けて教育を施すことが大切だと言えます。例えば、「36協定と特別条項付き36協定の違い」や「残業することによる健康への影響」などは、意外と知らない管理職も多いものです。また、「部下の適性の見極め方」「部下とのコミュニケーションの取り方」も必須スキルです。外部の研修も活用し、管理職の能力を伸ばす努力が必要になります。
(4)新しい勤務制度の導入
残業削減に寄与できるような、新しい勤務制度を取り入れるのも有効です。例のひとつとして、フレックスタイム制度が挙げられます。フレックスタイム制度では、コアタイムと呼ばれる時間帯のみ必ず勤務すれば、出社・退社の時間は各人の自由です。これなら、従業員が自分の予定に合わせて柔軟にスケジュールを組むことができます。かつ、限られた時間で成果を出せるように各自が取り組めるようになるでしょう。また、決められた曜日は必ず定時に帰る「ノー残業デー」や、「有給休暇」「リフレッシュ休暇」といった休暇の取得励行なども有効です。
大切なのは、こうした勤務制度は「取り入れて終わり」にしないことです。ノー残業デーであれば、「人事からリマインドのメールを送る」「残っている従業員がいないか、上司が見回りをする」など、従業員に浸透するように取り組むべきです。勤務制度の内容と、その広報・運用のプロセスはセットで考えるようにしましょう。
(5)評価制度の見直し
「残業してでも成果を挙げれば、評価が上がる」と考える従業員が多いと、組織全体の長時間労働につながる恐れがあります。大切なのは、「成果」だけを重んじるのではなく、「時間当たりの成果」や「生産性」も加味した評価制度に変えることです。これによって、従業員は限られた時間のなかでどう成果を出すか考え、生産性高く働けるようになります。特に在宅勤務においては、従業員の集中力が続かず、長時間労働につながりやすいです。「生産性」を重視する評価制度であれば、従業員もメリハリをつけて業務に取り組めるようになるでしょう。
(6)トップと人事が率先して指針を示す
意識改革において最も大切なのは、トップが率先してメッセージを発信することです。残業削減について指針を打ち出す際も、「月○○時間削減する」という具体的な目標、「毎週水曜日は必ず定時に帰ることを徹底する」という具体的な行動計画とともに発表しましょう。また、残業削減の目的について語るときは、「会社のため」ではなく「従業員のため」という目線が大切です。「誰もが健康的に働けるようにするため」「無駄なコストを省いた分を、賞与の増加に回すため」など、従業員が自分事化できる目的の方が、より浸透しやすくなります。
そして、トップが発表したメッセージに沿って、人事が現場への広報を徹底することも重要です。メールや社内報、掲示板などで残業削減の呼びかけ・有休取得の励行などを行うことで、より効果を高められるでしょう。
(7)チーム内のコミュニケーションを活性化する
チーム内での連携が不足していることも、長時間労働の原因になります。例えば、一部の従業員に業務が偏っているにもかかわらず、上司や同僚がサポートしなかった場合、業務量の多い従業員は残業せざるを得ません。また、それが納期遅れといった思わぬトラブルにつながり、余剰な業務が生まれる可能性もあります。チーム内で積極的にコミュニケーションを取り合い、業務が全体最適で分配されれば、残業の削減にもつながるでしょう。
特に在宅勤務では、お互いの働き方が見えないことによるコミュニケーション不足を課題に感じる企業も多いです。具体的には、チャットツールや社内SNS、Web会議システムなどで、日ごろからチーム内でコミュニケーションを取るようにしましょう。また「業務を見える化」する機能も搭載されたツールであれば、より効果的です。
- ※参考:「社内コミュニケーション」については、こちらで詳しく解説しています。ぜひ合わせてご覧ください。
【在宅勤務にも対応】社内コミュニケーション活性化の方法“8選”!
まとめ
長時間労働の対策としては、「労働時間・業務の見える化」と「社内コミュニケーション活性化」が非常に重要な鍵になります。ぜひ新しいツールの導入も含めて、現状の業務フローを見直してみてはいかがでしょうか。
ちなみに当社では、チーム内の長時間労働を是正できるツールとして『働き方見える化サービス Plus』を提供しています。ツールでは従業員のPC操作時間を記録できるため、勤務時間の正確な把握が可能です。働き方改革と言えば、上層部からトップダウンで推し進めるイメージがあります。ただ、ツールによって働き方が可視化されることでチーム内での意識改革が推進され、“ボトムアップ”で働き方改善につながる効果も期待できます。
そして、当ツールでは従業員のタスクや気分も可視化できるので、チーム内で円滑に連携も図りやすくなります。さらには、閲覧したアプリやファイルの履歴も見える化できるため、働き方の改善にも有効です。在宅勤務時の残業削減・コミュニケーション活性化にもお役立ちできるツールですので、残業対策についてお困りの際はお気軽にご相談ください。
特集コラム
関連資料
3分でわかる。NEC働き方見える化サービスPlus
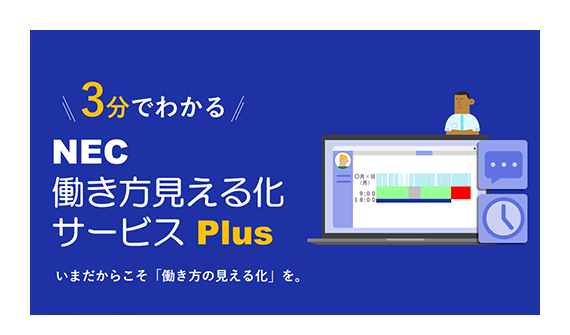
在宅勤務の3大課題
「コミュニケーション不足」「生産性の低下」
「隠れ残業」をいかに解決するか?
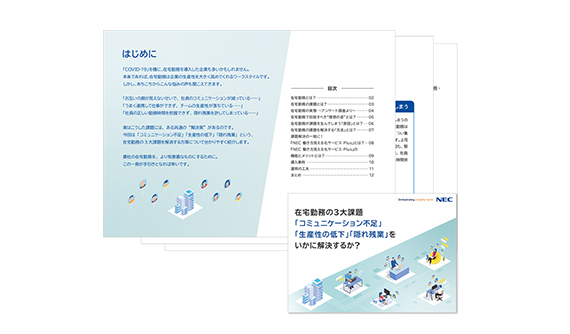
 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説|厚生労働省(PDF)
時間外労働の上限規制 わかりやすい解説|厚生労働省(PDF) 過労死等防止対策|厚生労働省
過労死等防止対策|厚生労働省