サイト内の現在位置
インタビュー
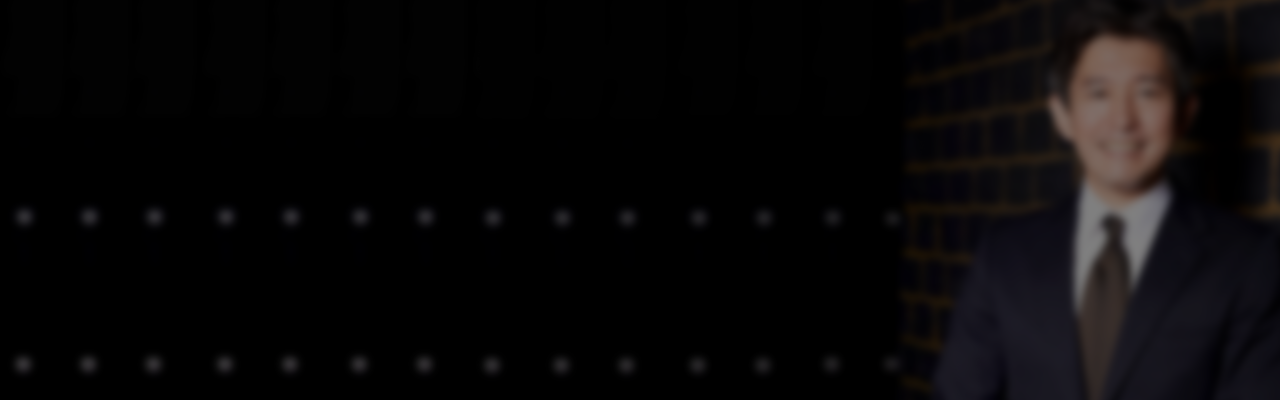
UPDATE : 2021.10.13
日本をはじめ海外でも高い評価を受ける日本酒「獺祭」。“おいしい酒”を造るため従来とは違う方向に踏み込み、追求しています。
伝統を大切にするイメージの強い酒造業において、なぜこのようなフレキシブルさが受け入れられたのか。人材開発において大切にしていることは何なのか。
旭酒造・桜井一宏社長に伺いました。

インタビューに答えてくれた方
桜井 一宏(さくらい・かずひろ)さん
旭酒造株式会社 社長
1976年山口県生まれ。早稲田大学社会科学部を卒業後、東京都内のメーカーに勤務。2006年旭酒造に入社し、常務取締役となる。2013年取締役副社長就任を経て、2016年代表取締役社長に就任。4代目蔵元となる。
INDEX
杜氏制度なし、純米大吟醸のみを仕込む。
伝統ある酒造業で異例の挑戦
―日本酒造りといえば、酒の製造を一手に引き受ける責任者・杜氏の監督の元行われるのが普通です。
しかし旭酒造には杜氏制度がなく、社員の皆さんが酒造りの担い手となっています。
これにはどのような意図があったのでしょうか?
桜井社長:かつては当社にも杜氏さんがいらっしゃって、酒造りを担っていましたが、事業は伸び悩んでいました。
当時の社長(現会長)もさまざまな事業に挑戦し、もちろん失敗することもあった。そんな中で、杜氏さんに「旭酒造はもう未来がないんじゃないか」と見限られてしまったんですね。いわば逃げられた状態です。
そんな経緯で、仕方なく自分たちで酒を造らなければならなくなったわけです。
けれど、実は杜氏さんに逃げられたのが良かった。とにかく“おいしい酒”を造ろう“という想いを、酒造りにストレートに反映できるようになったんです。
つまり、杜氏さんや杜氏さん率いる職人チームができるだけ避けて通りたいと感じるような造りにも抵抗なく入っていくことができた。
その想いに従って会社が変わってきた結果、普通酒メインで冬に小規模仕込む酒蔵から、純米大吟醸を小さなタンクで年間3,000回以上仕込む、現在のある種異常なスタイルへと変化していきました。

―杜氏制度が立ち行かなくなった、その逆境から生まれたスタイルだったのですね。
桜井社長:当社がその頃可能性を感じ、追求しようとしていたのが純米大吟醸ですが、杜氏さんもあまり造ったことがないものでした。
一般的な、そして伝統的な酒造りに比べると非効率で、大変な部分も多く、新しい道に踏み込むので失敗のリスクも高い。
杜氏さんからすれば、そんなこと積極的にやりたくないですよね。そんな中で何もわからないメンバーだけが残ってやるしかない状況になった。
古いスタイルは知らず、変化に対する抵抗勢力もなかったので、スムーズに移行できたんです。0から企業文化の醸成が始められました。
人材獲得おいて重要視するのは、獺祭を愛し、造ることを楽しめるかどうか
―現在は130名以上が製造部門に在籍しているそうですが、採用にあたっては「製造部門」と「事務部門」など業種をわけて募集しているのですか?
桜井社長:一部スペシャリストのような形で業種を限定して入社する場合もありますが、9割以上の新入社員は、まずは製造に配置しています。
当社が大事にしている部分はやはり製造ですし、うまい酒を造ることが最も重要なことですので。製造部門で大事な部分をしっかりと刻んでもらい、適正をみて他の部門へ異動する流れが一般的です。

―採用の際に経験値などは重視されているのでしょうか?
桜井社長:酒造業の経験者や大学の醸造科、発酵やバイオ系の大学を出ているなどの、経験や知識があるかどうかは必要ないと考えています。
当社の場合、酒造メーカーの中でも純米大吟醸のみという特殊な環境ですし、1年間に3,000回以上仕込むので経験値はすぐにつく。
また、ほかの酒造業だと、酒の種類によって力を入れる・入れないの差がはっきりしている場合があるので、そういった「効率的な」考え方も当社ではプラスになりにくい。
もちろん、まったく採用しないというわけではありませんが、あくまで経歴ではなくその人の適正を見つつ、獺祭を愛し、造ることを楽しめる人と一緒に働きたいと考えています。
県内トップクラスの生涯年収を約束。若手のモチベーションアップへ
―旭酒造の特徴的な人事施策について教えてください。
桜井社長:新卒〜40歳まで、年5%の昇給を給与モデルにしています。当社のメンバーには誇りをもって働いてほしい、そのためにはきちんと対価を支払いたい、という思いから制度化しました。
若いうちにがむしゃらに頑張る中で、着々と給与が上がる実感があるとモチベーションも上がりますし、結婚など節目のタイミングでもまとまった金額は安心感につながります。
そして、「うちのお父さん・お母さんは獺祭を造っているんだ! すごい!」って子どもが思えるような存在でいてほしいし、会社はその手伝いをしなければならないとも思います。
これは、県内ではトップクラス、東京都内でも一般的な企業の給与と比較し見劣りしない生涯年収を目指しています。
―若手のみでチームを組み、獺祭を仕込むというミッションもあるそうですね。
これにはどのような思いが込められているのでしょうか?
自信も付くし面白さもより感じられます。また、獺祭という酒の教育にもつながっています。出来上がった酒は「クラフト獺祭」として直売店でも販売します。
ラベルにはチームの名前も載せているので、お客様も製造の人間を間近に感じられるようになっています。
―製造部門のモチベーションアップに繋がりますね。
桜井社長:売り上げや、お客様からいただいた声など、何かあれば随時共有し、本人たちもやりがいを感じているようです。
去年組んだこのチームが好評だったから今年もひき続きやってみようということもありますし、逆に去年のチームで悔しい思いをしたからもう一度リベンジしたい、もしくは組む人を変えてやってみたい、と申し出るスタッフも多いですね。
風通しのよい環境を維持し、提案力のある社員を育てる
―お話しを伺っていると、伝統にこだわりすぎないからこそ、さまざまな試みに挑戦できるのだと感じます。
その考え方の礎になっているものは何なのでしょうか?
桜井社長:「小さく試す、ダメなら引き返す、いけそうなら進んでみる」ということが、当社の基本の考え方です。
会長の時代から、何か可能性を感じたら「まずはやってみよう」ということになる。例えば、アルコール度数の低いお酒に未来が見えるかもしれないと意見が出たら、まずは製造してみて、おいしければ直売所で売ってみる。
それで売れなければ、すぐに「じゃあやめよう」となる。一方、構想何年、会議に会議を重ねてようやくスタート、といった場合には、取りやめる際にも大変ですよね。うちはそんな企画はほとんどありません。
この考えは会長から引き継いだもののひとつなので、中心メンバーになればなるほど、その思いは強いです。これまで順調に進んでいたものが、土日のたった2日間で急に方向性が変わった、なんてこともよくありますよ。

―気軽に提案できるような社風なのですね。
桜井社長:そのようにありたいと思っています。当社では毎日その日に絞ったお酒をテイスティングしているのですが、製造チームのリーダーが、自分なりの問いと、その答えとして作った新しい酒をテイスティングに紛れ込ませてくることもよくあります。
そのテイスティングでメンバーから散々に言われて悔し涙を飲む、なんてこともあるし、これは可能性があるから正式に造ってみようと開発がスタートすることもあります。
ですので、新商品開発の部署などはとくに設けていないんですよ。いろいろな実験や失敗から新商品開発につながっていくケースがほとんどですから。
―そうすると、提案できたり、アイデアが持てたりするような社員の育成が、ひとつのミッションになっているのでしょうか?
桜井社長:そうですね。例えば新しい酒造りに失敗したとしても「なんでこんなことやっているんだ! 既存の商品をきちんと造れ!」とは絶対に言いません。
提案することは怖くないし、失敗しても大丈夫だよという空気を維持するように努めています。
そのために「提案書」という施策も設けました。例えばトイレットペーパーが硬いとか、上司が気に食わないとか、なんでもいいから提案できるのですね。
この提案書を書いただけで、QUOカードが配布されたり社食の食券が1枚もらえたりする。このように得をしている社員を側で見て、「だったら自分も1回提案してみようかな」と思ってもらう。その繰り返しで、提案するクセが付けばと考えています。
放っておいたらブランド維持に注力してしまいがちなのですが、それでは成長がありません。我々は、ある意味無理矢理にでも軽くにいなければならない。そのためには社員の提案力がとても重要だと考えています。
伝統にこだわりすぎることなく、フレキシブルな人材を育てていければと思っています。
まとめ
ともすれば伝統と格式にとらわれがちな酒造業にあって、これまでにない革新的な取り組みを続ける旭酒造。
会長の時代から培った、“小さく試していけそうなら進む”という細かなトライが、人材を育て、業績アップを叶えています。
「ある意味、ミーハーなんですよ」と微笑む桜井社長の人柄もまた、軽やかな社内風土の醸成につながっているのではと感じました。
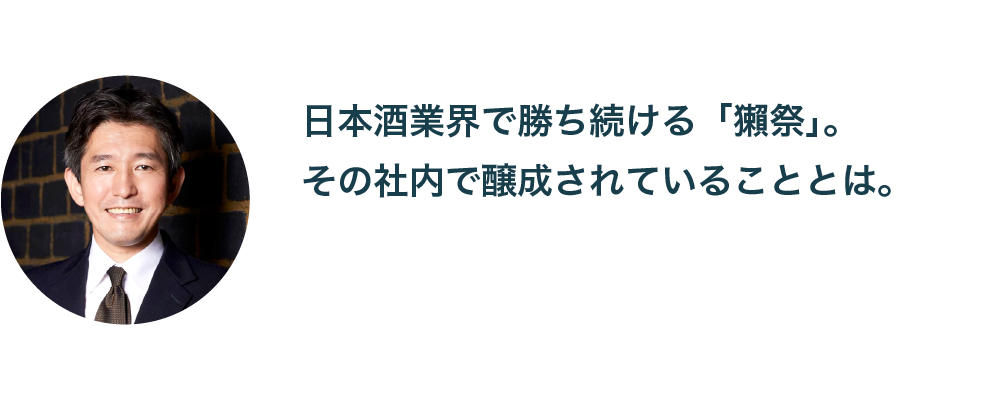






 公式Facebook
公式Facebook





