サイト内の現在位置
CTO塩谷が導く変革の時代
AI時代の技術戦略と新たな可能性


生成AIをはじめとする最先端テクノロジーの急速な進化は、社会の価値観をも変えつつあります。こうした変革の時代において、NECソリューションイノベータの技術戦略を牽引するCTO(Chief Technology Officer)の塩谷幸治は、どのような未来を見据えているのでしょうか。1万人を超えるエンジニアを擁するNECソリューションイノベータが目指す技術の方向性と成長の可能性を聞きました。
病気のリスク予測を可能にするバイオテクノロジー
NECソリューションイノベータの主要事業であるシステムインテグレーション(SI)は、お客様の課題をICTで解決するビジネスモデルです。塩谷はその本質を「お客様ごとに異なる要求に応える業務」と語ります。
「業務課題は業界や環境によって多岐にわたりますが、『この課題は解決できるが、これはできない』とは言えません。そのため、エンジニアには最新の技術やトレンドを常に吸収・アップデートする姿勢が求められますし、貴重なエンジニアパワーを様々な技術やソリューションにバランスよく配置する必要があります。一方で、変化の激しい社会において価値あるソリューションを提供し続けるには、未来を見据えた新規事業の創出も欠かせません」

エグゼクティブフェロー兼 CTO兼 CIPO
| アーキテクトとしてIaaSやSaaSといった様々なクラウド基盤SIに従事。現在はエグゼクティブフェロー兼CTO兼CIPOとして、新規事業の創出や新技術の獲得、社内での最新技術活用の啓発、さらにはバイオセンシングなどの研究開発を進めるイノベーションラボラトリの責任者などを務めている。 |
塩谷のもとで推進されているイノベーションラボラトリは、新技術獲得と新事業創出の双方を担うR&D組織(社内ラボ)です。ここでは幅広い領域の研究開発が行われており、中でも特徴的な技術がバイオセンシングです。
「バイオセンシングとは、生物学的な素材を用いて特定の化学物質や生体情報を検出・測定する技術です。病気の発症リスクを高精度に予測するだけではなく、他の医療や健康分野への貢献が期待されており、さらに食品や環境分野でも情報の可視化に役立つ可能性があります。IT企業がバイオ領域を扱うことに驚かれる方もいますが、バイオ以外にもさまざまな分野の研究者が在籍しており、バイオセンシングによる人の状態検知から介入まで一連のサイクルを最新のデジタル技術を掛け合わせてカバーできるのが当社の強みです」
より良く生きる── Well-beingが、価値を生む時代へ
長年にわたりNECソリューションイノベータの新事業創出を牽引してきた塩谷は、現在「Well-being」に着目しています。それはなぜでしょうか?
「今後さらに進化するAIによって業務の効率化や人間作業の代替が進むことで、社会全体の可処分時間は増加しています。その先にあるのは、単なる経済的成功ではなく、『より良く生きること』を重視する社会だと考えています。そこで、身体的・精神的・社会的に良好な状態をあらわすWell-beingが重要になると捉えています。その根幹となる心身の状態把握には当社のバイオセンシングが適用できますし、ビジネス的にも注目しています」
NECソリューションイノベータの経営方針としても、社員の「健康」「成長」「働きがい」を重視したWell-being経営を推進しています。
「事業が成長する中で、誰が幸せになるのかという視点は欠かせません。報酬だけではなく、福利厚生や教育など、より良く生き、より良く働ける環境を用意することが、個人のWell-beingの源泉につながると考えています」
一人ひとりが多様な能力を発揮して個人のバリューを高めた結果、会社も成長する ── 個人と会社が互いにバリューを高め合うサイクルを、NECソリューションイノベータでは「Value creation cycle」と定義しています。これを循環させることで、新たな価値を創出する試みを進めています。
「Well-being経営についてあらためて感じるのは、社員はこうした企業で働くことを望み、消費者はそうした企業を選ぶ傾向が強まっているという点です。この潮流は今後さらに顕著になるでしょう」
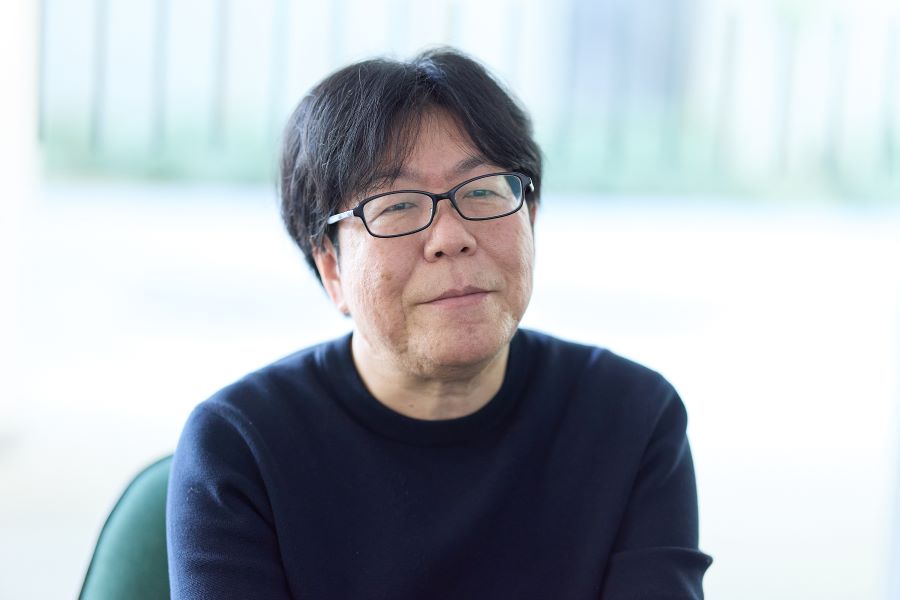
エンジニアに求められる“選択する力”とは?
個人が成長し、最大限に能力を発揮するには、教育制度の充実が不可欠です。NECソリューションイノベータでは、豊富な育成メニューに加え、外部教育機関の受講制度など、さまざまな学習の機会を提供しています。
「当社では、エンジニアとして身につけるべきスキルを学習するさまざまなプログラムを用意していますが、大切なのは“自ら選択して学ぶこと”です。自ら選択することで主体性を高めることができますし、幸福感や充実感を得ることにつながります。自分で選ぶことに慣れていない場合は、日頃から“選択する”行為を習慣化するといいかもしれませんね。例えば、何を食べたいかと聞かれたとき、『なんでもいい』と答えるのではなく食べたいものを選んで答える。なんでもない事のようですが、身近な選択の積み重ねによって自分の人生も自分で選べるようになっていくんだと思います。当社でもValue creation cycleの中で、自ら選択しながらキャリアを形成できる仕組みを今後さらに強化していきたいと考えています」

若いエンジニアには何が求められるのでしょうか?
「自分の価値観に自信を持って活動してほしいですね。無理に上の世代の価値観に合わせる必要はありません。なぜなら、いずれ今の若い世代が中心となる時代が必ず来るからです。それは社会の価値観が変わることを意味します。その変化に適応できなければ、私たちのサービスは選ばれなくなります。だからこそ、若いエンジニアの皆さんには、自分たちが主役の時代に備え、より良い意思決定ができる“選択する力”を身につけてほしいですね」
外部とのつながりが、新たな“知”を生む
塩谷は2022年から、社内向けのオンライン番組「しおトーク」をスタートしました。ほぼ毎週ライブ配信され、技術に関するさまざまなテーマを取り上げています。
「どんな仕事でもそうですが、アウトプットをしなければ、フィードバックが得られず、成長や気づきも生まれません。そんな思いから番組を始めたので、配信中はチャットを活用したオープンな意見交換も行なっています」
成長に欠かせないアウトプット。塩谷が重要視しているのは、こうした社内向けの発信にとどまらず、企業や組織の枠を超えた「外部とのつながり」です。

「社内に閉じこもっていては、新しい“知”を獲得できず、世の中の変化にも取り残されてしまいます。自分たちの常識や文化とは異なる社外の人々と交流し、インプットを蓄えていくと『これを誰かに伝えたい』と、自然とアウトプットしたくなる。そうやって人は成長していくのだと思います」
そのインプットを得るために、塩谷自身も時には肩書きを伏せてスタートアップ系の交流会に参加することがあります。
「秘密にしているわけではないのですが、先に肩書きを知ると相手が身構えてしまい、密度の濃い情報交換が難しくなることがあります。世の中の動向を正しく把握するためにも、いちエンジニアとして参加できるミートアップには積極的に足を運ぶようにしています」
AIはチャンス。技術で価値をつくる挑戦
急速に進化するAI技術について塩谷はどう考えているのでしょうか。
「チャンスでしかないと思っています。次々と生まれる新しいツールの恩恵が、あらゆる業界に広がり続けています。それは、私たちにとってビジネスチャンスの拡大です。
例えば、共働きで子育てをしている夫婦がいるとします。仕事と育児で忙しく、食事を作る時間が取れない。その結果、冷凍食品や電子レンジを購入したいと考える場面が生まれます。そこには、限られた時間を有効に使うために“お金を払ってでも解決したい課題(=ペイン)”が存在します。ビジネスとはペインを解決して対価を得ることですから、『AIにお金を払ってでも解決したい課題は何か?』という視点で世の中を眺めれば様々な種類のペインが見つかるはずです」
“お客様ごとに異なる要求に応える業務”であるSIでは、個別のお客様のニーズを起点にして課題を捉えることが不可欠です。一方で、Well-beingのような社会全体に共通する概念では、そこから生まれる課題は社会全体の課題として捉えられます。
「こうした課題を解決するバリューを提供し続けるために、新技術獲得や新事業創出をはじめとした新たな可能性にチャレンジしています。そして、お客様と共創しながら、より明るい社会を描くバリュー・プロバイダとしての信頼を築いていく。こうした取り組みの積み重ねこそがNECソリューションイノベータの未来につながると考えています」

<関連リンク>
UPDATE:2025.4.23
 プロフェッショナルとしてのスキル向上に注力 社員自ら考え、行動する文化を醸成したい: コーポレートブログ | NECソリューションイノベータ
プロフェッショナルとしてのスキル向上に注力 社員自ら考え、行動する文化を醸成したい: コーポレートブログ | NECソリューションイノベータ