会計コラム 公認会計士・税理士 横山 公一氏・第7回第1回 法規制概要1 ~電子帳簿保存法~ コラム執筆者:公認会計士・税理士 横山 公一氏 掲載日:2020年12月9日
2020年は新型コロナウイルス感染症が世界的に蔓延し、いまだに先が見えない状況が続いています。
世界中で社会的距離を保つための指針「ソーシャルディスタンシング」が義務付けられ、仕事のスタイルはリモートワーク、テレワークが通常になりはじめています。特に我が国は長年の「紙」と「ハンコ」を多用してきたワークスタイルの変容を余儀なくされ、社内の稟議・申請や会社間でやりとりする取引関係書類もデジタル化へ突き進まざるを得ない状況です。
ビジネス文書における“ペーパーレス化”と“脱ハンコ”においてキーとなるものは「法的要件の充足」と「内部統制のデジタル化」です。全3回のコラムの構成は第1回(今回)「法規制概要1 ~電子帳簿保存法~」、第2回「法規制概要2 ~会社法/e-文書法/電子署名法/会計監査の指針等~」、第3回「電子のハンコ(電子認証)」について説明していきます。
皆さまのニューノーマルな働き方の一助になれば幸いです。
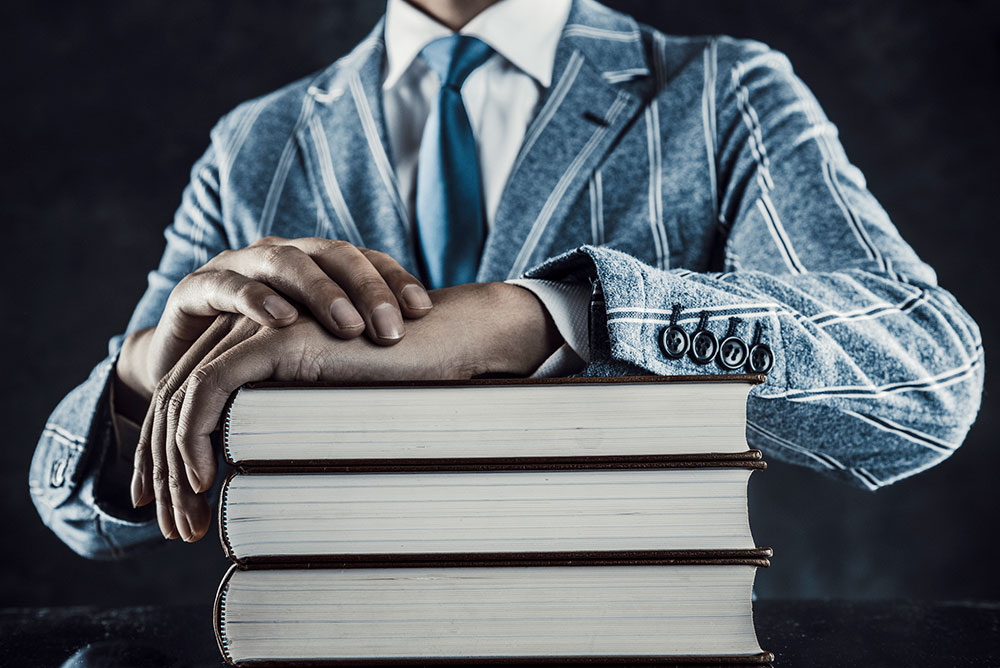
ペーパーレスに関する法律とその要件
紙文書の保存を義務付けている法規制が我が国には約300あります。規制緩和の流れのなか、9割近くが紙に代えてPDFなどデジタル形式にて保存することが可能になりました※1。しかしながら、個々の法規制のデジタル化の措置および保存の要件は一様ではなく、各法律法令から要求される要件を整理して実装しなければ、ビジネス文書の完全なデジタル化は実現できません。
特に、電子帳簿保存法の緩和が相次ぎ、一定の要件を満たせば会計帳簿や証ひょうなどの帳簿書類に関してデジタルデータを原本として扱うことが認められ、紙の保存を大幅に削減できるようになりました。電子帳簿保存法の基本要件※2は以下の通りです。
- 真実性(完全性)
税務上の重要な記録にはエビデンスとしての証明力が求められる。特にスキャナによるデジタル化は、原本受領からスキャニングまでの事務処理フロー(適格事務処理要件【=内部統制要件】の具備、例えば認定事業者のタイムスタンプを適切なタイミングで決裁権限者が付与するなど)、スキャン品質や電子化文書に改ざんや消去がないかを確認できる(例:認定事業者のタイムスタンプ、一括検証機能、履歴管理等)など証明力を確保することが必要。 - 見読性
パソコンやディスプレイを用いて明瞭な状態で見ることができる「見読性の確保」が求められる。 - 関係書類の備付
デジタル化の事務処理マニュアル、規程類、システム概要書等の備付けが求められる。 - 相互関連性
帳簿と書類間のトレーサビリティーが求められる。 - 検索性
電子化文書を有効活用するため、必要なデータをすぐに引き出せる「検索性の確保」が求められる。
デジタル化の対象となる国税関係帳簿書類と電子帳簿保存法の関係は表の通りです。
| 根拠条文 | 内容 | 説明 |
|---|---|---|
| 法第4条1項 | 国税関係帳簿の電磁的記録による保存等 | 国税関係帳簿について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合、その電磁的記録を帳簿の備付けと保存に代えることができる。 |
| 法第4条2項 | 国税関係書類の発行控 | 国税関係書類に関しても、最初から一貫して電子計算機で作成できるものに限り、その電磁的記録を紙書類の保存に代えることができる。 |
| 法第4条3項 | スキャナ保存制度 | 作成・受領した国税関係書類のスキャナ保存、つまり紙を電子化データ(画像データ)にして保存することができる。 |
| 法第10条 | 電子取引に係る電磁的記録の保存義務 | 所得税および法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。 |
第4条3項のスキャナ保存制度に関してはこの数年、度重なる規制緩和が行われています。参考に2016年、2017年、2019年施行の緩和の概要をまとめてみます。
2016年施行の規制緩和概
| 内容 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| スキャナ保存対象の契約書・領収書等 | 記載金額が3万円未満の契約書・領収書等のみ | すべての契約書・領収書等が対象。但し、適正事務処理要件の遵守が条件 |
| 電子署名等 | 電子署名および(認定事業者の)タイムスタンプが必要 | 電子署名を不要とし、(認定事業者の)タイムスタンプのみに |
| スキャナ保存に関する要件の一部改正(重要書類※3以外について) | スキャナ保存を行うすべての税務関係書類について
|
スキャナ保存を行うすべての税務関係書類のうち契約書・領収書等以外の書類について
|
| 重要書類について、スキャナ保存する場合の要件 | 重要書類について、業務処理後にスキャナ保存を行う場合は関係帳簿の電子保存の事前承認が必要 | 会計帳簿の電子保存の承認を経ずしてスキャナ保存制度が活用可能に |
2017年施行の規制緩和概要
| 内容 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 電磁的記録に記録(スキャン)する際に用いる装置について | スキャナについて、原稿台と一体となったものに限定 画質要件はA4で200dpi、4P文字認識 |
|
| 受領者が記録(スキャン)する際の手続要件の見直し | 領収書を受け取った者は、領収書を会社に持ち帰り、社内の担当者等が原本を確認してから記録(スキャン) | 領収書を受け取った者は、スマートフォン等の写真機能を使って、いつでも、どこでも、領収書を記録(電子化)可能社内の担当者等の原本突合が必須ではなくなり、画像の確認のみに |
| 小規模事業者向けの手続要件緩和の特例を設置 | 適正事務処理要件(内部統制)の為、チェック体制は最低でも3名が必要
|
顧問税理士にチェックしてもらうことにより、最低2名(顧問税理士を含む)でも運用可能に
|
2019年施行の規制緩和概要
| 内容 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 承認を受ける前に作成又は受領をした重要書類のスキャナ保存の可能性 | 不可 | スキャナ保存の承認を受けている保存義務者は、過去分重要書類について、適用届出書を提出した場合には、一定の要件を満たすことで、スキャナ保存をすることが可能 |
| 内容 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 1.通達等の改訂 | ||
| ①入力等に係る期間制限に関する解釈の見直し | 速やかに:受領後「1週間以内」 | 「おおむね7営業日以内」 |
| 業務処理方式:受領後 「1か月+1週間以内」 | 「2か月+おおむね7営業日以内」 | |
| 特に速やかに:受領後「3日以内」 | 「おおむね3営業日以内」 | |
| ②定期的な検査の頻度に関する解釈の見直し | 全ての事業所等を対象として1年に1回以上行うこと | おおむね5年のうちに全ての事業所等の検査を行うこともOK |
| ③検索機能の確保に関する解釈の見直し | 請求書や領収書など書類の種類別に検索できること | 勘定科目別に検索が可能な場合もOK |
| 2.その他 ①承認申請手続の見直し ②事前相談体制の整備 |
N/A |
|
また、電子商取引が活発になってくると、今後ますます重要になるであろう第10条「電子取引に係る電磁的記録の保存義務」に関しても2020年10月1日より、選択肢の拡大が行われました。
緩和前は:
A.改ざん防止等のための事務処理規程を作成し運用
B.データの受領後遅滞なくタイムスタンプを付与
緩和後は新たに下記が追加されました:
C.ユーザー(受領者)が自由にデータを改変できないシステム(サービス)等を利用
D.発行者側でタイムスタンプが付与されていれば、受領者側は不要に
更には、2021年税制大綱において、税務署の事前承認や定期検査を不要にする方向のようです。引き続き、電子帳簿保存法の改正の動向には留意が必要です。
次回、第2回は「法規制概要2 ~会社法/e-文書法/電子署名法/会計監査の指針等~」を説明します。
- ※1 消費者保護などの観点から事前に承諾が必要であったり、紙での授受が必要な書類も存在しますが、昨今の流れから規制緩和は加速して行くでしょう。
- ※2 我が国の税法は欧米とは異なり、立証責任の所在は当局側にあるため、電磁的記録に関して詳細な要件を設けています。
- ※3 重要書類とは契約書・領収書およびこれらの写し、預金通帳、請求書、納品書、送り状などを指します。






