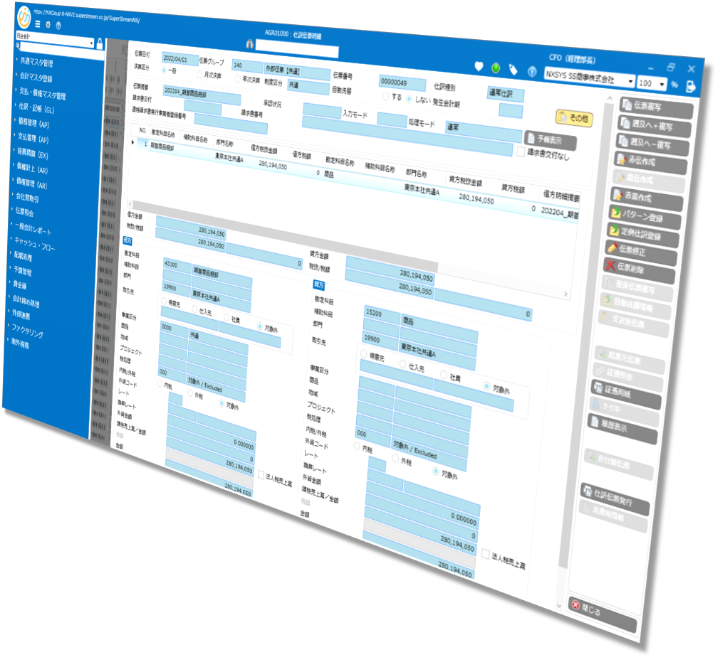これまで多くのセミナーで新しいリースの会計基準(新リース会計基準)について講演をしてきました。講演後にいただいたアンケートで、「リース会計を適用すべきでない契約について、適用しそうになっていた」とか「契約期間以上にリース期間を延ばす必要があると思い込んでいた」などといったお声が後を絶ちません。
言い換えれば、リース負債や使用権資産を計上してはいけない取引なのに、計上しようと思い込んでいたことになります。また、契約期間以上に延長してはいけないのに、延長しなければならないと思い込んでいたことになります。
これらの原因は、「新リース会計基準では、『すべてのリースについて資産・負債計上する必要がある』」という情報を鵜呑みにして、きちんと会計基準に目を通して理解をしていないことです。この場合の『すべてのリース』というのは、「新リース会計基準でリースの定義を満たした取引はすべて」という意味です。したがって、リース契約や不動産賃貸借契約が締結されていても、その契約内容が、「新リース会計基準でリースの定義を満たした取引」でなければ、それは「会計上のリース」ではないので、資産・負債計上をしてはいけないのです。
このスタートで大きく勘違いをしている方々が非常に多いと痛感しています。
特に重要なのが、設例1の「リースの識別に関するフローチャート」の3番目の部分です。
「リースの識別に関するフローチャート」の3番目の内容は以下です。
使用期間全体を通じて特定された資産の使用方法を指図する権利を有しているのは、顧客か、サプライヤーか、それとも、どちらにもないか(日本の適用指針第8項(1)参照)
この条文で、重要なのに理解が難しいのが、「使用方法を指図する権利」です。いわゆる「使用権」と言われます。
今回の新リース会計基準で最も重要な概念の一つです。なぜなら、取得してもいないのに資産を計上する、根源的な概念だからです。言い換えれば、「使用権」の定義を満たさなければ、資産計上してはならないのです。この大変重要な「使用方法を指図する権利」を理解するためのガイダンスともいうべき記載が、新リース会計基準にはほとんどないので、多くの方々が困り、間違えやすくなっていると思います。
「使用方法を指図する権利」については、日本の適用指針のBC13項に以下の記載があります。
顧客が使用期間全体を通じて特定された資産の使用を指図する権利を有しているか否かの判断を行うにあたっては、使用期間全体を通じて使用から得られる経済的利益に影響を与える資産の使用方法に係る意思決定を考慮する。当該意思決定は、資産の性質及び契約の条件に応じて、契約によって異なると考えられる。
当該意思決定に関して、IFRS第16号では具体的な例示があるが、本適用指針に当該例示を取り入れないこととした。これは、IFRS第16号の基準の本文では、資産の使用方法及び使用目的に係る意思決定は資産の性質及び契約の条件に応じて、契約によって異なる可能性が高いと定められているのに対し、これらの例示を示すことで資産の使用方法及び使用目的が限定的に解釈される可能性があるためである。
これだけでは、「使用方法を指図する権利」とは一体何なのか、理解することは非常に困難です。そして問題なのは、新リース会計基準がベースとしているIFRS第16号には、具体的な例示があるのに、今回の日本の基準としては割愛したという部分(太字の部分)です。IFRS第16号では、このもっとも重要な概念について、例示を含めてガイダンスともいうべき記載が充実しているのですが、なぜか日本の企業会計基準委員会(ASBJ)は、とても大事な部分をカットしてしまっているのです。
このカットされているIFRS第16号の記載の中でも、私が最も重要だと考えている記載が以下です。IFRS第16号のBC105項です。
IFRS 第16号は、顧客が特定された資産の使用を一定期間(所定の使用量によって決定される場合もある)にわたり支配するのかどうかに基づいて、リースを定義している。
顧客が特定された資産の使用を一定期間にわたり支配する場合には、当該契約はリースを含んでいる。顧客が資産の使用に関する重要な決定を、自らが使用する所有資産に関して決定を行うのと同様の方法で行う場合には、これに当てはまる。
そのような場合、顧客(借手)は資産を使用する権利(使用権資産)を獲得しており、それを貸借対照表に認識すべきである(ただし、IFRS第16号の第5項における認識の免除の適用がある)。これと対照的に、サービス契約では、サービスの提供に使用される資産の使用を供給者が支配している。
この記載があれば、かなり理解が進みます。特に下線部分です。すなわち、「借りたものでも、買ったものと同じように使い方を決められることができれば、それは『使用方法を指図する権利』を獲得しているということであり、その資産を支配している状況であるので、リースの定義を満たし、資産として計上すべきだ」ということになるのです。
ここまで理解ができれば、「リースの識別に関するフローチャート」における「使用方法を指図する権利」を顧客が持っているかどうかは、「顧客が、買った場合と同じように、この借りている物件の使い方を自由に決められるかどうかだ」ということになるでしょう。
これがリース会計の原点です。
皆さんが借りている物件は、買った場合と比べて、同じように使い方を自由に決められていますか?
オフィスを借りている際に、リモートワークが多くなり、空いているスペースが目立つようになったとしたら、少しでも収益を増やすために、転貸することはできますか?そのオフィスを買ったのであれば、空きスペースはどんどん貸し出して少しでも稼ぐべきでしょう。
転貸禁止条項は、この「使用方法」を自由に指図できない典型的な的な例だと思います。