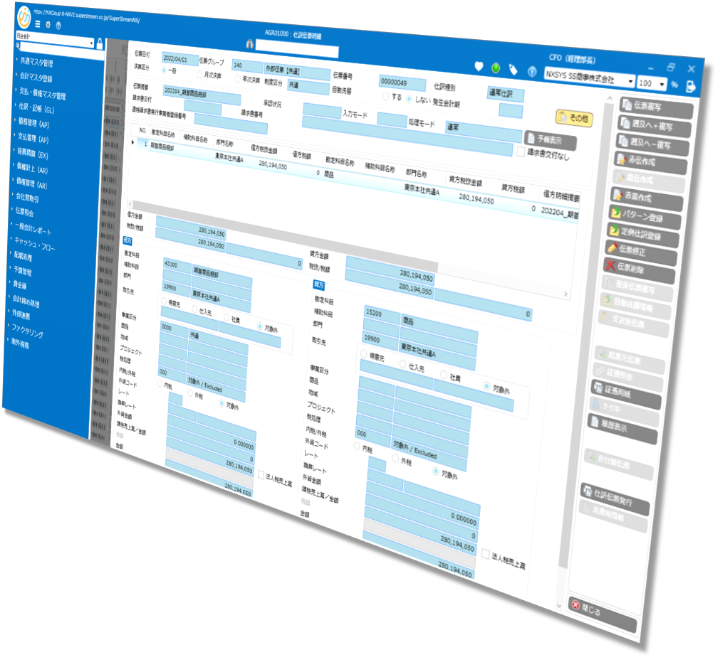会計コラム
移転価格税制「金銭の貸借取引・債務保証取引」改正のポイントと実務対応
コラム執筆者:田中 秀樹氏掲載日:2023年6月6日

国税庁は2022年6月、「移転価格事務運営要領」(事務運営指針)の一部改正を発表しました。この改正は2022年1月にOECD移転価格ガイドラインの金融取引に関する指針を反映したものと考えられ、金融取引と費用分担契約に関する取扱いについて、指針の内容を一部改正しました。
本改正は令和4年7月1日以後に開始する事業年度分の法人税の調査または事前確認審査について適用されます。決算期が3月の法人であれば2024年3月期から、12月の法人であれば2023年12月期から適用になるため、既に担当部署は取引銀行や顧問税理士等から情報収集をしていると思いますが、その実務対応方法は費用対効果も含め、いつまでに何を準備すればよいかは悩ましいところがあるのではないでしょうか。
本コラムでは、金融取引に係る改正について焦点をあて、改正のポイントや実務対応において留意すべき点を解説します。
改正前の金銭の貸借取引の独立企業間利率は、独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法を適用することを前提に、次の①②③の順に独立企業間利率を算定することができるとされていました。
①借手が第三者の銀行等から当該取引と通貨、時期、期間等が同様の条件下で借入したときに付されるであろう利率 ②貸手が第三者の銀行等から当該取引と通貨、時期、期間等が同様の条件下で借入したときに付されるであろう利率 ③当該取引と通貨、時期、期間等が同様の条件下で国債等により運用した場合に得られるであろう利率
この度の改正では、これらの手順は削除され、最も適切な方法により独立企業間利率を算定することになります。具体的には、借手の信用力を適切に評価し、その信用力をもとに公開データ等から金利を算定することが求められます。
借手の信用力の評価を事業会社が自ら評価することは実務的に困難だと思いますが、信用格付機関から親会社の信用格付けを取得している場合は、例えば、信用格付機関が公表している「グループ格付け手法」により親会社の信用格付けをベースとした子会社の信用力を評価する方法が考えられます。
また、信用格付機関から親会社の信用格付けを取得していない場合には、信用格付機関(例えば、ムーディーズ、スタンダード&プアーズ、格付投資情報センター等)や外部専門家等に依頼し、親会社の信用格付を算出してもらうことがよいでしょうが、高額な費用を必要とすることが予想されますので、移転価格の専門家等に依頼し、データベース等から親会社の財務状況と類似する法人の信用格付けを用いて、親会社の信用格付けを算出する方法も考えられます。
当該取引と通貨、時期、機関、信用力その他の比較可能性に影響を与える要素が同様の条件下であれば、公開されている銀行間金利、金利スワップレート、国債等により運用した場合に得られるであろう利率を比較対象取引とすることができます。
ただし、これらの市場金利は、借手の信用力を反映していないため、前出のとおり親会社の信用格付けをベースとした子会社の信用力を加えた独立企業間利率を算定することが求められます。この方法以外にも借手または貸手と業種、規模、信用格付け等が類似する法人が発行する社債利回りを用いて独立企業間利率を算定することも検討できます。
銀行等に照会して取得した見積り上の利率やスプレッドは、現実に行われる取引に依拠しない指標と考えられますので、原則、市場金利や借手の信用力の評価には使用できません。しかしながら、銀行等が長年の経験や確立した算定方法等から算出した情報であると評価できますので、前述のデータベース等から算出したみなし格付やスプレッドの確かめ算として活用することは有用であると考えられます。
従来のアプローチにおいては、保証者と被保証者の格付け・信用力に基づくデフォルト確率の差を保証料算定の基礎とするアプローチを採用している会社が多かったのではないでしょうか。
この度の改正では、債務保証取引により保証者は法的な責任を負うか否か、被保証者は信用力が増しているかを検討し、取引に有償性があると判断できれば、具体的には次の2つの算定方法を検討すべきとされています。
①保証のない場合と保証がある場合に支払う金利の差を保証料の根拠とする手法(イールドアプローチ) ②保証者に生じる予想損失額を保証料の根拠とする手法(コストアプローチ)
債務保証取引においても被保証者の信用力の評価が必要になりますが、金銭の貸借取引にて確認した方法により対応が可能だと思います。
また、イールドアプローチとコストアプローチのどちらを採用すべきか。あるいは両手法の平均値を採用すべきかについては、移転価格税制の適用に当たっての参考事例集においては、イールドアプローチ及びコストアプローチの両アプローチを用いて算出し、その両アプローチの結果の平均で保証料率を算出していますが、保証者が負担する信用リスクや被保証者により生じる経済的便益という観点から最も適切な方法により独立企業間価格を算定することになるため、必ずしも両アプローチを適用して算出する必要はないと考えられます。
金利や保証料の算出は、多くのケースで前述のデータベースを活用して比較可能性分析を行うことになるであると思いますが、その結果は取引単位営業利益法(TNMM)のように、独立企業間価格レンジ(幅)を算定することがよいと考えられます。税務調査において調査官がピンポイントの値を抽出する可能性は低いと考えられますし、既に運用している金利の検証やデータベース算定日と契約締結日の差を吸収する上でも幅を持たせて独立企業間価格レンジ(幅)を設定することが実務レベルでは合理的であると考えられます。
問題になりそうなのが業績の悪い赤字の海外子会社に対する取引だと思います。このような状況下では海外子会社へのローン金利や債務保証料率は低めに設定したいという親心がはたらくと思いますが、今後は業績の悪い会社に対しては、業績の良い会社に比べて信用力が劣りますので、高めの金利等の設定が求められます。
更に、金利の減免を検討したいという場合においても、ご承知のとおり、法人税基本通達では「合理的な再建計画」が条件となっているため、その適用はかなりハードルが高いことになります。このようなケースでは借手の金利負担を他の国外関連取引の分析に含めて検証する等の工夫が必要になってまいります。
金融取引は事業会社にとっては本業ではないことから、移転価格のメソッドに基づかない価格の決め方や税務調査で指摘を受けてから対応すればよいとする考えが見受けられますが、今後は、既存の金融取引、新規金融取引については、借手や被保証者の信用力を適切に評価したうえで、その信用力を基に独立企業間価格(率)を設定することが求められます。
昨今中小企業の海外進出が盛んになり、海外子会社との取引も増えていることから、税務当局の移転価格調査の対象となることが少なくありません。ぜひ、これを機に金融取引を含む国外関連取引のリスク分析を行い、税務調査に備えた移転価格ポリシーの策定や文書化等の事前準備を進めることを推奨いたします。