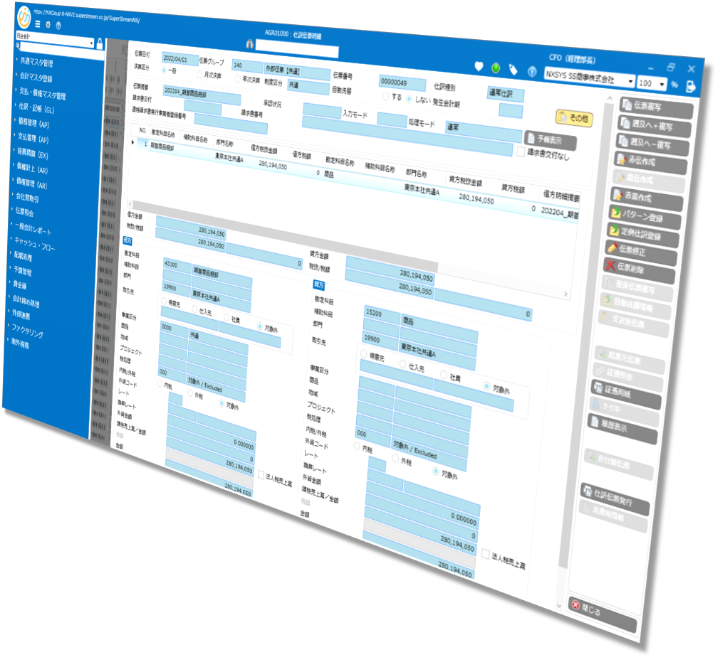会計コラム
103万円の壁の改正を考える
~令和7年度税制改正~
コラム執筆者:金子 真一氏掲載日:2025年3月19日

令和7年1月から3月にかけて国会で令和7年度税制改正が議論されていますが、その中の一つに103万円の壁対策があります。令和7年度税制改正大綱からその内容を見ることにします。
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げ並びに大学生年代の子等に係る新たな控除の創設を行う。
一 個人所得課税
1 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応
(国 税)
(1)基礎控除
① 基礎控除について、合計所得金額が 2,350 万円以下である個人の控除額を10 万円引き上げる。
(2)給与所得控除
① 給与所得控除について、55 万円の最低保障額を 65 万円に引き上げる。
(3)特定親族特別控除(仮称)
① 居住者が生計を一にする年齢 19 歳以上 23 歳未満の親族等(その居住者の配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が 123 万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額等から次のとおりの控除額を控除する。
(4)上記(1)から(3)までの見直しに伴う所要の措置
「令和7年度税制改正の大綱(令和6年12月27日閣議決定)」より抜粋
この改正が、私たちにどのような影響を及ぼすのかを考えてみます。
政治家、マスコミが「103万円の壁」という言葉を使うため、あたかもこのルールがあるように誤解する方もいらっしゃるかもしれませんが、きちんと定義された用語ではないので、このコラムで使う際の定義をします。
岸田政権時代の首相官邸の内閣官房室が公表していたHPの表現を一部抜粋すると
したがって、このコラムでは労働したら収入が増え、その分手取りが増えるはずなのに、所得税や社会保険料が発生することによって逆に手取りが減ることになる分岐点となる年収を壁と表現することにします。
諸説ありますが、
この合計額103万円と言われています。すなわち、給与所得者に係る所得税の世界から出てきた数字になります。もし給与ではなく、不動産所得や雑所得等の納税者の場合は103万円ではなく48万円となるでしょう。
給与による収入(額面)が103万円の壁を超えた場合、次の事態が発生する可能性があります。
大学生の子ども(19歳)がアルバイトしたケースで、納税者(親)の所得税の税率が20%と仮定します。
| アルバイト収入 | 子ども(扶養親族) | 親(納税者) |
|---|---|---|
| 100万円 | ― | 所得税▲126,000円 扶養控除63万円×20%=▲126,000円 |
| 110万円 | 所得税+3,500円 (給与所得(110-55)万円―基礎控除48万円)×5%=3,500円 |
扶養控除の適用なし |
子どもの収入がネット96,500円増えていますが、世帯収入としては29,500円減少します。親自身にとっては12.6万円もの減収となり、年末調整で還付あったのに、逆に納税が必要になったりしますので、親から子どもへのプレッシャーが強くなり、子どもはアルバイト時間を調整しようということになるかもしれません。これが壁と呼ばれる所以です。
令和7年度税制改正では、給与所得控除の最低額を10万円増やして65万円、個人所得税の基礎控除を10万円増やして58万円とすることで、103万円の壁を123万円の壁にすることが議論されています。併せて扶養控除の要件の引き上げも議論されていますので、実際の法律がどうなるのか注目する必要があります。
ただし、これは所得税に限った議論であり、社会保険については別のルールがあります。
103万円の壁は所得税に係るものでしたが、岸田政権時代に内閣官房内閣広報室が公表していたのが社会保険に係る106万円の壁と130万円の壁です。社会保険とは、主に保険証の交付を受けたりする健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料(個人の場合は国民年金保険料)や雇用保険料等の総称です。
夫が給与所得者の場合、配偶者である妻の収入が一定額以下であれば、扶養親族として健康保険料を納付することなく夫の会社の健保組合から健康保険証が交付されますし、2号被保険者として国民年金保険料の支払いが免除されます。一方、妻が一定の収入以上となり扶養親族から外れると、妻個人で健康保険料を納付し、国民年金保険料等を負担しなければならなくなります。
この場合、妻自身に社会保険料が発生する可能性があります。
| 発生する社会保険料 | 対象となる要件 | |
|---|---|---|
| 106万円の壁 |
|
|
この場合、妻自身が国保に加入しなければならない可能性があります。
| 発生する社会保険料 | 対象となる要件 | |
|---|---|---|
| 130万円の壁 |
|
|
ただし、この130万円という基準は夫が勤める会社の健保組合によって異なりますので、個別に確認する必要があります。
パートやアルバイトで働く者の厚生年金保険や健康保険の加入に合わせて、手取り収入を減らさないための取り組みをする企業に対し、労働者1人当たり50万円支援があります。企業等は、これを原資に年収の壁の範囲内で調整していたパートやアルバイトで働く者が、もっと働くことが出来る環境を作ることができます。
この施策は令和5年10月からの2年間となっており、この期間で制度の見直しにも取り組むとされています。
パートやアルバイトで働く者が、繁忙期に労働時間を延長したことなどにより、収入が一時的に上がり130万円を超えた場合、会社が一時的な収入の増加であることを証明することにより、引き続き配偶者の扶養に入ることが可能とされています。
この施策も令和5年10月からの2年間となっており、この期間で制度の見直しにも取り組むとされています。
今回の税制改正の議論は社会保険制度の見直しと直接リンクしていません。仮に令和7年度税制改正の大綱とおり税制が改正された場合、103万円の壁が123万円になったからといっても社会保険の壁が別途存在します。
社会保険制度は適用範囲を拡大する方向にあり、また税制改正と異なり厚生労働省を中心とした所で議論、改正されるため、いつ変わったのか気づかないことも多いです。私たちは所得税だけでなく、社会保険の改正についても注視していく必要があります。