人事・総務コラム 特定社会保険労務士 菊地 加奈子氏・第2回長時間労働が“違法”となる?労働基準法改正でますます重要性が高まる労働時間管理コラム執筆者:特定社会保険労務士 菊地 加奈子氏 掲載日:2018年1月29日
安倍内閣主導のもと、一億総活躍社会の実現に向けて働き方改革実現会議が行われ、10回にわたる議論が繰り返されてきました。
この会議が立ち上がった背景として、長時間労働による過労死や過労自殺といった社会問題が顕在したことが挙げられます。
長時間労働を美化してきたいわゆる「昭和型」の働き方では女性のキャリア形成が進まないこと、家庭における夫婦の役割分担も変化せず、少子化問題が解消されないこと、そして何より長時間労働は多くの健康被害をもたらすということが社会全体の課題として共有されました。
こうした問題を打開していくために「働き方改革実行計画」がまとまり、2019年4月を目処に労働基準法が改正される方向で進んでいます。
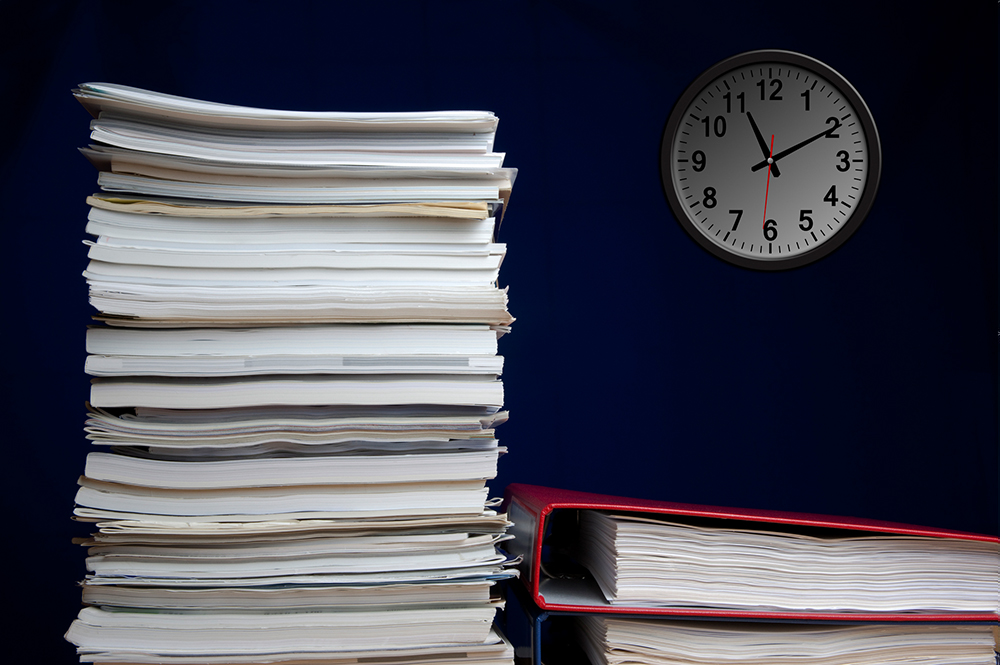
36協定の特別条項と過労死ライン
36協定には厚生労働省告示の中で月に45時間、1年間で360時間以内という基準が設けられていますが、罰則がない上に特に忙しい場合などには「特別条項」を設ければ、実質いくらでも残業時間が設定できる状況にありました。
これを見直すため、36協定を超えて働かせる特別条項に上限ができるようになります。
改正ポイント① 特別条項に上限。1か月100時間へ
・36協定の年間の時間外労働は720時間(月平均60時間)
・2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月の平均でいずれにおいても、休日労働を含んで80時間以内
・単月では、休日労働を含んで100時間未満
これまでは厚生労働省告示という“基準“だったのが、労働基準法という法律の中に時間の上限が明記されることになるため、違反した場合には当然罰則が適用されることになります。
働き方改革実行計画の中でも「かつてのモーレツ社員という考え方自体が否定される日本にしていく」と強く訴えているように、働き方改革の根本にある長時間労働の文化を変えることを最重要課題としています。
改正ポイント② 中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し
平成22年の労働基準法改正により、60時間を超えた場合の時間外労働の割増率が50%に引き上げられましたが、これまで中小企業は猶予されていました。今回の法改正により、割増率の適用猶予が廃止され、大企業と同様のルールとなります。
時間外労働が60時間を超えると割増率が50%になるということは、時間外労働が深夜時間帯にかかった場合、75%の割増率になるということです。中小企業にとって残業代の大幅な増加は、経営上の大きなリスクといえるでしょう。
法改正までにやるべきこと① 労働時間把握
これまでの日本の労働慣行を大きく変えていくことは簡単なことではありません。
ノー残業デーや業務改善と謳っても、自社努力だけではどうにもならない問題があるというのが実情です。そのため、労働基準法改正のための周辺の法規制の整備を含めた、具体的な準備が進められようとしていますが、労働時間管理の義務化もそのひとつです。
厚生労働省は2017年8月に労働安全衛生法施行規則を改正して、従業員の労働時間を適切に把握することを、企業などの義務として明記する方針を固め、関連法施行までに労働安全衛生法施行規則を改正するとしています。
賃金台帳には労働時間数や割増賃金の計算根拠として、残業時間や深夜時間を記載する必要があるため、以前から法律で労働時間把握は義務付けられていたということはできますが、現在は「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」をもとに指導が行われている状況で、労働時間把握・管理のための具体的な方法について法律上の定めはありません。
今後は法律によって労働時間把握が義務化されることにより、企業の人事部は従業員の残業時間を日々把握し、長時間労働者については残業時間を減らすための対策を打つ必要が出てくることでしょう。
法改正までにやるべきこと② メンタルヘルス対策
すでにストレスチェックについては法制化されていますが、過労死等防止対策推進法に基づく大綱においても、メンタルヘルス対策の目標が示されています。長時間労働をなくしていくことが大前提ではあるものの、今まさに長時間労働による過労死や精神疾患に陥る人の数は増え続けているという現状から、社員の健康管理にかかる措置を徹底し、良好な職場環境を作りながら心身の負荷を軽減していくことが求められています。
そして法改正によって労働時間に上限を設けたとしても、「その時間まで働かせることができる」のではなく、限りなく短縮してくことを求める、というのが国のスタンスでもあります。職場における労働時間の状況とあわせて社員一人ひとりのメンタルヘルスについて適正に把握していくことも重要です。
まとめ
残業時間の上限規制や残業代の割増率アップは経営上のリスクともいえますが、一方で、これまでの働き方、企業文化を根本から見直す大きなチャンスでもあります。2019年までの準備期間にじっくりと体制を整えていくことが今まさに企業に求められていることといえるでしょう。






