
40年に及ぶ金融事業の歴史が「金融×AI」を推進する可能性とは
全国の金融機関向けに40年に及びITサービスを提供してきた金融事業。FISC安全対策基準に基づき金融業界において急速にDXが進む中で、歴史を持つ金融事業が果たすべき役割は何か。入社後20年以上金融事業に携わってきたベテランエンジニアと、2024年度に金融事業に異動してきた中堅エンジニアのお二人に、金融事業の優位性やAIとの共生などについてお聞きしました。
 メンバー
メンバー
-
S.M.
2003年に新卒入社。金融ソリューション事業部に配属後は証券会社を担当し、アプリチームのリーダー、PMを経験する。2019年からは保険会社を担当。2021年からNECに兼務出向し、大手生保・損保のプロジェクトにシニアマネージャーとして参画。
-
Y.A.
2014年に新卒入社。クラウド系オープンソースソフトウェアの開発コミュニティ活動や技術開発、自治体へのスマートシティ基盤の導入に携わり、2024年に金融ソリューション事業部に異動。金融向けのクラウドや生成AIの基盤構築を担当。
今までのキャリアと、お二人の関係性について教えてください。
S.M.
2003年に新卒で入社して以来、ずっと金融ソリューション事業部で勤務しています。当初は証券会社様を担当し、アプリチームのリーダー、テスト推進、オフショア推進、PMを経験しました。2019年に保険会社様の担当に異動し、DX関連システムや基幹システムをマルチプロジェクトで担当しています。2021年にNECに兼務出向し、現在も継続中です。
Y.A.
私は2014年にNECソフト沖縄(現・NECソリューションイノベータ 沖縄支社)に新卒で入社しました。これまでクラウド系オープンソースソフトウェアの開発コミュニティ活動や技術開発、自治体へのスマートシティ基盤の導入など様々な領域に携わってきています。2024年度から金融ソリューション事業部へ異動し、メガバンク向けのクラウドや生成AIの基盤構築を担当しています。
S.M.
現在は保険領域のアプリ、例えば大手生命保険のアプリ、大手損害保険のDX、オンラインを担当しています。シニアマネージャーとしてチームのメンバー22名をマネジメントしながら、各プロジェクトの体制調整などを実施中です。
Y.A.
私のチームはAzure、AWS、GCPなどクラウドインフラの専門部隊として、メガバンク様の大型のインフラ構築案件を担当しています。私はプロジェクトマネージャー兼ITアーキテクトとして複数の案件を推進。大規模案件ではアプリ開発ベンダーやクラウドベンダーなどと協力しながら、チーム全体で数十名のメンバーでプロジェクトを進めています。
S.M.
Y.A.さんにお会いするのは2024年7月の沖縄出張以来ですね。その時は損保のお客様をお連れして沖縄の開発体制を視察しつつ、社内のAI有識者の会議を行いました。その後の懇親会でY.A.さんにいきなり泡盛を振る舞われたことを覚えています。
Y.A.
そうでしたね。私は金融ソリューション事業部に異動してまだ数カ月というタイミングで、S.M.さんの保険領域と私のメガバンク領域の間で会議や懇親会で交流ができたことは、とてもありがたかったです。

現在の業務について教えてください。
Y.A.
私はメガバンク様向けの大規模なクラウドインフラ環境を整備する業務を行っています。新規にクラウドを構築するものであったり、オンプレミスにあるレガシーなインフラをクラウドネイティブな仕組みに作り替えるクラウドシフトの案件も担当しています。最近の案件で言うと、生成AIの活用が前提になることが多いので、インフラとしても情報漏洩対策などのセキュリティを考慮したインフラを作っています。
S.M.
私は2023年10月から大手損害保険会社様のサービスセンターにおける生成AIチャットツールのプロジェクトにPMとして参画しました。NECとして初めて金融機関に対して生成AIを業務適用した案件として社内のプロジェクト表彰を受賞、当社WEBサイトに掲載しているサステナビリティ経営に関するレポートにも掲載されています。
Y.A.
読ませていただきました。損保様サイドのシステム子会社様を通さない直取引だったんですよね。
S.M.
証券会社様を担当していた頃はそういうケースもありましたが、損保領域での直取引は金融ソリューション事業としては初めてのことです。NECがプロジェクト全体についてスピード感を持って推進する必要があったため、マネジメントでは様々な工夫が必要でしたね。お客様と配下のLLM・音声テキスト化の専門部隊をつなげる役割を担い、特にお客様目線に立ったマネジメントを心がけました。例えば画面レイアウト設計やLLMのプロンプトの作成、専門用語辞書の作成などでは、サービスセンターの社員の方々にプロジェクトに参画していただき、より使いやすい画面や要約結果の出力ができるシステムを構築しました。
Y.A.
お客様目線に立つことは重要ですね。これは金融業界に限ったことではありませんが、私が担当するメガバンク様は特定の技術・ベンダーへの依存を避けたいという志向が顕著です。そのため標準的なアーキテクチャを理解して設計していくことが求められますが、一方で標準化しすぎると柔軟性に欠けるシステムになってしまう。お客様の要求を満たしつつ、使いやすさ、ガバナンスなど、トレードオフのバランスを考えながら理想的なシステムを作っていくことに日々挑戦しています。
S.M.
ただ、だからこそやりがいも大きいですよ。私はお客様にお声がけいただいて、サービスセンター間の情報共有会議に参加させていただいたのですが、「誰でもすぐ使えます」「話し方を気をつけることでしっかりとした要約が返ってきます」という生の声が聞けたのは嬉しかったですね。その声はすぐにメンバーにも展開しました。
Y.A.
メガバンク様とのプロジェクトでは、多くの新しい技術を吸収し、高品質で実装していくチャンスにも恵まれています。大袈裟かもしれませんが、私がメガバンクのクラウドインフラを支えることで、多くのエンドユーザーの方々の金融資産を守る一助となっている、そのやりがいは確かに大きいですね。

金融事業の長い歴史によって培われた強みをどのように捉えていらっしゃいますか?
S.M.
そもそもNECソリューションイノベータ発足前のソフトウェア会社(NECソフト)から、全国の金融機関向けにITサービスを提供してきました。大手の銀行、保険会社、証券会社、そして地域金融機関向けに40年にわたる豊富な実績があり、お客様との強い信頼関係を築いています。
Y.A.
それは私も現場で感じています。所管しているシステムでもそれ以外でもお客様から「ここはNECさんでやっているから詳しいですよね」という声を聞くことが多いです。40年の歴史にはかなりの優位性があるでしょう。
S.M.
ただ、金融業界は急速に変化しているのも事実です。かつてはレガシーな技術を用いたシステム開発が主流でしたが、現在ではDXの進展によって先端技術を活用したサービス提供が求められています。そこで金融ソリューション事業部ではAIやクラウド技術を駆使し、柔軟で効率的なシステムを提供することでお客様のニーズに応じたITサービスを提供しています。
Y.A.
金融機関に対しては一般的に「レガシーの技術によって堅牢なシステムを高品質に開発していく」というイメージが強いと思います。しかし実際には、新しい技術にとても敏感で、良いものはどんどん取り入れようという意識がとても強いです。生成AIについては、お客様ご自身もかなり勉強されていて、すでにシステム開発や社内システムで活用が始まっています。「こういったことをやりたいのですが、できませんか?」といったご相談も多数いただきます。この点は私が金融領域に参画して、大きくイメージが変わったところです。
S.M.
そこで金融事業戦略としては、ITサービス市場の成長を見据え、全国拠点が一体となって対応するマルチサイト施策の拡充に重点を置いています。IT人材の確保と育成を強化することで競争力を高め、大手金融機関向け大型プロジェクトの確実な遂行と、地域金融機関向けの事業拡大に注力。金融機関向けITサービスの提供を通じて、社会全体の発展に貢献し続けることを目指しています。
Y.A.
私が沖縄で開発に携わっていることも、マルチサイト施策の一環と言えますね。
S.M.
Y.A.さんの沖縄拠点をはじめ、北海道、九州、四国、大阪、名古屋…全国に開発拠点を展開中です。お客様やNECの社員とともに拠点を訪問して、開発環境の充実度を確かめてもらう。この地道な取り組みも、信頼関係の強化につながっています。

今後「金融×AI」の発展に伴ってどのようなことが求められるとお考えですか?
S.M.
先ほどの損保様のプロジェクトで感じたのは、生成AIは使い方によって毎回答えが違い完璧ではない、ということです。LLMプロンプトチューニングや、音声の認識精度の改善を進めながら、お客様の業務に合わせてなるべく標準化された答えが出てくるようにすることは、かなり重要になってきますよね。ただ適用するのではなく、業務を最適化できるようなチューニングなどの場面で我々の技術が活きてくると思いますし、さらに技術力を伸ばしていきたいと考えています。
Y.A.
現在、様々なAIプラットフォームベンダーが出てきていますが、OpenAIの基盤からオープンソースのプラットフォームまで選択肢が広がる中での差別化は非常に難しくなるはずです。将来的には「いかにアプリ側でAIを組み込んで価値を出すか」で勝負となるでしょう。そこで私のチームでは、現在、メインにやっている基盤だけでなく、しっかりとアプリのレイヤーにも踏み込んでいき、トータルでシステムを作っていけるようにと考えています。また、お客様のニーズが顕在化する前に、こちらから提案する形でイニシアチブを握ることも大切です。
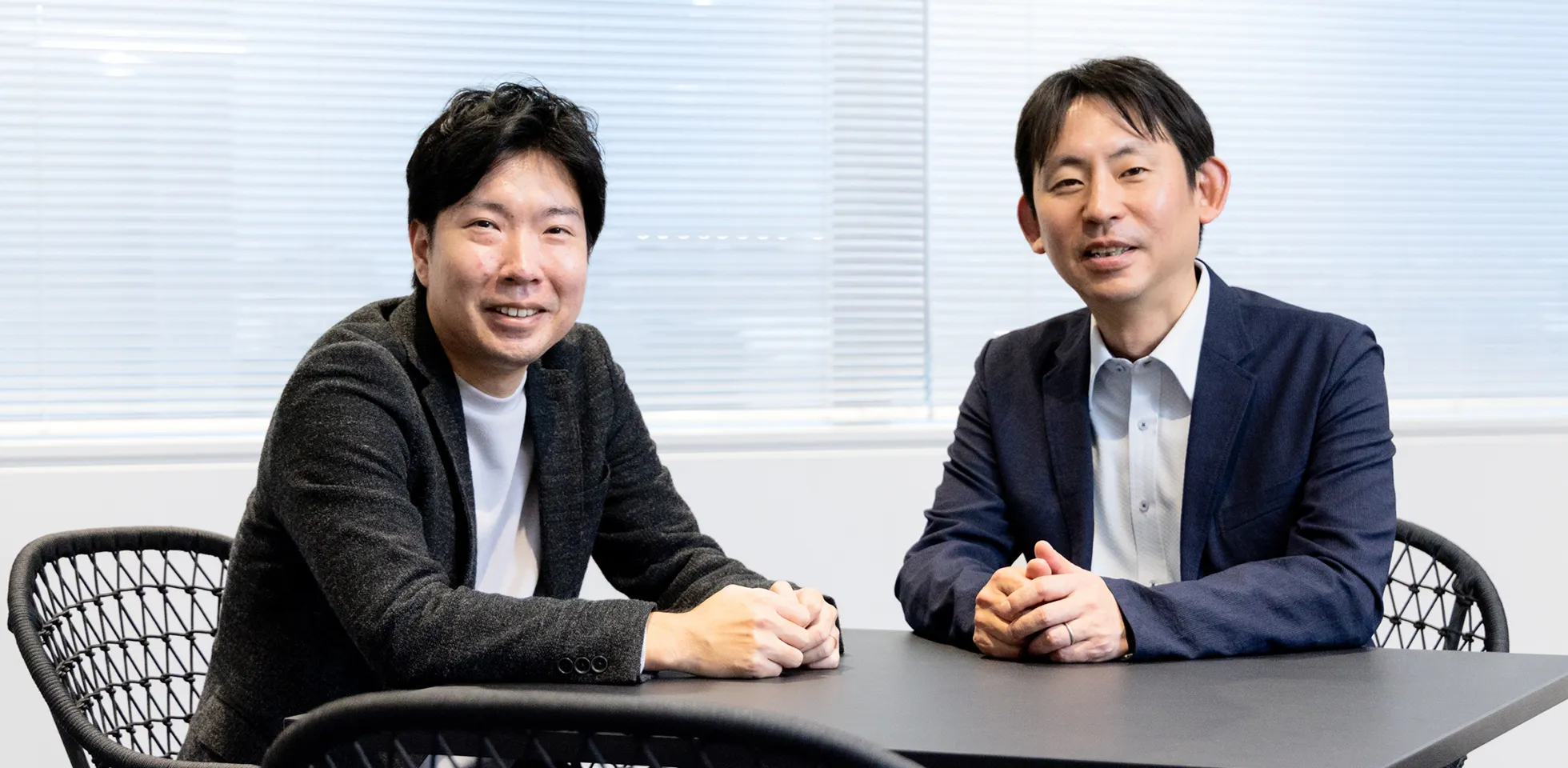
金融に関わる業務に興味がある方へメッセージをお願いします。
Y.A.
金融SEというのは、セキュリティや性能、可用性、堅牢性、などのミッションクリティカルな非機能要件の実現が求められる仕事です。これらの要件を実現できる技術者は、市場価値が高いとされていますので、技術者としてのキャリアの裾野を広げる良い選択になると考えています。
S.M.
私のチームでは、技術力を備えた上で「リーダー」という立場で動いていく機会が多々あります。若くてもお客様やビジネスパートナー様としっかりコミュニケーションを取り、自発的にプロジェクトを推進することができる人は、活躍するチャンスが豊富にあるでしょう。
※ 記載内容は2025年2月時点のものです










