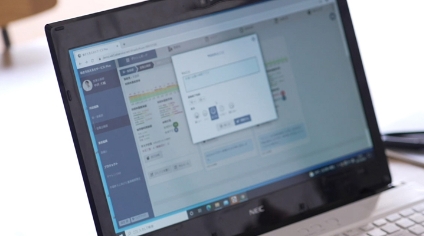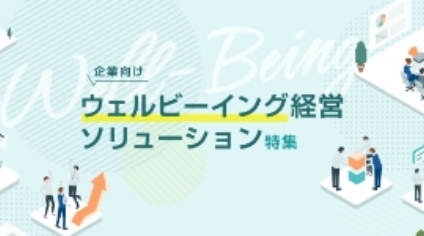サイト内の現在位置
コラム
GDW(国内総充実度)とは?
指標や動向、ウェルビーイングについて解説

UPDATE : 2024.03.12
GDWとは、日本語では「国内総充実」と呼ばれ、国民のウェルビーイング(幸福度)を測る新たな指標として注目されています。GDPだけでは、国民が実感できる幸福度を測るのは難しいという見方が広がり、国連やイギリスなどではGDWを重視する施策が実施されています。日本でも、政府の方針発表や民間企業などの動きがあり、関心を集めています。
本記事では、GDWの意味やGDPとの違い、GDWをめぐる世界と日本の動向などについてわかりやすく解説します。
INDEX
- GDW(国内総充実)とは?
- GDP(国内総生産)との違い
- GDWが注目される背景
- そもそも「ウェルビーイング」とは?
- GDWの指標
- カーネギー財団(イギリス)のGDWe
- GDWやウェルビーイングに関する世界の動向
- 経済協力開発機構(OECD)
- 国連(国際連合)
- ブータン
- イギリス
- GDWやウェルビーイングをめぐる国内の動き
- 日本政府の動き
- 内閣府による「満足度・生活の質に関する調査」
- Well-being Initiativeの発足
- 企業経営においてもウェルビーイングが指標として重視される時代に
- 非財務情報の企業価値がわかる「統合諸表」
- まとめ
GDW(国内総充実)とは?
GDWとはGross Domestic Well-beingの略で、日本語では「国内総充実」と言われており、国の発展と国民のウェルビーイング(幸福度)を測る新たな指標として注目されています。GDWは経済的な側面だけでなく、精神的・身体的健康、社会的つながり、教育、環境など幅広い要素を考慮します。そのため、持続可能な社会の発展や実感できる豊かさを目指すこの時代において、国内外から重要視され始めています。
日本では、2021年2月4日に行われた第204回国会予算委員会で、自民党政調会長の下村博文氏が「国民のウェルビーイングを測る指標として、従来のGDPに変わりGDWを新たな物差しとして検討したらどうか」と発言し、GDWを提唱しました。
GDP(国内総生産)との違い
GDPはGross Domestic Productの略で、「国内総生産」を意味します。一定期間内(通常1年間)に各国内で算出されたモノやサービスの生産や販売により得た利益の総額によって、国の経済活動の状態を判断することを目的としています。
一般的には、GDPの高さによって国の繁栄度合いが図られますが、「経済的な成長だけでは国民の幸福度は測れないのではないか」という見方が広がっています。例えば、GDPが高くても、国民の生活満足度が低く幸福を実感できていない状況では、国民の幸福度が向上することは期待できないでしょう。そのため、GDPという経済指標だけで国の豊かさを示すには、限界があると言われています。
GDWが注目される背景
先進国では、GDPで測る経済成長と、国民の幸福度に乖離が発生しています。国連の持続可能な開発ソリューション・ネットワーク(SDSN)が発表した「2023年度版世界幸福度ランキング」では、フィンランドが6年連続で1位。その理由として、政治に対する信頼性の高さ、充実した社会保障、高レベルの教育や医療を受けやすいことなどが挙げられています。続いて2位デンマーク、3位アイスランド、6位スウェーデン、7位ノルウェーと北欧諸国が上位を占めています。
一方、GDPランキング世界1位の米国は、幸福度ランキングでは15位。日本はGDPでは世界4位ですが、幸福度ランキングでは47位という結果でした。このようにGDPだけで国民の幸福度を測るのは難しいため、GDWという新たな指標に注目が集まっているのです。
そもそも「ウェルビーイング」とは?
ウェルビーイング(Well-being)とは、身体的・精神的・社会的に良好である状態を指す言葉です。世界保健機関(WHO)が1948年に発効した世界保健機関憲章では、「Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.(健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的、精神的、社会的にすべてが満たされた状態にあること)」と定義しています。厚生労働省はウェルビーイングを「個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態」と定義しており、瞬間的な幸せを表す「Happiness」とは違って、持続的な幸せを指します。
昨今では、企業経営を向上させる一環として、多様な人材を受容するダイバーシティ経営や、持続可能な開発目標であるSDGsが重要視されています。その流れを受け、従業員満足度を向上させることで人材不足へ対応し、経営の安定を図るために、ウェルビーイングの向上に注力する企業が増えています。
GDWの指標
国内外で関心が高まるGDWですが、現在においては、国際的にコンセンサスを得ている公式な指標はありません。そうした中、イギリスの民間機関がGDW試案を策定しているのでご紹介します。
カーネギー財団(イギリス)のGDWe
慈善家のアンドリュー・カーネギーによって設立された非営利組織であるカーネギー財団は、GDWの指標としてGDWe(Gross Domestic Wellbeing ™)を作成しています。個々のGDWを測定するため、「Personal well-being」「Our relationships」「Health」「What we do」など10の分野において、2~6種類の統計やアンケートデータを用いて指標を設定しています。
Creating the GDWe Score
| 1 | Personal well-being | 2 | Our relationships |
| 3 | Health | 4 | What we do |
| 5 | Where we live | 6 | Personal finance |
| 7 | Economy | 8 | Education and skills |
| 9 | Governance | 10 | Environment |
同財団はこのGDWeを用い、イギリスの実質GDPの推移と比較したところ、イギリスのGDWeは2013年から2015年まで上昇したものの、2018年からは低下傾向にあることが分かりました。一方でGDPは、2013年から2019年まで伸び続けており、物質的な豊かさと国民が実感する幸福度に乖離があると明らかになりました。
GDWやウェルビーイングに関する世界の動向
ここでは、GDWやウェルビーイングに関連する世界の動向を解説します。
経済協力開発機構(OECD)
日本やアメリカ、EUなど先進国38か国が加盟する国際機関である経済協力開発機構(OECD)は、ウェルビーイングや良い暮らしを追求することを目的として「Better Life Index(良い暮らし指標)」を策定しています。この指標では、住宅・所得・雇用・社会的つながり・教育・環境・市民参画・健康・主観的幸福・安全・ワークライフバランスの11の分野において、40カ国の指標を比較できます。2020年の報告によると、日本では「平均余命」や「就業率」では他国と比較として良い結果でしたが、「休暇」「過密率」「負の感情・バランス」に関してはOECD平均を下回る結果になりました。
国連(国際連合)
先述したように国連は、3月20日に「国際幸福デー」として世界幸福度調査(World Happiness Report)を発表しています。同調査では、個人の主観的な生活評価をスコア付けし、GDP・社会的支援・健康寿命・人生における選択の自由度・寛容度・社会の腐敗の認識といった6つの要因を分析・ランク付けしています。2023年の報告では、主要7か国(G7)はカナダ13位、米国15位、ドイツ16位、イギリス19位、フランス21位、イタリア33位で、日本は47位でした。
ブータン
ブータンでは、第4代国王がGNP(国民総生産)よりも、国民全体の幸福度を示す指標GNH(国民総幸福)を重視する政策を掲げました。GNHには、持続可能で公平な社会経済開発・環境保護・文化の推進・良き統治の4つの柱があります。具体的には、心理的な幸福・国民の健康・教育・文化の多様性・地域の活力・環境の多様性と活力・時間の使い方とバランス・生活水準・所得・良き統治の9つの分野で構成。国民の幸福度を中心とした国家運営は、世界的に大きな影響を与えています。
イギリス
イギリスでは、2010年から国家統計局がウェルビーイングを計測するダッシュボード(Measures of National Well-being Dashboard:MNW)」を策定。国民の幸福度の測定プログラムを開始し、内容はWebサイトなどで公表されています。ダッシュボードは、個人の幸福・対人関係・健康・仕事と活動・居住地域・個人資産・教育と職業技術・経済・統治・自然環境の10領域により構成。例えば個人の幸福では、生活満足度・やりがい・幸福感・不安などについて、 0~10の評価で回答を得る形式です。得られた調査データは、国民の幸福度を向上させる政策に活用されています。
GDWやウェルビーイングをめぐる国内の動き
日本国内でも近年、GDWやウェルビーイングに関する動きが活発になっています。
日本政府の動き
先述したように、2021年2月衆議院予算委員会で下村博文氏がウェルビーイングを測る物差しとしてGDW(国民総充実度)を提案。当時の菅内閣総理大臣から政府の目指す社会の方向性と同じものという答弁がなされ、ウェルビーイングをめぐる動きが加速しました。
同年6月には、閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針 2021」(骨太の方針)において、個人と社会全体のWell-beingの実現を目指すと記載。政府の各種基本計画には、ウェルビーイング関するKPI(重要業績評価指標)を設定しました。各省庁での取り組みも加速し、内閣官房、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省などで基本計画にウェルビーイングに関するKPIが盛り込まれました。
経済産業省では、2022年度から企業のウェルビーイングに関する調査を充実させるとして、健康経営度調査において、アブセンティーイズム(心身の体調不良により仕事を休業している状態)や、ワーク・エンゲージメント(従業員の仕事への「熱意・没頭・活力」の3点が満たされている心理状態)を項目に追加。主観的ウェルビーイングと企業経営の関係性を分析しています。
内閣府による「満足度・生活の質に関する調査」
2019年から内閣府は、国民の生活満足度(ウェルビーイング)の動向を調査する「満足度・生活の質に関する調査」を実施しています。同調査では、家計と資産・雇用環境と賃金・仕事と生活・健康状態・教育水準と教育環境・社会とのつながり・子育てのしやすさなど13の分野を設定。満足度や質問等により、主観・客観の両面から多角的にウェルビーイングを把握しています。
「満足度・生活の質に関する調査報告書2023」によると、仕事への意識と生活満足度の関係について、雇用形態や年収に関わらず仕事へのポジティブな意識を持つことは、満足度を上昇させると述べています。
Well-being Initiativeの発足
ウェルビーイングを重視する昨今の流れを受けて、日本国内の民間企業でもウェルビーイングの概念やそれを評価する新指標を社会に広めていこうとする動きが出ています。2021年、公益財団法人Well-being for Planet Earthと日本経済新聞社、そして複数の国内企業が参画する企業コンソーシアム「Well-being Initiative」が発足しました。
Well-being Initiativeでは、「いい企業」の定義をウェルビーイング視点で考え議論したり、ワークショップや有識者が集まるシンポジウムを開催したり、ウェルビーイングを普及させるためのメディア発信などを行っています。また企業経営においては、非財務情報や無形価値も重要であると考え、「事業」「社員」「社会」「環境」の4象限から統合的な視点で企業価値を評価する、財務諸表に変わる「統合諸表」の開発も行っています。
Well-being Initiativeには、NECソリューションイノベータを含む25社(2024年2月現在)が会員企業として参画しており、今後の世界経済において重要な視点となるGDWの概念を研究し、企業経営に活かす取り組みを実施しています。
企業経営においても
ウェルビーイングが指標として重視される時代に
Well-Being Initiativeの会員企業などをはじめ、大企業だけでなく中小企業においても、ウェルビーイングを考慮した取り組みが広がっています。自社内だけでなく、ステークホルダー全体のウェルビーイング向上を図る企業も増加傾向にあります。企業経営においても、業績や財務状況は重要ですが、社員の幸せが企業価値を生み出すことにつながると考え、ウェルビーイングを企業経営における外せない指標として重視されてきているのです。
非財務情報の企業価値がわかる「統合諸表」
これまで企業の価値は、おもに業績によって測られてきました。企業価値の測定に使用されているのが「財務諸表」です。しかし、この先も企業の成長を持続させるには、社員の状態、環境への取り組み、社会への貢献といったウェルビーイングに関する非財務情報も重要なカギを握ります。財務諸表では、業績や財務面は明示できますが、それ以外の情報については評価方法や開示についての課題がありました。
そうした中Well-being Initiativeは、ウェルビーイングなどの非財務情報を可視化するフォーマットとして「統合諸表」を開発しました。このフォーマットは、非財務情報に対する企業価値が一目でわかる一枚絵モデル。パーパス(会社の存在意義)を中心に、「事業」「社員」「環境」「社会」の4象限に戦略、アクション、KPI(非財務指標)を配置することで、企業の状態を一枚で表現できます。
「統合諸表」を活用すれば非財務情報が可視化できるため、ウェルビーイングを重視した企業経営の評価につながるでしょう。
Well-being Initiative事務局の株式会社電通が開発した「統合諸表」
まとめ
GDWは「国内総充実」と呼ばれ、国民のウェルビーイング(幸福度)を測る指標として注目されています。国の経済的な繁栄度合いはGDPで測られますが、「経済的な成長だけでは幸福度は測れない」という考えが広がり、世界的にもGDWを重視する施策が打ち出されています。国内でも、政府が骨太の方針などによってウェルビーイング向上を目指す指針を発表し、民間企業においてもウェルビーイングを企業経営に活かす取り組みが進められています。持続可能な社会の実現において重要な視点となるGDWを研究し、自社経営に活かす取り組みを今から進めていくと良いでしょう。