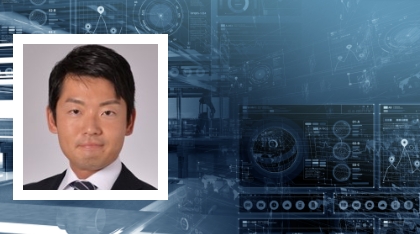サイト内の現在位置
専門家コラム
《連載》製造業DXの起点
~デロイト デジタル提言2022~
- 【執筆者】デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
- シニアコンサルタント 山下知輝氏
【第2回】製造業のチャネル変革におけるデジタル変革
(デジタルマーケティング)

UPDATE : 2022.01.07
昨今、デジタル技術の進展によって、私たちの生活やビジネスが急速に変化している。消費者や企業は必要な情報をオンラインで容易に収集することができ、またデータ活用によって各人・各企業の細分化したニーズや趣向に応えたサービスを提供することが当然のように求められている。
さらには、直近の新型コロナウイルスの影響により、マーケティングチャネルのデジタル化は待ったなしの状況が数年来続いている。そうしたデジタル化の流れに対応し、製造業企業が成長し続けるために求められるマーケティングチャネルの変革とは何なのか?
連載第2回では、デロイトトーマツコンサルティングのデジタル領域専門サービス「デロイトデジタル」のスペシャリストが、「製造業企業に今求められているマーケティングチャネルのデジタル変革とは何か?」をBtoB(企業から企業の取引)の観点から考察する。
INDEX
- 製造業企業のマーケティングチャネルの現状
- 製造業企業のマーケティングチャネルにおける課題(なぜデジタル化による成果が思うように出ないのか)
- ①戦略不在のパッチワーク的デジタル化
- ②デジタルチャネルにおける情報不足/情報過剰
- ③不十分なデータ活用
- 製造業企業に求められる マーケティングチャネルのデジタル変革
- ①最新デジタルテクノロジー動向もふまえたカスタマージャーニーの再設計
- ②顧客が得たい情報に最速で到達できるような情報提供の実現
- ③データ活用による付加価値創出/営業リソース集中
- まとめ
- そのほかの連載記事(第1回~第6回)
製造業企業のマーケティングチャネルの現状
元々のデジタル化の大きな流れに新型コロナウイルスの感染対策が加わり、企業のマーケティングチャネルのデジタル化は急速に進んでおり、それは製造業企業も例外でない。例えば、バーチャル展示会やウェビナーなども一般的となった。しかしながら、思うような成果を出せていない、従来のリアルチャネルでの展示会の方が大きな成果を出せていた、という声もしばし聞こえてくる。
また、製造業企業はニッチな製品を数少ない顧客・潜在顧客向けに扱っている企業も多く、いわゆるデジタルマーケティングの定石(リスティング広告やSEO対策で広く集客⇒ランディングページを作り込みコンバージョン)が通用しないケースも多い。
顧客への情報提供については、Webサイトやアプリの整備により着実にデジタル化が進展している。しかしながら、製造業企業は商品数や情報量(スペック情報など)が膨大であるケースも多く、その結果商品情報が複数サイトに散在するなど、不便さにより顧客のロイヤルティが低下しているケースも見られる。
製造業企業のマーケティングチャネルにおける課題
(なぜデジタル化による成果が思うように出ないのか)
なぜ、製造業企業のマーケティングチャネルのデジタル化はなかなか思うように成果が出ないのか。筆者は「①戦略不在のパッチワーク的デジタル化」「②デジタルチャネルにおける情報不足/情報過剰」「③不十分なデータ活用」に集約されると考えている。
①戦略不在のパッチワーク的デジタル化
自社のコアバリュー(他社との差別化ポイントとなる訴求価値)やカスタマージャーニー(顧客が自社製品/サービスを知り、関心/購買意欲が醸成され、比較検討し、社内稟議を通し、購買し、継続顧客化するまでの一連の流れ)の全体像、そして各チャネルの特性をふまえたうえでのチャネル変革でなければ、新規顧客獲得 / リテンション(既存顧客維持)といった望む成果の大きな向上にはつながらない。
例えば、新型コロナウイルスの感染対策の必要性に迫られ、急遽展示会というチャネルだけをパッチワーク的にウェビナーというチャネルに変えたとしても、望む成果は得られない。展示会には展示会の良さがあり、ウェビナーにはウェビナーの良さがある。仮にA社の製品のコアバリューが「実際に手に取ってはじめてわかる、圧倒的な使い心地の良さ」であり、カスタマージャーニーの中において、A社製品にある程度関心を持った顧客の購買意欲醸成に、展示会が重要な役割を果たしていたのであれば、そのチャネルをウェビナーに変えてしまうのは、良い打ち手とは言えない。
ウェビナーは、低コストで、世界中の、多数の人向けに、プレゼンテーションや動画を通じて情報提供・関心醸成を図ることのできる優れたデジタルチャネルの一つだが、言うまでもなく視覚・聴覚以外の感覚に訴えるのには不適である。そういった「デジタルが有効な部分」と「リアルが有効な部分」の見極めを、自社のコアバリューやカスタマージャーニーをふまえたうえで行うことが、肝要である。
②デジタルチャネルにおける情報不足/情報過剰
デジタル技術の進展により、顧客にとって、欲しい情報をオンラインでスピーディーに得ることができるのはもはや”当たり前”となっている。BtoBビジネスであっても結局、情報提供相手は一人ひとりの個人であるので、情報が足りなかったり、逆に情報が多すぎたりして肝心の得たい情報が見つけにくいような状況であれば、大きなフラストレーションを与えることとなる。
製造業特にBtoBの企業は、膨大な数の商品に関する膨大な情報(スペック情報など)を顧客に提供しなければならないことも多く、そのような情報を一つのwebサイトに集約して、わかりやすく提供することは実は難しい。また、技術情報流出に対する警戒感が強すぎる結果、顧客が求める情報を提供できない貧弱なコンテンツとなっていることもままある。
製造業においては本業の技術力がKFS(重要成功要因)であることが多く、技術力が圧倒的に高いためにそうしたデジタルチャネルのクオリティ不足が課題として顕在化していないケースも見られるが、あらゆる業界の垣根が崩れ、目まぐるしくプレイヤーが入れ替わるデジタル時代において、現状の優位にあぐらをかいてデジタルチャネルの改善を怠る企業は淘汰されるリスクを抱えている。
情報の1サイト集約・フォーマット統一、ホワイトペーパーの整備、商品検索機能の充実化などはもちろんのこと、さらに、例えば在庫情報・リードタイムのリアルタイムオンライン確認、リピートオーダーの効率化、履歴データを活用した能動的な提案などのデジタルによる付加価値向上がなければ、既存顧客の維持もままならない時代となってきている。
③不十分なデータ活用
デジタル時代における勝敗を左右するのがデータ活用である。なぜならデータを分析し、その結果をふまえたアクションを取ることで、より確実に顧客のニーズにミートすることができるからである。チャネルのデジタル化により多くのデータを取得できるようになったにも関わらず、顧客体験の向上や営業精度の向上に資するようなデータを上手く取得できていないケースや、取得できていても分析・活用できていないケースが多い。
製造業企業に求められる
マーケティングチャネルのデジタル変革
前章で説明した課題をふまえ、製造業企業に求められるマーケティングチャネルのデジタル変革として以下三点を提言したい。
①最新デジタルテクノロジー動向もふまえた
カスタマージャーニーの再設計
自社のコアバリューをあらためて定義したうえで、新規顧客獲得 / リテンション(既存顧客維持)それぞれにおけるカスタマージャーニーを棚卸しする。そして、カスタマージャーニーにおける各プロセスにおいて、最適なチャネルは何なのか、最新のデジタルテクノロジー動向もふまえたうえで各種リアルチャネル/デジタルチャネルから見極める。
②顧客が得たい情報に最速で到達できるような
情報提供の実現
顧客(新規顧客/既存顧客それぞれ)が真に得たい情報を見極める。そのうえで、その情報を過不足なく集約して、わかりやすいフォーマットで提供する。また検索機能の充実化などにより、得たい情報を素早く見つけるための導線を整える。情報流出の懸念があるのであれば、既存顧客向けの会員制サイトをリリースし、規約などのリーガル面も整備したうえで、情報提供する。
③データ活用による
付加価値創出/営業リソース集中
在庫情報のリアルタイムオンライン確認や、リピートオーダーの効率化、履歴データを活用した能動的な提案など、データ活用により顧客にとっての付加価値を創出する。
例えば、顧客のホワイトペーパーダウンロード履歴/問い合わせ履歴/購買履歴などのデータを活用して、顧客のニーズを類推し、能動的な提案営業につなげる、などがありうる。あるいは、在庫情報などに関して、自社のシステムと取引先のシステムをAPI連携してしまうことも有効である。取引先の業務プロセスに入り込み、”なくてはならない存在”になることで、取引先にとってスイッチングコストが上昇しリテンションにつながる。
一方、顧客のホワイトペーパーダウンロード履歴/問い合わせ履歴などによって顧客の”ホットさ”(確度)を分類し、確度の高い顧客に営業リソースを集中することも有効である。デジタル時代にあっても対面営業の強さはもちろん顕在であり、とりわけ一顧客あたりの売上が大きいBtoBの製造業企業にとって営業リソースの効果的な活用は重要である。
まとめ
新型コロナウイルスの影響が一旦は最悪期を脱しつつあると思われる中、今まさに製造業企業にとっても、ウィズ/アフターコロナを見据えて、改めて自社のコアバリュー、それを顧客に伝えて顧客を獲得/維持するためのプロセス、各プロセスにおける最適チャネルを再考すべきタイミングではないだろうか。
その際、既存顧客のリテンションが重要である製造業企業は、まず既存顧客の得たい情報のわかりやすい提供を押さえることが肝要である。そのうえで、データ活用によって、付加価値を創出して既存顧客のロイヤルティやスイッチングコストを上昇させることや、確度の高い新規顧客をあぶり出して営業リソースを集中投下することが、製造業企業にとって一つの勝ち筋となってくる。

■執筆者プロフィール
山下 知輝(やました ともき)
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 シニアコンサルタント
都市銀行を経てデロイト参画。多くの業種のプロジェクトに従事。その後スタートアップの経営企画室室長を経て再び当社参画。マーケティング戦略策定やデジタル新規事業構想、WEBトランスフォーメーションに強みを持つ。Scrum Inc.認定スクラムマスター(LSM)。