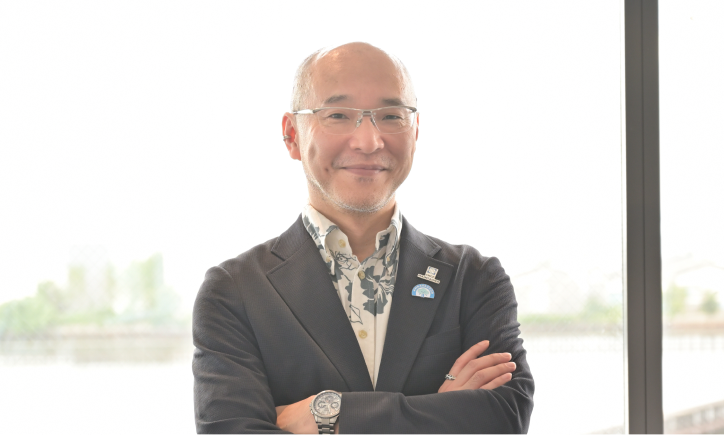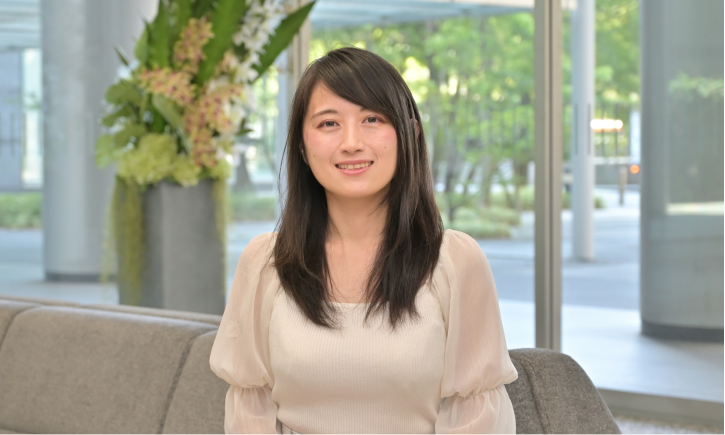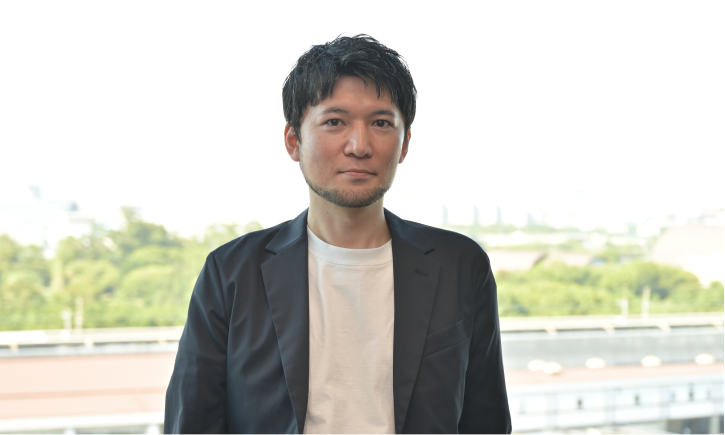サイト内の現在位置


オープンソース活動
・Innovation Story 02
#エンジニアリング #オープンソース活動
オープンイノベーションを加速させるオープンソース活動
#エンジニアリング #オープンソース活動
「オープンソース」という言葉は、もはやソフトウェア開発の世界だけのものではありません。IT業界のみならず、あらゆる産業において、イノベーションの基盤として欠かせない存在となっています。しかし、多くの企業はオープンソース活動によって作られているOSSを「ただ使うもの」として捉え、その真価を十分に引き出せていないのが現状ではないでしょうか。オープンソース活動は単なる無料のツールを作る場ではなく、世界中の開発者とコラボレーションし、新しい価値を共創する「オープンイノベーション」を実践するための場です。
本稿では、オープンソース活動を単なる技術貢献に留めず、全社的な文化として浸透させることで、技術力向上、ブランド力向上、そして社会貢献を目指す先進的な取り組みをご紹介します。この記事を通じて、オープンソース活動に興味を持つ専門家や既に取り組んでいる他社の皆様が、自社のオープンソース活動をさらに深化させ、社会に対する責任と価値を再認識するきっかけとなることを願っています。 技術戦略グループの武藤と共に現在のオープンソース活動の今をご紹介いたします。
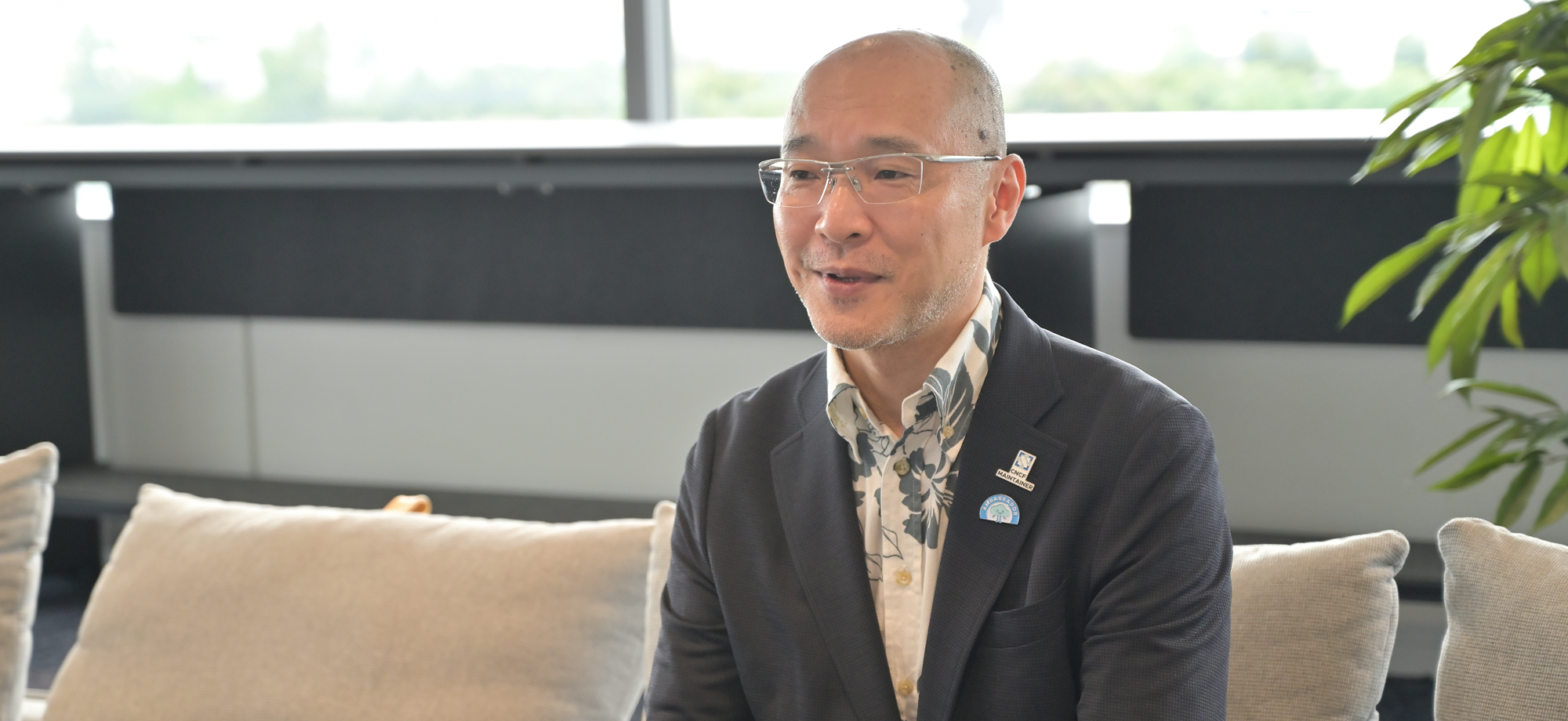
イノベーションラボラトリ 技術戦略グループ
武藤 周(むとう しゅう)
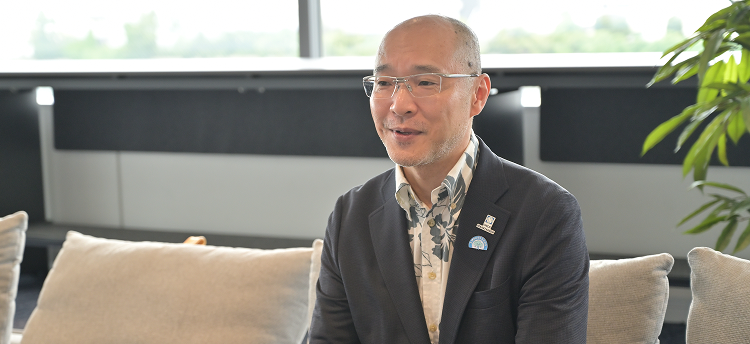
イノベーションラボラトリ 技術戦略グループ
武藤 周(むとう しゅう)
オープンソース活動とは?
オープンソース活動とは、単にオープンソースのソフトウェアを利用することに留まらず、その開発コミュニティに積極的に参加し、貢献する一連の活動を指します。具体的には、コードのコントリビューション(貢献)、カンファレンスでの発表、コミュニティ運営への参画、ミートアップの開催、そしてコントリビューションを支援するトレーニングの開催など、多岐にわたります。
この活動の根底にあるのは、OSSを「デジタル公共財」と捉える考え方です。現代のソフトウェア製品のほとんどにはOSSが組み込まれており、その含有量は7割を超えるとも言われています。私たちは、日々当たり前のようにOSSの恩恵を受けているのです。この状況において、ソフトウェア企業として、OSSをただ利用するだけでなく、その発展に貢献することは、IT業界や社会に対する最も王道な社会貢献であると言えます。
また、オープンソース活動は、企業にとって単なる社会貢献に留まらない、多大な価値をもたらします。OSSコミュニティに日常的に参加することで、最新の技術や市場の動向をいち早くキャッチアップでき、自社の技術力や事業の将来性を高めることができます。さらに、オープンな場で活動実績を積み重ねることは、企業のブランド力向上や採用力の向上にも直結します。つまり、オープンソース活動は、企業の成長戦略そのものに深く関わる、戦略的な取り組みなのです。
コミュニティと共に歩む、日本から世界への挑戦
NECソリューションイノベータが推進するオープンソース活動は、「オープンイノベーション」の実践と、その文化を全社に浸透させることを最大の特徴としています。これは、単に一部の技術者が貢献するだけでなく、オープンソース活動が持つ様々な価値(技術動向のキャッチアップ、ブランド力向上など)を全社的に獲得し、持続的な活動としていくことを目指しています。
この活動の独自性は、以下の点に集約されます。
- 個人的な活動を起点としたコミュニティ醸成
このオープンソース活動は、特定の社員が個人的に  Kubernetesコミュニティでメンテナーや
Kubernetesコミュニティでメンテナーや Special Interest Group(SIG)のChairを務め、コントリビューション入門講座
Special Interest Group(SIG)のChairを務め、コントリビューション入門講座 Kubernetes Upstream Training Japan(KUTJ)の活動を開始したことが起点となりました。こうした個人的な活躍が、社内外に大きな影響を与え、やがて組織的な活動へと発展していきました。
Kubernetes Upstream Training Japan(KUTJ)の活動を開始したことが起点となりました。こうした個人的な活躍が、社内外に大きな影響を与え、やがて組織的な活動へと発展していきました。
- ベンダーニュートラルなコミュニティとの連携
この活動は、 Cloud Native Community Japan(CNCJ)のようなベンダーニュートラルなコミュニティとの連携を重視しています。これにより特定の企業の利害を超えた、真のオープンイノベーションを実現し、日本全体のクラウドネイティブ技術の発展に貢献しています。
Cloud Native Community Japan(CNCJ)のようなベンダーニュートラルなコミュニティとの連携を重視しています。これにより特定の企業の利害を超えた、真のオープンイノベーションを実現し、日本全体のクラウドネイティブ技術の発展に貢献しています。
- 技術貢献と文化醸成の両輪
オープンソース活動は、単にコードを書くことだけではありません。ミートアップの開催や、オープンソース活動のガバナンスを学ぶコミュニティ(  TODO Group、
TODO Group、  OpenChain Japan WGなど)への参加を通じて、OSSを取り巻く文化やエコシステム全体への理解を深め、社内にその文化を浸透させることを目指しています。
OpenChain Japan WGなど)への参加を通じて、OSSを取り巻く文化やエコシステム全体への理解を深め、社内にその文化を浸透させることを目指しています。
これらの活動は、オープンソースが持つ力を最大限に引き出し、企業としての競争力を高めると同時に、日本のIT業界全体を活性化させるための重要な役割を担っています。


オープンソース活動の壁を乗り越える
オープンソース活動は、多くの企業にとって計り知れない価値をもたらす一方で、いくつかの課題も存在します。これらの課題を乗り越え、オープンソース活動活動をさらに広めていくことが、今後の社会的な責任であると言えるでしょう。
- 「英語の壁」とコミュニケーションの難しさ
日本国内の多くの企業や開発者が、オープンソース活動の本家である海外コミュニティとのコミュニケーションに二の足を踏んでいるのが現状です。しかし、重要なのは「伝わればいい」というスタンスです。完璧な英語を話す必要はなく、翻訳ツールや開発言語そのものをコミュニケーションの手段と捉えることで、この壁は乗り越えられます。
- 「なぜオープンソース活動に投資するのか」という経営層の理解
オープンソース活動は、そのメリットが直接的かつ数値的な利益として算出されにくいという性質を持っています。 欧州委員会のレポートでは、「オープンソース活動の貢献が10%増加すると、GDPが0.4〜0.6%上昇する」といったマクロな試算はありますが、個々の企業レベルでROI(投資対効果)を算出することのは困難です。しかし、オープンソース活動が技術力向上、ブランド力向上、そして優秀な人材の獲得に不可欠な「文化」であることを、経営層に理解してもらうことが、活動を継続していく上で不可欠です。
欧州委員会のレポートでは、「オープンソース活動の貢献が10%増加すると、GDPが0.4〜0.6%上昇する」といったマクロな試算はありますが、個々の企業レベルでROI(投資対効果)を算出することのは困難です。しかし、オープンソース活動が技術力向上、ブランド力向上、そして優秀な人材の獲得に不可欠な「文化」であることを、経営層に理解してもらうことが、活動を継続していく上で不可欠です。
- 「秘匿すべきところ」と「公開すべきところ」の線引き
多くの企業が抱える課題として、自社のビジネスロジックや知財をどこまでOSSとして公開すべきか、という線引きの難しさがあります。しかし、OSSを活用することで得られる効率性や、グローバルな技術トレンドへの追随といったメリットを考慮すれば、APIやインターフェースといった標準化すべき部分は積極的に公開し、独自性の高いビジネスロジックは秘匿するという切り分けが重要になります。
デジタル公共財としての役割
オープンソース活動の最大の魅力は、単なるビジネスや技術の枠を超えた、「未来へのロマン」と「社会貢献」にあります。オープンソース活動は、千年後の未来にも残り続ける可能性を秘めた、壮大なプロジェクトです。GitHubにあるソースコードが、北極圏のアーカイブに保存されるといった話は、まさにオープンソース活動が持つ社会的インパクトの大きさを物語っています。この活動に参加することは、遠い未来の誰かのために、デジタル公共財を育むというロマンに満ちた営みです。
また、オープンソース活動は、ソフトウェア企業にとって最も王道の社会貢献です。OSSはもはやデジタルインフラであり、世界中の人々が利用するサービスの基盤となっています。この基盤をより強固にし、より良いものにしていくことは、持続可能な社会を築くための重要な貢献です。OSSのガバナンスやコンプライアンスに関する活動も、この社会貢献の一環として非常に重要であり、企業の責任として取り組むべきテーマとなっています。
展望 ー日本から生まれるグローバルスタンダードー
NECソリューションイノベータが今後目指すのは、オープンソース活動をさらに発展させ、日本からグローバルスタンダードを生み出すことです。
現在のオープンソース活動は、IT業界における人材不足や、OSSに対する責任(サイバーセキュリティなど)の顕在化といった課題に直面しています。これに対し、オープンソース人材の定義や認定資格、そして教材といった、日本における人材育成のスタンダードを、コミュニティと共に作り上げていくことを目指しています。IPAが公開しているITスキル標準レベルでの人材定義や、認定に役立つ資格の創設は、この目標を達成するための重要な一歩となるでしょう。
最終的には、この取り組みを通じて、「問い」を立て、共に考え、小さく試してみるという営みが、誰にとっても身近な文化になることを目指しています。それは、社員一人ひとりが、自らの問いを起点に動き出し、オープンソースという開かれた場で、世界とつながり、新しい価値を創造していく未来です。NECソリューションイノベータのオープンソース活動は、技術や文化の革新をリードし、日本全体が再び世界をリードする国へと成長するための、重要な原動力となるでしょう。
イノベーションラボラトリ 技術戦略グループ
武藤 周(むとう しゅう)
Web アプリケーションエンジニアとして従事する傍ら、社外コミュニティにおいては、 Kubernetes Dashboard Maintainer、
Kubernetes Dashboard Maintainer、 Kubernetes SIG UI Chair、
Kubernetes SIG UI Chair、 Kubernetes Upstream Training Japan Organizer、CNCF Ambassador、
Kubernetes Upstream Training Japan Organizer、CNCF Ambassador、 Cloud Native Community Japan Organizerとして活動してきました。現在は、OSS戦略のミッションも拝命し、企業におけるオープンソース活動のあり方について、自ら実践(
Cloud Native Community Japan Organizerとして活動してきました。現在は、OSS戦略のミッションも拝命し、企業におけるオープンソース活動のあり方について、自ら実践( コミュニティ間連携イベント開催や
コミュニティ間連携イベント開催や TODO Group の OSPO Bookの翻訳、
TODO Group の OSPO Bookの翻訳、 OSPO AllianceのOpen Source Good Governance ハンドブックの翻訳など)しながら社内に浸透させるために尽力しています。
OSPO AllianceのOpen Source Good Governance ハンドブックの翻訳など)しながら社内に浸透させるために尽力しています。