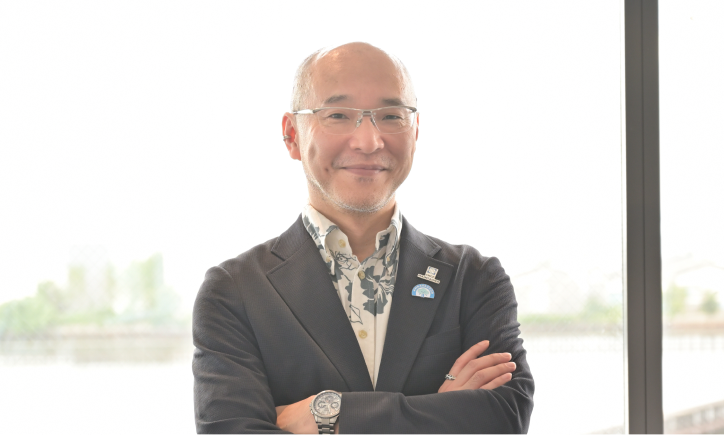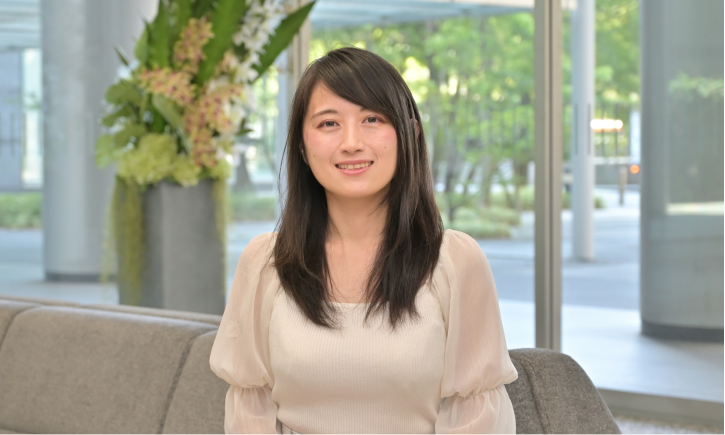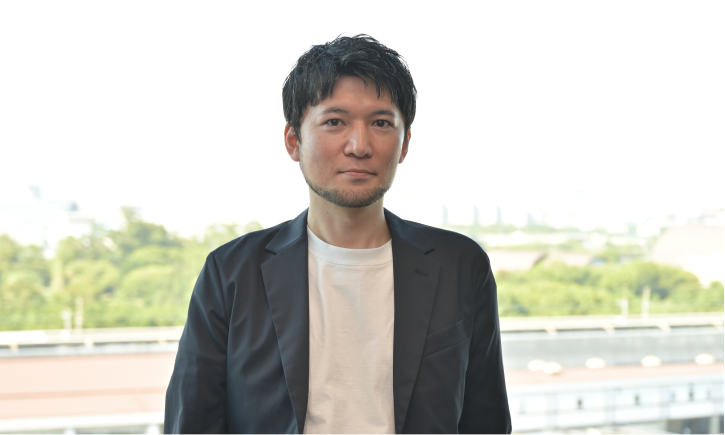サイト内の現在位置


次世代インターフェース
・Innovation Story 05
#研究開発 #次世代インターフェース
思考を現実にするインターフェース:人とデジタルの新しい関係を創る
#研究開発 #次世代インターフェース
「人とデジタルのやりとりは、もっと自然でスムーズになるはずだ。」
スマートフォンやPCが私たちの生活に不可欠な存在となった今、私たちは常に画面を見つめ、キーボードやタッチパネルを操作しています。しかし、このインターフェースは本当に人とデジタルが対話する上で最適な形なのでしょうか。デジタルツインやAIが当たり前になる未来、情報に溢れた世界で私たちはどのようにして必要な情報と出会い、思考を表現すればよいのでしょうか。
本稿では、この問いに真摯に向き合い、「次世代インターフェース」の技術研究に取り組む試みをご紹介します。この研究は、単に新しいデバイスやUI(ユーザーインターフェース)を開発するだけでなく、人とデジタルがシームレスに繋がり、相互に理解し合うための新しい関係性を創造することを目指しています。まだ明確な答えが見つかっていない「リサーチクエスチョン(RQ)」の探索から、各種調査、そして未来の社会への展望まで、この研究が描く壮大なビジョンを本研究を通じて推進するテクノロジーラボラトリグループ渡辺と多角的に掘り下げます。

イノベーションラボラトリ テクノロジーラボラトリグループ
渡辺 泳樹(わたなべ えいき)
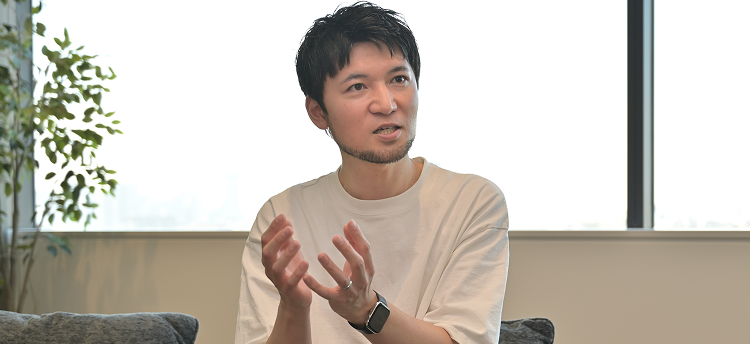
イノベーションラボラトリ テクノロジーラボラトリグループ
渡辺 泳樹(わたなべ えいき)
技術研究活動の紹介|次世代インターフェースの研究とは?
「次世代インターフェース」とは、人とデジタル、そしてその間に存在するすべての情報を、より自然で直感的なやりとりで結びつけるための技術全般を指します。現在、研究テーマを探索している段階ですが、その大枠は、以下の4つの未来像から構成されています。
- 必要な情報が自動的に届くインターフェース
AIやデジタルツインが進化し、情報が氾濫する社会では、自分では気づかない有益な情報が数多く生まれます。次世代インターフェースは、ユーザーが能動的に情報を取得しにいかなくても、システム側が状況に応じて必要な情報を自動的に、かつ自然な形で伝えてくれるようになることを目指します。
- 思考を汲み取るインターフェース
質問の全文をインプットしなくても、ユーザーが見ているもの、聞いているもの、感じているものといった周囲の状況をAIが自動的に理解し、「これどうなってる?」といった自然な問いかけにも正確に回答してくれるようになることを目指します。
- 状況に応じた最適なインターフェース
PCやスマホのように、何かをしようと思ってデジタルにアクセスするのではなく、日常生活の中に自然にデジタルが溶け込み、ユーザーの状況やニーズに応じて最適なUI/UXを提供してくれるようになることを目指します。
- 五感全体を活用するインターフェース
現在の視覚と聴覚に偏ったインターフェースに加え、触覚、嗅覚、味覚といった五感を活用することで、人とデジタルのやりとりの幅を広げ、より豊かな体験を創出します。
この研究活動は、単に一つの技術を開発するのではなく、これらの未来像を実現するために必要な技術を探索し、獲得していくことを目的としています。
研究の原点と動機|一人の研究者が見た、未来の「驚き」
この研究の原点には、一人の研究者がMicrosoftのHoloLens(1st gen)を体験したときの、鮮烈な「驚き」があります。当時、AR(拡張現実)やMR(複合現実)技術はまだ黎明期にありましたが、HoloLensは現実の空間を認識し、その上にデジタルの情報を重ねて表示することができました。それは単に目の前に画面があるだけではなく、リアルのテーブルの上にデジタルの物体を置くといった、まるでSF映画のような体験でした。
この体験が、研究者を「人とデジタルのやりとり」というテーマに強く引きつけました。それまで携帯電話の開発を通じて「自分で作ったものを誰かに自慢したい」というモチベーションでモノづくりを続けてきた研究者は、HoloLensが示す未来に、技術が人々の生活を根本から変える可能性を見出したのです。
この動機は、研究を個人的な興味から社会的な意義へと広げる原動力となりました。その後、ARやMR技術を活用したシステム開発に携わり、スポーツ観戦や工場での作業支援といった分野で実証実験を重ねていきました。例えば、競泳の観戦では、選手のリアルタイムのデータや記録を目の前に表示することで、観戦体験をより豊かにすることに成功しました。これは、単に技術が使えるかどうかだけでなく、それが人々にどのような新しい体験をもたらすのかを深く考察するきっかけとなりました。この「未来へのワクワク感」と「社会への貢献」という二つの動機が、次世代インターフェース研究を推進するエネルギーとなっています。
研究の今|未来の問いを探求する「建設的な議論」のプロセス
現在、この次世代インターフェース研究は、まだ明確な技術テーマを決定する前の「リサーチクエスチョン(RQ)」探索の段階にあります。この段階では、具体的な技術を開発するのではなく、「どのような課題を次世代インターフェースで解決すべきか」という問いそのものを見つけることに注力しています。
その探求プロセスは、以下のようなユニークな手法で進められています。
- 「建設的な議論」を歓迎する文化
このチームには、最初から「これだ」という正解はありません。メンバーは日々、様々な事業や社会課題をテーマに、次世代インターフェースで解決できる可能性を模索しています。その仮説に対し、互いに厳しくも建設的な意見を投げかけ、安易な結論に飛びつくことなく、より深いリサーチクエスチョンを見つけ出すための議論を徹底的に行います。この「建設的な議論」を歓迎する文化が、安易な結論に飛びつくことなく、より深いリサーチクエスチョンを見つけ出すための重要なプロセスとなっています。
- 多様なバックグラウンドを持つメンバーによる協創
このチームには、元々、システムインテグレーター(SIer)としてお客様から提示された課題を解決してきた経験を持つメンバーが集まっています。彼らは、顧客の課題を深く理解し、それを解決するためのシステムを構築することに長けています。しかし、RQを自ら設定するという経験はまだ浅く、その点で互いに補完し合う関係を築いています。彼らの探索しながらも前進させるという姿勢が、議論に多様性をもたらし、思いもよらないアイデアや問いを生み出す原動力となっています。
- 「課題から探る」アプローチ
この研究は、まず「この技術で何ができるか」から始めるだけではなく、社会に「どのような課題があるか」からもアプローチをします。社内の部門や、代理存在AIを研究するチームなど、様々な事業領域が抱える課題をヒアリングし、その中で次世代インターフェースが解決できる可能性のある問いを探しています。例えば、AIとのより自然な対話といった具体的な課題から、次世代インターフェースに必要な技術要素を逆算して導き出しています。このアプローチにより、技術を先行させるのではなく、社会的なニーズに基づいた、本当に価値ある研究テーマを見つけることを目指しています。


研究の楽しさ|「分からない」を「面白い!」に変える探求の旅
この研究活動は、まだ明確なRQが定まっていないという特性上、多くの困難を伴う一方で、それを乗り越える大きな楽しさがあります。この「分からない」を「面白い!」に変える探求の旅こそ、この研究の最大の魅力と言えるでしょう。
- 「未来を自分たちで創り出す」喜び
誰もが漠然と「できたらいいな」と思っている未来の姿を、自らの手で描き、それを実現するための道を模索するプロセスは、何物にも代えがたいやりがいをもたらします。メンバーは、AIが予測した未来のシナリオを、人間的な感性や経験を加えて議論し、より血の通った、リアルな未来像へと昇華させています。
- 「小さな成功体験」の積み重ね
このチームは、明確なゴールがない中でも、小さな成功体験を積み重ねることで、モチベーションを維持しています。例えば、メンバーの一人が「このテーマは面白そうだ」と提案したものが、議論を重ねるうちに「これは新たな技術研究のテーマになるかもしれない」というレベルにまで高まる瞬間は、大きな喜びとなります。この「小さな成功」の積み重ねが、次世代インターフェースという壮大なテーマに、少しずつ、しかし着実に近づいていくための原動力となっているのです。
今後の展望|社会全体を巻き込む「共創」の場へ
この次世代インターフェース研究は、今後、社会全体を巻き込む研究活動と進化していくことを目指しています。
また、「人材育成」としての役割も担っていくことを目指しています。現在、このチームは若手メンバーの育成にも注力しており、「リサーチクエスチョンを設定する力」「議論を通じて洞察を生み出す力」といった、次世代の研究者に不可欠なスキルを、実践を通じて育んでいます。今後は、このノウハウを蓄積し、今後の技術研究の担い手の支援をしていきたいと考えています。
この研究を通じて、「未来の当たり前を創る」という壮大な展望に大して、まだ誰も答えを知らない「問い」を探す旅の楽しさと真摯な葛藤が感じられます。この哲学が新たな価値を社会に届ける姿を楽しみにしています。
イノベーションラボラトリ テクノロジーラボラトリグループ
渡辺 泳樹(わたなべ えいき)
2009年入社。ガラケー向けミドルウェア開発を皮切りに、Androidアプリ開発や中央研究所での画像認識技術の研究支援など、モバイルとAI領域を横断する経験を積む。近年はAR・MRアプリ開発に注力し、先端技術を活用したユーザー体験の向上に取り組んでいる。技術の進化を捉え、現場での実装を通じて価値を創出することを得意とする。