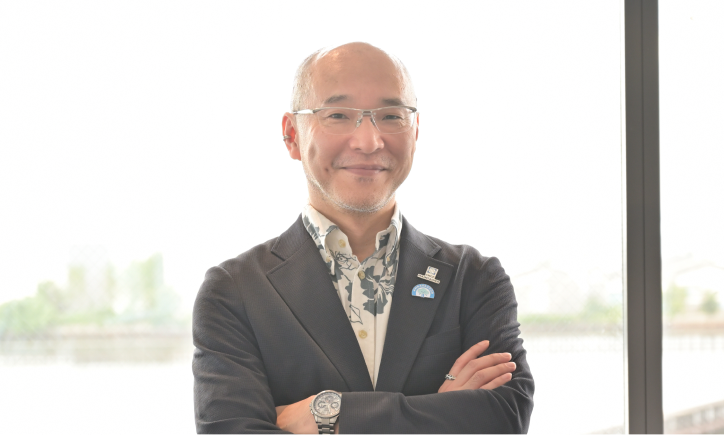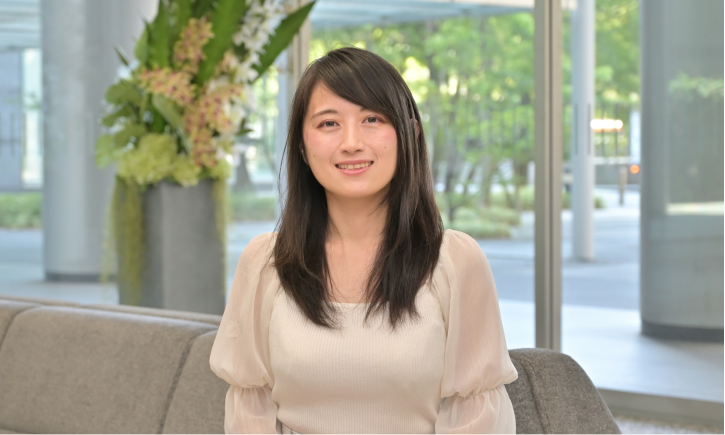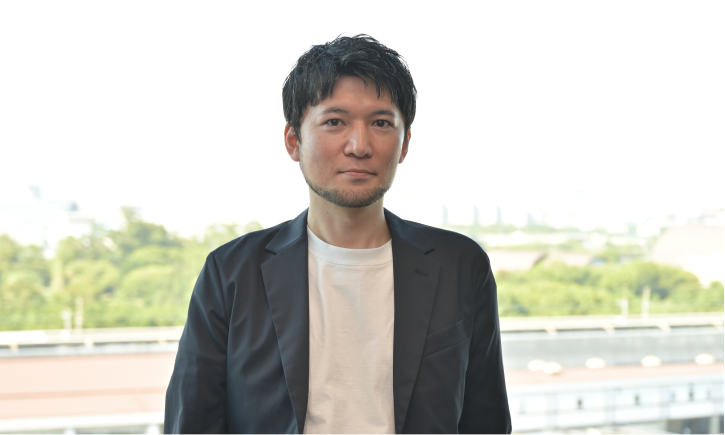サイト内の現在位置


AIメンタリングシステム
・Innovation Story 03
#事業開発 #心豊かに暮らす #AIメンタリングシステム
AIメンタリングシステムが拓く教育の未来
#事業開発 #心豊かに暮らす #AIメンタリングシステム
「探究学習」という言葉が、日本の教育現場でも定着し始めています。生徒が自ら課題を設定し、情報を収集・分析し、自分なりの解決方法を見出すという、この学習方法は、未来を生きる子どもたちに必要な「自ら考える力」を育む上で不可欠とされています。しかし、多くの先生方は、生徒一人ひとりの個性や進度に合わせて指導するリソースの不足や、指導スキルに悩みを抱えています。そして、生徒側もまた、何から手をつけて良いか分からず、単なる調べ学習に終わってしまうという課題に直面しています。
このような教育現場が抱える課題に対し、一つの答えを提示するのが「AIメンタリングシステム」です。これは、単に答えを教えるAIではありません。プロフェッショナルなメンターの問いかけをAIで再現することで、課題に対する深い思考を巡らせると同時に生徒自身の内省的思考を促し、好奇心や探究心に火をつけることを目指しています。
本稿では、この革新的な「AIメンタリングシステム」の核心をビジネスラボラトリ第一グループの阿部と共に迫ります。そのユニークな技術的アプローチから、教育現場での実証検証で得られた具体的な成果、そしてこの事業が目指す教育の未来像まで、多角的にご紹介します。この新たな教育ソリューションの可能性を深く理解し、未来の教育を共に創造するためのインスピレーションを得ていただけることを願っています。

イノベーションラボラトリ ビジネスラボラトリ第一グループ
阿部 由莉(あべ ゆうり)

イノベーションラボラトリ ビジネスラボラトリ第一グループ
阿部 由莉(あべ ゆうり)
AIメンタリングシステムとは? ー探究学習を支援するAIー
「AIメンタリングシステム」とは、学校の探究学習の授業を支援するために開発されたシステムであり、大きく分けて2つの主要機能を持っています。一つは、生徒の内省的思考を促す「メンタリング機能」、もう一つは、生徒の成長を可視化する「成長点分析機能」です。このシステムの最も革新的な点は、提示された質問に対して「答えを提示しない」AIであることです。一般的なAIが効率や正解を重視するのに対し、このシステムは、プロのメンタリング指導者が投げかけるような、本質的な問いを生徒に投げかけます。これにより、生徒は与えられた情報を鵜呑みにするのではなく、自らの力で課題に対する深い思考を巡らせ、本質的な問いを見つける力を養うことができます。
このシステムが解決しようとしている課題は、探究学習における教員の「生徒一人ひとりに寄り添うリソースの不足」です。探究学習は、生徒の自主性を重んじるがゆえに、画一的な指導が難しく、教員一人ひとりのスキルに依存する側面が強いです。また、生徒一人ひとりのテーマや進度に合わせて個別に指導することは、教員の多忙な業務の中では現実的に不可能な場合が多いです。このAIメンタリングシステムは、これらの課題を解消することで、単なる調べ学習に留まらない、「自ら課題を見つけ、解決に向けて行動できる」という未来の人材を育成する質の高い教育の実現を目指しています。
このAIとの対話を通じて、生徒は深い思考を促されるだけでなく、自己理解を深め、自分の思考や感情を言語化する習慣を身につけることができます。これにより、生徒は自分の興味関心や将来の展望をより明確に捉えられるようになり、探究学習を単なる授業科目としてではなく、将来の自分につながる活動として向き合うことができるようになります。
AIメンタリングシステムのコア技術
「AIメンタリングシステム」の核となるのは、「代理存在AI技術」です。これは、特定の人物が持っている知識・ノウハウを基に、その人らしい行動をAIで再現する独自技術であり、このメンタリングAIでは、課題解決のメンタリング指導を行うプロフェッショナルの問いかけをAIに学習させています。これにより、AIは単なる対話エンジンではなく、まるで本物のメンターがそこにいるかのような、質の高い問いかけを生徒に投げかけることができるのです。
この技術は、一般的な生成AIとは一線を画します。多くの生成AIは、与えられた情報に基づいて最適な「答え」を生成することを目的としていますが、このメンタリングAIは、「答えを提示しない」という逆転の発想に基づいています。これは、生徒の思考をショートカットさせることなく、自力で答えを導き出すプロセスを大切にするという教育哲学に基づいています。このアプローチは、生徒がステレオタイプな考え方に染まったり、AIが提示する正解に依存したりすることを防ぎ、生徒自身の内発的な思考力を養う上で不可欠です。
既存の探究学習支援サービスと比較しても、このAIメンタリングシステムの独自性は際立っています。現在の主流サービスは、進捗管理をベースに、教材の配信やeラーニングの提供といった包括的な学習支援に重点を置いています。一方、生成AIを活用した生徒の学習支援はまだ進んでいないのが現状です。それらはあくまで「学習の効率化」に主眼が置かれている場合が多いです。
このメンタリングAIが目指すのは、「いかにして生徒の好奇心・探究心に火をつけていくのか」という本質的な問いへの挑戦です。これは、単に授業や探究学習を「楽にする」ことではなく、生徒一人ひとりが「自ら課題を見つけ、解決に向けて行動できる人材」として成長するための、深い学びの体験を創出することを目的としています。この独自の技術と哲学が、探究学習のあり方を根本から変える可能性を秘めています。


実証検証によって得られた示唆
この革新的なメンタリングAIは、机上の理論に留まらず、実際の教育現場での実証検証を着実に進めています。そのプロセスは、2023年にとある1つの高校で、一部の生徒を対象に使っていただくところから始まりました。これは、プロトタイプの有効性を検証するための重要なステップであり、生徒や先生からの率直なフィードバックを収集する場となりました。
この初期の実証検証での手応えを経て、2024年にはその高校で正式に授業へ導入されるに至りました。これは、システムの有効性が一定程度評価された証拠であり、より多くの生徒が日常的にメンタリングAIと対話する中で、その効果を測定する貴重な機会となりました。そして、2025年度現在では、この成功事例を基に、他の高等学校での導入も始まっています。
この一連の実証検証プロセスを通じて、開発チームは多くの課題に直面し、それを乗り越えるための工夫を重ねてきました。例えば、「AIからの問いかけの内容が難しい」「どう回答したら良いか分からない」という声が聞かれることがありましたが、その「難しさ」が、単なるシステムの不具合なのか、それとも深い思考が促された結果なのかを見極めることが重要でした。このようなフィードバックを基に、システムを改善し、生徒の学習体験を最適化するための努力が続けられています。
これまでの実証検証を通じて、メンタリングAIがもたらすポジティブな効果が、定性・定量の両面から明らかになってきました。
定量的な効果として、2024年度の実証後のアンケート結果がその有効性を示しています。生徒回答総数84件のうち、9割以上が「自身が設定した探究テーマへの興味関心が深まった」、「次のアクションへのヒントが得られた」、「探究意欲が向上した」と回答しました。これは、メンタリングAIが、生徒の学習意欲や探究心に火をつけるという、このシステムの最も重要な目標を達成していることを示しています。
定性的な効果としては、先生や生徒から寄せられた生の声が、このシステムの可能性を雄弁に物語っています。ある先生からは、「メンターAIをしっかり使った子は、日常対話も筋が通っていると感じる。主語述語もしっかり使う」という声が聞かれました。これは、メンタリングAIとの対話を通じて、生徒の論理的思考力や言語化能力が自然と養われていることを示唆しています。また、2年間システムを使い続けた(現在大学一年生の)卒業生からは、「答えを教えてくれないAIは、タイムパフォーマンスが悪いと思わない?」という質問に対して、「AIを先に使って答えをもらうと、ステレオタイプに染まる。自分の経験から来ていたはずの考えが消えてしまう。簡単に言えば、AIが正解になってしまう。自分の考えを語れるようになりたい」という、AIとの向き合い方に関する深い洞察が語られました。さらに、大学でのプレゼンテーションで「メンタリングAI、哲学的な問いで学んだ『そもそも』を考える癖がついたことが活きている」という声も聞かれ、このシステムが単なる探究学習の支援ツールではなく、生徒の人生にまで影響を与える学習体験を提供していることが明らかになりました。
これらの検証結果は、メンタリングAIが、生徒の深い思考を促し、内省を促進し、自己理解を深めるという3つの想定効果を確かに実現していることを示しています。このシステムは、教員の指導負担を軽減しながらも、教育の質を向上させるという、両立が困難とされてきた課題への解決策となり得るのです。
未来への展望
「AIメンタリングシステム」の未来は、単なる教育現場への導入に留まりません。今後、この事業が目指すのは、個人の成長を支援するプラットフォームとして、教育分野を超えて展開していくことです。現在の高校での導入から、中学、大学、そして企業の研修プログラムへと、対象ユーザーを広げていく構想を持っています。
この事業が未来の社会において果たす役割は、「自ら課題を見つけ、解決に向けて行動できる未来の人材」を育成することです。この学習体験を通じて育まれた個人の成長が、新たな産業の創出など、社会全体の発展に繋がっていくことを目指しています。
事業化に向けては、いくつかの重要な課題が残されています。その一つが、「答えを提示しない」というAIの特性を、教育関係者や利用者に正しく理解してもらうことです。特に、効率や即時性を重視する現代において、タイムパフォーマンスの悪さを指摘する声に対し、このAIが提供する「自ら考える、考える時間をとる、考える視点を拡げる」という機会とその中で育まれる「自ら考える力」の価値を明確に伝えていく必要があります。
しかし、これらの課題を乗り越え、このシステムが広く普及したとき、私たちは、AIが単なる道具ではなく、人間の能力を引き出し、自律的な成長を促す「伴走者」となる新しい教育の形を目にするでしょう。このメンタリングAIは、AIと人間の新しい共生関係を築くための、重要な一歩となるのです。この分野に興味を持つ教育関係者や研究者の皆様と、この未来を共に創造していけることを期待しています。
イノベーションラボラトリ ビジネスラボラトリ第一グループ
阿部 由莉(あべ ゆうり)
新規事業の企画・開発担当。これまで、介護・教育領域向けの企画プロジェクトに従事。
「すべてのヒトが、自分のやりたいことを諦めずに挑戦できる世界を実現すること」をモットーに、日々未踏の領域に挑戦しています。