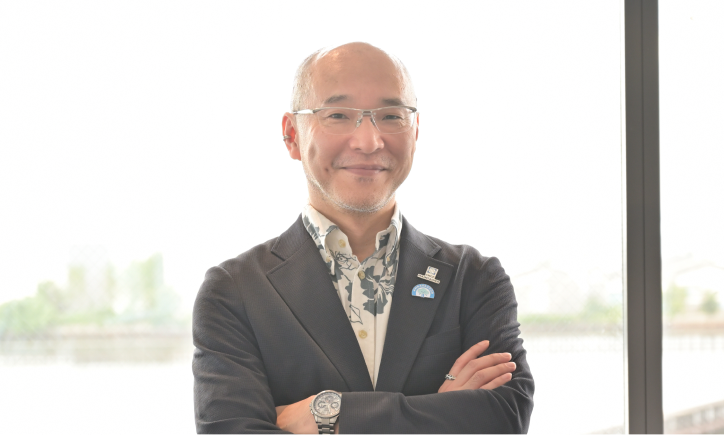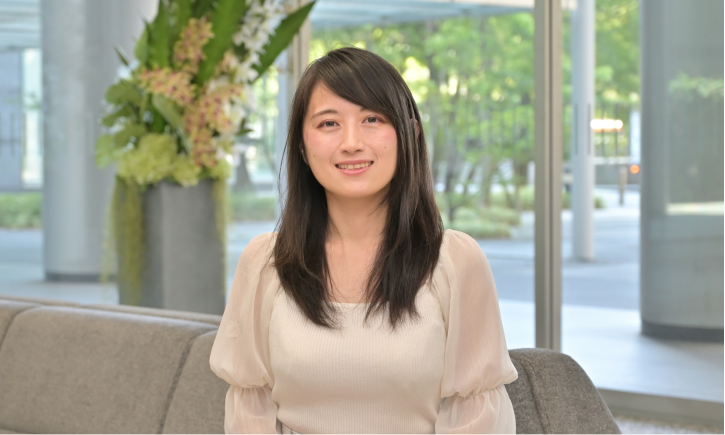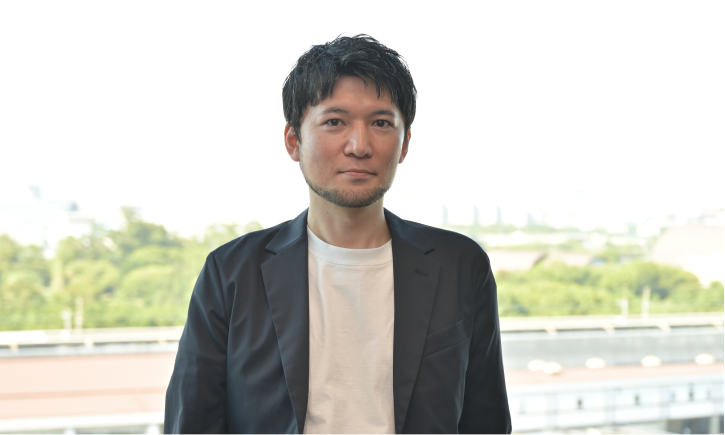サイト内の現在位置


NEC 白浜リビングラボが拓く、新事業創出の未来
・Innovation Story 06
#事業開発 #NEC 白浜リビングラボ
NEC 白浜リビングラボが拓く、新事業創出の未来
#研究開発 #NEC 白浜リビングラボ
新しい技術やサービスを開発したとき、その真価を問うのは、完成された製品を市場に投入した後だけではありません。実際に利用する人々の声に耳を傾け、試行錯誤を繰り返す「仮説検証」のプロセスこそが、事業の成功を左右します。しかし、この仮説検証には多くの課題が伴います。多額のコスト、複雑な調整、そして何よりも、生活者のリアルな声を集めることの難しさです。特に、地域が抱えるユニークな課題や、特定の層のニーズに応えようとする際には、そのハードルはさらに高くなります。
本稿では、この課題に対し、和歌山県白浜町という自治体を舞台に、革新的なアプローチで仮説検証を行う「NEC 白浜リビングラボ」をご紹介します。ここでは、単なる仮説検証に留まらず、地域の課題解決と連携することで、より実践的で価値ある新事業創出を目指しています。NEC 白浜リビングラボは、白浜を拠点とし、その地に築き上げた関係資本を活かして、新事業創出に向けた仮説と検証のサイクルを加速させています。オンライン調査や生成AIによるリサーチがコモディティ化する時代だからこそ、現場での体験から得られる「ゼロ次情報」や、まだ誰もリーチできていない「一次情報」の重要性は増しています。NEC 白浜リビングラボは、そうした貴重な情報を獲得するためのフィールドなのです。
NEC 白浜リビングラボで活動する中尾、佐野とその実態に迫ります。

イノベーションラボラトリ 探索グループ 白浜リビングラボ
中尾 勇介(なかお ゆうすけ)

イノベーションラボラトリ 探索グループ 白浜リビングラボ
佐野 香織(さの かおり)

イノベーションラボラトリ 探索グループ 白浜リビングラボ
中尾 勇介(なかお ゆうすけ)

イノベーションラボラトリ 探索グループ 白浜リビングラボ
佐野 香織(さの かおり)
NEC 白浜リビングラボとは? ―設立の背景と役割―
「NEC 白浜リビングラボ」では、白浜を拠点に、「実験フィールド」をいかした事業開発を進めています。ここでいう「実験フィールド」は、企業のオフィスや研究施設のような閉じた環境ではなく、社会そのものを舞台に、技術やサービスの仮説を検証する場を指します。NEC 白浜リビングラボでは、白浜全体を豊かな自然や、事業者や生活者との近さなどの特性をもつ一つの「実験フィールド」と捉え、住民の日常生活の中に溶け込んだ形で小規模な実験を繰り返し行っています。これにより、単なる机上のシミュレーションでは決して得られない、生活者のリアルな声や行動データを直接的に収集し、新事業創出のための仮説検証を加速させています。
このNEC 白浜リビングラボ設立の背景には、新事業創出における「仮説検証サイクルの高速化」という大きな課題があります。
仮説を立て、それを検証する実験を繰り返すことは新事業において不可欠ですが、このサイクルは往々にして時間とコストがかかります。NEC 白浜リビングラボは、約10年間にわたって築き上げた白浜との関係資本を活かし、フィールドへのアクセスを容易にすることで、このサイクルを劇的に高速化しています。この取り組みは、オンラインリサーチだけでは見出せない、個人の体験や感覚に基づく深い洞察を獲得するための強力な手法です。


NEC 白浜リビングラボのコンセプト
NEC 白浜リビングラボの核となるコンセプトは、「問いを起点にした価値のデザイン」です。この活動は、「まだ形になっていない想いや問いの種」を、丁寧なプロセスで形にしていく文化を組織内に根付かせようとしています。チームが抱える言語化できない違和感やもやもやを、共に探求し、「問い」として明確にすることで、自信を持って前進できるようになります。あるチームからは、「言語化できずに抱えていた違和感やもやもやが、問いとして形になったことで、自信をもって前進できるチームが完成した」という声が寄せられました。これは、NEC 白浜リビングラボが、単なる仮説検証の場ではなく、チームの成長を促し、組織文化を創造する場であることを示しています。
このコンセプトは、当社の新事業に貢献するだけではありません。社会全体に対して、「問いを立て、共に考え、小さく試してみる」という営みが、誰にとっても身近な文化になることを目指しています。NEC 白浜リビングラボでの活動は、地域で暮らす人たちの声なきニーズをすくい上げ、若い世代が自分自身の価値観を起点に動き出せるような協働を生み出す可能性を秘めています。ここで大切なのは、「まだ形になっていない想い」や「問いの種」のようなものに対して、すぐに評価したり、判断したりせずに、丁寧に構造をつくり、一緒に見つめ直していく姿勢です。白浜で積み重ねてきたこのやり方や感覚が、今後さまざまな場所で、動き出すきっかけとして届いていくことを目指しています。


実験フィールドとしての実施内容
NEC 白浜リビングラボは、新事業創出におけるクリエイティビティを組織的に高める仕組みとして機能しています。イノベーションには、ビジネス(B)、テクノロジー(T)、クリエイティビティ(C)の結合が重要とされていますが、多くの日本企業が「クリエイティビティの弱さ」という課題を抱えています。NEC 白浜リビングラボは、地域をいかした仮説検証を通じてユーザー視点での価値のデザインという役割を担うことで、BTCのバランスのとれたチームやプロセスを実現し、連続的に新事業を創出することを目指しています。具体的に行っていることには、以下の四点が挙げられます。
-
仮説の言語化を支援する初期フェーズからの協働
特に新事業を検討しはじめた初期フェーズでは、体系立てて調査した情報だけでなく、探索的なアプローチで幅広く集めた情報や原体験に基づく情報も大事となりますが、その分、仮説の言語化が難しいケースが少なくありません。この課題に対し、NEC 白浜リビングラボは、仮説以前の初期段階からチームに協働し、「仮説の元となる問いのデザイン」から始めることで、チームが自信をもって検証に進めるよう支援しています。あるチームからは、「こんなふうに自分のもやもやが問いになるとは思わなかったし、それを一緒に考えてくれる人がいるのはありがたい」という声が寄せられており、このアプローチの有効性が示されています。 -
小さな実験の実施
そもそも成功確率の低い新事業において、初めから事業アイデアの仮説が正しいことの方が稀であり、その誤りに気付き、軌道修正を繰り返すことが重要です。しかし、顧客のセグメントや課題、その解決策などのたくさんの仮説を一気に確認しようとすると、大がかりな実験になり、時間や労力がかかるだけでなく、たくさんの人に協力いただく必要がでてきます。そこで、誤っていたときに最もインパクトの大きい仮説を抽出して、その仮説に対して小規模の実験を行い、検証を行っています。例えば、顧客課題の仮説を立てた翌日に想定顧客にインタビューして、課題設定の誤りに気付くことも多々あります。 -
研究と市場の接続
競合他社に負けない新事業を創出するうえで、研究者が生み出す優れた技術と、マーケティングで発見した市場機会を結びつけることも重要になります。しかし、多数ある社内の技術と市場機会をマッチングさせることは、どちらも深い理解が必要となり、属人性の高さが課題となります。そこで、このギャップを埋めるために、フィールドを用いて、技術がユーザーにもたらす便利さや、市場にいる顧客の実際の困りごとを具体化し、つなぐことで、技術と市場機会を両立した事業アイデアの発想を支援し、技術の実用化を加速させています。 -
地域との共助となる関係性構築
一般的に都市部の企業が地域を実験フィールドとして活用することには、地域内で賛否両論が起こることがよくあります。そこで、社員が白浜町役場に出向したり、地域人材を採用したりすることで、地域の視点から、企業と地域との持続可能な関係づくりを企画・推進しています。現在は、一般社団法人 白浜イノベーションハブの設立・運営にも関わり、当社だけでなく、都市部企業と地域の新しい関係性をデザインしています。
目指す未来のかたちー地域を超えた場づくりー
NEC 白浜リビングラボの活動は、多くの可能性を示唆しています。
仮説検証で得られた最も重要な示唆は、「小さな実験の重要性」です。「小さな実験ってこういうことだよね」というコメントがあり、この活動が、一気に唯一の正解を求めるのではなく、手触り感をもって小さなサイクルを回すことの価値を、組織に浸透させていることがわかります。この「小さな実験」を重ねることで、イノベーションに必要な「問いの質と接続」が深まり、最終的に大きな事業の成功へと繋がるのです。
また、NEC 白浜リビングラボの未来への展望は、「日本全体でイノベーションが起こるモデルケースとなること」です。都市部の企業と地域が協力しあいながら新事業を成功させるモデルを確立し、ひいては、日本の都市部も地域も経済的に潤っていくことを目指しています。これは、都市部の企業が地域を単なる「調査対象」として見るのではなく、地域の声や知見を「イノベーションの種」として尊重し、パートナーとして共に成長していくべきだという強いメッセージでもあります。 NEC 白浜リビングラボは、単なる企業活動としての仮説検証の場ではなく、地域の未来を創るための場でもあるのです。企業や研究者は、ここで得られた知見を活かし、他の地域へと応用することで、社会全体の課題解決に貢献できる可能性を秘めているのです。
新事業創出の拠点へ
NEC 白浜リビングラボは、今後、さらに活動の幅を広げ、多くの企業や研究者との連携を深めていき、「リビングラボ」という概念を社会に定着させ、地域創生の新しいモデルを確立することを目指しています。
事業実用化への展望としては、NEC 白浜リビングラボで生まれた技術やサービスが、全国の他の自治体へと展開されていくことです。そのために、白浜という特定の地域で表層化する問題に対して、地域の中から原因を分析し、他地域も含めた日本社会全体の課題を抽出し、課題解決のための技術やサービスを試すことを繰り返していきます。
また、これから描く未来は、NEC 白浜リビングラボにおいて「問いを起点にした価値のデザイン」が、誰にとっても身近な営みになるような文化を育てていくことです。ここでは、制度や組織の枠にとらわれずに、小さく試して学ぶことを大切にしています。そのプロセスに地域の方々や事業の関係者が一緒に関わり、自分たちの感覚や想いを起点に問いを立て、形にしていく。そうした日々の積み重ねは、仮説検証の仕組みを整えるだけでなく、「誰かの問いが、他の誰かの行動のきっかけを与える」ような連鎖を社会の中に静かに生み出していると感じられます。
NEC 白浜リビングラボは、新しい事業の種を見つけ、育て、そして社会に実装するための、理想的な拠点となり得ます。白浜の豊かな自然と温かい地域住民、そして新しい技術が交差するこの場所で、未来を創っていきます。
イノベーションラボラトリ 探索グループ 白浜リビングラボ
中尾 勇介(なかお ゆうすけ)
日本人間工学会 認定人間工学専門家。UXデザイナーとして、UI/UXの研究・社内推進、事業開発に携わった後、2022年にNEC 白浜リビングラボを立ち上げる。同年からは、地域活性化起業人として白浜町役場に3年間勤務し、地域行政にも関与。現在は、一般社団法人 白浜イノベーションハブの理事を務める。

イノベーションラボラトリ 探索グループ 白浜リビングラボ
佐野 香織(さの かおり)
NPO法人で約8年間、地域創生の一環として和歌山県への移住促進やワーケーション推進に従事し、地域課題の解決と新しい働き方の実現に取り組む。2023年にNECソリューションイノベータに入社。NEC 白浜リビングラボにて、地域との持続可能な関係づくりや、仮説検証の企画、運営を担当。