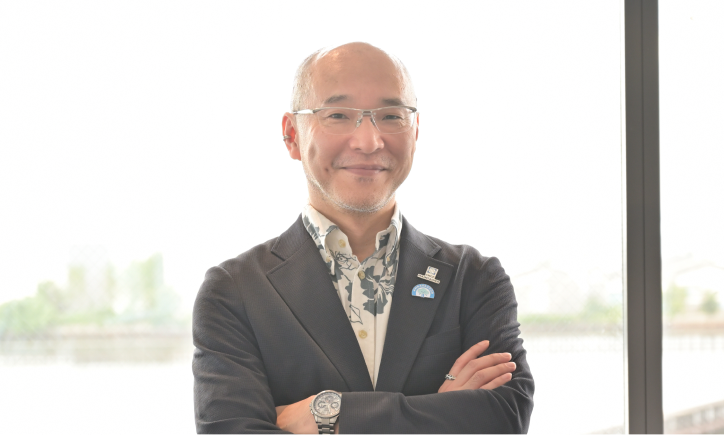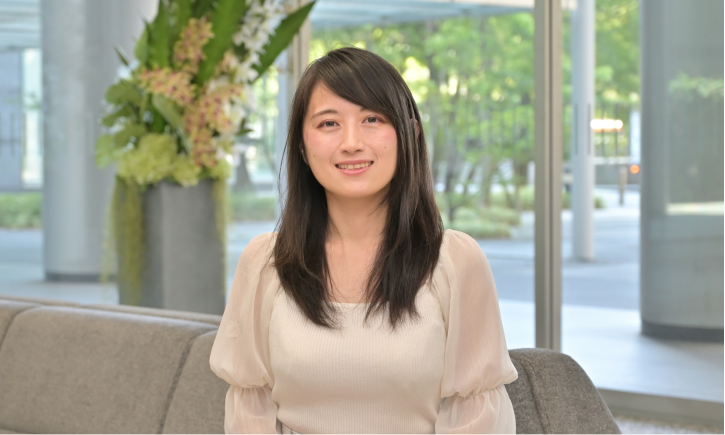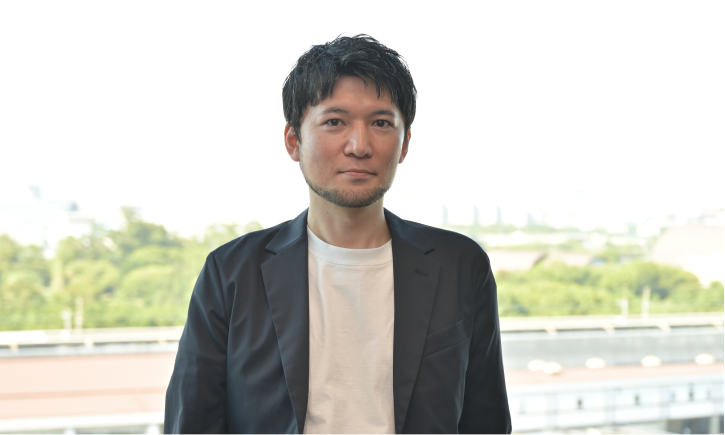サイト内の現在位置


MI(マーケットインテリジェンス)活動
・Innovation Story 04
#事業開発 #マーケットインテリジェンス
経営の羅針盤を創るMI活動:事業創出を加速させる「洞察」の力
#事業開発 #マーケットインテリジェンス
未来の事業を構想するとき、私たちは何を手掛かりにするでしょうか。市場のトレンド、競合の動向、そして最新のテクノロジー。しかし、これらの断片的な情報を集めるだけでは、次の時代を切り拓く事業は生まれません。重要なのは、情報と情報をつなぎ合わせ、まだ誰も気づいていない本質的な「洞察」を導き出すことです。この「洞察」こそが、事業開発の精度を飛躍的に高め、未来を予見する経営の羅針盤となります。
本稿では、この「洞察」を導き出すために、独自の手法でMI(マーケットインテリジェンス)活動を推進する取り組みをご紹介します。この活動は、単なる市場調査に留まらず、多様なバックグラウンドを持つメンバーが議論を重ね、未来の可能性を多角的に探求することにその真髄があります。この記事を通じて、マーケットインテリジェンス活動のヒントを見つけられることを願っています。マーケティングインテリジェンスグループでMI活動を牽引する佐伯と活動の概要を紹介します。

イノベーションラボラトリ マーケティングインテリジェンスグループ
佐伯 みずほ(さえき みずほ)

イノベーションラボラトリ マーケティングインテリジェンスグループ
佐伯 みずほ(さえき みずほ)
MI活動とは|定義解説と設立の背景
MI(マーケットインテリジェンス)活動とは、当社の事業創出や、その戦略策定に貢献することを目的に、市場のトレンド、競合情報、自社分析などのデータを掛け合わせ、事業機会に関する「洞察」を導き出し、社内に提言する一連の活動です。この活動は、イノベーションラボラトリ(以下、イノベラボ)の中で、以下の2つの重要な役割を担っています。
- 事業機会の提言者
イノベラボが掲げる事業方針に沿って、市場軸から具体的な事業機会を調査・分析し、取り組むべき領域を提言します。
- 事業化の壁打ち相手
他のグループが行う事業探索に対し、第三者的な立場で市場を分析し、事業化の精度を高めるための情報を提供します。
このMI活動が開始されたのは、イノベラボが組織として刷新された2023年4月のタイミングでした。以前から事業開発を経験してきたメンバーが集められ、マーケティングを専門とするメンバーはいないものの、多様な業界のノウハウや知見を持つ集団として活動をスタートさせました。このユニークな構成は、メンバーが過去の経験や固定観念にとらわれず、多角的かつ客観的に市場を分析できるという、MI活動の大きな強みになっています。
MI活動の最大の狙いは、単なる市場調査レポートで終わることなく、そこから次の事業につながる可能性を引き出すことです。メンバーは、調査結果を「事業を立ち上げるグループにどのように渡すべきか」という視点を常に持ち、自らの経験からも事業開発の難しさを知っているからこそ、より実践的で有効な「洞察」を提供することを目指しています。
MI活動の特徴|未来を予見する、ユニークな分析手法
MI活動の独自性は、単なる情報収集に留まらず、未来の変化を捉えるためのユニークな分析手法と、それを支えるチームの姿勢にあります。
-
「今」だけでなく「少し先の未来」を捉える視点
MI活動は、来年や再来年の事業だけでなく、その先の未来を見据えた市場分析を行います。2,3年程度で社会実装を目標とする事業開発においても5年後など中期的な未来を考えることが重要であり、市場がどう変化していくかを洞察することが不可欠です。 -
独自の手法とフレームワークの活用
MIチームは、市場分析において既存の手法のみに捉われず、独自の分析手法を多用します。既にあるフレームワークを拡張し、市場をA・B・C・Dの4つの象限に分け、それが5年後、10年後にどのように変化するかを予測します。この未来予測に、市場のペインポイントや潜在的な機会を重ね合わせることで、今取り組むべき領域を特定します。また、「今・次・将来シート」や「市場俯瞰図」など、独自のツールも活用し、複雑な情報をわかりやすく可視化しています。 -
AIと人間の「対話」を重視する分析プロセス
MI活動は、AIを情報収集の強力なツールとして活用します。しかし、AIが生成した情報で完結させることはしません。出てきた情報に対し、人間的な感覚や感情を加え、「なぜそうなるのか」「本当にそうだろうか」と深く議論する時間を大切にしています。この「人vsAI」の対話が、単なるデータの羅列ではない、血の通った「洞察」を生み出します。未来のシナリオ分析においても、AIが予測するベストシナリオとワーストシナリオを突き詰め、そのギャップをどう埋めるか、あるいはワーストシナリオを逆転させるにはどうすべきか、といった議論を徹底的に行います。このプロセスが、突拍子もないような革新的なアイデアを生み出す原動力となっています
MI活動の実施内容|「調査」から「提言」へ
MI活動は、単なる情報提供者ではなく、事業創出のプロセスに深く関与する提言者としての役割を果たしています。
その活動は、以下の3つの段階で構成されています。
-
調査(インフォメーション)
市場外観、競合・自社分析といった基本的な調査から活動は始まります。この段階では、AIを活用した机上調査や、展示会・イベントへの参加、必要に応じてコンサルタントや専門家との壁打ちなどを通じて、多岐にわたる情報を収集します。情報の正確性を担保するため、情報源の確認を徹底します。 -
洞察(インテリジェンス)
収集した情報をグループ内での議論や独自の分析手法を通じて深く掘り下げ、事業機会に関する「洞察」を導き出します。このプロセスにおいて、異なるバックグラウンドを持つメンバーの視点が、新たな気づきや発想の転換を生み出します。 -
提言(レコメンデーション)
導き出された洞察を基に、経営層や事業開発グループに具体的な提言を行います。この提言は、単なる報告ではなく、事業が成功するための可能性とリスクを明確に示しています。
MI活動のテーマは、経営層から与えられることもあれば、メンバーの日々の業務や関心事の中から自律的に生まれることもあります。この自律性が、MI活動を常に新鮮で活発なものにしています。


事例紹介|環境事業の常識を覆した「再発見」
MI活動の成果は、実際に事業の方向性を変えるほどのインパクトを持っています。その象徴的な事例として、ある事業領域における提言が挙げられます。
このプロジェクトの当初の仮説は、「環境関連事業は、法規制をきっかけに企業が動き出す」というものでした。つまり、パリ協定のような国際的な取り決めが国内法に落とし込まれ、企業がコンプライアンスとして動かざるを得ないタイミングを狙うべきだ、という考え方です。この仮説を検証するため、MIチームは環境関連の法律の整備状況と、実際の企業の取り組み事例を調査しました。
しかし、調査結果は意外なものでした。法律がまだ整備されていないにもかかわらず、多くの企業が環境関連の取り組みを活発に行っていたのです。この「法律と事例のギャップ」こそが、このプロジェクトにおける最大の「再発見」でした。これは、企業が法律によって動きだすのではなく、「コスト削減」や「売上アップ」といった営利活動の結果として環境に良いことが行われるという、事業の本質を浮き彫りにしました。
この洞察を基に、MIチームは、環境関連の取組が経済的な価値を生むモデルを検討し、提案しました。この提言は、事業開発グループを動かし、具体的なビジネスモデルの検討へ進むきっかけになりました。
この事例は、MI活動が単なる市場調査ではなく、事業の本質的な構造を解き明かし、新しい事業の可能性を見出す強力なツールであることを証明しています。
今後の展望|MI活動の未来と社会に伝えるべきこと
MI活動は、今後、さらに進化を目指します。最も重要な目標は、「MIの提言から新しい領域・事業が生まれること」です。そのためには、活動のスピードアップと、提言の精度向上を継続的に追求していく必要があります。
また、MI活動が社会に対して果たすべき役割は、「イノベーションのモデルケースとなること」です。多くの日本企業が「事業開発がうまくいかない」という悩みを抱える中で、MI活動を通じて得られた知見やノウハウを共有し、日本全体でイノベーションが起こるための土壌を育んでいきたいと考えています。
この活動を通じて、私たちが最も伝えたいメッセージは、「誰もがMIの担い手になり得る」ということです。様々なバックグラウンドを持つメンバーが、自身の興味や経験を起点に、日々情報を収集し、議論を重ねています。この「問いを立て、共に考え、小さく試してみる」という営みは、特別なスキルがなくても誰にでもできることです。
MI活動は、新しい事業の種を見つけ、それを現実の場で育て、そして社会に実装するための、理想的なパートナードライブフォースとなり得ます。ぜひ、この活動を通じて、未来の事業を共に創造していきましょう。
イノベーションラボラトリ マーケティングインテリジェンスグループ
佐伯 みずほ(さえき みずほ)
システムエンジニアとして海外のナショナルプロジェクトに携わったあと、海外関係会社において採用・育成スキームの構築と確立に貢献。帰国後は全社の海外戦略立案・推進や海外案件支援のほか、新規事業立ち上げ、技術・市場調査業務に従事。現在は、マーケティングインテリジェンスグループに所属。海外業務経験や市場調査の知見を活かし、大学の外部講師も務めている。