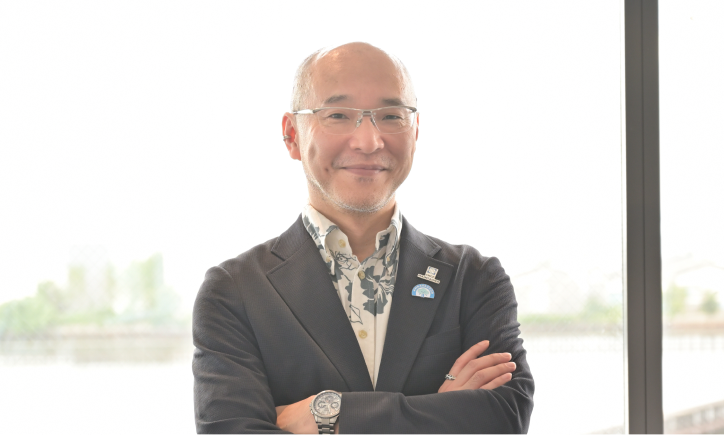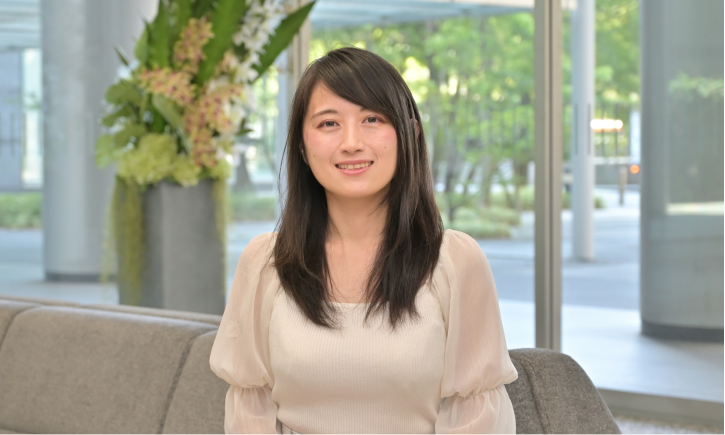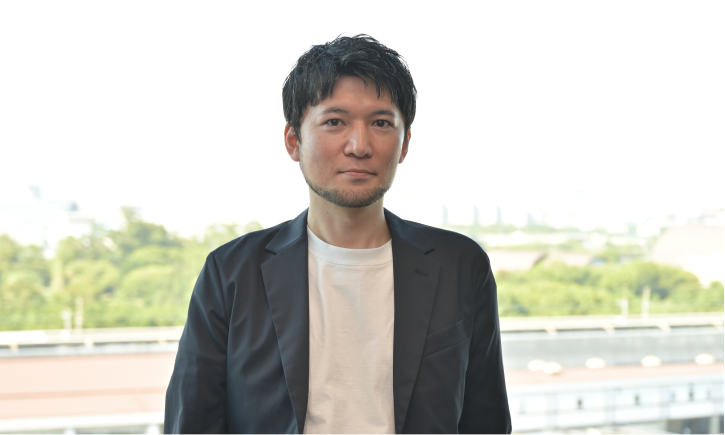サイト内の現在位置


ウェルビーイング経営
・Innovation Story 07
#研究開発 #心豊かに暮らす #ウェルビーイング経営
ウェルビーイング経営が拓く、幸福と利益を両立させる未来
#研究開発 #心豊かに暮らす #ウェルビーイング経営
現代のビジネス環境は、目まぐるしい変化の渦中にあります。テクノロジーの進化、働き方の多様化、そして予期せぬ社会の変動。こうした時代において、企業が持続的な成長を遂げるための羅針盤は何でしょうか。かつての資本主義が追求してきた「成長」や「効率」だけでは、もはや社員の心を満たし、組織を一つにまとめることは困難になりつつあります。多くの企業が直面しているのは、単なる売上や利益の追求を超えた、より本質的な経営のあり方ではないでしょうか。
本稿では、この問いに真正面から向き合い、「ウェルビーイング経営」を研究するサイエンスラボラトリ第二グループの山本とともに深掘りします。特に、西洋発のウェルビーイング概念に東洋思想の光を当て、日本ならではの幸福感に基づいた日本式ウェルビーイング経営の可能性を探ります。この概念は、単なる福利厚生の充実や働き方改革に留まらず、企業の存在意義そのものを問い直し、社員の心に深く響く経営の実現を目指すものです。
私たちは、市場調査や学術調査を独自に行い、ウェルビーイング概念の階層が経営における「心構え→経営思想→組織文化→事業→収益」という階層に対応し、ウェルビーイング経営ではその階層がうまく連動しているという仮説を立て、そのメカニズムを解き明かそうとしています。この記事を読み進めることで、読者である若手研究者の皆様が、ウェルビーイング経営を単なる流行の一時的な概念ではなく、次世代の経営を牽引する重要な研究テーマとして見出していただけることを願っています。

イノベーションラボラトリ サイエンスラボラトリ第二グループ
山本 純一(やまもと じゅんいち)

イノベーションラボラトリ サイエンスラボラトリ第二グループ
山本 純一(やまもと じゅんいち)
ウェルビーイング経営とは?ー幸福と利益を両立させるメカニズムの解明ー
ウェルビーイング経営とは、社員一人ひとりの幸福(ウェルビーイング)を経営の中心に据え、それを企業の持続的な成長へと結びつける経営手法です。ウェルビーイング経営は多様な定義がありますが、私たちは「社員が最終日に『この会社で働いてきて良かった』と思える経営」と定義しています。これは、単に金銭的な報酬や地位の向上だけでなく、仕事を通じて得られる深い満足感、自身の成長実感、仲間との強い絆、さらには苦労を乗り越えた先にある充実感を重視するものです。
この定義をさらに深く掘り下げてみましょう。社員が「働いてきて良かった」と感じる瞬間は、単一の出来事ではなく、日々の小さな積み重ねによって生まれます。例えば、困難なプロジェクトをチームで乗り越えた達成感、上司や同僚から受けた心からの感謝、自分のアイデアが事業に活かされたときの誇り、そして何よりも、会社という組織が社会に貢献しているという実感です。これらの要素は、社員のエンゲージメントを自然と高め、結果として組織全体のパフォーマンス向上につながります。
このウェルビーイング経営は、特定の要素を個別に導入するだけでは効果を発揮しません。例えば、組織文化を改善するために「毎朝、あいさつする」という施策を実施したとしましょう。しかし、施策推進者が毎朝玄関であいさつしたとしても、多くの社員は無反応でしょう。なぜなら、「なぜ、挨拶をするのか?」という経営思想が理解されていないからです。それならばと、施策推進者が説明会を開催し、社員の理解を促進したとしましょう。しかし、「行き当たりばったりだ」とか「点数稼ぎだ」などと社員に思われてしまっては、やはり社員の多くは無視するでしょう。なぜなら、施策推進者の心構えが「やらせよう」という自分本位だからです。したがって、「心構え→経営思想→組織文化」の連動性が重要なのです。さらに、コミュニケーションの基本である「あいさつ」は人間関係を円滑にし、助け合いにより事業の労働生産性が向上します。そして、お客様へのあいさつを通じて、活気のある会社といった評判が向上すれば、お客様の最終的な意思決定に影響が及ぶこともあるかもしれません。このような「心構え→経営思想→組織文化→事業→収益」この一連の流れをデザインすることが、ウェルビーイング経営の鍵となります。このモデルは、ウェルビーイングが単なる「人事施策」ではなく、経営そのものの中核をなすことを示唆しています。
「日本式ウェルビーイング経営」の可能性
西洋発のウェルビーイング概念は、自己実現理論や自己決定理論などと関連して自己に重きを置く傾向が強い一方で、京都大学の内田先生らは関係性の中に幸福があると考える「協調的幸福感」というウェルビーイング概念を日本文化から見出しました。これは、日本文化の中には、他にもまだ知られていないウェルビーイングが存在する可能性を示しており、この研究では成功している日本企業はこのような未知のウェルビーイングが関与しているのではないかと考えています。
この研究の原点には、「日本式の企業経営には、東洋思想と関連した未知のウェルビーイングが隠されている」という直感が存在します。具体的には、近江商人の「三方よし(売り手よし、買い手よし、世間よし)」の精神や、茶道の「わび・さび」といった共助的な思想に、資本主義が抱える限界を超えるヒントが隠されていると考えています。三方よしの精神は、利益追求だけでなく、顧客や社会全体の幸福を同時に追求するものであり、まさにウェルビーイング経営の根幹をなす思想です。また、「わび・さび」は、物質的な豊かさだけでなく、質素さの中にある精神的な豊かさを重んじるもので、過度な成長や効率を求める現代社会へのアンチテーゼとなり得ます。
欧米を中心として研究されてきた経営学や産業心理学には、ストレス・マネジメントの文脈でマインドフルネス(座禅)やコンパッション(慈悲)が取り入れられていますが、その他の東洋思想の考え方はほぼ含まれていません。1980年代、米国で日本式経営がよく研究され、例えばトヨタ生産方式はシックスシグマ法として体系化されました。しかし、日本式経営の埋もれた知恵の多くは、実践として残りつつも、解明・体系化されてはいません。そこで、日本式経営の古くて新しい概念をウェルビーイングの文脈で解明し、現代経営のメカニズムとして落とし込めれば、多くの企業にとって有用な独自性のある知見となるはずです。このアプローチは、日本の強みである文化や精神性を経営に活かし、世界に通用する新しい経営モデルを創出する可能性を秘めているかもしれません。


研究の原点―「仕事が楽しい」という問いから始まった旅
この研究の原点には、「仕事が愉しい人と愉しくない人は何が違うのか?」という問いがあります。当初、これはエンゲージメントの違いではないかと考え、エンゲージメントの研究をしていました。しかし、たとえエンゲージメントが高くても、快楽的な「楽しい」仕事だけを追求すると、会社が困難に陥いった途端、社員は辞めていくでしょう。一方で、困難で苦しい仕事を乗り越えたとき「この仕事をやって良かった」と「愉しさ」を感じることがあります。ウェルビーイングの1つであるユーダイモニア(善い生き方)という概念を知ったとき、持続的な経営のためにはこのような「愉しさ」の感覚が重要だと強く感じました。
アリストテレスによるユーダイモニアは西洋的ウェルビーイングの概念ですが、日本のウェルビーイング経営を実践する企業を数社訪問して見えてきたのは、むしろ「利他の心」「助け合い」「おもてなし」「心を磨く」「人間力」といった東洋的あるいは日本的な概念でした。訪問した企業のほとんどは、業績が悪化した時にウェルビーイング経営をはじめ、業績を急激に回復させたという共通点があります。名経営者である稲盛和夫は企業理念で「従業員の物心両面の幸福」を言及し、仏門に入った晩年の著書では「利他の心」を経営者に求めています。これらの事実から、東洋思想に基づく日本式経営には企業業績を改善させる可能性があります。
しかし、東洋思想に基づくウェルビーイング経営が企業業績を改善するメカニズムは自明ではありません。「心構え→経営思想→組織文化→事業→収益」というのは、このメカニズムを最も抽象的に構造化したモデルです。このモデルを前提に、訪問した企業の訪問メモや経営者の書籍、メディアでの発言、企業の歴史などを分析し、より詳細モデルを検討しました。その結果、検討の中から、経営者の心構え、経営思想の構造、組織文化と事業の連動、などに共通項を導き出しました。例えば、日本式のウェルビーイング経営を実践する経営者の心構えには「顧客よりも社員を大切にする」といった共通点があります。
社会に対する役割
もしウェルビーイング経営のメカニズムが解明できれば、ウェルビーイング経営を意図的にデザインすることができるようになり、ウェルビーイング経営の戦略論を描くことができると考えています。この戦略論は、そのメカニズムから収益に結び付くため、多くの企業に採用される可能性があります。そして、ウェルビーイング経営戦略論を採用する企業が増えれば、世界全体がウェルビーイングな方向に向かうのではないでしょうか?このようにして、この研究は、人々が心豊かに生きられる社会を築くための羅針盤となることを目指しています。
一方で、訪問企業の分析から得られた共通点の1つに、経営者の最上位の志が「永続企業になる」である点があり、これは西洋的な競争戦略論とは相容れません。西洋的戦略論は、競争に勝利(成功)し、成長し続けることを企業に求めます。しかし、日本では、むしろ他の企業と共生し、永続することを企業に求めます。日本は100年以上続く企業が世界で最も多いことで有名ですが、これは日本企業が「永続」に価値を見いだしてきたことの証拠に見えます。また、「家業を自分の代で潰すわけにはいかない」といった「次世代へ継承する」感覚も、「永続」に価値を見いだしていると言えます。このような日本的な思想は、現代資本主義における「成長」を軸とした社会から、「永続」を軸とした社会への転換を促すきっかけになるかもしれません。
資本主義は、マルクスの予測とは異なり、経済成長によって多くの中流階級を生み出し、社会全体を豊かにしてきました。しかし、現在、分断や格差などの増加で資本主義が限界を向かえているとも言われます。これは、「個人の成長と勝利」の正当化が行き過ぎた結果ではないでしょうか。私たち人類は、「個人の成長と勝利」の上位目的に「人類の永続と共生」を設置する必要性に迫られているのかもしれません。この研究が、その一助になれば嬉しいです。
未来への展望
このウェルビーイング経営に関する研究は、フィールド調査を終え、詳細な仮説を立てた段階です。今後は、その詳細な仮説の確からしさを、科学的に検証していく必要があります。検証には主に心理学的統計や経営学的統計を用いますが、特に東洋思想的概念は心理学ではあまり研究されておらず、測定できないものが多く存在します。そのため、哲学や宗教学を参考にしながら、概念定義から検討するものもあることでしょう。こうした研究を経て、ウェルビーイング経営のメカニズムを明らかにし、実践的で応用可能な戦略へと昇華させることを目指します。
今後の展望としては、まず、この「ウェルビーイング経営」を体系化し、多様な企業が自社に合った形で導入できるフレームワークを構築することです。具体的には、どのような組織文化がどのような事業成果につながるのかを分析し、「日本式ウェルビーイング経営」の成功モデルを提示していきます。
イノベーションラボラトリ サイエンスラボラトリ第二グループ
山本 純一(やまもと じゅんいち)
Ph.D.(Physics)、MBA、Marketing Specialist (公益社団法人日本マーケティング協会公認)、 Gallup認定ストレングスコーチ