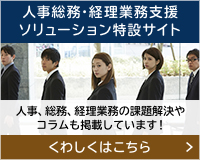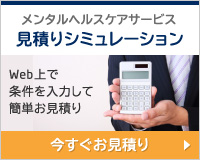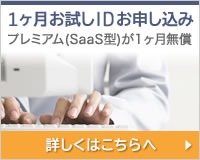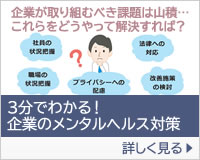座談会:メンタルヘルスの現状と将来
IT企業だからこそ取り組むメンタルヘルス問題
NECソリューションイノベータが語る、メンタルヘルスの現状と将来
近年、社員がメンタル不調に陥ることで企業活動へ及ぼす影響が大きな問題となっています。そこでNECソリューションイノベータでは、同社が提供するヘルスケアソリューションにおいて、メンタルヘルスの分野に注力。さまざまな手段でメンタル不調を予防する「メンタルヘルスケアサービス」を開発し、市場での提供を目指しています。今回は、「メンタルヘルスケアサービス」の企画者と開発者、そしてサービス利用者の3者に、メンタルヘルスの現状と将来について語ってもらいました。

向かって左から
パブリック第一事業本部 医療ソリューション事業部 事業部長 柴田 学
VALWAYテクノロジーセンター ニューソリューショングループ グループマネージャー 山口 美峰子
人事総務部 人事マネージャー 丸岡 晶
※本座談会は2015年3月に行われました。
メンタル不調者の増加により、企業は年間数千万円~1億円の損失
―最近、うつや不安などメンタル面での不調(以下、メンタル不調)に悩む人が増えていると聞きますが、どのような状況でしょうか?
柴田:厚生労働省の調査によると、国内でメンタル不調と診断された人の数は100万人を超えており、大きな社会問題になっています。またそこから生まれる経済的な負担も大きく、総額39兆円といわれる国民医療費のうち、メンタルに関する障害が約2兆円となっています(※1)。また、欠勤者(Absenteeism)と低生産性出勤者(Presenteeism)による影響まで加えると、社会的コストは8兆円を越えるとの調査報告もあります(※2)。
―企業活動においてもメンタル不調による損失は大きいのですね。

柴田:メンタル不調による休職者を出すと、1人あたり1年間で1,000万円~2,000万円の損失となるという試算があります。また、休職率は一般企業で0.4%程度、情報通信業では2.0%程度という調査結果もあり(※3)、以上を考えると1,000人規模の企業なら年間数千万から1億円以上の損失を出している計算です。例え休職まで至らなくても、メンタル不調による労働生産性の低下が企業の業績に及ぼす影響は少なくないため、効果的な対策を求める声が高まっています。
―そこでこのたび、「労働安全衛生法の一部を改正する法案(通称:ストレスチェック義務化法案)」が国会で成立しました。
柴田:2014年6月に成立し、2015年12月までに施行される予定です(※4)。この法案では、事業者に対して、医師、保健師などによるストレスチェックの実施を義務付けています。事業者は、ストレスチェックの結果を社員に通知し、社員から希望がある場合は医師による面接指導を実施。さらに医師の意見を聴いた上で、適切な就業上の措置を講じなければなりません。ただし、従業員50人未満の事業場については、しばらくの間は努力義務とされています。

山口:これまでも、各企業はメンタルヘルスへの対策を自主的に行ってきました。しかしそれでもメンタル不調者の数は増え続け、企業活動に及ぼす影響は深刻化しています。国として、これまでの施策をより一層強化するために打ち出したのが、今回の法案といえますね。
―法律を守らなかった場合、罰則はあるのですか?
柴田:現時点ではありませんが、企業もこの問題を放っておいては業務に差し障りが出ますので、どちらにせよ、これまで以上に社員のメンタルヘルスへの配慮が求められることになるでしょう。
―なぜ「50人未満の事業場は努力義務」なのですか?
柴田:既存の労働安全衛生法では、産業医の選任基準が従業員50人以上と定められているので、運用のしやすさを考えたのではないでしょうか。また、小さな企業は体制的に環境を整備することが難しいのもあるでしょう。
―人事部門の立場から見て、現場でのメンタル不調の影響をどのように認識していますか?

丸岡:IT企業の休職率は一般企業の2倍という調査結果が出ていますが、当社も多くのSEがいるICT企業です。さらに当社は社会的に重要なシステムに関わる業務を担うことが多いため、社員には相当なプレッシャーがかかっていると思います。そこで当社では、厚生労働省の指針による「4つのケア」(※5)に基づき、さまざまな対策を実施してきました。例えば、各種研修を実施したり、社外の専門家などに相談できる窓口を設置したりしてきました。