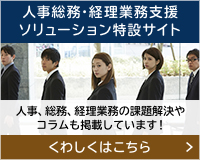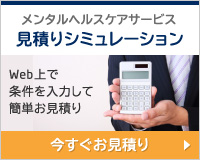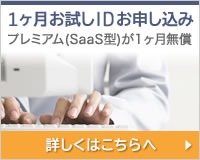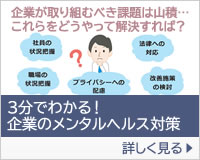座談会:メンタルヘルスの現状と将来
社会的貢献を目指し、メンタルヘルスまで含めた総合ヘルスケアビジネスを推進
―このたびNECソリューションイノベータはメンタルヘルス市場へ本格的に参入しますが、これにはどのような意図があるのでしょうか?
柴田:メンタルヘルスは社会や企業にとって重要な課題です。そして、社会が困っていることにICTを活用して貢献することが、私たちNECソリューションイノベータに与えられた使命だと考えています。そこで、全社方針では人と社会に優しい社会を実現するヒューマンケアを重点領域に制定し、その一つとしてメンタルヘルス事業を推進しています。これまで培ってきた電子カルテをはじめとする医療系システムのノウハウや研究開発部門の成果をベースに、こうした課題の解決に役立つサービスの開発を目指しました。
―研究・開発の具体的な経緯を教えてください。
山口:研究のテーマとして「メンタルヘルス」を設定したのが2009年のこと。当時のVALWAYテクノロジーセンター(NECソリューションイノベータ傘下の研究所。以下、VTC)のセンター長から、「今後、ヘルスケア事業への参入が見込まれる。研究テーマとなるキーワードをピックアップするように」との指示を受けたのがはじまりです。
VTCでは、人と社会の快適な未来を目指し、「高度で使いやすいソフトウェア開発」、「新しいユーザーインターフェースの開発」、そして「これまでにない新規サービスの提供」と3つのテーマで研究・開発を行っています。つまり、ありきたりなテーマではVTCが挑戦する意味がありません。多くの人が困っているのに見過ごされがちな課題がないか、解決のためにVTCができることはなんだろうか。いろいろな人からさまざまな意見をうかがい、キーワードをピックアップ。その中から最終的に選ばれたのがメンタルヘルスだったのです。
―研究の第一段階として、社内でヒアリングを実施したのですね。

山口:メンタルヘルスケアにおいて大事なのは、自分が置かれているストレス状態の把握や管理です。しかし人によっては、自分がメンタル不調に陥っていても気がつかなかったり、上手くストレスをコントロールできなかったりします。
また、どの部署でも、メンタル不調者が出ると周囲への影響が大きいため、予防に気を配っているところが多いようです。とはいえデリケートな問題ですので、なかなか実態がわからず、ある日いきなり誰かが欠勤して初めて事態が発覚することも少なくありません。しかしそんな中でも、「彼(彼女)はどうも最近おかしい」と気づいている人はいます。ただし、「気づき」は、よく気がつく人もいれば、そうでない人もいる。職場の環境によっても左右されます。
以上のような点から、本人のストレスに対する対処力強化を支援する「セルフケア」と、本人を取り巻く環境を改善する「ラインケア」の2つに着目しました。
柴田:ラインケアの重要性は従来から指摘されており、当社としても管理職を中心に教育を行ってきましたが、欠勤が始まる等とどうしても不調が進行してからの対応とならざるを得ませんでした。それだけに、従業員のメンタル不調の兆候を視覚化するものがあれば、人による管理レベルの差がなくなり、気づきも早くなるのではないかという思いがありました。
―開発行程ではどのような苦労がありましたか?
山口:メンタルヘルスの分野は、当社ではまだ誰も手がけていない、全く新しい研究テーマでした。事業化できるかどうかもわからなかったので、最初は私だけの「おひとり様プロジェクト」としてスタート。社内の各事業部でデータを取らせてもらったり、レポートを書いて報告したりという調整も、全て一人でやらなければなりませんでした。あまりのハードワークに私自身がメンタル不調に陥りそうになりましたが(笑)、幸い社内のほとんどの方がメンタルヘルスに対する関心が高く、丁寧に話を聞いてくれたので、たくさんの貴重な意見をいただくことができました。
柴田:当社の場合、ICT企業の中でも特に好奇心が強い会社なので、新しいことへのチャレンジを尊重する風土があります。ですから今回も、「面白い研究やっているね」という声が大きかったですね。
山口:実際、こうした声がなかったら、5年間も研究を続けていられなかったと思います。
―「これはいけるかも」という手応えをつかんだのはいつですか?
山口:社会的にメンタルヘルスへの関心が高まってきたこともあり、ここ1、2年でメンタルヘルス市場に参入するICT企業が増えています。これを聞いたとき、「私がやってきたことは間違っていなかった」と確信できましたね。ライバルは増えましたが、NECソリューションイノベータでは長年にわたり地道な研究と社内での検証を重ねてきており、他社に負けないソリューションが開発できたと自負しています。