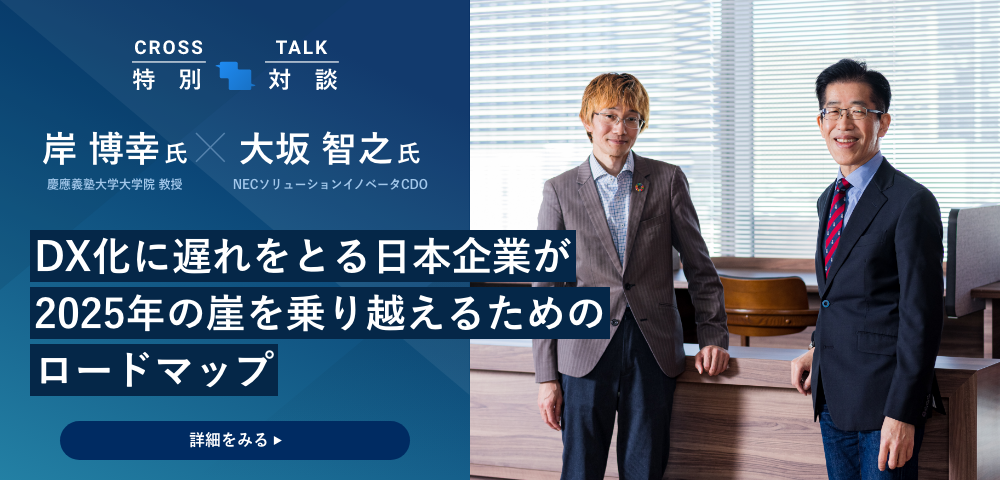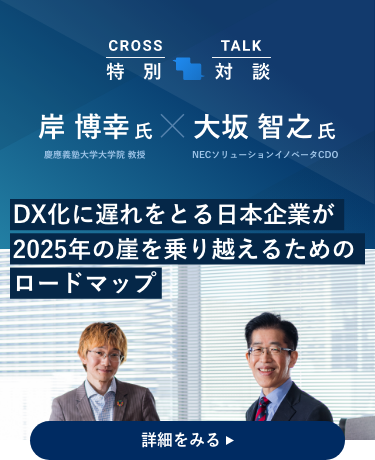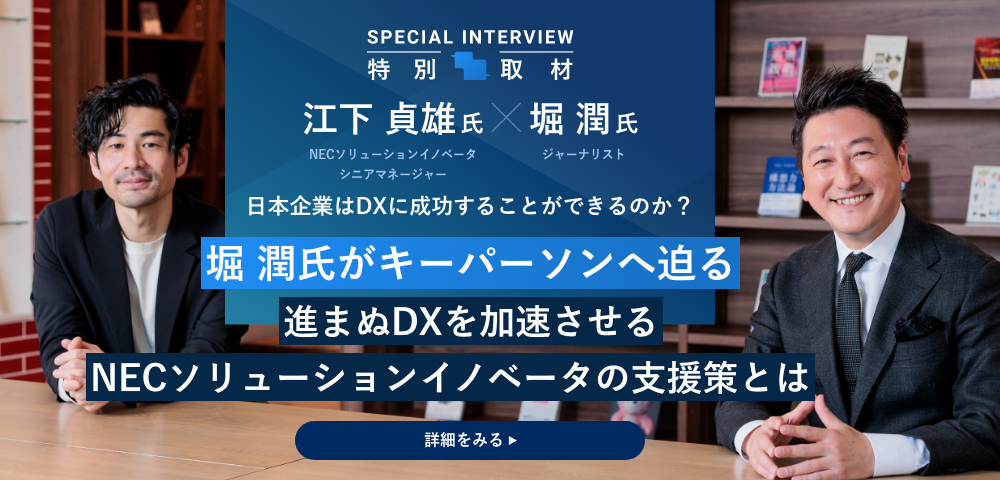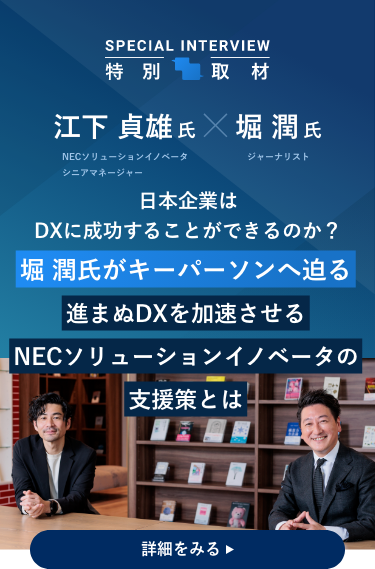サイト内の現在位置
【 営業DX 】
データドリブンを実践し、
ビジネスの成長に貢献する
イノベータ。
- マーケティング効果
- 案件創出金額 2.6 倍
-
データと事例から見るホワイトペーパーを
DX障壁の超え方
ダウンロード -
事例に関して詳しく聞く3/17
ウェビナー開催
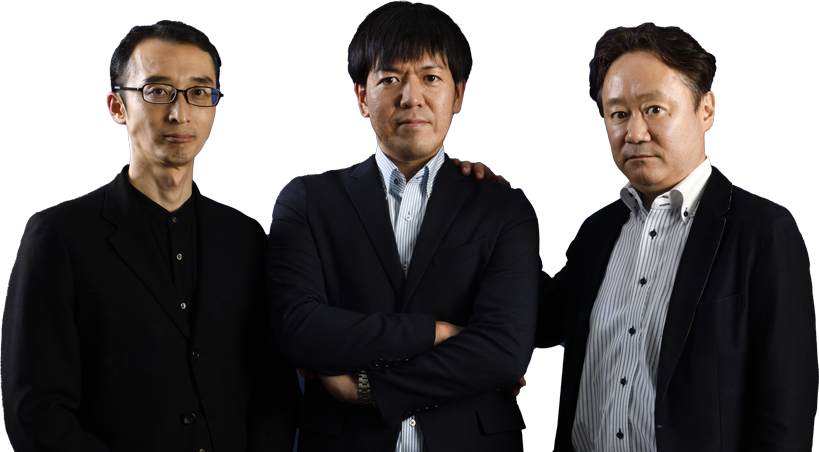

営業・マーケティングプロセスの統合とデジタル化
案件創出金額の倍増と、大幅なコスト削減
日本において、将来的な労働人口の減少は避けられない未来図だ。その中でも企業として成長戦略を描くには、組織や個人の労働生産性向上が必須となる。特に営業部門においては、生産性の向上がキーワードとして言われて久しい。この時に重要なのは、営業とマーケティングのプロセスを統合し、かつデジタルで自動化とインテリジェンス化を進めることである。NECソリューションイノベータでは、マーケティングのターゲティング、リード獲得から営業のクロージングまでを1つのプロセスと定義し、「営業DX」を推進。新型コロナウイルス感染拡大の影響で絶望的な状況にあった顧客獲得活動をV字回復させた。
- 課題
- 新型コロナウイルスの感染拡大で展示会出展やセミナー開催ができなくなった。その影響で、例年と比較してマーケティングリードの獲得数が70%減少した。
- 成果
- ウェビナー、Webサイト、デジタルイベントを活用し、顧客接点のデジタル化を促進。営業プロセス全体のDXを進め、案件創出金額を2.6倍に増やし、リード獲得コストを70%削減した。
新型コロナウイルスの感染拡大で展示会出展やセミナー開催ができない中、顧客接点を100%デジタルに素早く切り替え

マーケティング推進本部 本部長 飯島 圭一 氏
飯島「営業DX」に着手したのは、新型コロナウイルスの感染拡大が始まる前の2018年です。2030年の日本を見通した時、避けられない課題の1つに「労働人口の減少」があります。この影響はあらゆる日本企業に及び、当社も例外ではありません。成長を続けていくには、労働生産性の向上が不可欠。「営業1人当たりの生産性を上げる」というのが、私たちのテーマとなりました。そのために立ち上げたのが「営業DX」です。マーケティング部門と営業部門が協力し、プロセスの改善やテクノロジーによって、業務効率を飛躍的に高めることを目標に、プロジェクトをスタートしました。

営業統括本部DXソリューション営業部 部長 小澤 文章 氏
小澤少ない人数でいかに成果を上げられるかが課題です。それには、マーケティングから営業に至る全工程を1つの大きなプロセスととらえ、全体最適化を目指す必要がありました。
瀬崎私は現場に近いマーケティング担当者ですから、まずは現場レベルの業務効率化に取り組みました。デジタルの活用によって現場の課題解決に挑み、成功したものを社内に展開していくイメージです。
飯島そんな中、2020年に新型コロナウイルスの感染拡大が本格化し、わずか1~2カ月でこれまでに無いレベルで大きなダメージを受けました。マーケティング部門の主な仕事は、展示会やセミナーで有望な見込み客(マーケティング・リード)を獲得することでしたが、そうしたイベントが一切できなくなったのです。その結果、本来獲得すべきリード数の70%が一瞬で失われました。
小澤この事態は一刻も早く改善する必要がありました。多くのアイデアを皆で出し合い、可能性のあるものは試す、そのような動きを日々行っていました。その中で注目したのが、社内のセキュリティ営業部門が始めていたウェビナーです。「展示会に変わるものはこれだ」と確信しました。すでにやり方を知っている人がいたので、展示会で取れなくなったリードを、ウェビナーで獲得するべく、そこから利用を一気に広げました。
飯島私たちは、「デジタルリード戦略」の下に、顧客接点を100%デジタルに切り替える決断を下しました。リードを獲得する戦術は3つです。第1がウェビナーの全社展開。ライセンスの整備や技術検証、プロセス標準化、社内教育なども含まれます。第2がWebサイトをこれまで以上に重要な顧客接点としてコンテンツを磨き上げること。第3がデジタルイベントの活用です。
こうした大きな方針転換は、従来なら1年以上かけて議論するところですが、この時は1カ月で社長の了承まで取りつけました。このスピード感も、成功の大きな要素だったかと感じています。
デジタル化は「戦略」があってこそ機能する
飯島例えばウェビナーですが、ただやればいいと言うものではありません。「ターゲティング」「集客」「実行」「フォロー」の4つのプロセスで標準化を進めました。お客様に一貫したデジタル体験をご提供するために、それぞれの段階では多数のデジタルツールを活用しています。
ターゲティングでは、BtoB事業向け顧客戦略プラットフォーム「FORCAS」を用い、当社の商材と相性のよい見込み客や、「増収増益、急成長」などのシナリオに合致した顧客をバイネームでリストアップします。この見込み顧客にデジタルでのアプローチを行い、ウェビナーに誘導を行います。出席者やアンケートのデータは、顧客管理システムの「Salesforce」に格納します。そこから電話や電子メールで顧客にアプローチし、スクリーニングして可能性の高いリードを営業と共有します。
小澤営業から見ると、顧客接点の最上流、つまりリード獲得の部分が一気にデジタル化したイメージです。

マーケティング推進本部 DXアーキテクトマネージャー 瀬崎 大輔 氏
瀬崎例えば、ウェビナー受講後のアンケートに対するフォローを例に挙げてみますと、従来ならマーケティング担当者がアフターフォローでお客様からヒアリングを行い、「後ほど営業から連絡させます」と伝えて営業担当者へ引き継ぎます。営業担当者は改めてお客様に連絡し、訪問の日程調整などをするわけです。お客様から見れば、マーケティングと営業で2回のやり取りが必要でした。
現在は、ウェビナー受講後のアンケートでミーティングの希望日時までを聞き、お客様の二度手間を解消しています。これは一例に過ぎませんが、こうした施策をマーケティングと営業が協働して検討し、日々の業務効率を高めています。
飯島新型コロナウイルスの感染拡大の影響で大きく落ち込んでいたリード獲得ですが、結果的には対前年比で1.2倍もの新規リードを獲得することが出来ました。その内、デジタル接点でのリードが99.7%を占めていますので、何も手を打っていなかったとしたら、相当大きな打撃を受けていたと思います。案件創出金額も、一時は落ち込んでしまったのですが、再び成長軌道に乗せることができ、2018年上期の実績と比べると、案件創出金額は2.6倍に増え、1リード取るためのコストは70%ほど削減できています。
業務のデジタル化だけで成し遂げられたかといえば、答えはNOです。営業DXで最も重要なのは、マーケティング戦略と営業戦略の融合です。顧客は誰か、どのような価値を提供するか、どうやって届けるのか、クロージングまでのステップをどうするかなど、もう一度基本からしっかり定義し直すことが重要です。そうした戦略があるからこそ、そこにデジタルテクノロジーが入ることで高い効果が得られます。
瀬崎また、営業DXの成功にはしっかりと整理されたデータが必要です。例えば、ウェビナーのアンケートやWebサイトのお問い合わせフォームなどでお客様に入力していただいたデータは、社名に「株式会社」が無かったり、「(株)」と書く方もいたり、決してデータが整った状態で登録されるとは限りません。部署名や役職名もお客様によって定義はばらばらです。
このように整っていない状態のデータを整理する作業は、一般的にはデータクレンジングと呼ばれ、マーケティング活動においては非常に重要な取り組みとなります。以前は100%人手に頼っていたため、データ精度が期待以上に上がらなかったり、データ量に比例して工数が掛かったりと、非効率な状態が続いていました。そこで出会ったのが「Sansan Data Hub」というサービスです。このサービスを導入したことで今まで人手に頼っていたデータ・クレンジング作業を完全に自動化することができ、年間約500時間の工数削減に貢献しています。また、マーケティング活動で入手したお客様情報に対して、帝国データバンクの情報との紐づけも自動化することで、当社の顧客管理システムのマスターデータとも自動でつながるようにしました。これにより、従来ばらばらであったデータを整理された状態で効率よく管理することができるようになり、データが持つ価値を大きく向上させることができました。
上流から下流まで一貫した顧客体験を提供
小澤営業DXでは、細かい仕組みをたくさん活用しています。例えば、Salesforceの「5分速報」です。営業担当者が行動した後、すぐに報告を入れると上司もダイレクトに応える。足の速いコミュニケーションを増やす試みです。
また、従来は予算管理のシステムが別にあり、そのデータをSalesforceに手入力していましたが、それもやめました。Salesforceを中心に、マーケティング管理から営業組織の内部管理、上司とのコミュニケーション、予算管理までをシームレスにつないでいます。
それだけではありません。「NECソリューションイノベータオンラインマーケット」を立ち上げ、単価の低い商材の見積り、受注、契約、といった定型業務、ご利用開始のサポートまでをオンライン化しています。さらに、利用を継続していただくためのユーザーコミュニティ作りの取り組みを開始しました。ユーザーの意見や満足度をフィードバックしてもらったり、ユーザー同士で情報交換できる仕組みです。
飯島上流から下流まで、一貫した顧客体験を提供することが大切です。お客様は当社の営業やマーケティング担当者と1度も会わずに製品知識を獲得し、内容や効果を深く理解して、契約までできる基盤が完成しています。
小澤営業の私たちがお客様に会う時には、もうお客様の中で購入する製品やサービスが絞り込まれ、意思決定の段階になっています。お客様の購買プロセスにもデジタル化が浸透しつつあると感じます。
成功の秘訣は、
マーケティングと営業が1つのゴールを共有したこと
飯島今回の営業DXでは、マーケティングと営業が1つのゴールを共有できたことが非常に重要でした。例えば、営業が100億円の売上目標を持っているとき、マーケティングのゴールが「100万人のリードを獲得すること」では同じゴールとは言えません。100億円なら100億円という1つのゴールを共有して初めて、チームとして機能し始めます。
小澤現場の若手社員には、DXに積極的な人が少なくありません。そうした人たちのやる気や熱意をうまく生かすことも大切です。現場の管理職が「まずはやってみよう」という姿勢を示し、未知なことに取り組む気運を積極的に作っていく必要があります。我々が取り組んできた営業DXという「デジタル化」の取り組みは新たな業務プロセス作り、いわばBPRであり、あらたなケイパビリティの獲得のための取り組みです。
飯島やってみなければわからないことばかりです。例えば、当社では「午後3時をまたぐウェビナーはやらない」というルールがあります。3時になると全社一斉に音楽が流れるので、その音がウェビナーに入ってしまうからです(笑)。また、会議室でウェビナーをする際は「人が入って来ないようにドアに張り紙をする」といった細かいルールもあります。すべて体験して初めてわかったことばかりです。
小澤このように、よりよい顧客体験にむけて、我々は自ら実践し、変化しようと心がけています。自ら実践した者にしかわからない細かいノウハウをつみかさね、必要なクオリティで再現性高く実行できるようにするため、組織でノウハウを共有しています。
瀬崎初めからDXに取り組むというよりは、目の前の課題解決や生産性の向上に努めていたら、結果としてDXになったという感覚が強いです。成功には3つのポリシーが必要だと考えています。1つ目は「味方を作ること」。同じ目標に向けて協力できる人と一緒に進めることが重要です。2つ目は「自分が動くこと」。誰かがやってくれるだろうとは考えず、できるだけ自分が率先して動くように心がけることです。3つ目は「ダメな理由を探さないこと」。DXは誰にとっても未知の取り組みなので、必ず賛否両論が出てきます。その際に「できない」ではなく、「どうすればできるか」と考えることが大切です。こうした姿勢で小さな課題をコツコツ解決していくことが、結果としてDXにつながると考えています。
飯島今後は、更なる高みを目指して営業DXを続けていくと同時に、私たちが体験した営業DXのノウハウを広くお客様のために生かしていきたいと思います。

※取材は感染対策を徹底して実施しております
Other Contents
-

- 【 人事DX 】
- 「2025年の崖」の
先を見据えたリソース戦略で
人材の最適なアサインメントを
全社レベルで可能にする
- ITリソースのデジタル化基盤
10,000名規模
-

- 【 健康経営 】
- デジタル技術を駆使し
未来を可視化した
健康経営で
社員の「心身の健康」をサポート
- 自社DXサービスを用いた健康促進イベント
参加社員
約1000名の完遂率78.1%
-

- 【 業務効率化 】
- RPAを駆使して年間約10万件の
受発注業務を“自動化”
- 受発注業務
- 20,000 時間/年 削減
-

- 【 働き方改革 】
- 制度とテクノロジーを駆使した
「見える化」で後押し
全社員13,000人のテレワーク移行を
1カ月で実現
- テレワーク率 70 %
-

- 【 経営ダッシュボード 】
- データ分析をすべての人の
ものにするイノベータ。
- 社内レポーティング業務
- 12,000 時間/年 削減
-
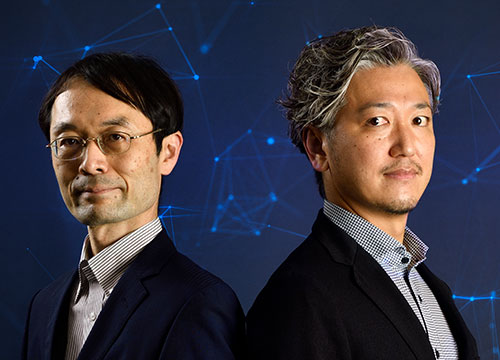
- 【 チャットボット+AI 】
- 自動化で人手を解放し
生産性向上の
成果を出すイノベータ。
- オペレーションコスト
- 4.7 億円/年 削減

- NEC デジタル変革支援サービス
- NEC
デジタル変革支援サービスは、DXの実現にむけたデジタル化ビジョンの策定と、目指す価値の実現・検証を行うサービスです。
当社のDXエンジニアがアイデアのプロトタイピングをおこない、お客様が実現したいことを見える形にします。やってみて、そこから学んで、またやってみる、アジャイル型でゴールを目指します。

NECソリューションイノベータは、2022年1月、経済産業省指針に基づくDX認定を取得しました。