しょうわくん、いよいよインボイス制度が導入されるわね
すぐに役立つ!人事総務・経理コラム スーパー総務、岡本リカの人事・会計講座
会計コラム・第14回
インボイス制度とは?企業がすべき取り組みと留意点を紹介
- トップ>
- すぐに役立つ!人事総務・経理コラム スーパー総務、岡本リカの人事・会計講座>
- 会計コラム・第14回 インボイス制度とは?企業がすべき取り組みと留意点を紹介
-

-
最近話題に上がっている消費税に関する制度ですよね
でも…イマイチ内容がわからなくて…
-
ちょっと!経理としてインボイス制度は知っておかないとマズいわ!
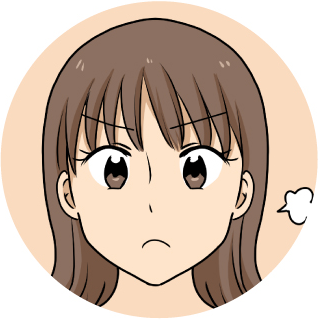
-
す、すみません…!
そもそも、「インボイス」って何ですか?
-
インボイスとは、売手が買手に対して適用税率や消費税額等を伝える請求書のことよ

-
え!ボイスなのに音声データじゃないんですか!

-
続けるわね…
「インボイス制度」は、この記載要件を満たした請求書によって消費税を計算し納付しましょうという制度なの
インボイス(適格請求書)の発行または保存により、消費税の仕入額控除を受けることが可能になるわ
-
僕たちはこの請求書の取り扱いに対応する必要があるんですね

-
そうね、私達は適格請求書の発行や保存をする必要があるわ
記載項目も増えるし、税額の計算も複雑になるのよ
-
ひ~それは大変だ!
もっと勉強しなきゃ…インボイス制度について詳しく教えてください!
-
任せて!今回はインボイス制度の概要から、具体的な取り組み、実施の注意点まで、まとめてすべて解説するわね
これを読んでぜひ早めに準備してくださいね!
すぐに役立つ!人事総務・経理コラム スーパー総務、岡本リカの人事・会計講座 会計コラム・第14回インボイス制度とは?企業がすべき取り組みと留意点を紹介
インボイス制度の導入については、話題に取り上げられることも多く、対応の必要性を感じている企業も少なくないと推測されます。しかし実際には、具体的にどうすればいいのか、よく理解できていないケースも少なくないのではないでしょうか。インボイス制度が開始されれば、取引において売手側は要件を満たした請求書や仕入れ明細書を発行しなければなりませんし、仕入れ側である買手側も保管義務が生じます。売手側・買手側双方で必要な取り組みを紹介します。
インボイス制度の概要
インボイスとは、10%と8%の複数税率に対応した消費税の仕入税額控除方式として、2023年10月1日より導入される制度で、正式名称は、「適格請求書等保存方式」です。本制度により、2023年10月1日以降は原則として取引先(売手側)から適格請求書の受け取り・保存をしないと、消費税の仕入額控除が受けられなくなります。
適格請求書と消費税の仕入税額控除とは?
適格請求書とは、従来の請求書(区分記載請求書)に「登録番号」と「適用税率および消費税額等の記載」の項目を追加したものです。これには、一定の事項が記載された請求書、納品書のほか、これらに類する書類として、領収書やレシートなども含まれます。
消費税額の仕入額控除とは、課税売り上げにかかる消費税額から、仕入れにかかった消費税額を控除することです。具体的には、製造元であるA社がある製品を2万2千円(消費税額2千円)でB社に販売し、B社が消費者に3万3千円(消費税額3千円)で販売したとします。
この際、B社は「3千円」を消費税として税務署に支払うと、A社にも「2千円」の消費税を支払っているため、支払った消費税の合計は「5千円」です。これでは実際に受け取った消費税額を超えてしまい、二重課税になってしまうため、製造者に支払った2千円を引いた千円だけを税務署に納めます。これが仕入額控除です。
インボイス制度における売手の取り組み
売手側は税額控除を受ける側ではないため、インボイス制度に取り組む必要がないかといえば、そうではありません。なぜなら売手側がインボイス制度に対応していないと、買手側は仕入額控除を受けられなくなってしまうからです。インボイス制度導入後も買手側と良好な関係を保つためには、インボイス制度への対応を検討する必要があるでしょう。
免税事業者から課税事業者へ
売手側がインボイス制度に対応するためにやるべきことは適格請求書の発行ですが、注意すべき点は、適格請求書は課税事業者でないと発行できない点です。
これまで、基準期間(個人事業主は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の事業者は免税事業者として、商品、サービスの販売で受け取った消費税を国に納める義務がありませんでした。
しかし、免税事業者のままでは、適格請求書が発行できません。課税事業者になるには、原則として2023年3月31日までに、「消費税課税事業者選択届出書」「適格請求書発行事業者の登録申請書」を所轄の税務署長へ提出します。
適格請求書の発行
課税事業者になり、適格請求書発行事業者として登録したら、次に適格請求書の発行を行います。記載事項は次のとおりです。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および適用税率
- 消費税額等(端数処理は1請求当たり、税率ごとに1回ずつ)
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
また、次のように自社の状況に応じた対応も可能です。
- 仕入れ明細書による対応
請求書ではなく、課税仕入れの相手方の名称及び登録番号を入れた仕入れ明細書で対応することも可能です。
- 複数の書類による対応
例えば請求書と納品書の記載内容を合わせることで、適格請求書の記載事項をすべて満たすことも可能です。
また、適格請求書は紙・電子データ双方での提供が可能であり、電子データによる請求書の発行が難しい場合は紙の請求書でも問題ありません。しかし、オンライン取引が普及しているため、電子データで提供できる体制を整えておくことをおすすめします。
インボイス制度における売手の留意点
インボイス制度導入により、何がどのように変わるのでしょう。経理担当者はこれまでの区分記載請求からの変更点をしっかりと把握しなくてはなりません。適格請求書が正しく記載されていないと、買手(取引先)が仕入額控除を受けられなくなるため、「要件を満たしているか」「誤りがないか」を厳重にチェックする必要があります。
端数処理や返品、値引きがある場合の対応についても間違いのないよう、変化をしっかりと把握し、かつ担当部署全体で共有しなければなりません。
インボイス制度における買手の取り組み
インボイス制度における買手側の取り組みとしては、適格請求書の保存要件の把握があります。経理担当者は、受領した適格請求書に間違いがないかを確認したうえで、紙もしくは電子データを適正に保存し、仕入額控除の適用を受けられるようにしなければなりません。
保存期間は、課税期間の末日の翌日から2ヵ月を経過した日から7年間です。なお、電子データで保存する場合は、電子帳簿保存法に則した形での保存が必要になります。
インボイス制度の経過措置
売手が課税事業者ではなく免税事業者であった場合には買手側は仕入れ額控除はできませんが、経過措置があり、一定の期間仕入額相当額の一定割合を仕入税額として控除できます。具体的な期間と割合は次のとおりです。
- 2023年10月1日~2026年9月30日まで:仕入額相当額の80%
- 2026年10月1日~2029年9月30日まで:仕入税相当額の50%
- 2029年10月1日以後:控除不可
経過措置の期間と割合を把握したうえで適正に保存しておかないと、課税事業者からの適格請求書の仕入額控除と混乱してしまう可能性があります。課税事業者と免税事業者の区分けをし、別々のフローを構築しておくとよいでしょう。
インボイス制度に取り組むうえでの課題
インボイス制度では、売手側、買手側どちらであっても新たな対応が必要となります。多くの企業では仕入れ時に買手側となり、商品販売時に売手側となります。つまりどちらかだけの対応をすればすむわけではなく、それぞれの立場での対応をしなければなりません。
それらの対応をするのは主に経理部と考えられますが、これまでの通常業務に加え、インボイス制度への取り組みを実施するのは非常に困難です。取引先の数が多ければ多いほど手間が増え、管理も煩雑になってしまうでしょう。
インボイス制度への取り組みで経理担当者の手間を軽減するポイントは、会計システムの助けを借りることです。そのため、まずは自社で扱っている会計システムがインボイス制度に対応しているか確認します。インボイス制度に対応していれば、かなりの負担軽減となるでしょう。
これから会計システムの導入を検討している場合はもちろん、導入をしていてもインボイス制度に未対応の場合は、システムの切り替えを視野に入れることをおすすめします。
また、現状の会計システムに対し「高度な管理会計を実現したい」などの不満がある場合は、より高機能な会計システムに乗り換えるいい機会となるでしょう。会計システムは製品ごとにできることに差があります。導入当初は機能に満足していても、企業規模の拡大によって物足りなさを感じることがあります。また、市場の変化が目まぐるしい現在では、変化に迅速対応するためにより早いデータ分析が必要だとされます。
インボイス制度対応は早めの準備が大切
インボイス制度導入後は、適格請求書発行事業者以外から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除を行うことができなくなります。直近になって慌てることのないよう、事前に十分な情報の確認と体制整備を行っておかなければなりません。
経理部の負担が大きくなりがちですが、会計システムがインボイス制度に対応していれば、負担を軽減することが可能です。まずは現行の会計システムを確認しておきましょう。
NECソリューションイノベータでは、インボイス制度対応への経理業務をサポートするサービスをご提供しております。経理・財務部門における業務の効率化と最適化に向けて、ぜひお役立てください。


