う~ん うまくいかないな…
すぐに役立つ!人事総務・経理コラム スーパー総務、岡本リカの人事・会計講座
会計コラム・第7回
経営分析の目的と効果は?主な財務分析の指標を紹介します
- トップ>
- すぐに役立つ!人事総務・経理コラム スーパー総務、岡本リカの人事・会計講座>
- 会計コラム・第7回 経営分析の目的と効果は?主な財務分析の指標を紹介します
-
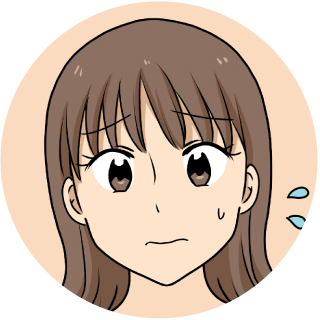
-
どうしたんですか、リカさん?
珍しく難しい顔してますね
-
今度の経営者会議に提出する資料が、なかなかまとまらなくて

-
あれ?財務諸表ならこの間、もう作成しましたよね?

-
今回はちょっと違うの
経営分析に役立つ情報として財務諸表を元に分析レポートを作っているのよ
-
え!僕たちが経営に関わることがあるんですか?

-
私達が作る財務諸表をベースに幅広い情報を取り込んで判断するのが経営分析なの
経営には財政状況の把握は欠かせないし、経理がサポートできることは実はとっても多いのよ!
-
う~なんだか身が引き締まってきました
ぜひ僕も一緒に考えさせてください!
-
ありがとう、しょうわくん!
でもその前に経営分析の目的や方法をわかりやすくまとめているから、まずはこのコラムをチェックしてみて!
すぐに役立つ!人事総務・経理コラム スーパー総務、岡本リカの人事・会計講座 会計コラム・第7回経営分析の目的と効果は?主な財務分析の指標を紹介します
変化の激しい経営環境ではスピード感のある意思決定が必要です。会社の意思決定において重要なのが経理の作成する会計書類です。意思決定のための経営分析は主に財務諸表を利用しますが、財務諸表を作成すれば経理の業務が終わるわけではありません。財務諸表の数字を活用して、経営分析に有効な資料を作成することも求められます。経理人材が理解しておくべき経営分析の指標や、指標の活用方法について紹介します。
経営分析の意味を知る!財務分析とは違うもの?
最初に経営分析の概要を紹介するとともに、似た名称の「財務分析」との違いも紹介します。
経営分析とは
自社の経営状況を客観的に見ることができる決算書や財務諸表などを分析して経営に役立てるのが経営分析です。経営分析の基本となるのは貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー表などの財務諸表です。ただし、限られた情報では判断を見誤る可能性があるため、経営分析は広い視野で行うべきものとされています。そのため財務諸表のような定量的な数字の分析を柱としつつ、社員や取引先の状況、経済情勢などの定性的な情報も考慮して経営分析を行うのが望ましいです。
財務分析との違い
一般的に、「経営分析」と比較して「財務分析」の方が分析対象の幅が狭いとされています。厳密な定義はありませんが、経営分析のうち特に「財務諸表の数字」のみを活用するものが財務分析であると考えるといいでしょう。
なお、財務分析の目的は経営分析と同じであるため、「経営分析=財務分析」と表現されることもあります。本記事でも、経営分析の中に財務分析が含まれているものとして定義しつつ、解説を進めていきます。
経営分析の目的と効果
経営分析を適切に行うためには、目的と効果をしっかり認識しておきたいところです。
経営分析では、会社の状況を客観的な数値(指標)で見ることができるため、経営成績や財政状態を冷静に判断しやすくなります。的確に問題点を把握し、改善策を立てられるプロセスです。経験や勘を生かして経営判断することもできますが、過去の経験だけでは時代の変化に追いつけないリスクがあります。また、会社の規模が大きければ自社の状況を把握し損ねることもあるでしょう。
数字からどのように問題点や改善案を導き出すのか、不安に思うかもしれません。しかし財務諸表等には複数の要素の数値が含まれているため、「本業の売上が足りないのでは」「人材を有効に活用できていない気がする」など、疑問に応じた分析が可能です。
なお、財務諸表等には複数の要素があるとはいえ、過去のデータを分析するものです。迅速に分析を行っても、一定のタイムラグは生じます。また、財務諸表等の作成時から分析までの間に経営状況が大きく変わる要素が発生する可能性もあります。有効な分析手法ではありますが、万能ではない点に注意しましょう。
5つの観点から財務分析を行う
経営分析の効果を得るために財務指標を分析して客観的に現状を把握することが重要です。財務分析は、「収益性」「安全性」「生産性」「活動性」「成長性」の観点からみることができますので、順に紹介します。
1:収益性分析
「収益性」とは、会社がどの程度稼ぐ力を持っているかを計るための指標です。収益性に関する指標が高い場合、少ないコストで効果的に売り上げを上げていると言えます。かけるコストが小さいので不況時も強いですし、生産性が高いので資金調達時にも有利に働くでしょう。収益性は会社の根幹に関わる部分ですので、もしも指標が悪い場合は、早急に対策を練らなければならないことも分かります。
収益性に関する指標は、主に損益計算書の「売上高」と各「利益」の比較から計算します。多くの指標がありますが、ここでは2つの指標を見ていきます。
【売上高総利益率(売上総利益÷売上高×100)】
売上高総利益は総売上額から原価を差し引いた利益で、「粗利益」とも呼ばれます。売上高総利益率は粗利益が売上高に占める割合で、「粗利益率」とも呼ばれます。数値が高いほど稼ぐ力があると判断されます。この指標が対前年比で下落している場合には、仕入原価や製造原価などのコストが上昇している可能性がありますので、コスト高の原因を探って今後に備えるのが得策です。
【売上高営業利益率(営業利益÷売上高×100)】
売上高に対する営業利益の割合を表す指標です。営業利益は営業によって稼いだ利益なので、この指標が高ければ「本業で稼ぐ力」が高いと言えます。逆に、この指標が低いと本業で稼ぐ力が弱いと判断されますので、大きな経営改善が求められます。
2:安全性分析
安全性分析とは、負債と資本の構成や比率を確認することで、「支払い能力」や「財務の安定性」を計るための指標です。経営の健全性を見ると言ってもいいでしょう。なお、負債があるから「経営状況が良くない」わけではありません。負債が少ない方が安全性は高いかもしれませんが、負債を避けすぎている会社は経営が保守的である可能性もあります。指標を用意することで、返済能力とのバランスが適正なのかを見ることが重要でしょう。
安全性分析には次のようなものがあります。
【流動比率(流動資産÷流動負債×100)】
流動比率とは、貸借対照表の流動資産を流動負債で割ったもので、短期的な会社の支払い能力を計る指標です。流動資比率「現金もしくはすぐに現金化できる資産(当座資産、棚卸資産)」と「すぐに支払わなければならない負債(売掛金、受取手形)」の割合です。不良売掛金や長期間動かない在庫などがあると数値が下がり、一般にこの割合が200%を超えていれば堅実な経営であるとされます。
【自己資本比率(自己資本÷総資本×100)】
総資本に対して、返済不要の自己資本がどれだけあるかを見る指標です。比率が低いと他人資本が多いことになり、突発的な支払いが発生したときに自己資本が不足してしまう懸念があります。融資を受ける際も自己資本比率が高い方が有利です。しかし一見指標が高い場合でも、過去からの推移でみると徐々に減少しているケースもありますので、注意が必要です。
3:生産性分析
生産性分析とは、売上額を向上するため、会社資源である「ヒト」「モノ」「カネ」を有効に活かしているかを判断するための指標です。「社員1人当たり」「設備1つ当たり」「資金1,000万円当たり」などさまざまな指標がありますが、なかから2つ紹介します。
【労働生産性(付加価値÷従業員数×100)】
労働生産性は、従業員1人当たりが生み出す成果を計る指標です。ここで言う「付加価値」とは「労働による対価」のことです。業界や会社によって算出方法は異なりますが、中小企業の場合は「売上高-外部から購入した費用(原材料費、外注加工費、機械の修繕費、動力費など)」で算出されるのが大半です。また、従業員数は2期の平均値を用いることが多いようです。数値が高いほど、従業員が付加価値の高い仕事をしていると言えます。逆に数値が低いと、人材をうまく活用できていないことや長時間労働の懸念があります。
【資本生産性(付加価値額÷総資本×100)】
資本生産性は、投入した資本金に対してどれだけ付加価値が生じているかを計る指標です。数値が高いほど、資本を投下した設備投資が高い付加価値を生みだしていると言えます。資本力にかかわらず判断できるメリットがあり、多額の資本を投入しているのに数値が悪いといった場合は、資本投入の考え方を改める必要があるかもしれません。
4:活動性分析
活動性とは売り上げと資本を見ることで、資本が有効に使用されているかを計る指標です。持っている資本を効率的に使って売り上げを得ることが企業活動とも言えるため、会社経営の根幹を見極める指標でもあります。資本を効率的に使い、多くの売上をあげているほど活動性が高いと言えるでしょう。
活動性分析には、次のようなものがあります。
【総資本回転率(売上高÷総資本×100)】
資本回転率は、資本が期中に売り上げとして何回回収され再投資されるかを計る指標で、その「回転数」を見ていきます。売り上げが総資本と同じなら1回転、総資本の2倍なら2回転で、回転数が多いほど少ない資本で多くの売り上げをあげていることになります。社内での推移を見たり、同業他社と比較したりすることで、自社の状態を客観的に評価することが可能です。なお、ここでの総資本は当期・前期末平均で考えます。
【固定資産回転率(売上高÷固定資産×100)】
固定資産回転率は売り上げを用いて、固定資産を無駄なく活用できているか計る指標です。指標が低い場合は、過剰な設備投資である、もしくは固定資産が有効に活用されていないと判断されます。もともと固定資産は金額が大きい傾向の支出であるため、無駄が生じないようしっかりとチェックしたいところです。なお、ここでの固定資産は当期・前期末平均で考えます。
5:成長性分析
成長性分析とは、会社の売り上げや利益がどのように変化しているのかを確認することでその「成長性」を計る指標です。成長性分析のうち、2つの指標を紹介します。
【売上高増加率(当期売上高-前期売上高)÷前期売上高×100】
前期に対していくら売上高が伸びたかという指標です。指標がプラスであれば「成長」、マイナスであれば「衰退」したと見なされます。原則として指標は高い方が良いのですが、あまりに高い場合は急成長による弊害も考えられるので注意しましょう。
【経常利益増加率(当期経常利益-前期経常利益)÷前期経常利益×100】
前期の経常利益と比較してどれだけ増加、もしくは減少したのかを判断するための指標です。数値が高い方が会社は発展していると言えます。数値が低い場合や、数値は低くないが前期より小さくなっているなどの場合は対策が必要です。
※指標は特に断りがなければ「%」が単位です
経営分析の方法
経営分析をどう役立てていくかを見ていきます。
経営指標を活用するコツ
指標は、自社の強みと弱みを把握するのに有効です。強みを伸ばし、弱みを克服するために活用していきます。自社の指標については一定期間ごとに比較して活動の成果を確認するべきです。同時に、「同業種比較」や「他業種比較」などにも使用するといったように、多角的な視点で活用していきましょう。
ただし、指標は種類が多いので、やみくもに作成すると分析しにくくなりますし、経理の負担も大きくなります。自社にとって必要な指標を絞ることも重要です。
経営分析のベースになるデータの重要性
経営分析の基本になるのは「数字データ」なので、数字は正確でなければなりません。そのため、日々の記帳を正確、かつ迅速に行うことが重要になってきます。
また、あとでデータを活用することを考えると、もとのデータはシンプルにしておくといいでしょう。今後さまざまなツールを利用していくためには、データの標準化・正規化を意識しておくことが必要になります。
効果的に実施して強い経営を行おう
経営分析のメリットは、客観的に自社の状態を把握できることです。強みは活かし、弱みはカバーもしくは改善することで会社の経営が強固になります。ただし、経営分析を行うための指標や書類作りは簡単ではありません。経理の負担が重い場合は、経理の作業効率を上げることから着手していくといいでしょう。
SuperStreamなら集計・ピボットのようなExcelライクな使い方も可能なので、あらかじめデータ加工することで、二次加工の手間を減らせます。業務効率化もかなう、SuperStreamの経営分析機能を活用してみてはいかがでしょうか。


