ああ!もう今月の残業時間が上限ギリギリになっちゃいました…
すぐに役立つ!人事総務・経理コラム スーパー総務、岡本リカの人事・会計講座
人事・総務コラム・第13回
今さら聞けない「働き方改革」を背景やポイント、メリット・デメリットから解説
- トップ>
- すぐに役立つ!人事総務・経理コラム スーパー総務、岡本リカの人事・会計講座>
- 人事・総務コラム・第13回 今さら聞けない「働き方改革」を背景やポイント、メリット・デメリットから解説
-

-
時間外労働は「月45時間」まで
ウチは特に厳しいからオーバーしないように気をつけて
-
それにしても、時間外労働や有給休暇に対するみんなの意識が変わってきましたね
「働き方改革」が浸透してきたんでしょうか?
-
そうね、確かに一人ひとりの意識は以前と比べると高くなったと思うわ
でも今度はルールを守らせるために無理やり早期退社を強制する…といった新たな問題も起きているのよ
-
よく聞く、ジタハラ(時短ハラスメント)ですか!?

-
働く人の心身が健康になって、それを企業の生産性向上につなげていくことが本来の目的だったはずなのに…
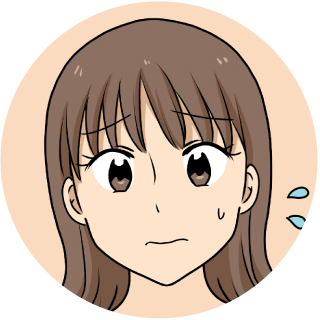
-
なんだかせっかく動き始めた改革が、形だけで終わるのはもったいないですね

-
働き方改革から得られるメリットって企業と社員、それぞれにあるはずよね

-
もう一度基本に立ち返って、あらためて働き方改革について考えてたいですね!

-
それじゃあ 今回は働き方改革の背景やポイントのまとめ、
企業と社員にとってのメリット・デメリットを解説するわ
すでにご存にの方も、あらためておさらいしてみてね!
すぐに役立つ!人事総務・経理コラム スーパー総務、岡本リカの人事・会計講座 人事・総務コラム・第13回今さら聞けない「働き方改革」を背景やポイント、メリット・デメリットから解説
働き方改革という言葉を耳にするようになって数年が経ちました。しかしそのように年数が経った結果、「働き方改革とは何だったのか」ピンと来ない人もいるのでは? この記事では働き方改革について、背景やポイント、メリット・デメリットを解説します。ここで改めて「働き方改革」について見直してみませんか?
働き方改革とは?
働き方改革とは、社員おのおのが、自分に合った働き方を選べるような社会を作り出すため、いくつかの措置を講ずること。
どうして働き方改革をするようになったのか、その背景
少子高齢化が進む現在、労働力人口(15歳以上の人口から、就業者と完全失業者を合わせた人口)が減りつつあります。2022年1月分の数値は、下記のとおりです。
- 就業者数 6,646万人で2021年1月と比較して32万人減っている
- 完全失業者数 185万人で2021年1月と比較して14万人減っている
このように就業者数も完全失業者数も大きく減っています。また今後も同様に減ると見込まれているのです。そうした状況のなか、引き続き経済を発展させたり社会を継続したりしていくには、働く人それぞれの生産性向上が欠かせないでしょう。
しかし、そこにはさまざまな問題があります。それを改革していこうというのが働き方改革なのです。
働き方改革が持つ3本柱・ポイント
前述のとおり、引き続き経済を発展させたり社会を継続したりしていくには、働く人それぞれの生産性向上が欠かせません。しかしそこには問題があります。その問題を改善・解決するための事柄が「3本柱」なのです。それぞれについて解説しましょう。
社員の有給をきちんと確保「年次有給休暇の時季指定」
毎年5日間、必ず年次有給休暇を確保できるようにする措置です。「半年以上の継続雇用」「労働する日のうち8割以上は出勤」といった条件を満たせば、社員は年次有給休暇を取得できます。社員一人に対し、年次有給休暇が付与された基準日から数えて1年以内に、企業は「社員からの請求」もしくは「企業が指定した時季か計画年休」どちらかで5日間の年次有給休暇を取得させなくてはなりません。
また社員がいつ年次有給休暇を取得したのかをまとめた年次有給休暇管理簿を作成したうえで、3年間保存する義務があるのです。
労働時間を見直して社員の健康を確保「時間外労働の上限規制」
これまでの日本では長時間労働が一般的になっており、心身への悪影響や過労死リスクなどのさまざまな面から問題視されていました。これらを是正して社員の心身を健康にしていけるよう、「時間外労働は月45時間・年360時間まで」といった時間外労働の上限規制が設けられるようになったのです。
また臨時かつ特別の事情があり、かつ労使が合意していても、下記の労働時間を超えるのは違反となります。
- 複数月における時間外労働の平均時間が80時間以内
- 休日労働と時間外労働を合わせた時間が月100時間未満
- 年で720時間以内
違反になると、6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金になる可能性もあります。
なお、「時間外労働の上限規制」は、下記の時期から施行されています。
- 大企業:2019年4月1日
- 中小企業:2020年4月1日
格差をなくして非正規社員の待遇を確保「同一労働同一賃金」
これまで正社員と非正規社員との間には、基本給や手当に待遇差があり、問題となっていました。たとえば非正規社員は正社員と同じ仕事をしても、正社員より基本給や手当が低い場合が多いため、不満を抱えやすくなっていたのです。そうした差を埋めるため、「同一労働同一賃金」が進められました。対象は派遣社員や契約社員、パートタイマーといった「正社員以外の非正規社員」です。たとえば職務内容が同じという場合、待遇で差別をしてはいけません。また正社員と待遇が異なる際、非正規社員は理由について企業に「なぜそうしているのか」尋ねる権利があるのです。企業は非正規社員から問い合わせがあった際、それに答える義務があります。さらに行政から無料かつ非公開で助言・指導やADR(裁判外紛争解決手続)も実施されます。
働き方改革のメリット
働き方改革にはどんなメリットがあるのでしょう。企業と社員、それぞれの目線から解説します。
企業が得られるメリット
企業が得られるメリットは4つです。
- 社員の心身が健康になり、生産性向上
働き方改革によって年次有給休暇を社員に確保させるうえ、時間外労働にも上限が設けられました。そのため社員はきちんと休めるようになり、長時間労働労働から解放されるようになったのです。それらによってリフレッシュできるため、生産性も向上します。
- 非正規社員のモチベーションアップ
同一労働同一賃金によって非正規社員は、待遇の差が埋まるためモチベーションが高まります。それにより非正規社員からこれまでにないアイデアが出る可能性もあります。生産性にくわえて業績向上が見込めるでしょう。
- 企業のイメージアップ
「働き方改革に取り組んでいる」姿勢によって、内外に「人材を大切にしている」とアピールできます。それにより優秀な人材の獲得や離職の防止にもつながり、企業のイメージアップも見込めるでしょう。
- タレントマネジメントや人材管理が加速する
社員の心身が健康になるだけでなく、非正規社員のモチベーションもアップするため、人材の能力がこれまで以上に発揮されやすくなります。それによりタレントマネジメントや人材管理も今以上に良い形となるでしょう。適材適所の配置も実現しやすくなります。
社員が得られるメリット
社員が得られるメリットは2つです。
- 仕事と私生活のメリハリがつく
年次有給休暇の確保と時間外労働の上限規制によって、社員は休みが確実に確保できるうえ、ワークライフバランスも整います。つまり仕事と私生活におけるメリハリがつきやすくなるのです。よってストレスも減り、生産性も向上するでしょう。
- 待遇の改善
これまで非正規社員は、社員と同じ仕事をしていても基本給や手当といった待遇に差がある場合も多かったのです。しかし非正規社員は、待遇の差を埋めて欲しいと要望するのは難しい状況でした。なぜなら「契約が更新されないかも」といった不安がつきまとうからです。
それが同一労働同一賃金によって、待遇の改善が見込めるようになりました。
働き方改革のデメリット
働き方改革にはデメリットもあります。企業と社員、それぞれの目線から解説しましょう。
企業におけるデメリット
企業におけるデメリットは2つです。
- 人件費が高くなる
同一労働同一賃金によって非正規社員の賃金が増えるため、人件費はこれまでより高くなります。
- 仕事が終わらない場合、管理職の負担が増える
社員に年次有給休暇を取得させるうえ、社員に決められた上限以上の残業をさせることもできなくなりました。そのためもし仕事が終わらない場合、管理職が仕事を引き受ける形になります。なぜなら管理職は残業時間の上限規制対象外だからです。結果、管理職の負担がこれまで以上に増えてしまうと考えられます。
社員におけるデメリット
社員におけるデメリットは1つです。
- 給与の総支給額が減る人もいる
残業代で給与の総支給額を増やしていた人は、その金額が減ってしまいます。残業時間に上限規制が設けられたうえ、多くの企業では勤怠管理を行っています。それにより不必要な残業ができなくなり、給与の総支給額が減ってしまう人も存在するのです。
社員と企業、双方が働き方について考える意識が重要!
働き方改革の推進によって、改めてこれまでの働き方を見直す機会が訪れました。また改革といった言葉のとおり、これまで良くない習慣となっていた部分も改善されつつあるのです。しかし「働き方改革関連法で定められたから」といった受け身の姿勢では、一過性の改善で終わってしまいます。働く社員そして使用者である企業、双方で「今の時代に合っていて、なおかつ社員も企業も喜べる」働き方を追求し続けるとよいのではないでしょうか。




