今、360度評価が注目されているわね
ウチも採用を検討しているそうよ
すぐに役立つ!人事総務・経理コラム スーパー総務、岡本リカの人事・会計講座
人事・総務コラム・第15回
改めて知っておきたい360度評価!
メリットやデメリット、評価項目や成功に導くポイントから解説
- トップ>
- すぐに役立つ!人事総務・経理コラム スーパー総務、岡本リカの人事・会計講座>
- 人事・総務コラム・第15回 改めて知っておきたい360度評価!メリットやデメリット、評価項目や成功に導くポイントから解説
-

-
360度評価って上司だけじゃなくて、同僚や部下からも評価を受ける制度ですよね
なんで注目されているんですか?
-
コロナ禍でテレワークを採用する企業が増えたでしょ?
部下の様子が見えづらくなったことで、上司が一方的に評価することが難しくなったのが大きいかもしれないわね
-
たくさんの人からの評価なら客観的で公平になりやすいですよね

-
確かに360度評価は対象者の納得感を得られやすいというメリットがあるわ

-
それに色々な人が自分をどう見ているのかわかれば、成長につながりそうですね!
ぜひウチにも取り入れましょう!
-
そうね、でも360度評価には注意しなければいけないポイントも多いのよ
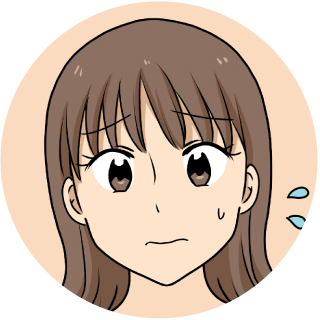
-
え、どんなことですか?

-
評価に主観が入りすぎてしまったり、上司は部下を厳しく教育しなくなったり…
それに仲の良い社員同士が互いに評価を上げる可能性だってあるわ
-
いいことばかりではないんですね…

-
でも大丈夫!今回のコラムを読めば、360度評価を成功させるコツや評価項目など、抑えておきたいポイントが丸ごとわかるわ!
ぜひ最後まで読んでね!
すぐに役立つ!人事総務・経理コラム スーパー総務、岡本リカの人事・会計講座 人事・総務コラム・第15回改めて知っておきたい360度評価!
メリットやデメリット、評価項目や成功に導くポイントから解説
360度評価は、昨今当たり前になりつつある評価の仕組みです。しかし言葉は知っていても360度評価とは一体どんな評価なのか、忘れてしまった人はいないでしょうか。ここでは360度評価について、メリットやデメリット、評価項目や成功に導くポイントを解説します。
360度評価とは?
上司や部下、取引先といったさまざまな人から評価を受けること。従来あった上司からの評価だけでは、人材の一面しかわかりません。360度評価はそういった評価では推し量れなかった被評価者の強みや弱みが、多く発見されるのです。また人材管理(人材マネジメント)のひとつともいえます。
人材管理(人材マネジメント)とは?
人材管理(人材マネジメント)とは、どんな人材がいるか確認したり人材を集めたり人材の能力を引き出したりすること。そもそも人材は、経営資源のひとつです。経営資源は「ヒト・モノ・カネ・情報」の4つからなり、人材はそのうちのヒトに当たります。
360度評価はどう役立つ? そのメリット
360度評価は何に役立ち、どんなメリットをもたらすのでしょう。
客観性の高い評価のため、納得しやすくなる
上司からの一方的な評価ではなく、「360度」の文字どおりさまざまな人から評価を受けるため、客観性が高まります。そのため被評価者は、評価の内容に納得しやすくなります。
自己分析と改善に役立つ
360度評価ではさまざまな人から評価を受けるため、自分では気づいていなかった面について知っていけます。また自分に対しても評価を行うため、「自分から見た自分」と「他者から見た自分」の違いがわかるのです。それにより強みや改善点が明確になりますし、「今後どのようにしていくか」も組み立てていけるでしょう。
それだけではありません。「自分に対しても評価」しているため、他者からの内容を含めて「自分ごと」として捉え、主体的に自己分析や改善に取り組めるのです。
周囲も被評価者について深く知っていける
360度評価では、「改めて考えるとどういった面があるのだろうか」と、周囲が被評価者をじっくり見ていきます。そのため、周囲も被評価者の強みや弱み、性格や思考について深く知っていけます。
人間関係が浮き彫りになる
周囲の評価によって、被評価者を取り巻く人間関係が明確になります。気づいていなかっただけで、さまざまな人脈を持つ被評価者が存在するかもしれません。
一方、「ある部署で一人だけ評価が低い」場合、注意しましょう。その被評価者の周囲に改善を要する人間関係が存在するかもしれません。たとえば「被評価者がハラスメントを受けている」「何らかのトラブルがあり、そのために評価が低い」といったものです。
管理職が自身を振り返っていける
360度評価は一般社員にだけ行われるものではありません。管理職もその対象となるのです。360度評価によって、管理職も「自身がどう見られているのか」「どういった強みがあるのか」「早くに直しておきたい点は何か」などを振り返っていけます。
ISO30414に役立つ情報を集められる
ISO30414とは、内外に「人的資本についてどう取り組んでいるのか」を開示する際、どういった情報や指標を用いるか定めたガイドラインのこと。実はこれまで世界的に使えるガイドラインがなく、企業にとって悩みとなっていました。
しかし2018年12月、ISO(国際標準化機構)がISO30414を発表。これにより企業は人的資本の開示に関する悩みが減ったのです。
360度評価にはデメリットもある
メリットが多く見える360度評価にもデメリットがあります。
評価を気にしすぎて正しい指導が行われなくなる
360度評価では上司も評価を受けます。結果、上司がどう評価されるか気にしすぎたり部下に良い評価をつけてもらおうと考えたりして、正しい指導が行われなくなる可能性も高まるでしょう。たとえば「部下が間違っていても指摘できない」「正しいやり方を伝えられない」などです。
適切な評価になりにくい
評価をした経験の少ない社員は、「そもそもどのように評価をするのか」わかりません。そのため適切な評価にならなくなってしまいます。たとえば「主観が入りすぎて、客観的な評価になっていない」「どういった点を見て評価すればいいかわからず、評価に一貫性がなくなってしまう」などです。
談合や不信感につながる可能性も高い
お互い良い評価になりたいと考え、談合をする社員が出る可能性もあります。またお互いに評価をつけ合う状況になるため、不信感といった感情が生まれ、コミュニケーションがうまくいかなくなる可能性もあります。
周知や集計などで手間がかかる
社員や管理職は「360度評価の実施」で、人事は「360度評価を始める際の周知」「360度評価の結果を集計」といった点で、非常に手間がかかります。そのままでは通常の業務に影響する可能性も高いでしょう。どう効率化して時間を作るか、が課題となります。
360度評価ではどういった項目を設定するのか
360度評価ではどんな項目を設定するのでしょう。
一般社員用に使う項目
チームワークやコミュニケーション、態度や主体性、業務遂行力などを設定します。
管理職に使う項目
管理職用では、一般社員用にいくつか項目を追加する形となります。たとえば人材育成やリーダーシップ、判断力や自己啓発、目標達成といったものです。
360度評価を成功に導くポイント6つ
360度評価を成功に導くには、何に気をつければよいのでしょう。そのポイントを6つ、解説します。
ポイント①ルールや目的をはっきりさせ、評価時はそれを守る
初めに、
- 「どうして360度評価を行うのか」といった目的
- 「どのように360度評価を行うのか」といったルール
を明確かつ詳細に決めていきます。そのうえでそれを社員に知らせ、納得してもらってから360度評価を始めるのです。また評価時に「目的やルール」が守られるよう、チェックリストを作成します。
ポイント②誰が書いたかわからないよう配慮する
360度評価では「誰が書いたかわかってしまった」というトラブルがよく起きます。そしてお互いに不信感を抱いたり人間関係がこじれてしまったりしてしまうのです。
360度評価は「誰が書いたか相手に伝わらない」からこそ、正直な評価ができるもの。
- 「誰が書いたかわかるような内容は書かない」よう、社員に徹底する
- 評価者自身について書く欄に、個人が特定できるような質問を含まないよう徹底する
などで、「誰が書いたかわからない」よう配慮しましょう。もちろん人事もフィードバックをする際、どんなに尋ねられても「どこの誰が書いたか」答えてはなりません。
ポイント③360度評価の対象は全社員
360度評価は、すべての社員を対象とします。なぜなら客観性や公平性を保つためだからです。もし「特定の部署だけに360度評価を導入する」「特定の社員だけに360度評価を行う」といったやり方にしてしまうと、社員に不信感を抱かせてしまいます。
ただし360度評価の導入初期に、「スモールスタートとして特定の部署だけに導入」というのは比較的問題ありません。とはいえ説明不足ではやはり社員から疑念を抱かれてしまうもの。「導入当初のため、スモールスタートとして360度評価に協力してほしい」といった説明を必ず行いましょう。
ポイント④360度評価がどう使われるのか明らかにする
ただ「360度評価を行います」だけでは、「なぜなのか」「どこに使うのか」社員が不審に思ってしまいます。必ず「360度評価を行う目的」と「360度評価の結果を使う先」を明確にしておきましょう。
ポイント⑤360度評価に使うのは「平均値」
360度評価は、「被評価者と評価者にどのようなつながりがあるか」でスコアが変わります。たとえば「非常に親しい同僚からは最高値」が、「よく知らない異なる部署の社員からは最低値」が出るといったものです。
こうした最高値や最低値を評価得点にしてしまうと、公平性かつ客観性のある評価からかけ離れてしまうでしょう。あくまでも評価に使うのは「平均値」にします。
ポイント⑥必ずフィードバックを行う
「360度評価によってどのような結果が出たのか」「今後どのように活用すればよいのか」などを含めて必ずフィードバックを行いましょう。なぜならその内容こそが社員の改善や育成につながる大きなヒントになるからです。
ただしその際、「フィードバックをした・フィードバックを受けた」だけにとどめてはいけません。フィードバックをもとに「計画・施行・評価・改善」といったPDCAサイクルを回せるような仕組みが必要です。
360度評価は社員や管理職を育てる重要な仕組み
360度評価が適切に行われると、社員と管理職、ともに自らを振り返っていけます。それにより弱みの改善や強みを伸ばすといった育成が進むのです。360度評価を成功させて社員や管理職の能力を伸ばし、業務効率化や業績向上を目指してみてはいかがでしょう。
また360度評価には人事システムを活用すると便利です。




